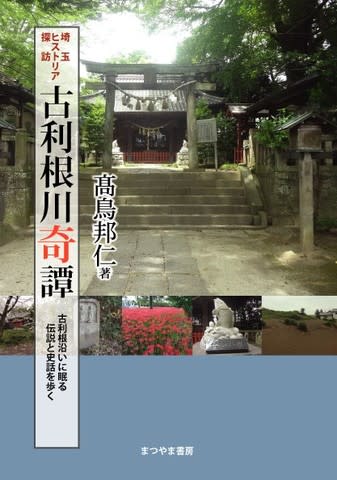9月17日、“早稲田大学本庄高等学院”の定期演奏会が
埼玉県本庄市において開催されました。
会場は本庄市民文化会館。
この施設は女堀川沿いに建ち、
本庄駅から歩いて15分程度といったところでしょうか。
22年前、この文化会館を訪れたのも演奏会がきっかけです。
高校とは関係ありません。
ある吹奏楽団に所属する同級生の恩師が出演するというので、
一緒に出掛けたのです。
羽生駅から秩父線に乗り、熊谷駅で高崎線に乗り換え。
本庄駅から文化会館まで歩いていきました。
22年前の秋のことですが、
この日のことは不思議と印象深く覚えています。
と言っても、何か事件があったわけではなく、
電車に乗って吹奏楽団の演奏会を聴きに行った、というだけのことです。
その日のことが記憶に残っているのは、
色々なものが壊れそうだったからかもしれません。
いま目にしている風景がもうすぐ終わってしまう。
隣を歩いている同級生も、多分あと少しでいなくなってしまう。
僕自身もどこか別のところへ行かざるを得ない。
そんな終わりの予感に似た胸騒ぎと不安を抱えての本庄でした。
駅から文化会館までの道のりが少し遠くに感じられたのは、
同級生の口数が少なかったからかもしれません。
駅から続く1本道を歩き、「るーぱん」の前を通り過ぎます。
やがてぶつかるのは女堀川。
川幅は狭く、流れも速くはありませんが、川面までが深い川です。
橋を渡り、舗装されていない川沿いの道を歩きました。
22年前の記憶で最も残っているのは、この川沿いの道です。
駅前の開発された土地を歩いてきた目に、
女堀川とその土手上の道は、世界が変わったように見えたからでしょう。
川から文化会館まではほんのわずかな距離ですが、
その道を通ったことだけはよく覚えています。
ところで、同級生にとっては「恩師」でも、僕には「他者」でしかありません。
その日の演奏も、同級生と僕とは違って聴こえたと思います。
その視線も恩師にあったでしょうか。
コトバに対して人一倍感受性が強かった同級生。
いつも丁寧語で話し、映像が浮かぶ歌詞の曲が好きと言ったことがあります。
吹奏楽団の演奏には「歌詞」がありません。
でも、同級生には演奏がコトバとして聞こえ、
物語のような映像を思い浮かべている気がしました。
演奏会が終わったのは5時か6時頃だったでしょうか。
川沿いの道を再び歩き、「るーぱん」に寄り道。
隣を歩いても、「るーぱん」でテーブルを挟んでも、
同級生がどこか遠くに見えたのを記憶しています。
そして店を出て本庄駅まで歩くと、
高崎線の上り電車に乗り、本庄をあとにしたのです。
いま、22年の歳月を経て文化会館を目にしても、
とりわけ懐かしさがこみ上げてくることはありません。
1980年に開館したという文化会館。
銅鏡やハニワが施されたロビー壁面のレリーフは当時のままのはずです。
でも、それらも初めて目にするかのよう………。
「るーぱん」も変わらず建っていました。
22年ぶりに来店。
しかし、特に懐かしさはありませんでした。
22年前、どこの席に座ったのか記憶になく、
むろん店員さんも変わっているでしょう。
本庄駅、女堀川、川沿いの道……。
記憶に残る風景とあまり変わらないように感じますが、
感傷じみた想いに駆られないのは、
開発の波が町の空気を変えたからでしょうか。
それとも、何かが壊れそうな予感に駆られていたあの頃の感受性が、
すでに失われているからなのかもしれません。
22年ぶりに文化会館の椅子に座り、高校生たちの演奏を聴きます。
当時はまだ生まれてもいなかった子たちです。
同級生と来たのがついこの間のようなのに、
1人の人間が成人するだけの歳月が流れたことに、ぼんやりとした痛みを感じます。
演奏会には卒業生もたくさん聴きに来ていたようです。
かつての部活仲間とおぼしきグループをいくつか見かけました。
僕もそんな風に、誰かと一緒に来ることがあったかもしれない。
そんなふうに思うことがあります。
実は、ほんの少しだけ吹奏楽部に籍を置いたことがあったからです。
担当していたのはチューバ。
もしあのままチューバを吹き続けていたら、
いまでも連絡を取り合う吹奏楽部員がいたかもしれない。
たまに音を出すこともあったかも。
ちょうど吹奏楽部員だった妻が、そんな「その後」を送っているように。
もう一つの生き方を想像しても、後悔するわけではありません。
部活を辞めようと続けようと、おそらく結末は似たものでしょう。
演奏を聴きに同級生と本庄へ足を運んだでしょうし、
色々なものが壊れては、
また新しいものが創られていくという歳月を送ったはずです。
2018年9月17日に開かれた早稲田大学本庄高等学院の定期演奏会。
平成最後の秋は、
顧問の先生の最後の定期演奏会でもあったそうです。
30年以上指揮を執ってきたということですから、
僕らが高校生だった頃も指導をしていたことになります。
会場には1997年卒の同窓生もいたでしょうか。
始まりがあれば終わりがある。
終わりがあれば何かが始まる。
その繰り返しです。
22年前も、いま現在も。
改めてそう感じます。
戦国時代に存在した本庄城よりも、
22年前の方が遠くに感じるのはなぜでしょう。
終わりと始まり。
わかっているつもりでも、
そこに伴う寂しさは未だ慣れることがありません。
たぶん、これからも。