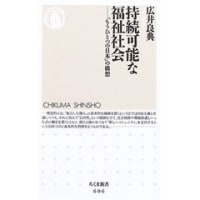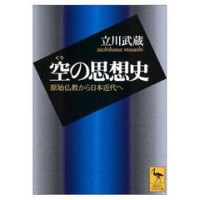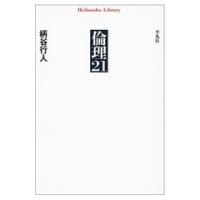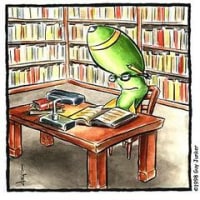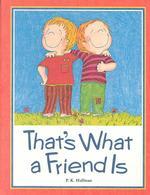
予備校は個性的な先生が集まるところだが、英語のS先生は特に個性的で、どういう英語を教わったのかは全く思い出せないが、彼の雑談は今でもよく思い出す。美大で非常勤でフランス語を教えているというその先生は、ひげを蓄えて、ダンディというか、儚げで怪しいインテリな雰囲気を醸し出していた。フランス語訛りで英語を朗読しながら、常にラ・ロシュフーコーのアフォリズム風の毒舌を吐いていた。ある日、彼が囁くように言ったのは、「友だちができないって悩んでいる人いるけど、そんなの簡単です。誰か見つけて、『君だけに打ち明けるけど』って深刻な悩みを相談すれば、すぐに親友になれますよ」ということだった。これも毒のある言い方だと思うが、一面の真理をついているかもしれない。
大学に入って専攻する政治学以外で特に興味をもった科目は社会心理学で、その関係の本も結構読んだ。社会心理学や集団心理学は社会科学を学ぶ上でも重要な学問だが、何よりも人間関係に興味をもって、政治学や社会学を学んでいる人にとっては興味深い科目である。とくに対人社会心理学という分野があり、その中で重視されているのが「自己開示」ということだと知った。自分の弱い部分を見せない人、本音を語らない人はなかなか人から信頼されたり、好きになってはもらえないだろう。しかし人間はたとえ何か悩みを告白している時でもどこか自分を良く見せたい気持ちが残っているし、自分にとって望ましい自画像を他人を通じて確認しようとする傾向がある。また反対に過度に偽悪的になって、他人が聞きたくないような性癖、経済事情、家庭事情や非常識な行動をべらべらと「ぶっちゃけて」しゃべって、それが「飾らない」自分を話しているからいいのだと勘違いしている人もいる。そういう人は自分が他人から「お高く」見られがちなので、自分の低俗さをあえて強調することで親しみをもたせようと努力しているのかもしれないが、残念ながら他人は最初からその人のことをそれほど尊敬もしておらず、ただ周囲を幻滅させるだけのみっともない結果に終わることも多い。このように適切な「自己開示」というのは極めて難しいものだ。
自己開示型のコミュニケーションを重視するアメリカではたくさんの本が出ていて、日本語でも例えばV・J・ダーレガ著『人が心を開くとき、閉ざすとき-自己開示の心理学』という翻訳書も出ているので、興味のある方は読んで頂きたいが、知識がついても実践するには勇気とセンスと敏感さが必要であろう。
私自身も悩んでいる内容に応じて相談する相手が何人かいるが、本当に困っていることを素直に隠さずに話せるのは大学時代以来の友人一人かもしれない。今は遠く離れてお互い忙しく暮らしているため、普段はあまり連絡をとらず、何か悩んでいる時に連絡を取り合う関係だが、私の性格や弱点、特徴などを知りつくしていて、しかも説教くさくならずに、無責任でない助言をしてくれるのでとても助かっているし、頼りにしている。相談しながら結局その通りに行動できないことも少なくないし、同じ失敗も何度も繰り返しているのだが、彼のお陰で悩みが解消、とはいかなくても、軽減されたことは数知れないし、相談した以上、彼の信頼を裏切らないように行動したいといつも思っている。まことに英語のThat's what a friend is. というフレーズを思い出させる存在である。しかし大切なのはいくら付き合いが長く親密になっても、お互いの感情と最低限の礼儀を尊重する気持ちがあることだと思う。このブログを読んでくれているとは思えないが、この場を借りて日頃の友情に心から感謝したい。
大学に入って専攻する政治学以外で特に興味をもった科目は社会心理学で、その関係の本も結構読んだ。社会心理学や集団心理学は社会科学を学ぶ上でも重要な学問だが、何よりも人間関係に興味をもって、政治学や社会学を学んでいる人にとっては興味深い科目である。とくに対人社会心理学という分野があり、その中で重視されているのが「自己開示」ということだと知った。自分の弱い部分を見せない人、本音を語らない人はなかなか人から信頼されたり、好きになってはもらえないだろう。しかし人間はたとえ何か悩みを告白している時でもどこか自分を良く見せたい気持ちが残っているし、自分にとって望ましい自画像を他人を通じて確認しようとする傾向がある。また反対に過度に偽悪的になって、他人が聞きたくないような性癖、経済事情、家庭事情や非常識な行動をべらべらと「ぶっちゃけて」しゃべって、それが「飾らない」自分を話しているからいいのだと勘違いしている人もいる。そういう人は自分が他人から「お高く」見られがちなので、自分の低俗さをあえて強調することで親しみをもたせようと努力しているのかもしれないが、残念ながら他人は最初からその人のことをそれほど尊敬もしておらず、ただ周囲を幻滅させるだけのみっともない結果に終わることも多い。このように適切な「自己開示」というのは極めて難しいものだ。
自己開示型のコミュニケーションを重視するアメリカではたくさんの本が出ていて、日本語でも例えばV・J・ダーレガ著『人が心を開くとき、閉ざすとき-自己開示の心理学』という翻訳書も出ているので、興味のある方は読んで頂きたいが、知識がついても実践するには勇気とセンスと敏感さが必要であろう。
私自身も悩んでいる内容に応じて相談する相手が何人かいるが、本当に困っていることを素直に隠さずに話せるのは大学時代以来の友人一人かもしれない。今は遠く離れてお互い忙しく暮らしているため、普段はあまり連絡をとらず、何か悩んでいる時に連絡を取り合う関係だが、私の性格や弱点、特徴などを知りつくしていて、しかも説教くさくならずに、無責任でない助言をしてくれるのでとても助かっているし、頼りにしている。相談しながら結局その通りに行動できないことも少なくないし、同じ失敗も何度も繰り返しているのだが、彼のお陰で悩みが解消、とはいかなくても、軽減されたことは数知れないし、相談した以上、彼の信頼を裏切らないように行動したいといつも思っている。まことに英語のThat's what a friend is. というフレーズを思い出させる存在である。しかし大切なのはいくら付き合いが長く親密になっても、お互いの感情と最低限の礼儀を尊重する気持ちがあることだと思う。このブログを読んでくれているとは思えないが、この場を借りて日頃の友情に心から感謝したい。