言の葉 28 言語にとって美とはなにか ⑥その2韻律・選択・転換・喩
言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行
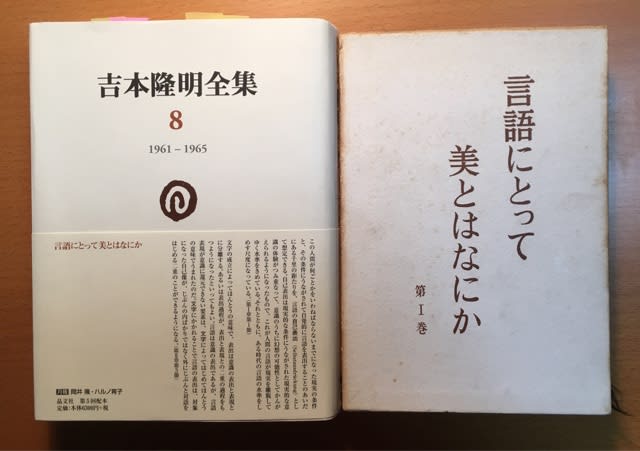
抜粋その2
同書第Ⅲ章 韻律・選択・転換・喩 2 詩的表現より
喩(当方注)
たとえば、いままで喩という言葉や暗喩というコトバを無造作につかってきたが、それは無意識のうちに詩の世界、散文の世界の住人を、あてにしてきたからだ。しかも当てにした住人が、それの応じてくれるものかどうか、あらかじめあきらかではないのである。すでに流通している喩の概念が存在するかもしれないから、それと角遂するにしても包みこむにしても、もともと流通している概念をはっきりさせておかなければならない。
ピエール・ギロー『文体論』(佐藤信夫訳)は、喩についてつぎのようにのべている。
語のあやすなわち転義法(比喩)は、意味の変化である。そのうちでいちばんよく知られているものは、隠喩である。そのほかたとえば、提喩は、白帆といって船を意味するように、部分を全体とみなすものだ。また換喩はお酒のかわりに容器を内容とみなすものである。
転義法のおもなものは、隠喩[メタフォール]、諷喩 [アレゴリイ],引用喩「[アリュジョン],反語法[イロニイ],皮肉[サルカスム],等(当方 以下略)
喩が意味の変化であるということをのぞいては、またしても壁画的分類をみている。欲しいのは壁画ではなく言語本質から喩を理解することである。言語学者の言語観にたいして、破壊するのも、独走するのもなれてしまっているし、感覚的な曲芸にも食傷しているため、このような分類には耳をかたむけるものは、ふくまれていない。
日本現代詩のすぐれた理論家である鮎川信夫『現代詩作法』ははるかに実際的に喩について語っている。
ところが、詩の表現に必要な言語の特性のひとつとして、その代表的なものに比喩があります。比(譬)喩は、直喩(シミリ)と隠(暗)喩(メタフォール)に分けるのが普通であり、若しこの意味の範囲を広くとれば象徴(シンボル)も寓意(アレゴリー)も映像(イメージ)も、すべて比喩的表現のうちに含まれると思いますが、ここではいちおう直喩と隠喩を、その標準単位として考えてゆくことにします。
詩の隠喩は、直喩のばあいと同様、やはり対象に私たちの注意をひきつけ、同時にそれを新しく価値づけるものでなければならないのです。
一つのものと他のものとの類似した関係を把握する能力は、隠喩の場合、ほとんど想像力の働きによるものであり、詩人はかぎられた言葉で無限に変化する自分の観念を示すために、広い想像の領域をもつこの方法を用いるのです。
シュルリアリストの隠喩的表現はかたちのうえでは『隠喩』であっても詩の『隠喩』ではなく、そこには『一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す』というはたらきがありません。そこには、異質のもの、あるいは異質の『観念』を同時平面的に並置しただけの、一首の型(パターン)があるだけなのです。
隠喩法には、<もの>と<もの>との対照の観念とともに調和の観念も含まれており、それ自体が独立した表現として一つの全体性を形づくる傾向があります。それは言葉のスピードと経済を本旨とし、すくない言葉で、ある事柄を言いつくそうとする心があると言えましょう。
隠喩についてのすべての定義に共通している観念は、『一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す』ということです。そしてこの『別の意味に移す』という働きが、直喩と隠喩を区別する最も大切な点なのです。
(略)
さきに鮎川信夫は、シュルリアリストの隠喩的な表現は、形のうえでは隠喩であるが、そこには「一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す」という働きがないから喩とはいえず一種の型だとのべている。いままで考察してきたところでは、シュルリアリストは、ただ、指示表出と自己表出のないまぜられた言語構造を、自己表出の機能を極端に緊張させてつかっているにほかならないから、このばあいの喩は(自己表出としての)意味喩または像的な喩とよぶことができる。喩は言語をつかって探索をおこなう意識の探索であり、たまたま遠方にあるようにみえる言語が闇のなかからうかんできたり、たまたま近くにあるともおもわれた言語が遠方にに訪問したりしながら、言語を意識からおしださせる根源である現実世界にたいして、人間の幻想が生きている仕方ともっともぴったりと適合したとき、探索は目的に当たり、喩として抽出される。
(1) 運命は
屋上から身を投げる少女のように
僕の頭上から落ちてきたのである 黒田三郎「もはやそれ以上」)
((2)(3)略)
これらのいわゆる直喩や暗喩は意味にアクセントをおいれあらわれた意味的な喩である。運命が自分の身上を訪れたという観念的な意味を、現実的にうらずけるために、「屋上から身を投げる少女のように」という直喩的なおきかえがつかわれる(1)。これは意味のアクセントでつかわれているから、屋上から身を投げる少女の像ではなくて、恋か生活苦か何かいわば失意によって屋上から投身自殺した少女の行為の意味にアクセントをおいて、「僕」に訪れた「運命」と連合されていると、みることができる。
(4) 靄は、街のまぶた
夜明けの屋根は 山高帽子
曇りガラスの二重窓をひらいて
僕は無精ひげの下にシガレットをくわえる (北村太郎「ちいさな瞳」)
((5)略 )
(4)はいわゆる暗喩で、(5)は直喩だが、これらが像的な喩であることに言語本質からの喩としての意味がかかっている。
(4)で「靄」と「まぶた」とは<意味>として結びつくことができないから、意味的な喩としては、ふたつは結びつくことができそうもない。靄が、地面や家々のあいだを白く垂れ込めている像は、あたかも上のまぶたをとじる像とむすびつくことができるため、像的な喩としてはじめて連合される。第二行の「屋根」と「山高帽子」もまったくおなじで<意味>としてだけかんがえれば、どのように自在な意識の暗闇もこのふたつをおなし表出に連合させることはできないが、夜明けのまだ薄明かりの街の屋根屋根の像は、黒い山高帽子の像と結びつくことができるため、ふたつの言語はまねきよせられて喩を形成しているということができる。
夜明けの屋根と山高帽子のあいだの像的な喩はこの詩人の西欧的な嗜好をすめすにすぎないだろうが、「まぶた」と「靄」との連合は、「まぶた」がただちに実体をしめすとともに、<まぶたの母>というように観念的な意味をあたえられることをかんがえると、おそらくこの詩人の深いところから喚びよせられているのである。
(略)
価値としての言語において、わたしたちは、現在の言語の水準をかんがえるかぎり、本質的にはいままでみてきたものの外の喩の表現に出遇うことはできない。ただ、類型をふやし喩としての多様さを壁画のように、ひとりの詩人がうまれるごとにひとつづつ殖やしていくことはできても、言語構造自体をこれ以上すすめることはできない。また、これ以上の喩の形態を考察する必要はないとかんがえられる。じっさいの文学(詩)作品でわたしたちがぶつかるのは、いままであたってきた喩がつぎつぎに繰りだされる波のようなうねりであり、また、それによる共鳴(Resonanz)や相乗(Synergie)の効果にほかならない。
(略)
(8) どこか遠いところで
夕日が燃えつきてしまった
かかえきれぬ暗黒が
あなたの身体のように
重たく僕の腕に倒れかかる (鮎川信夫「淋しき二重」)
当方注 「淋しき二重」が収録されている鮎川信夫全詩集
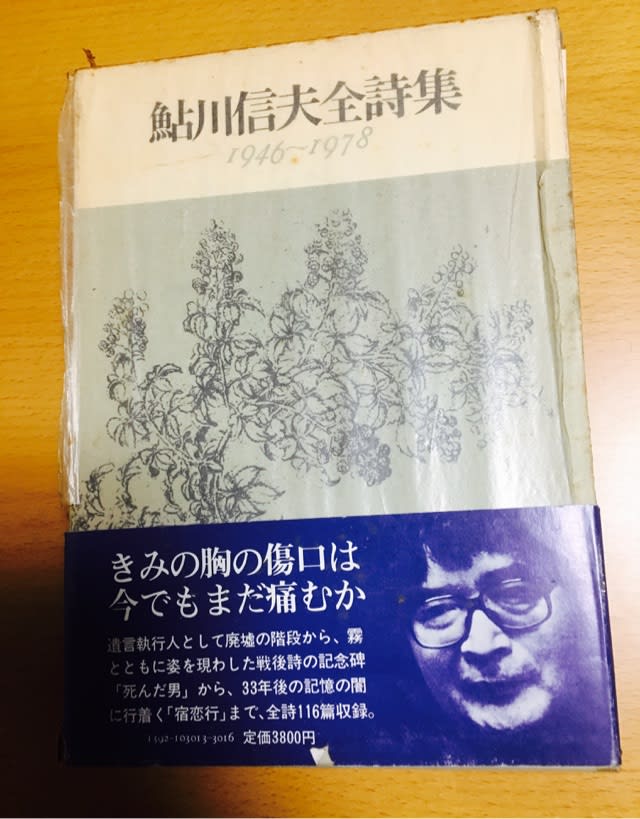
(9、10略)
おそらく、喩は言語表現にとって現在のところもっとも高度な選択であり、言語がその自己表出のはんいをどこまでもおしあげようとするところにあらわれる。<価値>としての言語のゆくてを見さだめたい欲求、予見にまでたかめることができるものとすれば、わたしたちは自己表出としての言語がこの方向にどこまでもすすむことをいいうるだけである。そして、たえず<社会>とたたかいながら死んだり変化したりしなければならない指示表出としての言語との交錯するところに価値があらわれ、ここに喩と価値とのふしぎなななめにおかれた位相と関係が描かれる。
(略)
抜粋その3
同書第Ⅲ章 韻律・選択・転換・喩 4 散文的表現より
選択(当方注)
わたしたちは、めぐるべき螺旋の階段をひとめぐりしてきたようだ。まえに、価値としての言語というように、散文作品の断片をとりあつかったときよりはるかによく視えるところから散文作品をあつかうことができるはずである。わたしたちは、喩と喩における韻律のはたらきと、言語における韻律のはたらきをながめることによって、つぎのようなことをみてきたのである。ひとつは、ある作品のなかで場面の転換はそのままの過程として抽出せられたとき喩の概念にまで連続してつながっており、また、喩はその喩的な本質にまで抽出せられない以前では、たんなる場面の転換にまでつながっているということである。喩の抽出がすでに習慣まで通常化したものが、たとえば、ギローが『文体論』であげているような隠喩・諷喩・引用喩・反語法……などといったような修辞的な区別となる。そして、喩の概念が縮退した状態をかんがえれば、たんなる場面の転換というところにたっする。
それならば、場面の転換が縮退したところ、あるいはより混沌とした未分化なところを想定すれば、なにが残るのだろうか。
これにはきわめて興味ある挿話を想い出したほうがいい。以前にある文芸評論家が、「南極探検」の記録映画が公開されたとき、任意にとられたフィルムをつなぎあわせたようなその映画は、映画でなければとれないような技巧が使われていないから記録映画であるかもしれないが、記録芸術ではないと評した。これのたいして、ある哲学者が、そんな馬鹿なことはない、赤ん坊や白痴は人間でなければできないような高度な活動をなしえないからとて人間ではないと云うことができようか、それは、芸術か非芸術かのもんだいではなく、いい芸術かそうでない芸術化のもんだいにすぎないと反駁した。
もちろん、哲学者のほうがまともにもんだいをとらえていたのだ。なぜならば、たんに任意にとったフィルムをつなぎあわせたにすぎないようなその「南極探検」の映画も、場面を意識的にしろ無意識的にしろ選択したところですでに初原的な美のもんだいが成り立っているからである。なぜ、「宗谷」丸の背景に氷山と空をえらび、前景にペンギンの群れを、しかじかの角度からえらんだかというところに。
言語の表現のもんだいも、自己表出の意識としてべつもんだいではない。言語の場面の転換の縮退したところには、場面そのものの選択ということがのこるのである。
(略)
(5)いいか、ここにあるものはなんでも持っていけ、アメや野郎にとられるよりは、みんな持っていけ、とわめく魚雷班兵曹のくしゃくしゃになった顔を踏みつけるように、突如ザッザッと銃剣をつけた水兵たちの一隊があらわれて何処にいくのか、軍需部の岸壁を速足で行進していき、なんだあいつら、戦争に負けたというのに、と鹿島明彦の背後で酔いつぶれていた兵曹がひどく血走った眼をあげて呟いた。
(井上光晴「虚構のクレーン」)
これも場面の転換とかんがえていい。作者は、まず、「ここにあるものはなんでも持って
いけ、アメ野郎にとられるよりは、みんな持っていけ」とわめく魚雷班兵曹に移行し、つぎ
に、とつぜん作者の位置にかえって銃剣をつけた水兵の一隊の行進を描写し、また、とつぜん「なんだあいつら、戦争に負けたというのに」とつぶやく兵曹に転換し、さいごの「ひどく血走った眼をあげて呟いた」でその<兵曹>を対象に転化するため作者の位置にもどって描写したうえで、この文章はおわっている。その人称転換は複雑をきわめており、このめまぐるしい転換が喩として抽象しうるまでになっていないが像や意味のうねりをかたちづくっている。
言語の表現は、作家がある場面を対象としてえらびとったということからはじまっている。これは、たとえてみれば、作者が現実世界のなかで、<社会>とのひとつの関係をえらびとったこととおなじ意味性をもっている。そして、つぎに言語における場面の転換がこの底辺からより高度に抽出されたものとしてやってくる。この意味は作家の現実世界のなかで、<社会>との動的な関係のなかに意識的にまた無意識的にはいりこんでいることに、たどることができる。
さらに、場面の転換からより高度に抽出されたものとして喩が存在している。その喩のもんだいは作家の現実世界で、現に<社会>との動的な関係にある自己自身を外におかれた存在とみなし、本来的な自己を奪回しようとする無意識の欲求にかられていることににている。
このようにして、わたしたちは現在、韻律を根源において、場面の選択というもっとも底辺にあるもんだいから、場面の転換をへて、言語の現在的水準としてもっとも高度な喩のもんだいにまで螺旋状にはせのぼり、また、はせくだる表現の定形をもっている。そして、表現としての言語がつみかさねてきたこれらの過程は、現在の水準のなかにすべて潜在的には封じこめられているとみることができる。そして、これが、指示表出としての言語が<意味>の構成としてもつ思想的ひろがりと交錯するところに詩的空間・散文的空間の現在的水準がくりひろげられている。
まだ、唱うべき対象をえらびとることができないままに表現された記紀歌謡のような古代人の世界から、すでに高度な喩をつかって現実に選択している<社会>との関係を否定しそれを超えようとする欲求を表出している現代の文学の世界にいたるまでのげんごのつみかさねられてきた長い過程は、いままで、言語を成り立たせてる共通の基盤として分析してきた特性として、現在の言語空間のなかに並列されている。
当方注 ご参考 吉本隆明著「記紀歌謡論」

言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行
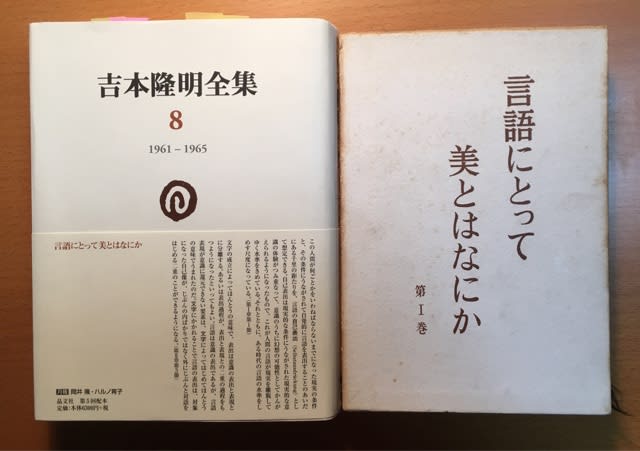
抜粋その2
同書第Ⅲ章 韻律・選択・転換・喩 2 詩的表現より
喩(当方注)
たとえば、いままで喩という言葉や暗喩というコトバを無造作につかってきたが、それは無意識のうちに詩の世界、散文の世界の住人を、あてにしてきたからだ。しかも当てにした住人が、それの応じてくれるものかどうか、あらかじめあきらかではないのである。すでに流通している喩の概念が存在するかもしれないから、それと角遂するにしても包みこむにしても、もともと流通している概念をはっきりさせておかなければならない。
ピエール・ギロー『文体論』(佐藤信夫訳)は、喩についてつぎのようにのべている。
語のあやすなわち転義法(比喩)は、意味の変化である。そのうちでいちばんよく知られているものは、隠喩である。そのほかたとえば、提喩は、白帆といって船を意味するように、部分を全体とみなすものだ。また換喩はお酒のかわりに容器を内容とみなすものである。
転義法のおもなものは、隠喩[メタフォール]、諷喩 [アレゴリイ],引用喩「[アリュジョン],反語法[イロニイ],皮肉[サルカスム],等(当方 以下略)
喩が意味の変化であるということをのぞいては、またしても壁画的分類をみている。欲しいのは壁画ではなく言語本質から喩を理解することである。言語学者の言語観にたいして、破壊するのも、独走するのもなれてしまっているし、感覚的な曲芸にも食傷しているため、このような分類には耳をかたむけるものは、ふくまれていない。
日本現代詩のすぐれた理論家である鮎川信夫『現代詩作法』ははるかに実際的に喩について語っている。
ところが、詩の表現に必要な言語の特性のひとつとして、その代表的なものに比喩があります。比(譬)喩は、直喩(シミリ)と隠(暗)喩(メタフォール)に分けるのが普通であり、若しこの意味の範囲を広くとれば象徴(シンボル)も寓意(アレゴリー)も映像(イメージ)も、すべて比喩的表現のうちに含まれると思いますが、ここではいちおう直喩と隠喩を、その標準単位として考えてゆくことにします。
詩の隠喩は、直喩のばあいと同様、やはり対象に私たちの注意をひきつけ、同時にそれを新しく価値づけるものでなければならないのです。
一つのものと他のものとの類似した関係を把握する能力は、隠喩の場合、ほとんど想像力の働きによるものであり、詩人はかぎられた言葉で無限に変化する自分の観念を示すために、広い想像の領域をもつこの方法を用いるのです。
シュルリアリストの隠喩的表現はかたちのうえでは『隠喩』であっても詩の『隠喩』ではなく、そこには『一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す』というはたらきがありません。そこには、異質のもの、あるいは異質の『観念』を同時平面的に並置しただけの、一首の型(パターン)があるだけなのです。
隠喩法には、<もの>と<もの>との対照の観念とともに調和の観念も含まれており、それ自体が独立した表現として一つの全体性を形づくる傾向があります。それは言葉のスピードと経済を本旨とし、すくない言葉で、ある事柄を言いつくそうとする心があると言えましょう。
隠喩についてのすべての定義に共通している観念は、『一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す』ということです。そしてこの『別の意味に移す』という働きが、直喩と隠喩を区別する最も大切な点なのです。
(略)
さきに鮎川信夫は、シュルリアリストの隠喩的な表現は、形のうえでは隠喩であるが、そこには「一つの言葉を、通常の意味から別の意味に移す」という働きがないから喩とはいえず一種の型だとのべている。いままで考察してきたところでは、シュルリアリストは、ただ、指示表出と自己表出のないまぜられた言語構造を、自己表出の機能を極端に緊張させてつかっているにほかならないから、このばあいの喩は(自己表出としての)意味喩または像的な喩とよぶことができる。喩は言語をつかって探索をおこなう意識の探索であり、たまたま遠方にあるようにみえる言語が闇のなかからうかんできたり、たまたま近くにあるともおもわれた言語が遠方にに訪問したりしながら、言語を意識からおしださせる根源である現実世界にたいして、人間の幻想が生きている仕方ともっともぴったりと適合したとき、探索は目的に当たり、喩として抽出される。
(1) 運命は
屋上から身を投げる少女のように
僕の頭上から落ちてきたのである 黒田三郎「もはやそれ以上」)
((2)(3)略)
これらのいわゆる直喩や暗喩は意味にアクセントをおいれあらわれた意味的な喩である。運命が自分の身上を訪れたという観念的な意味を、現実的にうらずけるために、「屋上から身を投げる少女のように」という直喩的なおきかえがつかわれる(1)。これは意味のアクセントでつかわれているから、屋上から身を投げる少女の像ではなくて、恋か生活苦か何かいわば失意によって屋上から投身自殺した少女の行為の意味にアクセントをおいて、「僕」に訪れた「運命」と連合されていると、みることができる。
(4) 靄は、街のまぶた
夜明けの屋根は 山高帽子
曇りガラスの二重窓をひらいて
僕は無精ひげの下にシガレットをくわえる (北村太郎「ちいさな瞳」)
((5)略 )
(4)はいわゆる暗喩で、(5)は直喩だが、これらが像的な喩であることに言語本質からの喩としての意味がかかっている。
(4)で「靄」と「まぶた」とは<意味>として結びつくことができないから、意味的な喩としては、ふたつは結びつくことができそうもない。靄が、地面や家々のあいだを白く垂れ込めている像は、あたかも上のまぶたをとじる像とむすびつくことができるため、像的な喩としてはじめて連合される。第二行の「屋根」と「山高帽子」もまったくおなじで<意味>としてだけかんがえれば、どのように自在な意識の暗闇もこのふたつをおなし表出に連合させることはできないが、夜明けのまだ薄明かりの街の屋根屋根の像は、黒い山高帽子の像と結びつくことができるため、ふたつの言語はまねきよせられて喩を形成しているということができる。
夜明けの屋根と山高帽子のあいだの像的な喩はこの詩人の西欧的な嗜好をすめすにすぎないだろうが、「まぶた」と「靄」との連合は、「まぶた」がただちに実体をしめすとともに、<まぶたの母>というように観念的な意味をあたえられることをかんがえると、おそらくこの詩人の深いところから喚びよせられているのである。
(略)
価値としての言語において、わたしたちは、現在の言語の水準をかんがえるかぎり、本質的にはいままでみてきたものの外の喩の表現に出遇うことはできない。ただ、類型をふやし喩としての多様さを壁画のように、ひとりの詩人がうまれるごとにひとつづつ殖やしていくことはできても、言語構造自体をこれ以上すすめることはできない。また、これ以上の喩の形態を考察する必要はないとかんがえられる。じっさいの文学(詩)作品でわたしたちがぶつかるのは、いままであたってきた喩がつぎつぎに繰りだされる波のようなうねりであり、また、それによる共鳴(Resonanz)や相乗(Synergie)の効果にほかならない。
(略)
(8) どこか遠いところで
夕日が燃えつきてしまった
かかえきれぬ暗黒が
あなたの身体のように
重たく僕の腕に倒れかかる (鮎川信夫「淋しき二重」)
当方注 「淋しき二重」が収録されている鮎川信夫全詩集
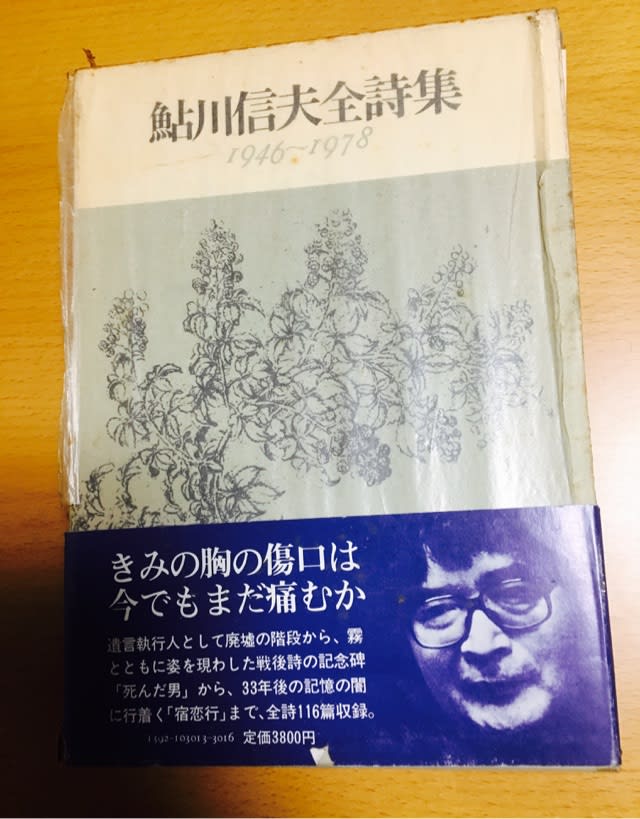
(9、10略)
おそらく、喩は言語表現にとって現在のところもっとも高度な選択であり、言語がその自己表出のはんいをどこまでもおしあげようとするところにあらわれる。<価値>としての言語のゆくてを見さだめたい欲求、予見にまでたかめることができるものとすれば、わたしたちは自己表出としての言語がこの方向にどこまでもすすむことをいいうるだけである。そして、たえず<社会>とたたかいながら死んだり変化したりしなければならない指示表出としての言語との交錯するところに価値があらわれ、ここに喩と価値とのふしぎなななめにおかれた位相と関係が描かれる。
(略)
抜粋その3
同書第Ⅲ章 韻律・選択・転換・喩 4 散文的表現より
選択(当方注)
わたしたちは、めぐるべき螺旋の階段をひとめぐりしてきたようだ。まえに、価値としての言語というように、散文作品の断片をとりあつかったときよりはるかによく視えるところから散文作品をあつかうことができるはずである。わたしたちは、喩と喩における韻律のはたらきと、言語における韻律のはたらきをながめることによって、つぎのようなことをみてきたのである。ひとつは、ある作品のなかで場面の転換はそのままの過程として抽出せられたとき喩の概念にまで連続してつながっており、また、喩はその喩的な本質にまで抽出せられない以前では、たんなる場面の転換にまでつながっているということである。喩の抽出がすでに習慣まで通常化したものが、たとえば、ギローが『文体論』であげているような隠喩・諷喩・引用喩・反語法……などといったような修辞的な区別となる。そして、喩の概念が縮退した状態をかんがえれば、たんなる場面の転換というところにたっする。
それならば、場面の転換が縮退したところ、あるいはより混沌とした未分化なところを想定すれば、なにが残るのだろうか。
これにはきわめて興味ある挿話を想い出したほうがいい。以前にある文芸評論家が、「南極探検」の記録映画が公開されたとき、任意にとられたフィルムをつなぎあわせたようなその映画は、映画でなければとれないような技巧が使われていないから記録映画であるかもしれないが、記録芸術ではないと評した。これのたいして、ある哲学者が、そんな馬鹿なことはない、赤ん坊や白痴は人間でなければできないような高度な活動をなしえないからとて人間ではないと云うことができようか、それは、芸術か非芸術かのもんだいではなく、いい芸術かそうでない芸術化のもんだいにすぎないと反駁した。
もちろん、哲学者のほうがまともにもんだいをとらえていたのだ。なぜならば、たんに任意にとったフィルムをつなぎあわせたにすぎないようなその「南極探検」の映画も、場面を意識的にしろ無意識的にしろ選択したところですでに初原的な美のもんだいが成り立っているからである。なぜ、「宗谷」丸の背景に氷山と空をえらび、前景にペンギンの群れを、しかじかの角度からえらんだかというところに。
言語の表現のもんだいも、自己表出の意識としてべつもんだいではない。言語の場面の転換の縮退したところには、場面そのものの選択ということがのこるのである。
(略)
(5)いいか、ここにあるものはなんでも持っていけ、アメや野郎にとられるよりは、みんな持っていけ、とわめく魚雷班兵曹のくしゃくしゃになった顔を踏みつけるように、突如ザッザッと銃剣をつけた水兵たちの一隊があらわれて何処にいくのか、軍需部の岸壁を速足で行進していき、なんだあいつら、戦争に負けたというのに、と鹿島明彦の背後で酔いつぶれていた兵曹がひどく血走った眼をあげて呟いた。
(井上光晴「虚構のクレーン」)
これも場面の転換とかんがえていい。作者は、まず、「ここにあるものはなんでも持って
いけ、アメ野郎にとられるよりは、みんな持っていけ」とわめく魚雷班兵曹に移行し、つぎ
に、とつぜん作者の位置にかえって銃剣をつけた水兵の一隊の行進を描写し、また、とつぜん「なんだあいつら、戦争に負けたというのに」とつぶやく兵曹に転換し、さいごの「ひどく血走った眼をあげて呟いた」でその<兵曹>を対象に転化するため作者の位置にもどって描写したうえで、この文章はおわっている。その人称転換は複雑をきわめており、このめまぐるしい転換が喩として抽象しうるまでになっていないが像や意味のうねりをかたちづくっている。
言語の表現は、作家がある場面を対象としてえらびとったということからはじまっている。これは、たとえてみれば、作者が現実世界のなかで、<社会>とのひとつの関係をえらびとったこととおなじ意味性をもっている。そして、つぎに言語における場面の転換がこの底辺からより高度に抽出されたものとしてやってくる。この意味は作家の現実世界のなかで、<社会>との動的な関係のなかに意識的にまた無意識的にはいりこんでいることに、たどることができる。
さらに、場面の転換からより高度に抽出されたものとして喩が存在している。その喩のもんだいは作家の現実世界で、現に<社会>との動的な関係にある自己自身を外におかれた存在とみなし、本来的な自己を奪回しようとする無意識の欲求にかられていることににている。
このようにして、わたしたちは現在、韻律を根源において、場面の選択というもっとも底辺にあるもんだいから、場面の転換をへて、言語の現在的水準としてもっとも高度な喩のもんだいにまで螺旋状にはせのぼり、また、はせくだる表現の定形をもっている。そして、表現としての言語がつみかさねてきたこれらの過程は、現在の水準のなかにすべて潜在的には封じこめられているとみることができる。そして、これが、指示表出としての言語が<意味>の構成としてもつ思想的ひろがりと交錯するところに詩的空間・散文的空間の現在的水準がくりひろげられている。
まだ、唱うべき対象をえらびとることができないままに表現された記紀歌謡のような古代人の世界から、すでに高度な喩をつかって現実に選択している<社会>との関係を否定しそれを超えようとする欲求を表出している現代の文学の世界にいたるまでのげんごのつみかさねられてきた長い過程は、いままで、言語を成り立たせてる共通の基盤として分析してきた特性として、現在の言語空間のなかに並列されている。
当方注 ご参考 吉本隆明著「記紀歌謡論」










