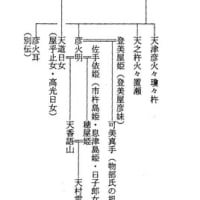現代の私たちにもなじみのある「秋の七草」は万葉集巻八の旋頭歌によって伝えられたものです。
山上臣憶良、秋の野の花を詠む歌二首
1537 秋の野に咲きたる花を指(および)折りかき数(かぞ)ふれば七草の花
1538 萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 をみなへし また藤袴 朝顔の花
4500余首ある万葉歌の中で現代人にも口ずさめる数少ない歌の一つでしょう。
この歌が暗号歌とは長い年月誰にも気付かれることはありませんでしたが口承ある
いは口誦させることを目的とした歌ならば非常にうまく出来た歌だろうと思います
美しいもの可憐さを好む女性向きの愛唱歌足りうること。
秋の七草を供え仲秋の名月を愛でる風習の起源らしいこと。
「秋」は季語のみに使われたわけでなく、記紀では「豊秋津島」と日本を表す
言葉として用いられています。
現代は「秋の七草」と表記しますが万葉集では「秋の七種」と記し七種類ある
いは七種族とも理解できるように考えられています。
この歌が長く伝承された上で後の世の人が暗号と気づいて欲しいと願った人物が憶
良の他にもおりました。万葉集の歌人であり編纂者でもある大伴家持です。
山上憶良が74歳で死去した西暦733年、大伴家持はまだ15歳の少年でしたが
太宰師(太宰府の長官)であった父・大伴旅人と憶良は筑紫歌壇を形成しつつ親し
く交友しておりました。当然家持少年にとって憶良は尊敬の念や親愛の情を抱かせ
る人物だったでしょう。
万葉集には憶良が重い病の床にあって涙ながらに詠んだと伝えられる辞世歌
士(をのこ)やも空しくあるべき万代に語り継ぐべき名はたてずして
が載っていますが、その17年後に家持はこの辞世歌に和す「勇士の名を振るはむ
ことを慕(ねが)ふ歌」を作りました。その中で「・・・さしまくる心障らず後の
世の語り継ぐべく名を立つべしも」「ますらをは名をし立つべし後の世に聞き継ぐ
人も語り継ぐがね」と「後の世」「名を立てる」「語り継ぐ」等、憶良の想いを伝
えるべく明確な意志を示す宣言歌を残しています。
この壮大な暗号の仕掛けは大伴家持の存在が無かったらあり得なかっただろうと思
います。
次回は憶良の辞世歌と家持の追和歌について通釈とは違う研究レポートを載せたい
と思います。
山上臣憶良、秋の野の花を詠む歌二首
1537 秋の野に咲きたる花を指(および)折りかき数(かぞ)ふれば七草の花
1538 萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 をみなへし また藤袴 朝顔の花
4500余首ある万葉歌の中で現代人にも口ずさめる数少ない歌の一つでしょう。
この歌が暗号歌とは長い年月誰にも気付かれることはありませんでしたが口承ある
いは口誦させることを目的とした歌ならば非常にうまく出来た歌だろうと思います
美しいもの可憐さを好む女性向きの愛唱歌足りうること。
秋の七草を供え仲秋の名月を愛でる風習の起源らしいこと。
「秋」は季語のみに使われたわけでなく、記紀では「豊秋津島」と日本を表す
言葉として用いられています。
現代は「秋の七草」と表記しますが万葉集では「秋の七種」と記し七種類ある
いは七種族とも理解できるように考えられています。
この歌が長く伝承された上で後の世の人が暗号と気づいて欲しいと願った人物が憶
良の他にもおりました。万葉集の歌人であり編纂者でもある大伴家持です。
山上憶良が74歳で死去した西暦733年、大伴家持はまだ15歳の少年でしたが
太宰師(太宰府の長官)であった父・大伴旅人と憶良は筑紫歌壇を形成しつつ親し
く交友しておりました。当然家持少年にとって憶良は尊敬の念や親愛の情を抱かせ
る人物だったでしょう。
万葉集には憶良が重い病の床にあって涙ながらに詠んだと伝えられる辞世歌
士(をのこ)やも空しくあるべき万代に語り継ぐべき名はたてずして
が載っていますが、その17年後に家持はこの辞世歌に和す「勇士の名を振るはむ
ことを慕(ねが)ふ歌」を作りました。その中で「・・・さしまくる心障らず後の
世の語り継ぐべく名を立つべしも」「ますらをは名をし立つべし後の世に聞き継ぐ
人も語り継ぐがね」と「後の世」「名を立てる」「語り継ぐ」等、憶良の想いを伝
えるべく明確な意志を示す宣言歌を残しています。
この壮大な暗号の仕掛けは大伴家持の存在が無かったらあり得なかっただろうと思
います。
次回は憶良の辞世歌と家持の追和歌について通釈とは違う研究レポートを載せたい
と思います。