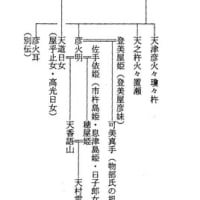聖徳太子が四天王を彫り物部守屋軍との戦いに戦勝祈願をしたところ勝利することが出来
(587年)、そのお礼として難波の四天王寺が創建されました(593年)。また、聖徳太子
の廷臣である秦河勝が太子から仏像を賜り、それを本尊(弥勒菩薩)として603年に建立し
たのが京都・太秦の広隆寺(蜂岡寺・秦寺・葛野寺とも)です。どちらも聖徳太子ゆかり
の寺ですが、このふたつの寺に牛祭(うしまつり)と呼ばれる奇祭が伝えられています。
①四天王寺の牛祭り

四天王寺の牛まつりは「どやどや」と称される裸まつりで、元旦から14日まで天下太平
五穀豊穣を祈願する修正会の法要が亀の池の前の六時堂(現講堂)で行われるが、この法要
中に祈祷された<牛王宝印>の護符をお堂の縁の天井から撒きそれを奪い合うという風習
がいつの頃からか始まり今日まで続いています。
<牛王宝印>を押した何百枚もの護符を群衆の中に投じるとそれを取ろうとして東西から
裸の人々がひしめきあいまことに勇ましい行事らしい。
この護符は柳の枝に差して帰るが、昔はこの枝を稲田に立てておくと悪虫がつかず豊作に
なったと言われ、「どやどや」の名称は俗に牛王宝印を受けんとしてどやどやと群衆が集
まることから起こったといわれています。
昔は酉の刻(6時)からはじまり、お札を投じるのは夜8時から9時頃であったが最近は
混乱を避けるため近隣の中高生や園児たちによって午後行われるという。
②広隆寺の牛祭り

広隆寺の牛まつりは境内にある大避(おおさけ・大酒)神社の奇祭で、元は旧暦9月(現
在10月)12日夕刻より広隆寺の境内に町内の代表者が裃姿で集まってくると、そこに
白塗りの面を被り白装束の異形の神が雄牛に乗って登場する。この神が摩多羅神(またら
じん)で(赤鬼2青鬼2)4人の鬼(四天王)を従えている。
行列は神灯、囃子方、松明を先頭に特異な面をつけた摩多羅神(インド伝来の神)が牛の
背に乗り(江戸時代の絵図には後ろ向きに乗っている)、白装束の四天王と共に西門から
出て三条通りを東に移動、薬師堂前の祭壇を三周し、長い祭文を独特な調子で読み上げる
が、これに参拝者が悪口雑言を浴びせる。祭文を読み終えると摩多羅神と四天王は堂内に
駆け込み祭りは終了するという。
聖徳太子と深い縁のある四天王寺と広隆寺の<牛祭り>。
祭りの形態は全く違いますが
①の四天王寺の場合は<牛王宝印>の護符の<牛>。
②の広隆寺の場合は<摩多羅神>を乗せる<牛>。
このふたつの牛が重要な役割を担っていると思われます。そして四天王を登場させることに
よってふたつの<牛祭り>に関わりのあることを暗示しているようです。
前回のブログでこのふたつの<牛祭り>が西域のホータン(和田・于闐)と繋がっていると推量
した理由を述べてみたいと思います。
現在のホータンは中国・新疆自治区に属していますが、玄奘三蔵(602~664)の『大唐西域記』
には瞿薩旦那国(クスターナ)と記されており、その建国説話から毘沙門天の国・地乳の国とも
解されていました。玄奘三蔵も『大唐西域記』も唐の時代の中国の人、書ですから漢字を用いて
表記していますが、彼らが中国以外の言語を表記する必要がある場合には耳で聞き取った言葉を
音の似ている漢字を宛てて表記しました。これを音写といいます。さらに音写された漢文が日本
に伝来しました。日本人は日本語で話しますから漢文をさらに日本流に読み換えて通用させてい
ます。音写された外来語が日本に伝わり、それを漢字の意味でもって理解しようとしたら全く元
の意味が通じる訳がありません。
このことを気づかせてくれたのが西域の研究者として著名な故・羽田明氏の解説でした。
それは玄奘三蔵より200年ほど前に中国から求法の旅に出て西域→中インド→中国へ帰った
法顕(337~422)の『仏国記』(『法顕伝』とも)の中で、ホータンに立ち寄った際に<瞿摩
帝寺の釈迦誕生祭「行使の儀式」>を見て、その光景を記していますが、それを解説した羽田氏
は<瞿薩旦那国><瞿摩帝>が<梵語(古代インドの文章語。サンスクリット)>を音写したも
のであると説き、その意味をも示していました。
*「瞿薩旦那国」は梵語の「ゴースタナ」の音写
*「ゴースタナ」の意味は「牛の国」
*「瞿摩帝」は梵語の「ゴーマティ」の音写
*「ゴーマティ」は「牛の糞」の意味
仏教で牛は神聖な動物であり「ゴーマティ」は神聖な物とされている。
私の子供の頃は車社会ではなかったので公道を牛や馬が荷車をひいて通っていました。当然な
がら道には牛馬が糞を落として行き、不潔な代物を始末することが必要でした。馬はともかく牛
糞は固形状ではなくて大変いやな思いをしましたので、「牛の糞」を神聖なものと考えることは
出来ません。ところが広隆寺の牛祭りが始まったころには、「牛の糞」が神聖なものと正確に
伝えられていたらしい絵図が残されています。

上図は江戸時代(1790年)に発行された『都名所図会』「太秦牛祭図絵」ですが、詞書には「9月
12日太秦牛祭聖徳太子はじめて執行ひたまひ祭文は弘法大師の作りたまふといひ伝え侍る」の文
字が確認できます。この絵をよく見ると牛の背にまたがる摩多羅神の足の向きから判断して後ろ向
きに乗っている事が判ります。普通にはあり得ない姿ですが、「瞿薩旦那国」の「瞿摩帝」つまり
神聖な「牛の糞」の意味が正確に認識されていたために、牛のお尻に背を向けたら失礼に当たると
考えた結果後ろ向きに乗ったとしか思えません。聖徳太子とホータン(瞿薩旦那国)が繋がってい
る証でしょう。

上図も明治か大正時代の牛祭りの貴重な写真ですが、摩多羅神は前を向いて乗っています。
私は四天王寺や広隆寺のふたつの牛祭りを見たことがないのでネットで情報を集めましたが、拝見
した中に大変参考になる指摘をされているブログがありました。
「梅原猛著『うつぼ船1翁と河勝』からー蘭鋳郎の日常から/ウエブリブブログ」
広隆寺の牛祭りー蘭鋳郎の日常から/ウエブリブブログ」
から「牛祭り」の考察の要旨を紹介しますと<「牛祭」は従来の日本型の祭りにあてはまらない>
としその理由をあげています。
①牛を祭りの主役とする。
②周囲から神を貶めるような野次を浴びせる。
これは中近東から中央アジアに見られる形式である。
③広隆寺の弥勒菩薩像・宝髻弥勒像には衣裳の部分に牛の皮が用いられている異例の造りである。
関心のある方にお勧めしたいブログです。
摩多羅神についても良く判らない神ですが、「5-(21)広隆寺と摩多羅神~すべては古事記か
ら~」というブログで摩多羅神とは<ミトラ神>では?という説も参考になりそうです。
*ミトラ神はインドではマイトレーヤー」と呼ばれそれが仏教に取り込まれ弥勒菩薩となった。
広隆寺の創建当初の本尊は弥勒菩薩。(現在は聖徳太子)。
*牛祭で摩多羅神は牛に乗るが、ミトラ神も牛に深い関わりがある。
*仮面につかわれる青・赤・白は過去・現在・未来を表し、摩多羅神は白。未来仏の弥勒菩薩に
対応している。
もうひとつの
四天王寺の牛祭り「どやどや」がホータンと係わりがあろうと思った理由は、法顕が見たという
釈迦誕生祭の行われた<瞿摩帝寺>の<瞿摩帝>です。梵語では「ゴーマティ」で「牛の糞」との
事ですが、これが日本に伝えられた時に「牛の糞」とは受け入れ難かった人々がいて、<瞿摩>は
<牛>。<帝>を(帝王・みかど・皇帝)の意味に解釈し<瞿摩帝>=<牛王>とした可能性があり
ます。そのために「どやどや」では<牛王宝印>のお札が撒かれるようになったと思うのです。
四天王寺の牛祭りで撒かれる<牛王宝印>の護符は紀州・熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社
・熊野那智大社)で配布される神符です。
(587年)、そのお礼として難波の四天王寺が創建されました(593年)。また、聖徳太子
の廷臣である秦河勝が太子から仏像を賜り、それを本尊(弥勒菩薩)として603年に建立し
たのが京都・太秦の広隆寺(蜂岡寺・秦寺・葛野寺とも)です。どちらも聖徳太子ゆかり
の寺ですが、このふたつの寺に牛祭(うしまつり)と呼ばれる奇祭が伝えられています。
①四天王寺の牛祭り

四天王寺の牛まつりは「どやどや」と称される裸まつりで、元旦から14日まで天下太平
五穀豊穣を祈願する修正会の法要が亀の池の前の六時堂(現講堂)で行われるが、この法要
中に祈祷された<牛王宝印>の護符をお堂の縁の天井から撒きそれを奪い合うという風習
がいつの頃からか始まり今日まで続いています。
<牛王宝印>を押した何百枚もの護符を群衆の中に投じるとそれを取ろうとして東西から
裸の人々がひしめきあいまことに勇ましい行事らしい。
この護符は柳の枝に差して帰るが、昔はこの枝を稲田に立てておくと悪虫がつかず豊作に
なったと言われ、「どやどや」の名称は俗に牛王宝印を受けんとしてどやどやと群衆が集
まることから起こったといわれています。
昔は酉の刻(6時)からはじまり、お札を投じるのは夜8時から9時頃であったが最近は
混乱を避けるため近隣の中高生や園児たちによって午後行われるという。
②広隆寺の牛祭り

広隆寺の牛まつりは境内にある大避(おおさけ・大酒)神社の奇祭で、元は旧暦9月(現
在10月)12日夕刻より広隆寺の境内に町内の代表者が裃姿で集まってくると、そこに
白塗りの面を被り白装束の異形の神が雄牛に乗って登場する。この神が摩多羅神(またら
じん)で(赤鬼2青鬼2)4人の鬼(四天王)を従えている。
行列は神灯、囃子方、松明を先頭に特異な面をつけた摩多羅神(インド伝来の神)が牛の
背に乗り(江戸時代の絵図には後ろ向きに乗っている)、白装束の四天王と共に西門から
出て三条通りを東に移動、薬師堂前の祭壇を三周し、長い祭文を独特な調子で読み上げる
が、これに参拝者が悪口雑言を浴びせる。祭文を読み終えると摩多羅神と四天王は堂内に
駆け込み祭りは終了するという。
聖徳太子と深い縁のある四天王寺と広隆寺の<牛祭り>。
祭りの形態は全く違いますが
①の四天王寺の場合は<牛王宝印>の護符の<牛>。
②の広隆寺の場合は<摩多羅神>を乗せる<牛>。
このふたつの牛が重要な役割を担っていると思われます。そして四天王を登場させることに
よってふたつの<牛祭り>に関わりのあることを暗示しているようです。
前回のブログでこのふたつの<牛祭り>が西域のホータン(和田・于闐)と繋がっていると推量
した理由を述べてみたいと思います。
現在のホータンは中国・新疆自治区に属していますが、玄奘三蔵(602~664)の『大唐西域記』
には瞿薩旦那国(クスターナ)と記されており、その建国説話から毘沙門天の国・地乳の国とも
解されていました。玄奘三蔵も『大唐西域記』も唐の時代の中国の人、書ですから漢字を用いて
表記していますが、彼らが中国以外の言語を表記する必要がある場合には耳で聞き取った言葉を
音の似ている漢字を宛てて表記しました。これを音写といいます。さらに音写された漢文が日本
に伝来しました。日本人は日本語で話しますから漢文をさらに日本流に読み換えて通用させてい
ます。音写された外来語が日本に伝わり、それを漢字の意味でもって理解しようとしたら全く元
の意味が通じる訳がありません。
このことを気づかせてくれたのが西域の研究者として著名な故・羽田明氏の解説でした。
それは玄奘三蔵より200年ほど前に中国から求法の旅に出て西域→中インド→中国へ帰った
法顕(337~422)の『仏国記』(『法顕伝』とも)の中で、ホータンに立ち寄った際に<瞿摩
帝寺の釈迦誕生祭「行使の儀式」>を見て、その光景を記していますが、それを解説した羽田氏
は<瞿薩旦那国><瞿摩帝>が<梵語(古代インドの文章語。サンスクリット)>を音写したも
のであると説き、その意味をも示していました。
*「瞿薩旦那国」は梵語の「ゴースタナ」の音写
*「ゴースタナ」の意味は「牛の国」
*「瞿摩帝」は梵語の「ゴーマティ」の音写
*「ゴーマティ」は「牛の糞」の意味
仏教で牛は神聖な動物であり「ゴーマティ」は神聖な物とされている。
私の子供の頃は車社会ではなかったので公道を牛や馬が荷車をひいて通っていました。当然な
がら道には牛馬が糞を落として行き、不潔な代物を始末することが必要でした。馬はともかく牛
糞は固形状ではなくて大変いやな思いをしましたので、「牛の糞」を神聖なものと考えることは
出来ません。ところが広隆寺の牛祭りが始まったころには、「牛の糞」が神聖なものと正確に
伝えられていたらしい絵図が残されています。

上図は江戸時代(1790年)に発行された『都名所図会』「太秦牛祭図絵」ですが、詞書には「9月
12日太秦牛祭聖徳太子はじめて執行ひたまひ祭文は弘法大師の作りたまふといひ伝え侍る」の文
字が確認できます。この絵をよく見ると牛の背にまたがる摩多羅神の足の向きから判断して後ろ向
きに乗っている事が判ります。普通にはあり得ない姿ですが、「瞿薩旦那国」の「瞿摩帝」つまり
神聖な「牛の糞」の意味が正確に認識されていたために、牛のお尻に背を向けたら失礼に当たると
考えた結果後ろ向きに乗ったとしか思えません。聖徳太子とホータン(瞿薩旦那国)が繋がってい
る証でしょう。

上図も明治か大正時代の牛祭りの貴重な写真ですが、摩多羅神は前を向いて乗っています。
私は四天王寺や広隆寺のふたつの牛祭りを見たことがないのでネットで情報を集めましたが、拝見
した中に大変参考になる指摘をされているブログがありました。
「梅原猛著『うつぼ船1翁と河勝』からー蘭鋳郎の日常から/ウエブリブブログ」
広隆寺の牛祭りー蘭鋳郎の日常から/ウエブリブブログ」
から「牛祭り」の考察の要旨を紹介しますと<「牛祭」は従来の日本型の祭りにあてはまらない>
としその理由をあげています。
①牛を祭りの主役とする。
②周囲から神を貶めるような野次を浴びせる。
これは中近東から中央アジアに見られる形式である。
③広隆寺の弥勒菩薩像・宝髻弥勒像には衣裳の部分に牛の皮が用いられている異例の造りである。
関心のある方にお勧めしたいブログです。
摩多羅神についても良く判らない神ですが、「5-(21)広隆寺と摩多羅神~すべては古事記か
ら~」というブログで摩多羅神とは<ミトラ神>では?という説も参考になりそうです。
*ミトラ神はインドではマイトレーヤー」と呼ばれそれが仏教に取り込まれ弥勒菩薩となった。
広隆寺の創建当初の本尊は弥勒菩薩。(現在は聖徳太子)。
*牛祭で摩多羅神は牛に乗るが、ミトラ神も牛に深い関わりがある。
*仮面につかわれる青・赤・白は過去・現在・未来を表し、摩多羅神は白。未来仏の弥勒菩薩に
対応している。
もうひとつの
四天王寺の牛祭り「どやどや」がホータンと係わりがあろうと思った理由は、法顕が見たという
釈迦誕生祭の行われた<瞿摩帝寺>の<瞿摩帝>です。梵語では「ゴーマティ」で「牛の糞」との
事ですが、これが日本に伝えられた時に「牛の糞」とは受け入れ難かった人々がいて、<瞿摩>は
<牛>。<帝>を(帝王・みかど・皇帝)の意味に解釈し<瞿摩帝>=<牛王>とした可能性があり
ます。そのために「どやどや」では<牛王宝印>のお札が撒かれるようになったと思うのです。
四天王寺の牛祭りで撒かれる<牛王宝印>の護符は紀州・熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社
・熊野那智大社)で配布される神符です。