
ラミーカミキリ。
黒と薄緑色のコントラストが鮮やかなカミキリムシです。
見つけたのは、隣の畑のヘリ。
以前から、気を付けてみていたんですが。
この近所にも分布が広がってきたのかも知れませんね。
分類:コウチュウ目カミキリムシ科フトカミキリ亜科
体長:10~15mm
分布:本州(関東以西)、四国、九州
平地~低山地
成虫の見られる時期:5~7月中旬
幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:カラムシ、ラミー(ナンバンカラムシ)、ヤブマオ、ムクゲ、フヨウ、シナノキ,
コモンマロウなど
成虫・・・葉、特に葉裏の葉脈を好む
幼虫・・・茎~根
その他:体色は黒色で、水色の微毛で覆われ、黒と薄緑色のコントラストが鮮やか。
前胸背板に一対の黒紋がある。
前翅の中央後方に水色~黄緑色の横帯があるが、前翅全体が黒色の個体もあるなど、変異が大きい。
♀はより体が太く、触角が短い。
名前の「ラミー」は、ナンバンカラムシとも呼ばれる植物で、江戸時代、繊維をとるために、長崎から輸入された植物。
その際、一緒に入って来た外来種と考えられている。
(「朝鮮の役」の際、朝鮮経由で九州に入ったとの説あり。)
太平洋戦争中、ラミーの栽培が盛んになったことにより、分布を広げたという。
茨城県では近年、県央部を中心に分布が拡大してきた。
分布は、冬季の平均気温4℃の線以南とほぼ一致すると言われる。
かつてはキョンシーに似ているということで話題になったこともある。
最近では「パンダ」「ロボット」「ガイコツ」「ガチャピン」など、様々な表現がされている。
昼行性。
人の気配に敏感で、飛び立ったり、葉裏に隠れたりする。
樹林と林縁、水田周辺の土手、路傍など、食草の群生する場所に見られる。
♀は食草の茎などをかじって傷をつけ、産卵する。
孵化した幼虫は茎内部を喰い進み、晩秋には根に入って越冬する(非休眠)。
翌春に地下で蛹化する。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版・刊)
かたつむりの自然観撮記
Wikipedia
侵入生物データベース
ねとらぼ
カミキリ情報館
黒と薄緑色のコントラストが鮮やかなカミキリムシです。
見つけたのは、隣の畑のヘリ。
以前から、気を付けてみていたんですが。
この近所にも分布が広がってきたのかも知れませんね。
分類:コウチュウ目カミキリムシ科フトカミキリ亜科
体長:10~15mm
分布:本州(関東以西)、四国、九州
平地~低山地
成虫の見られる時期:5~7月中旬
幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:カラムシ、ラミー(ナンバンカラムシ)、ヤブマオ、ムクゲ、フヨウ、シナノキ,
コモンマロウなど
成虫・・・葉、特に葉裏の葉脈を好む
幼虫・・・茎~根
その他:体色は黒色で、水色の微毛で覆われ、黒と薄緑色のコントラストが鮮やか。
前胸背板に一対の黒紋がある。
前翅の中央後方に水色~黄緑色の横帯があるが、前翅全体が黒色の個体もあるなど、変異が大きい。
♀はより体が太く、触角が短い。
名前の「ラミー」は、ナンバンカラムシとも呼ばれる植物で、江戸時代、繊維をとるために、長崎から輸入された植物。
その際、一緒に入って来た外来種と考えられている。
(「朝鮮の役」の際、朝鮮経由で九州に入ったとの説あり。)
太平洋戦争中、ラミーの栽培が盛んになったことにより、分布を広げたという。
茨城県では近年、県央部を中心に分布が拡大してきた。
分布は、冬季の平均気温4℃の線以南とほぼ一致すると言われる。
かつてはキョンシーに似ているということで話題になったこともある。
最近では「パンダ」「ロボット」「ガイコツ」「ガチャピン」など、様々な表現がされている。
昼行性。
人の気配に敏感で、飛び立ったり、葉裏に隠れたりする。
樹林と林縁、水田周辺の土手、路傍など、食草の群生する場所に見られる。
♀は食草の茎などをかじって傷をつけ、産卵する。
孵化した幼虫は茎内部を喰い進み、晩秋には根に入って越冬する(非休眠)。
翌春に地下で蛹化する。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版・刊)
かたつむりの自然観撮記
Wikipedia
侵入生物データベース
ねとらぼ
カミキリ情報館










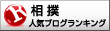
















コモンマロウにも来るんですか?
アオイ科ですもんね。
データに追加させて頂きます。