
ハイイロヤハズカミキリ。
コンビニの駐車場で、ひっくり返っているところを拾いました(笑)
ホワイトバックに挑戦?

失敗しました。
_| ̄|○
A4の紙じゃぁね(笑)

フレーム・アウト(笑)

この辺が矢筈(やはず)の形。
矢の端の弓弦をつがえるところ。

肩に窪みがある。

前胸背はシワシワ。
翅にうっすらとアーチ模様が浮かぶ。

分類:
コウチュウ目カブトムシ亜目ハムシ上科カミキリムシ科フトカミキリ亜科
体長:
11~21mm
分布:
本州、四国、九州、南西諸島(沖縄島以北)
平地~丘陵
成虫の見られる時期:
4~8月(年1化)
秋に羽化し、翌春、食樹から出てくる
エサ:
幼虫・・・マダケ、メダケ、モウソウチク、アズマネザサ、ネザサ、ミヤコザサ、ヤダケ、リュウキュウチク、ホウライチクなどのタケ類(枯れたもの、伐採したもの)、アシ、ススキ
成虫・・・枯れたタケ類
※麦の穂に集まるとの情報もある
その他:
翅端は矢羽根のように突き出しており(矢筈)、これが和名の由来となっている。
体色は黒色、灰黄色の微毛で密に覆われる。
前胸背板には不規則な縦隆がある。
上翅には白色の小紋を散布するが、特に中央部側縁に多く、基部近くに瘤状の隆起がある。
体下は前胸腹板中央と腹節に灰白色の微毛が多く、灰黄色の小紋を散らす。
♀の触角は翅端に明らかに届かない。
東北地方には類似種がいる。
樹上性で、樹林と林縁、社寺林、公園、伐採地、貯木場などで見られる。
灯りに飛来する。
飛翔は比較的緩やかで、活動はあまり活発でない。
日中は草の茎や木の枝などにしがみついてじっとしている。
普通種だが、個体数はそれほど多くない。
枯れて灰色になったタケ類に横真一文字の産卵痕を残す。
産卵痕は目の高さぐらいで見つかることが多いようだ。
早春に、その下を折ると木くずが出て、さらに根元寄りに成虫を見つけることがある。
サビアヤカミキリに習性が似るが、幼虫はより肉の薄い細いタケ類(枯れたもの)を食べる。
(サビアヤカミキリは生きたタケ類を食べる。)
下口節は後半の両側が大きく三角形に赤褐色を呈し、膨出部の前面の傾斜面には、中央近くのもののほか、側方にも左右2本ずつの長剛毛がある。
(サビアヤカミキリ幼虫は、下口節が大部分淡黄色、縫合線に沿う部分は黒褐色。
膨出部の頂の線は後方にふくれた弧状をなす。
その前面は強く傾斜し、その前部の中央近くに左右2本ずつの長剛毛がある。)
胸部と腹部はほとんど無毛。
側板隆起の剛毛は細く、ほとんどのものが2本。
終齢幼虫は頭幅約2.6mm、頭長約3.1mm、体長約25mm。
参考:
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫(文一総合出版)
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
原色日本甲虫図鑑(Ⅳ)(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅰカミキリ編(保育社)
かたつむりの自然観撮記
虫ナビ
昆虫エクスプローラ
KEI's昆虫採集記 我が家的カミキリムシ図鑑
カミキリ情報館
no+e
虫撮る人々
フォト・ギャラリーかみきりむしの季節
コンビニの駐車場で、ひっくり返っているところを拾いました(笑)
ホワイトバックに挑戦?

失敗しました。
_| ̄|○
A4の紙じゃぁね(笑)

フレーム・アウト(笑)

この辺が矢筈(やはず)の形。
矢の端の弓弦をつがえるところ。

肩に窪みがある。

前胸背はシワシワ。
翅にうっすらとアーチ模様が浮かぶ。

分類:
コウチュウ目カブトムシ亜目ハムシ上科カミキリムシ科フトカミキリ亜科
体長:
11~21mm
分布:
本州、四国、九州、南西諸島(沖縄島以北)
平地~丘陵
成虫の見られる時期:
4~8月(年1化)
秋に羽化し、翌春、食樹から出てくる
エサ:
幼虫・・・マダケ、メダケ、モウソウチク、アズマネザサ、ネザサ、ミヤコザサ、ヤダケ、リュウキュウチク、ホウライチクなどのタケ類(枯れたもの、伐採したもの)、アシ、ススキ
成虫・・・枯れたタケ類
※麦の穂に集まるとの情報もある
その他:
翅端は矢羽根のように突き出しており(矢筈)、これが和名の由来となっている。
体色は黒色、灰黄色の微毛で密に覆われる。
前胸背板には不規則な縦隆がある。
上翅には白色の小紋を散布するが、特に中央部側縁に多く、基部近くに瘤状の隆起がある。
体下は前胸腹板中央と腹節に灰白色の微毛が多く、灰黄色の小紋を散らす。
♀の触角は翅端に明らかに届かない。
東北地方には類似種がいる。
樹上性で、樹林と林縁、社寺林、公園、伐採地、貯木場などで見られる。
灯りに飛来する。
飛翔は比較的緩やかで、活動はあまり活発でない。
日中は草の茎や木の枝などにしがみついてじっとしている。
普通種だが、個体数はそれほど多くない。
枯れて灰色になったタケ類に横真一文字の産卵痕を残す。
産卵痕は目の高さぐらいで見つかることが多いようだ。
早春に、その下を折ると木くずが出て、さらに根元寄りに成虫を見つけることがある。
サビアヤカミキリに習性が似るが、幼虫はより肉の薄い細いタケ類(枯れたもの)を食べる。
(サビアヤカミキリは生きたタケ類を食べる。)
下口節は後半の両側が大きく三角形に赤褐色を呈し、膨出部の前面の傾斜面には、中央近くのもののほか、側方にも左右2本ずつの長剛毛がある。
(サビアヤカミキリ幼虫は、下口節が大部分淡黄色、縫合線に沿う部分は黒褐色。
膨出部の頂の線は後方にふくれた弧状をなす。
その前面は強く傾斜し、その前部の中央近くに左右2本ずつの長剛毛がある。)
胸部と腹部はほとんど無毛。
側板隆起の剛毛は細く、ほとんどのものが2本。
終齢幼虫は頭幅約2.6mm、頭長約3.1mm、体長約25mm。
参考:
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫(文一総合出版)
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
原色日本甲虫図鑑(Ⅳ)(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅰカミキリ編(保育社)
かたつむりの自然観撮記
虫ナビ
昆虫エクスプローラ
KEI's昆虫採集記 我が家的カミキリムシ図鑑
カミキリ情報館
no+e
虫撮る人々
フォト・ギャラリーかみきりむしの季節










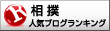
















まさにそんな感じでしょうね。
近くに竹とか笹とか無さそうですけど。
アシでもOKみたいなので、そこが発生源かも知れません。