倫理の起源24
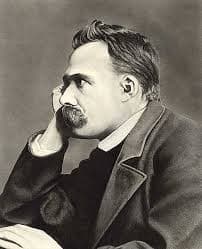
カントの倫理学を批判したあとでは、どうしてもニーチェ思想を批判的に検討しなくてはならない。
まず言っておきたいこと。ニーチェはひとりでたくさんである。こんな矯激で誇大妄想的で狂人に近い思想家は、あとにも先にも存在しない。事実彼は発狂したのだが、処女作『悲劇の誕生』およびその前後の論稿から、すでにその兆候はうかがい知れる。皮肉なタイトルである。この著作はまさに彼の人生にとって「悲劇の誕生」であった。1889年1月3日の路上での昏倒前後、コジマ・ワーグナー夫人はじめ何人かに送った書簡は、不意の精神錯乱の証拠として有名だが、逆に私はそう思わない。そこには、彼の年来の類を絶したこだわりが、ある連続性のもとに刻印されており、ここで突然おかしくなったなどとは言えないのである。
いまそれを追うことはしばらく措くが、ここで言いたいのは、以下の三点である。
第一。この思想家の悲劇が、彼の育った精神風土、文化的背景、彼の生きた時代に深く結びついたものであるということ、
そこで第二。その精神風土や文化的背景や時代の特殊性に想像力を馳せずに、ある抽象レベルで(たとえば「哲学」という名のターミノロジーによって)切り取られた彼の言葉群だけをとらえて合理的な解釈の枠組みの中に安置しようとするような試みは、この思想家の体質がもともとはらんでいた獅子身中の虫(自分や周囲を苛む猛毒)に目を塞ぐ以外のなにものでもないこと。
したがって第三。ニーチェ思想とできるだけ公正につきあうには、彼自身の独特の体臭、踊るようなその文体、大仰で極端な言葉の所作、矛盾も顧みずにやたら繰り出される語彙の驚くべき量とスピード感といったもの、要するに彼固有の思想体質そのものを常に感じとりながら、それに対してお前はどう思うのかとたえず自問するのでなくてはならないこと。
ちなみに右の第二点目に関して一言しておきたい。
一般に、ニーチェは、カントによって暗々裏に用意された認識論上の押さえをさらに一歩進めた哲学者として位置づけられている。カントによれば、世界はもともと現象の多様であり、それをとらえる感性的直観、カテゴリーによる悟性的な把握、さらに進んで純粋理性の統覚によって統合されることで初めて一定の仕方で認識されうる――カントはこの考え方をみずからコペルニクス的転回と呼んだ――が、「物自体」はけっして認識されえない。
これは理性の限界を画定する彼の試みの一つで、これによって人間理性は絶対的な真理そのものには到達しえず、ただそれに向かっての要請のみをもつという立場であるから、一種の相対主義を呼び込むものである。彼自身は人間の認識作用の基礎づけを行なったのだから、もちろん相対主義者ではない。人間の理論理性の限界設定を施したということは、それを超えるものの存在(神あるいは物自体)は実践理性によって承認するほかないと宣告したことでもあり、この承認の絶対感情はカント自身のなかでは、疑い得ないものだった。だがそれでも、このような思考様式が、相対主義を忍び込ませる木戸口を開いていたことは否めない。神や自然や道徳に対する敬虔感情の希薄化がその忍び込みを呼び起こすだろう。
ニーチェは、この相対主義的把握をもっと徹底化して、世界についての客観的真理なるものはそもそも存在せず、それぞれの主体、種族のもつ「遠近法」によるさまざまな解釈が存在するだけだと強調した。「真理」とは捏造でありでっち上げであり虚妄であるという表現は、彼が書き散らした断片のいたるところに散見される。
この相対主義的把握はやがてポストモダン哲学に継承されるのだが、ニーチェ自身は自分のこの相対主義的な把握に満足していたわけではなかった。それはあくまでも、絶えざる非合理的な創造として世界をとらえるための前提にすぎない。彼は、この前提に基いて、世界の究極原理としての「力への意志」というアイデアを何とか普遍化させようとしたのである。しかしこの概念は、現代の洗練された哲学的感性から見れば、ショーペンハウアーの「意志」概念をそれほど超え出ているわけではない。ニーチェはショーペンハウアーの仏教風「意志否定」の傾向には強く批判的だったが、それにしても、一種の「古き良き」形而上学臭を免れていない点では共通しているように思われる。
ところで私は、こういうニーチェの考え方それ自体を認識論哲学史上の「一大事件」として位置づけることに特段の意味を認めない。というのは、ニーチェがこういう問題意識に哲学的にとらわれていたのは、彼の生きた十九世紀ヨーロッパの知的風土を考えれば、別にそれほど珍しいことではないからである。十九世紀ヨーロッパは、ダーウィンの登場に象徴されるように、前世紀から続く自然科学の大きな成果を踏まえて、生物や生命の不思議な展開の仕方、その力の秘密という問題に強い関心が寄せられた時代である。たとえばスペンサーの社会進化論などは、明らかに有機体の生命力の秘密は何かというこの時代の関心を直接に社会構造の解明に適用しようとした産物である。
ニーチェも例外ではない。彼はよく最新の自然科学を勉強していたし、その影響を強く受けていた。その枠内では、彼は、生命論的、生気論的な唯物主義者の一員であったといっても過言ではない。客観的・絶対的な真理というようなものはなく、世界は、それぞれの個体、種族、民族、人類、生命体などの「力への意志」の伸長のために、それぞれのかたちでそのつど解釈されるものにすぎない――現にこの考え方は、生物学という枠内では、後に生物学者のユクスキュルの篤実な研究によって「実証」されることになる。ユクスキュルは、生物種によって、この世界の見え方、感じ取られ方がいかに違うか、それがその生物の行動パターン(生きる必要)といかに密接な関係を持っているかを指し示したのであった。
ニーチェの場合には、そこに生命体の生き抜く力による世界解釈の変更という力動論的な要因が付け加えられる。さまざまな力の作用によって解釈そのものが変更されてゆく。力のより強いものの解釈がより弱い者の解釈を踏み潰し圧服してゆくのである。すぐ連想されるように、これはダーウィニズムの「適者生存」の考え方にきわめて近い。ニーチェはその方法論を人間世界に援用したのだ。
こうして彼はいわば、当時のヨーロッパの学問的流行現象の一つであったダイナミックな生命力理論を、自分の思想的動機の表明のために利用したにすぎないのである。その動機とは何か。
これまでのキリスト教的、プラトニズム的な道徳主義の歴史は、生、肉体、欲望、エロス、芸術といった、この地上において創造的な展開をしてゆく運動を否定し、軽蔑し、抑圧する感覚の上に成り立ってきた。ニーチェは、この事態に我慢がならず、それを根底から覆そうとしたのである。
自分は、いわくありげに高尚ぶったキリスト教のこの道徳的権威主義の最大の犠牲者であるという自意識に彼は終生縛られていた。彼がしばしば、キリスト教道徳や学者たちの青ざめた禁欲主義を、単なる生理的、心理的な、治癒不能の「病気」としてしつこく論難しているのはそのゆえである。
じつはこの点が一番大事なのだ。だから彼の言葉を、抽象的に整理された認識論哲学史の棚のなかに画期的な転回点として収めることは、彼の思想の核心を理解することにとってさほど意味がない、と私は思う。それよりもなぜ彼が、ヨーロッパはプラトニズムやキリスト教によって二千年もの長い間ペテンにかけられていたとあれほど激しく告発し続けたか、という生々しい声を聞き取ることの方が重要である。そして、この生々しさは、じつは私たち日本人にとっては、さほど文化的・心理的なリアリティを感じられないはずのものである。
ところがおかしなことに、哲学好きの日本人読者、特に戦後の読者の間では、ニーチェは一番人気である。大いなる皮肉を込めて言いたいのだが、私には長い間、なぜこんな微温的で「民主主義」的で「八百万の神々」に親しみ「和」の精神を尊ぶこの国で、しかも敗戦によってかつてなく戦闘精神を去勢された時代に、それと全く反対と言っても過言ではないこの思想家に人気が集まるのか、さっぱり理解できなかった。想像するに、それには次の二つの理由が考えられる。だが第一のものは、ニーチェ思想に対する半端な理解であり、第二のものはほとんどニーチェ誤解である。
①日本型世間のムラ社会的な精神構造に同調できない不適応者、孤独者、インテリたちにとって、ニーチェの極端な個人主義、貴族主義精神による同時代嫌悪の感覚表出が、自分を代弁してくれるように感じられること。つまり日本でのニーチェ人気は、一部のインテリ読者たちが自分の生きている社会の空気に対して抱く被抑圧感の反動形成によって支えられていること。
②ニーチェ思想には、生き方に悩む一人ひとりの個人を勇気づけ、生きる意欲を与えてくれるようにみえる要素があるため、彼の言葉が、誰にとっても当てはまる人生哲学であると受け取られやすいこと。
なぜ①のような形で彼の思想が支持されるのか。それは次のような事情にもとづいている。
この日本社会のだらけた空気、蔓延の度を深める大衆社会(ミーハー社会)の支配、目先の私利私欲の追求や権威への卑屈な媚びへつらいにだけ走って、物事をきちんと考えて勇敢に行動しようとしない百姓根性。こうした傾向に対して我慢がならない感性や知性の持ち主が、ニーチェというとびきり反時代的な思想を貫いた哲人の権威を借りることによって、自分の社会批判の主張が正当性をもつように感じられ、結果的にアイデンティティがかろうじて自分のなかで保証されることになるからである。
しかし、こういう「利用」の仕方は、すでにニーチェ自身の遠近法によって「力への意志」の一形態として相対化されているし、また『ツァラトゥストラ』のなかで、「ツァラトゥストラ」のサルとして戯画化されている。
ニーチェはキリスト教奴隷道徳がもたらしたルサンチマンの正当化としての民主主義的風潮の支配をただ批判しただけではなく、それを乗り越えるための新しい価値観をいかに創造するかという問題意識に異常な熱意を持って終生こだわり続けた。資質のすぐれた人間をえりすぐって訓育と鍛錬を施すという教育的課題にしばしば言及しているのはその証である。
彼は、ソクラテス登場以前の古代ギリシア人の芸術精神と古代ローマ人の戦闘精神こそがそのお手本であり、あとの文化はすべて堕落である(ルネサンスだけは少々別)と決めつけ、古代ギリシアや古代ローマにその夢を託した。しかし結局それは見果てぬ夢に終わった。その点では、ルソーやD・H・ロレンスにもつながる。
彼は自分の孤独な性癖や貴族趣味から、同情や憐みや相互扶助の徳にとびきりの嫌悪を示したが、事実、常識的に考えて、こんな極端な自己投影がそのまま受け入れられるはずはない。ヨーロッパ古代社会の支配層においても、同情や憐みや相互扶助の徳が生きていたに違いないのである。ちなみにこの点では、人間には「憐れみの感情」が自然に備わっているとしたルソーとは異なる。
しかしいずれにしても、近代ヨーロッパの知識人たちにとって、古代社会があこがれの的であり、自分たちはそこから堕落の一歩をたどってきたという自己否定的な受け止めはわりあい共通しており、だからこそニーチェのような思想も受け入れられる素地があった。たとえば現代人の退屈な一日をそのまま綴ったことで有名なジェームス・ジョイスの『ユリシーズ』は、ホーマーの雄大な叙事詩『オデュッセイア』の冒険物語のパロディであり、卑小になってしまった現代人の自己批評、自己風刺にほかならない。ユリシーズとは、この叙事詩の主人公オデュッセウス(ウリクセス)の英語読みである。
近代ヨーロッパ知識人のこの自己否定的な心理を文化的な素地として、ニーチェ独特の大衆蔑視感覚と過激な通俗道徳批判、その底にある彼自身の根深いルサンチマンとを継ぎ足せば、彼の思想の骨格は概略その出所が明らかとなる。こうした歴史的文化的な背景を深く考えずに、現代日本の大衆社会になじめない感性・知性の持ち主が、彼の言葉そのものを自分の自己保存にとって有効な道具として利用する態度は、浅薄のそしりを免れない。再び言うが、ニーチェはひとりでたくさんである。ツァラトゥストラのサルは要らない。
*しばらくニーチェ論を続けます。
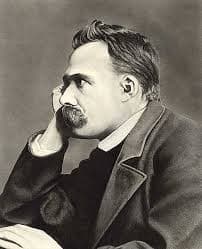
カントの倫理学を批判したあとでは、どうしてもニーチェ思想を批判的に検討しなくてはならない。
まず言っておきたいこと。ニーチェはひとりでたくさんである。こんな矯激で誇大妄想的で狂人に近い思想家は、あとにも先にも存在しない。事実彼は発狂したのだが、処女作『悲劇の誕生』およびその前後の論稿から、すでにその兆候はうかがい知れる。皮肉なタイトルである。この著作はまさに彼の人生にとって「悲劇の誕生」であった。1889年1月3日の路上での昏倒前後、コジマ・ワーグナー夫人はじめ何人かに送った書簡は、不意の精神錯乱の証拠として有名だが、逆に私はそう思わない。そこには、彼の年来の類を絶したこだわりが、ある連続性のもとに刻印されており、ここで突然おかしくなったなどとは言えないのである。
いまそれを追うことはしばらく措くが、ここで言いたいのは、以下の三点である。
第一。この思想家の悲劇が、彼の育った精神風土、文化的背景、彼の生きた時代に深く結びついたものであるということ、
そこで第二。その精神風土や文化的背景や時代の特殊性に想像力を馳せずに、ある抽象レベルで(たとえば「哲学」という名のターミノロジーによって)切り取られた彼の言葉群だけをとらえて合理的な解釈の枠組みの中に安置しようとするような試みは、この思想家の体質がもともとはらんでいた獅子身中の虫(自分や周囲を苛む猛毒)に目を塞ぐ以外のなにものでもないこと。
したがって第三。ニーチェ思想とできるだけ公正につきあうには、彼自身の独特の体臭、踊るようなその文体、大仰で極端な言葉の所作、矛盾も顧みずにやたら繰り出される語彙の驚くべき量とスピード感といったもの、要するに彼固有の思想体質そのものを常に感じとりながら、それに対してお前はどう思うのかとたえず自問するのでなくてはならないこと。
ちなみに右の第二点目に関して一言しておきたい。
一般に、ニーチェは、カントによって暗々裏に用意された認識論上の押さえをさらに一歩進めた哲学者として位置づけられている。カントによれば、世界はもともと現象の多様であり、それをとらえる感性的直観、カテゴリーによる悟性的な把握、さらに進んで純粋理性の統覚によって統合されることで初めて一定の仕方で認識されうる――カントはこの考え方をみずからコペルニクス的転回と呼んだ――が、「物自体」はけっして認識されえない。
これは理性の限界を画定する彼の試みの一つで、これによって人間理性は絶対的な真理そのものには到達しえず、ただそれに向かっての要請のみをもつという立場であるから、一種の相対主義を呼び込むものである。彼自身は人間の認識作用の基礎づけを行なったのだから、もちろん相対主義者ではない。人間の理論理性の限界設定を施したということは、それを超えるものの存在(神あるいは物自体)は実践理性によって承認するほかないと宣告したことでもあり、この承認の絶対感情はカント自身のなかでは、疑い得ないものだった。だがそれでも、このような思考様式が、相対主義を忍び込ませる木戸口を開いていたことは否めない。神や自然や道徳に対する敬虔感情の希薄化がその忍び込みを呼び起こすだろう。
ニーチェは、この相対主義的把握をもっと徹底化して、世界についての客観的真理なるものはそもそも存在せず、それぞれの主体、種族のもつ「遠近法」によるさまざまな解釈が存在するだけだと強調した。「真理」とは捏造でありでっち上げであり虚妄であるという表現は、彼が書き散らした断片のいたるところに散見される。
この相対主義的把握はやがてポストモダン哲学に継承されるのだが、ニーチェ自身は自分のこの相対主義的な把握に満足していたわけではなかった。それはあくまでも、絶えざる非合理的な創造として世界をとらえるための前提にすぎない。彼は、この前提に基いて、世界の究極原理としての「力への意志」というアイデアを何とか普遍化させようとしたのである。しかしこの概念は、現代の洗練された哲学的感性から見れば、ショーペンハウアーの「意志」概念をそれほど超え出ているわけではない。ニーチェはショーペンハウアーの仏教風「意志否定」の傾向には強く批判的だったが、それにしても、一種の「古き良き」形而上学臭を免れていない点では共通しているように思われる。
ところで私は、こういうニーチェの考え方それ自体を認識論哲学史上の「一大事件」として位置づけることに特段の意味を認めない。というのは、ニーチェがこういう問題意識に哲学的にとらわれていたのは、彼の生きた十九世紀ヨーロッパの知的風土を考えれば、別にそれほど珍しいことではないからである。十九世紀ヨーロッパは、ダーウィンの登場に象徴されるように、前世紀から続く自然科学の大きな成果を踏まえて、生物や生命の不思議な展開の仕方、その力の秘密という問題に強い関心が寄せられた時代である。たとえばスペンサーの社会進化論などは、明らかに有機体の生命力の秘密は何かというこの時代の関心を直接に社会構造の解明に適用しようとした産物である。
ニーチェも例外ではない。彼はよく最新の自然科学を勉強していたし、その影響を強く受けていた。その枠内では、彼は、生命論的、生気論的な唯物主義者の一員であったといっても過言ではない。客観的・絶対的な真理というようなものはなく、世界は、それぞれの個体、種族、民族、人類、生命体などの「力への意志」の伸長のために、それぞれのかたちでそのつど解釈されるものにすぎない――現にこの考え方は、生物学という枠内では、後に生物学者のユクスキュルの篤実な研究によって「実証」されることになる。ユクスキュルは、生物種によって、この世界の見え方、感じ取られ方がいかに違うか、それがその生物の行動パターン(生きる必要)といかに密接な関係を持っているかを指し示したのであった。
ニーチェの場合には、そこに生命体の生き抜く力による世界解釈の変更という力動論的な要因が付け加えられる。さまざまな力の作用によって解釈そのものが変更されてゆく。力のより強いものの解釈がより弱い者の解釈を踏み潰し圧服してゆくのである。すぐ連想されるように、これはダーウィニズムの「適者生存」の考え方にきわめて近い。ニーチェはその方法論を人間世界に援用したのだ。
こうして彼はいわば、当時のヨーロッパの学問的流行現象の一つであったダイナミックな生命力理論を、自分の思想的動機の表明のために利用したにすぎないのである。その動機とは何か。
これまでのキリスト教的、プラトニズム的な道徳主義の歴史は、生、肉体、欲望、エロス、芸術といった、この地上において創造的な展開をしてゆく運動を否定し、軽蔑し、抑圧する感覚の上に成り立ってきた。ニーチェは、この事態に我慢がならず、それを根底から覆そうとしたのである。
自分は、いわくありげに高尚ぶったキリスト教のこの道徳的権威主義の最大の犠牲者であるという自意識に彼は終生縛られていた。彼がしばしば、キリスト教道徳や学者たちの青ざめた禁欲主義を、単なる生理的、心理的な、治癒不能の「病気」としてしつこく論難しているのはそのゆえである。
じつはこの点が一番大事なのだ。だから彼の言葉を、抽象的に整理された認識論哲学史の棚のなかに画期的な転回点として収めることは、彼の思想の核心を理解することにとってさほど意味がない、と私は思う。それよりもなぜ彼が、ヨーロッパはプラトニズムやキリスト教によって二千年もの長い間ペテンにかけられていたとあれほど激しく告発し続けたか、という生々しい声を聞き取ることの方が重要である。そして、この生々しさは、じつは私たち日本人にとっては、さほど文化的・心理的なリアリティを感じられないはずのものである。
ところがおかしなことに、哲学好きの日本人読者、特に戦後の読者の間では、ニーチェは一番人気である。大いなる皮肉を込めて言いたいのだが、私には長い間、なぜこんな微温的で「民主主義」的で「八百万の神々」に親しみ「和」の精神を尊ぶこの国で、しかも敗戦によってかつてなく戦闘精神を去勢された時代に、それと全く反対と言っても過言ではないこの思想家に人気が集まるのか、さっぱり理解できなかった。想像するに、それには次の二つの理由が考えられる。だが第一のものは、ニーチェ思想に対する半端な理解であり、第二のものはほとんどニーチェ誤解である。
①日本型世間のムラ社会的な精神構造に同調できない不適応者、孤独者、インテリたちにとって、ニーチェの極端な個人主義、貴族主義精神による同時代嫌悪の感覚表出が、自分を代弁してくれるように感じられること。つまり日本でのニーチェ人気は、一部のインテリ読者たちが自分の生きている社会の空気に対して抱く被抑圧感の反動形成によって支えられていること。
②ニーチェ思想には、生き方に悩む一人ひとりの個人を勇気づけ、生きる意欲を与えてくれるようにみえる要素があるため、彼の言葉が、誰にとっても当てはまる人生哲学であると受け取られやすいこと。
なぜ①のような形で彼の思想が支持されるのか。それは次のような事情にもとづいている。
この日本社会のだらけた空気、蔓延の度を深める大衆社会(ミーハー社会)の支配、目先の私利私欲の追求や権威への卑屈な媚びへつらいにだけ走って、物事をきちんと考えて勇敢に行動しようとしない百姓根性。こうした傾向に対して我慢がならない感性や知性の持ち主が、ニーチェというとびきり反時代的な思想を貫いた哲人の権威を借りることによって、自分の社会批判の主張が正当性をもつように感じられ、結果的にアイデンティティがかろうじて自分のなかで保証されることになるからである。
しかし、こういう「利用」の仕方は、すでにニーチェ自身の遠近法によって「力への意志」の一形態として相対化されているし、また『ツァラトゥストラ』のなかで、「ツァラトゥストラ」のサルとして戯画化されている。
ニーチェはキリスト教奴隷道徳がもたらしたルサンチマンの正当化としての民主主義的風潮の支配をただ批判しただけではなく、それを乗り越えるための新しい価値観をいかに創造するかという問題意識に異常な熱意を持って終生こだわり続けた。資質のすぐれた人間をえりすぐって訓育と鍛錬を施すという教育的課題にしばしば言及しているのはその証である。
彼は、ソクラテス登場以前の古代ギリシア人の芸術精神と古代ローマ人の戦闘精神こそがそのお手本であり、あとの文化はすべて堕落である(ルネサンスだけは少々別)と決めつけ、古代ギリシアや古代ローマにその夢を託した。しかし結局それは見果てぬ夢に終わった。その点では、ルソーやD・H・ロレンスにもつながる。
彼は自分の孤独な性癖や貴族趣味から、同情や憐みや相互扶助の徳にとびきりの嫌悪を示したが、事実、常識的に考えて、こんな極端な自己投影がそのまま受け入れられるはずはない。ヨーロッパ古代社会の支配層においても、同情や憐みや相互扶助の徳が生きていたに違いないのである。ちなみにこの点では、人間には「憐れみの感情」が自然に備わっているとしたルソーとは異なる。
しかしいずれにしても、近代ヨーロッパの知識人たちにとって、古代社会があこがれの的であり、自分たちはそこから堕落の一歩をたどってきたという自己否定的な受け止めはわりあい共通しており、だからこそニーチェのような思想も受け入れられる素地があった。たとえば現代人の退屈な一日をそのまま綴ったことで有名なジェームス・ジョイスの『ユリシーズ』は、ホーマーの雄大な叙事詩『オデュッセイア』の冒険物語のパロディであり、卑小になってしまった現代人の自己批評、自己風刺にほかならない。ユリシーズとは、この叙事詩の主人公オデュッセウス(ウリクセス)の英語読みである。
近代ヨーロッパ知識人のこの自己否定的な心理を文化的な素地として、ニーチェ独特の大衆蔑視感覚と過激な通俗道徳批判、その底にある彼自身の根深いルサンチマンとを継ぎ足せば、彼の思想の骨格は概略その出所が明らかとなる。こうした歴史的文化的な背景を深く考えずに、現代日本の大衆社会になじめない感性・知性の持ち主が、彼の言葉そのものを自分の自己保存にとって有効な道具として利用する態度は、浅薄のそしりを免れない。再び言うが、ニーチェはひとりでたくさんである。ツァラトゥストラのサルは要らない。
*しばらくニーチェ論を続けます。



















