日本語を哲学する13

次に②の反論に答える。もう一度それを掲げよう。
②ボストン近郊のマーサス・ヴィニヤード島で使われていたヴィニヤード・サイン・ランゲージや、ニカラグァ聾学校(全寮制)の子どもたちの間で自然発生した手話の例などから見ると、音声言語以前に思想はないというあなたの考えは間違っているのではないか。これらの例は、チョムスキーが唱えた「人間には生得的に言語獲得能力がある」という説を証明するものでもある。
ヴィニヤード・サイン・ランゲージや、ニカラグァ聾学校(全寮制)の子どもたちの間で「自然発生した」といわれる手話の例については、繰り返しになるが、これらの言語は実験室での実験のように、まったく周囲から孤立した聾者のみの共同体の中から「自然発生」したわけではない。これらにおいても、当事者たちは、周囲の年長者たちが何やら口をあけて動かしながら共同生活を成り立たせていて、そのことが生きることにとってきわめて重要な役割を果たしていること、また、自分たちはその能力を欠いているか不十分にしか持ち合わせていないことを、ごく幼いころから直感するのである。また、周囲の人たち(特に母親)は、この欠落や不十分さに対して、それに見合うような対処法を懸命に講じようとする。この当事者たちの直感と周囲の努力とが、代替言語としての手話を発生させる必須条件なのである。
ニカラグァの例でも、それが「聾学校」という高度な社会的配慮と技術とによって設置された特殊な文化環境を背景にしていることに注意しよう。「特殊な文化環境」ということは、何ら「完全に孤立した共同体」であることを意味しない。むしろすでに自分たちの傷害をよく自覚している子どもたちが、まさにその自覚にもとづいて互いの表現欲求を交錯させようとしたからこそ、あたかも「自然発生」したかのような濃密な手話が出現したのである。彼らの言語共同体においては、はじめから音声言語共同体との関係が深く織り込まれている。
人間は本質的に関係を持とうとすることによって自己を成り立たせる存在であるから、その欲求を満たすふつうの道(この場合には聴覚を媒介にした交流の道)がふさがれているという欠如感覚があると、かえってその欠如感覚をテコにして別の回路を創造していくという本性をもっている。しっぽが切られても再生するトカゲのような強力な生理的補償作用は人間にはないが、代わりに観念の力による補償作用があるのだ。手話言語が独特な形で豊かに発達するのも、この「欠如そのものをポジティヴな力に変える」という、人間の普遍的な傾向に根ざしている。
チョムスキーの説との関連で言えば、私は別に人類に生得的な言語獲得能力があることを否定していない。そういう能力が潜在的に存在するにちがいないことは、むしろ当たり前のことで、そういう潜在能力(設計図のようなもの)がなければ、いかに経験的な学習を積んでも、現実に言語能力を開花させることは不可能だろう。犬やサルに言葉を教えようとしても、どうしてもあるレベル以上の抽象概念を教え込むことができない壁にぶつかることはよく知られている。
しかしまた逆に、いかに潜在能力があっても、適切な時期にそれを開花させるにふさわしい周囲からのはたらきかけを怠れば、現実に言語を獲得できないことは、イタールの「アヴェロンの野生児」の例などによっても明らかである。設計図だけあってもそれを有効に活かす大工さんや建設業者がいなければ家は建たない。楽譜だけあってもそれを演奏する人がいなければ、楽譜はただの紙屑である。
問題なのは、生得的な言語獲得能力という概念を、何か人間の共同生活における実践的な交流とは無縁に、個人が「自然に」獲得できる能力と思い込む誤りである。こういう一種の「自然発達主義」は、先に挙げた上農氏の著作でも徹底的に批判されているが、私には、こうした「自然主義」が受け入れられてしまう理由のひとつに、現代の異文化相対主義の風潮が一枚噛んでいるように思えてならない。
というのは、ニカラグァの例などに「異文化言語」としての手話の発生を目の当たりにして、これを純然たる「自然発生」と勘違いして興奮し、しかもそれを生得的な言語獲得能力が証明された例とみなすというようなおかしな論理の背景には、次のような価値観が無意識のうちに潜んでいると考えられるからである。
その価値観とは、個人や一集団は、それを取り巻くより大きな人間社会との関係がなくとも独自の「個性」や「文化」を築きうるのであって、いかなる個人やいかなる小集団といえども、その独自性をこそ尊重しなくてはならないといった、相対主義的な価値観である。いや、もっと正確に言えば、相対主義とは、価値を選び取ることの放棄であり、価値の軽重を論ずることそのものに対する否定である。また政治イデオロギー的には、素朴な権力アレルギーである。
個人や小集団を尊重しなくてはならないことは言わずもがなだが、この場合、「個人」とか「小集団」と呼ばれている対象群は、すでに完成された存在としてのそれである。それらが完成されたものとして一定の概念枠組みをもつためには、それらを取り巻くより優位な(ある場合にはより強い、ある場合にはより優れた)集団との実践的な関係交流が先立つのでなくてはならない。個人の場合で言えば、乳幼児はまだ「個人」とは言えず、そのように承認されるためには、より優れた社会的能力の持ち主である養育者とのかかわりを通して発達を遂げ、まがりなりにも一人前の意思表示、言語表現、生活自立力などをそなえるのでなくてはならない。乳幼児や子どもをはじめから自立した「個人」であるかのように大人と同列にとらえるのは、かえって人間個体のそれぞれの具体的あり方を尊重していないことになるのであって、それこそ粗雑な相対主義・平等主義イデオロギーであるというべきである。
ともあれ、この文化相対主義の傾向は、近年、中立の体裁を保たなくてはならない学問の分野ではますます隆盛を極めている。しかし現実の人間の生は空間的にも時間的にも限定された範囲内でしか成り立たないので、その限界内である価値を優先的に選び取るということが避けられないのである。学問がいつまでも中立性の体裁を気取ることで自らの「価値」を維持することを主張するならば、思想はどこかで学問と訣別しなくてはならない。言語思想もその例外ではない。
さて、最後に③の反論に答えよう。もう一度それを掲げる。
③先天的な聾者でも学力優秀な子どもは、現に読み書きをおぼえ、難しい本でも読解する能力を習得できるし、また高度な文章を書きこなすこともできる。もしあなたの言うように、読むことが「観念的な音声を聞く」ことならば、聞こえない子どもたちはどのようにしてこれらの能力を獲得したというのか。やはり音声言語に先立って人間には「思想」する力があるのではないか。
この反論は一見強力に思える。
まず第一に断るべきは、この反論は、言語と思想が別物であるという論拠を提示しているわけではないという点である。私が3節で「言葉は思想そのものである」という命題を掲げたのは、言語=コミュニケーションのツール・手段という軽薄な考え方を批判したいがためであった。この反論は、その私の動機の枠内に収まるもので、枠外からの批判ではない。
この反論の要点は、音声言語と思想との必然的な関係を疑っているのであって、聾者が読み書きするときに「観念的な音声」を用いているというのは論理矛盾であるから、彼らの文字理解や文字表現は、どのような内的プロセスによって行なわれているのかと問うているのだと考えられる。
たしかに、この例の場合には、「観念的な音声を用いる」という表現は的を射ていないだろう。聴者の場合は、黙読しているとき、明らかに「頭の中で音声が流れている」という感じがあるのだが。
そこで考えられるのは、文字を習得した聴覚障害者の頭脳のはたらきにおいては、視覚映像としての文字形態の差異の識別機能が精密に作動するのであろうということである。つまり彼らは文字の視覚的な形態を通して異なる音韻を識別しているのである。
この点につき、私は自信がなかったので、先の専門家に尋ねてみた。その結果得られた答えは、私の推定を十分に裏付けるものだった。
聴覚障害者は、手話の折にも頭の中に三次元空間を思い浮かべている場合が多く、そのため、相手の目を注視することはかえって対話に対する注意をそらしてしまうことになりがちである。本を読むときには、開いたページの視覚像が一気に目に入ってくる。話の中で本に書いてあったことを表現する場合には、それが書かれてあったページの視覚像が思い浮かべられていたり、その内容から想像される三次元空間がイメージされていたりする。その世界では名高いある人は、この視覚によって文字をとらえる能力が極めて優れていて、一時間で文庫本を読んでしまう、ということだった。
だから先天的な聴覚障害者は、書き言葉の読み取りにおいて、独特の回路をたどる脳神経系のシステムを発達させていることになる。この場合にも欠如をテコにした代替機能が旺盛に駆使されることによって、文字の習得が果たされるのであろう。
そのように聴者とはまったく違った回路をたどって書き言葉を習得するのだとしても、そのことは、思想と言葉とが別物であり前者が後者に先行して存在するということには、何らならない。なぜならば、聴覚障害者が文字を視覚的にとらえて理解するときにも(思想の受信主体)、また書き言葉で何かを表現するときにも(思想の発信主体)、それらの言語行為そのものを通してそのつど思想が組み立てられていくことには変わりがないからである。
(第Ⅰ章了。次回から、「第Ⅱ章・沈黙論」を掲載します。)

次に②の反論に答える。もう一度それを掲げよう。
②ボストン近郊のマーサス・ヴィニヤード島で使われていたヴィニヤード・サイン・ランゲージや、ニカラグァ聾学校(全寮制)の子どもたちの間で自然発生した手話の例などから見ると、音声言語以前に思想はないというあなたの考えは間違っているのではないか。これらの例は、チョムスキーが唱えた「人間には生得的に言語獲得能力がある」という説を証明するものでもある。
ヴィニヤード・サイン・ランゲージや、ニカラグァ聾学校(全寮制)の子どもたちの間で「自然発生した」といわれる手話の例については、繰り返しになるが、これらの言語は実験室での実験のように、まったく周囲から孤立した聾者のみの共同体の中から「自然発生」したわけではない。これらにおいても、当事者たちは、周囲の年長者たちが何やら口をあけて動かしながら共同生活を成り立たせていて、そのことが生きることにとってきわめて重要な役割を果たしていること、また、自分たちはその能力を欠いているか不十分にしか持ち合わせていないことを、ごく幼いころから直感するのである。また、周囲の人たち(特に母親)は、この欠落や不十分さに対して、それに見合うような対処法を懸命に講じようとする。この当事者たちの直感と周囲の努力とが、代替言語としての手話を発生させる必須条件なのである。
ニカラグァの例でも、それが「聾学校」という高度な社会的配慮と技術とによって設置された特殊な文化環境を背景にしていることに注意しよう。「特殊な文化環境」ということは、何ら「完全に孤立した共同体」であることを意味しない。むしろすでに自分たちの傷害をよく自覚している子どもたちが、まさにその自覚にもとづいて互いの表現欲求を交錯させようとしたからこそ、あたかも「自然発生」したかのような濃密な手話が出現したのである。彼らの言語共同体においては、はじめから音声言語共同体との関係が深く織り込まれている。
人間は本質的に関係を持とうとすることによって自己を成り立たせる存在であるから、その欲求を満たすふつうの道(この場合には聴覚を媒介にした交流の道)がふさがれているという欠如感覚があると、かえってその欠如感覚をテコにして別の回路を創造していくという本性をもっている。しっぽが切られても再生するトカゲのような強力な生理的補償作用は人間にはないが、代わりに観念の力による補償作用があるのだ。手話言語が独特な形で豊かに発達するのも、この「欠如そのものをポジティヴな力に変える」という、人間の普遍的な傾向に根ざしている。
チョムスキーの説との関連で言えば、私は別に人類に生得的な言語獲得能力があることを否定していない。そういう能力が潜在的に存在するにちがいないことは、むしろ当たり前のことで、そういう潜在能力(設計図のようなもの)がなければ、いかに経験的な学習を積んでも、現実に言語能力を開花させることは不可能だろう。犬やサルに言葉を教えようとしても、どうしてもあるレベル以上の抽象概念を教え込むことができない壁にぶつかることはよく知られている。
しかしまた逆に、いかに潜在能力があっても、適切な時期にそれを開花させるにふさわしい周囲からのはたらきかけを怠れば、現実に言語を獲得できないことは、イタールの「アヴェロンの野生児」の例などによっても明らかである。設計図だけあってもそれを有効に活かす大工さんや建設業者がいなければ家は建たない。楽譜だけあってもそれを演奏する人がいなければ、楽譜はただの紙屑である。
問題なのは、生得的な言語獲得能力という概念を、何か人間の共同生活における実践的な交流とは無縁に、個人が「自然に」獲得できる能力と思い込む誤りである。こういう一種の「自然発達主義」は、先に挙げた上農氏の著作でも徹底的に批判されているが、私には、こうした「自然主義」が受け入れられてしまう理由のひとつに、現代の異文化相対主義の風潮が一枚噛んでいるように思えてならない。
というのは、ニカラグァの例などに「異文化言語」としての手話の発生を目の当たりにして、これを純然たる「自然発生」と勘違いして興奮し、しかもそれを生得的な言語獲得能力が証明された例とみなすというようなおかしな論理の背景には、次のような価値観が無意識のうちに潜んでいると考えられるからである。
その価値観とは、個人や一集団は、それを取り巻くより大きな人間社会との関係がなくとも独自の「個性」や「文化」を築きうるのであって、いかなる個人やいかなる小集団といえども、その独自性をこそ尊重しなくてはならないといった、相対主義的な価値観である。いや、もっと正確に言えば、相対主義とは、価値を選び取ることの放棄であり、価値の軽重を論ずることそのものに対する否定である。また政治イデオロギー的には、素朴な権力アレルギーである。
個人や小集団を尊重しなくてはならないことは言わずもがなだが、この場合、「個人」とか「小集団」と呼ばれている対象群は、すでに完成された存在としてのそれである。それらが完成されたものとして一定の概念枠組みをもつためには、それらを取り巻くより優位な(ある場合にはより強い、ある場合にはより優れた)集団との実践的な関係交流が先立つのでなくてはならない。個人の場合で言えば、乳幼児はまだ「個人」とは言えず、そのように承認されるためには、より優れた社会的能力の持ち主である養育者とのかかわりを通して発達を遂げ、まがりなりにも一人前の意思表示、言語表現、生活自立力などをそなえるのでなくてはならない。乳幼児や子どもをはじめから自立した「個人」であるかのように大人と同列にとらえるのは、かえって人間個体のそれぞれの具体的あり方を尊重していないことになるのであって、それこそ粗雑な相対主義・平等主義イデオロギーであるというべきである。
ともあれ、この文化相対主義の傾向は、近年、中立の体裁を保たなくてはならない学問の分野ではますます隆盛を極めている。しかし現実の人間の生は空間的にも時間的にも限定された範囲内でしか成り立たないので、その限界内である価値を優先的に選び取るということが避けられないのである。学問がいつまでも中立性の体裁を気取ることで自らの「価値」を維持することを主張するならば、思想はどこかで学問と訣別しなくてはならない。言語思想もその例外ではない。
さて、最後に③の反論に答えよう。もう一度それを掲げる。
③先天的な聾者でも学力優秀な子どもは、現に読み書きをおぼえ、難しい本でも読解する能力を習得できるし、また高度な文章を書きこなすこともできる。もしあなたの言うように、読むことが「観念的な音声を聞く」ことならば、聞こえない子どもたちはどのようにしてこれらの能力を獲得したというのか。やはり音声言語に先立って人間には「思想」する力があるのではないか。
この反論は一見強力に思える。
まず第一に断るべきは、この反論は、言語と思想が別物であるという論拠を提示しているわけではないという点である。私が3節で「言葉は思想そのものである」という命題を掲げたのは、言語=コミュニケーションのツール・手段という軽薄な考え方を批判したいがためであった。この反論は、その私の動機の枠内に収まるもので、枠外からの批判ではない。
この反論の要点は、音声言語と思想との必然的な関係を疑っているのであって、聾者が読み書きするときに「観念的な音声」を用いているというのは論理矛盾であるから、彼らの文字理解や文字表現は、どのような内的プロセスによって行なわれているのかと問うているのだと考えられる。
たしかに、この例の場合には、「観念的な音声を用いる」という表現は的を射ていないだろう。聴者の場合は、黙読しているとき、明らかに「頭の中で音声が流れている」という感じがあるのだが。
そこで考えられるのは、文字を習得した聴覚障害者の頭脳のはたらきにおいては、視覚映像としての文字形態の差異の識別機能が精密に作動するのであろうということである。つまり彼らは文字の視覚的な形態を通して異なる音韻を識別しているのである。
この点につき、私は自信がなかったので、先の専門家に尋ねてみた。その結果得られた答えは、私の推定を十分に裏付けるものだった。
聴覚障害者は、手話の折にも頭の中に三次元空間を思い浮かべている場合が多く、そのため、相手の目を注視することはかえって対話に対する注意をそらしてしまうことになりがちである。本を読むときには、開いたページの視覚像が一気に目に入ってくる。話の中で本に書いてあったことを表現する場合には、それが書かれてあったページの視覚像が思い浮かべられていたり、その内容から想像される三次元空間がイメージされていたりする。その世界では名高いある人は、この視覚によって文字をとらえる能力が極めて優れていて、一時間で文庫本を読んでしまう、ということだった。
だから先天的な聴覚障害者は、書き言葉の読み取りにおいて、独特の回路をたどる脳神経系のシステムを発達させていることになる。この場合にも欠如をテコにした代替機能が旺盛に駆使されることによって、文字の習得が果たされるのであろう。
そのように聴者とはまったく違った回路をたどって書き言葉を習得するのだとしても、そのことは、思想と言葉とが別物であり前者が後者に先行して存在するということには、何らならない。なぜならば、聴覚障害者が文字を視覚的にとらえて理解するときにも(思想の受信主体)、また書き言葉で何かを表現するときにも(思想の発信主体)、それらの言語行為そのものを通してそのつど思想が組み立てられていくことには変わりがないからである。
(第Ⅰ章了。次回から、「第Ⅱ章・沈黙論」を掲載します。)












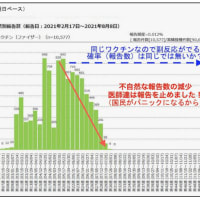

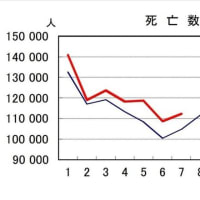
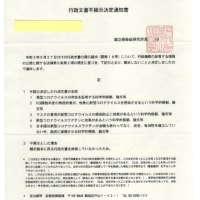
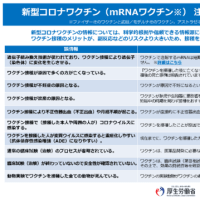

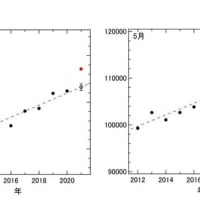

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます