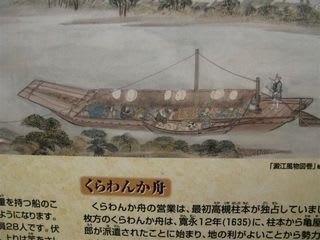民家の改修その7です。
基礎工事が1月19日に終わり、21日からいよいよ木工事が始まりました。
写真は24日と26日の施工状況です。
1階床下に据え付けられる土台や大引きと呼ぶ木材の施工です。

基礎の上の木材が土台です。120ミリ角の桧1等材です。

正面は仏壇が置かれていた8畳の座敷。手前左側が玄関。

8畳の座敷から逆に見たところ。

8畳の座敷と6畳のおくの大引き材は元の丸太材を再利用
しています。出来るだけ元の材料を再利用したいという
施主の意向を反映しようとしています。

基礎の上に載せれない土台と基礎を緊結するエル型のプレ
ート金物です。このような金物は既製品としてありません
ので仕様書に準じて製作します。

既設の柱の根元部分が蟻害などにより腐っていたところは
新しい桧材で写真のように根接ぎしていきます。

改修プランの間取りによって既設の柱を取り除いた部分には
新しい梁を既設の梁(黒い部分)の下側に据付て補強します。
枕梁と呼びます。

元々使われていた丸太の大引き材を再利用するため加工し
ているところ。

同上。新しい120ミリ角の桧材を使う方が手間が掛からない
のですがもったいないという気持ちを大切に。

土台に続き大引きの据付がほぼ終わったところ。

同上。

80年まえに建てられた時の梁です。
この下は土間でかまどが据え付け
られていた台所です。
今回の改修前に何回か改修が行
われており、かまどは取り払われ
て土間の上に床がはられ流し台な
どの台所家具が据え付けられてい
ました。この梁は天井材が貼られ
て見えない状態でした。
今回の改修ではこの梁を建てられ
た時のように見える状態にしてい
きます。

台所からの見上げ。
台所の上には吹き抜け(かまどの
煙抜きのための空間)と道具蔵と
呼ぶ収納部屋がありました。
今回の改修では道具蔵を一部残し
ながら吹き抜けを少し大きくして
いきます。
台所や食堂、居間のスペースに自
然光を出来るだけ取り入れようと
いう訳です。
基礎工事が1月19日に終わり、21日からいよいよ木工事が始まりました。
写真は24日と26日の施工状況です。
1階床下に据え付けられる土台や大引きと呼ぶ木材の施工です。

基礎の上の木材が土台です。120ミリ角の桧1等材です。

正面は仏壇が置かれていた8畳の座敷。手前左側が玄関。

8畳の座敷から逆に見たところ。

8畳の座敷と6畳のおくの大引き材は元の丸太材を再利用
しています。出来るだけ元の材料を再利用したいという
施主の意向を反映しようとしています。

基礎の上に載せれない土台と基礎を緊結するエル型のプレ
ート金物です。このような金物は既製品としてありません
ので仕様書に準じて製作します。

既設の柱の根元部分が蟻害などにより腐っていたところは
新しい桧材で写真のように根接ぎしていきます。

改修プランの間取りによって既設の柱を取り除いた部分には
新しい梁を既設の梁(黒い部分)の下側に据付て補強します。
枕梁と呼びます。

元々使われていた丸太の大引き材を再利用するため加工し
ているところ。

同上。新しい120ミリ角の桧材を使う方が手間が掛からない
のですがもったいないという気持ちを大切に。

土台に続き大引きの据付がほぼ終わったところ。

同上。

80年まえに建てられた時の梁です。
この下は土間でかまどが据え付け
られていた台所です。
今回の改修前に何回か改修が行
われており、かまどは取り払われ
て土間の上に床がはられ流し台な
どの台所家具が据え付けられてい
ました。この梁は天井材が貼られ
て見えない状態でした。
今回の改修ではこの梁を建てられ
た時のように見える状態にしてい
きます。

台所からの見上げ。
台所の上には吹き抜け(かまどの
煙抜きのための空間)と道具蔵と
呼ぶ収納部屋がありました。
今回の改修では道具蔵を一部残し
ながら吹き抜けを少し大きくして
いきます。
台所や食堂、居間のスペースに自
然光を出来るだけ取り入れようと
いう訳です。