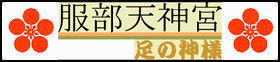吉志部神社

(きしべじんじゃ)
大阪府吹田市岸部北4-18-1

この鳥居をくぐった奥深い参道の向こうに境内が広がります。
〔御祭神〕
天照大御神
(あまてらすおおみかみ)
豊受大神
(とようけのおおかみ)
ほか6神
吉志部神社の創建年代は明らかではありませんが、6世紀末から7世紀初頭にかけて朝鮮半島より渡ってきた難波吉士氏(なにわのきしし)が、本拠地として勢力を伸ばしたこの地に祖霊神を祀って一族の守護神社としたことに始まるといわれています。一方、社伝では祟神天皇の治世であった紀元前41年に大和国の磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)から神を分霊して祀った祠が始まりだとされています。諸説ありますが、少なくとも平安時代にはここ紫金山の地に天照大御神などを祀る祠があったのは確かなようです。


緑豊かな静かな杜の中を伸びる参道(左)と、石段を登った先に建つ神門(右)。
吉志部神社の本殿には、天照大御神と豊受大神を中心に、左に八幡大神・素盞嗚大神・稲荷大神、右に春日大神・住吉大神・蛭子大神が祀られており、御祭神の数にちなんで「八社明神」と呼ばれたり、天照大御神と豊受大神を一対に数えて「七社明神」と呼ばれていたそうですが、当初の名称は「太神宮(だいじんぐう)」で、吉志部5ヶ村の産土神として崇敬を集めていました。1870(明治3)年に神仏分離令が出されたのを機に、吉士氏の本拠地であることを表す地名の「岸部」にちなんで「吉志部神社」という社名に変更されました。

この社殿は覆屋で、その中に国の重要文化財に指定されている本殿がありました。
※2008(平成20)年5月23日の火災で全焼する前の貴重な姿
応仁の乱の兵火に巻き込まれて応仁年間(1467~1477年)に社殿が全焼してしまった吉志部神社は、1610(慶長15)年になって三好長慶公の次男で吉志部姓を名乗っていた吉志部一次公によって再建されました。社殿は豊臣秀吉公が建立した方広寺大仏殿の余材を用いて建てられた桃山時代の作風が色濃く伝わるもので、柱と柱の間が7つある七間社流造の非常に珍しい造りの社殿でした。1833(天保4)年には社殿を包み込むように覆屋が建てられ、大正時代には拝殿や幣殿などが建てられましたが、国の重要文化財にも指定されていたこの社殿は、残念ながら2008(平成20)年5月に放火と見られる火事で全焼してしまいました。


社殿の右に並ぶ摂社。愛宕大神や大国主命などを祀る摂社(左)や大川神社など(右)。
「吉志部の里」と呼ばれたこの一帯では粘土質の焼き物に適した土が多く産出され、6世紀から7世紀にかけて須恵器が多く焼かれていました。794(延暦13)年に平安京への遷都が行われた際には内裏や皇族・貴族の邸宅など数多くの建物が建てられたため、短期間に大量の瓦が必要となりました。その爆発的な需要に応えるために各地に窯が設置されましたが、古くから窯業の生産拠点として栄えていた吉志部神社でも窯が整備されて次々と瓦や器が生産され、水利を利用して都へと輸送されていきました。現在発掘されているだけでも9基の平窯と4基の登窯の存在が確認されており、「吉志部瓦窯跡(きしべがようせき)」として国の史跡に指定されています。


7世紀初め頃に須恵器を焼いていたとされる「吹田34号須恵器窯跡」。
アクセス
・JR京都線「岸辺駅」下車、北西へ徒歩20分
・阪急電車京都線「正雀駅」下車、北西へ徒歩25分
 吉志部神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
吉志部神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・無料
拝観時間
・常時開放