早いですね~もう12月です。
個人事業の方は、12月が事業年度の最終となります。
税金対策、決算対策は大丈夫ですか?
早目、早目に整理をして準備しましょう。
利子税と延滞税
●利子税は必要経費・損金になる。
利子税は税法で認められた延納等を納税者が希望して納期限内に納付しなかった時に負担する本税以外の税金
 主なものとしては
主なものとしては
所得税の確定申告に際して納付すべき税額の2分の1以上を法定期限内に納付したときは、その残額は延納できる。(延納期限はその年の5月31日まで)
 確定申告書を見たことがある人は、気付いたかな?延納と言う欄があります。延納したことによりは発生する利子税は損金参入できます。
確定申告書を見たことがある人は、気付いたかな?延納と言う欄があります。延納したことによりは発生する利子税は損金参入できます。
●延滞税は必要経費・損金にならない。
延滞税は主として申告期限内に申告をし、それによって納付すべき国税があるのに、その法廷納期限内に納付しなかったとき、または、期限後申告書もしくは修正申告書を提出したり、正当な納期限までに国税を納めていなかったときに課せられる。
納期限から完納するまでの期間の日数に応じ、未納税額に年14.6%の割合をかけた金額。
ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合となる。



利子税は、他に法人税にかかる利子税、相続税にかかる利子税、贈与税に係る利子税があります。
延滞税は、利子税と違い、罰金に近い性格を持っていると思います。
期限内納めなくて、税務署などから督促されたときなど、本税以外の欄を見てください。なんと書かれているか。
個人事業の方は、12月が事業年度の最終となります。
税金対策、決算対策は大丈夫ですか?
早目、早目に整理をして準備しましょう。
利子税と延滞税
●利子税は必要経費・損金になる。
利子税は税法で認められた延納等を納税者が希望して納期限内に納付しなかった時に負担する本税以外の税金
 主なものとしては
主なものとしては所得税の確定申告に際して納付すべき税額の2分の1以上を法定期限内に納付したときは、その残額は延納できる。(延納期限はその年の5月31日まで)
 確定申告書を見たことがある人は、気付いたかな?延納と言う欄があります。延納したことによりは発生する利子税は損金参入できます。
確定申告書を見たことがある人は、気付いたかな?延納と言う欄があります。延納したことによりは発生する利子税は損金参入できます。●延滞税は必要経費・損金にならない。
延滞税は主として申告期限内に申告をし、それによって納付すべき国税があるのに、その法廷納期限内に納付しなかったとき、または、期限後申告書もしくは修正申告書を提出したり、正当な納期限までに国税を納めていなかったときに課せられる。
納期限から完納するまでの期間の日数に応じ、未納税額に年14.6%の割合をかけた金額。
ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合となる。



利子税は、他に法人税にかかる利子税、相続税にかかる利子税、贈与税に係る利子税があります。
延滞税は、利子税と違い、罰金に近い性格を持っていると思います。
期限内納めなくて、税務署などから督促されたときなど、本税以外の欄を見てください。なんと書かれているか。











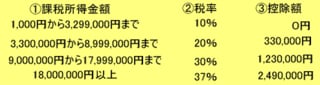
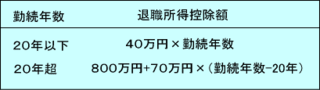
 平成10年3月31日までに取得した営業権は
平成10年3月31日までに取得した営業権は