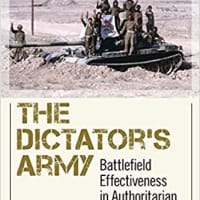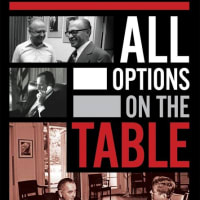政治学や国際関係論は、政策立案において、どのような役割を果たすべきなのでしょうか。自然科学における「基礎研究」のように、客観的な事実を追究すること自体に価値があるのであり、政治学や国際関係論もそうすべきだという見解があります。その一方で、これらの学問は、世界で実際に起こっていることへの対策を講じるのに貢献するべきだとの意見もあります。後者の立場から、政治学は政策から離れていることに警鐘を鳴らす重厚な研究書が、マイケル・デッシュ氏(ノートルダム大学)による『無関係性の崇拝―社会科学の国家安全保障への減退する影響―(Cult of the Irrelevant: The Waning Influence of Social Science on National Security)』(プリンストン大学出版局、2019年)です。
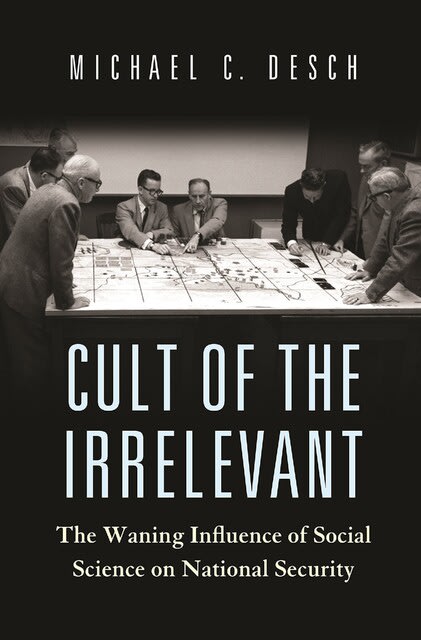
デッシュ氏は、膨大なデータから、政治学が定量的で数理化すると、政策の処方を行わなくなる傾向が認められることを実証しています。事実、この40年間で、政治学のトップジャーナルに掲載された国際関係論の論文は「科学化」する一方で、ますます政策から距離をとるようになりました。1980年時点においては、定量的・数理的アプローチをとる国際関係論の論文は全体の30%以下でした。ところが、2012年になると、その割合が倍以上に急増したのです。他方、政策的処方箋を示した論文は、1980年において約15%だったのが、2012年では10%を切ってしまいました。政治学がこうした状況になってしまったことを、かれは次のように説明しています。「現代科学の進歩は皮肉なことに、それ(政治学)がより専門的になるにしたがい、具体的な問題にますます直接適用できないものにしている…洗練された社会科学の方法(モデル、統計学、難解な専門用語)は、専門家以外の参入を阻む理想的な障壁を提供している…テクニックとして狭く定義された厳密さの追求は、政治学が実践的問題にますます関連しなくなることを意味する」(同書、3-15ページ)。
こうしたデッシュ氏の危機感は、健全な民主国家を形成する政治学の役割が失われつつあることから生じています。この点は重要なので、かれの主張を以下に引用します。
「学者は政策立案者より、他のいくつか優れた点がある。かれらは(国家が直面する)問題や地域について、大半の政策決定者に比べて、より深い知識を発展させる時間を持っている。組織での終身在職権は、少なくとも理論上は、かれらに論争となっている問題を探究する自由や不人気の立場を表明する自由も与えている…大学に籍を置く学者は政策決定者に比べれば、特定の政策や計画への既得権益がほんの少しだけである…われわれの民主的な政治システムは、アイディアという市場が上手に機能すること、さまざまな強みと弱みを持つ個人や集団における抑制と均衡、より広い政策論争に参入している偏見(バイアス)を相殺することに依存しており、したがって、それぞれの限界を補い合っているのである」(同書、242ページ)。
要するに、民主国家を市民にとってよりよいものにする政策を立案するには、政治家や官僚といった実務家だけでなく、学問の自由を享受している学者がさまざなまアイディアを出し合うことにより、より合理的で適切な選択肢は生み出されるのだから、政治学を生業とする者は、政策形成に貢献すべきだということでしょう。それでは、具体的に、政治学者は何をすればよいのでしょうか。政策立案者は忙しいので、政治学者は、かれらの立場を考慮した政策提言を行うべきだということです。新聞の論評やブログは、その媒体になります。また、それらでは、ジャーゴン(難解な専門用語)を避け、平易な英語(わが国であれば平易な日本語)で書くべきだとデッシュ氏は述べています(同書、250ページ)。
こうした主張に同意する少なからぬ政治学者は、自分の仕事はあくまでも「社会科学」なのであり、ジャーナリズムではないと悩ましく思うかもしれません。確かに、「職業としての政治学」はジャーナリズムではありません。両者の線引きは、どこにあるのでしょうか。デッシュ氏は、根本的に、多くの政治学者が政治における科学の追求を勘違いしていると、このように指摘しています。「多くの社会科学者は、自然科学の形式(数学と普遍的モデル)を科学の定義と混同している。しかしながら、これは安全保障研究にとって分類的な間違いである」(同書、252ページ)。この点は、少し分かりにくいでしょうから、別の文献に助けてもらいましょう。組織の戦略論で著名な野中郁次郎氏は、歴史研究者たちとの共同研究である『戦略の本質』(日本経済新聞社、2005年)において、次のように述べています。
「戦略論は、人間世界を研究対象とする社会科学の一分野である…われわれは戦略論の科学化を志向するけれども、自然科学と同一の厳密さでの科学化を意図していない…社会科学の面白さは自然科学ではうまく扱えない価値、コンテクスト、パワーなどの現象を事例や物語をベースに、できるだけ客観的に、禁欲的に、現実に迫っていき、最終的には『かくあるべきである』という規範的命題を提示することにある」(『戦略の本質』333-335ページ)。
上記の方法論的立場をとる研究者は、一般的に科学で推奨される演繹法ではなく、帰納法による命題の構築や限定的一般化を目指すことが少なくありません。上記の『戦略の本質』では、戦況を逆転した戦史の事例から、成功する戦略に共通するパターンを発見しようとしています。このブログでも過去に言及したアレキサンダー・ジョージ氏の抑止や強制外交の研究も、やはり帰納法をつかった事例から中範囲を理論を構築しています。独裁者の軍隊の軍事的効率性に関する研究や軍事組織のイノベーションに関する研究は、事例から理論を導出しています。これらには自然科学の研究で見られるたくさんの数式はありませんが、全て正真正銘の科学的な政治研究です。
デッシュ氏の議論に戻りましょう。かれは、政策分析やジャーナリズムと純粋な学問との間に中間地帯があると主張しています。政治学は、これらの間でバランスをとるべきだということです。そのために必要なことは、「方法論的多様性」であり、特定の方法だけを使うのではなく、目下の問題にとって最も適切なアプローチを採用するということです。ただし、これは十分条件ではありません。デッシュ氏によれば、政治学者は方法論から導出されるのではなく、取り組むべき問題から導出された研究に従事すべきだと指摘しています。これら2つの要件を満たすことにより、政治学は科学的で政策に役立つものになるのです(『無関係性の崇拝』250ページ)。
最後に、『無関係性の崇拝』を読んで、印象に残ったことを2点ほど指摘して、この記事を締めくくりたいと思います。1つは、アメリカの政治学において、「地域研究(area studies)」が、科学的ではないという理由により、「比較政治学(comparative politics)」に取って代わられたことです。第二次世界大戦時においては、アメリカで地域研究者は活躍していました。「地域研究は『戦略計画や軍事作成において最も価値』があった」ということです。日本との関連でいえば、文化人類学者のルース・ベネディクト氏による日本政治文化の研究は、応用社会科学の最も影響力のあった事例です。彼女の研究は、アメリカの戦後日本統治と再建に大きな役割を果たしたと考えられています。ところが、1960年代頃から政治学の分野でも、自然科学で用いられる数理的・数学的手法で政治現象を分析できると信じる、行動科学革命が深く入り込むようになりました。その結果、この方法に馴染まない地域研究は、政治学界では周縁化されてしまいました(「ソ連研究」は例外)。政策決定者は引き続き地域研究者を必要としていたにもかかわらず、大学は政策サークルに必要な地域の知識をますます提供できなくなってしまったのです。ベトナム戦争の悲劇は、アメリカにおける地域研究の衰退と無関係ではありません。政府の高官たちは、ベトナムに関する地域の専門知識を欲していましたが、大学から、その多くを得ることができませんでした。これは社会科学という学問が行動科学をますます志向したことにより、地域研究が衰退した結果だったのです(『無関係性の崇拝』48-49、58、199ページ)。
もう1つは、冷戦後に登場した安全保障研究「不要論」です。この主張を主導した1人が政治学者のデーヴィッド・ボールドウィン氏(コロンビア大学、プリンストン大学)でした。かれは安全保障研究者を強烈に批判して、政治学の専門分野としての安全保障研究は消滅させてもよいのではないかと、このように訴えたのです。「『政策に関連』づけたい欲求は、何人かの学者を政策立案者とのあまりにも緊密な関係に導いたために、かれらが自律した知識人とみなされなくなってしまい、政策立案の支配層の一部として考えられるようになった…安全保障研究の分野はしばしば戦略研究と同じだとされてきた…国政術の軍事的手段は…安全保障の専門家の中心的関心になった…かれらは軍事的安全保障は他の目標に優先すると主張する傾向にある…他の目標とのトレードオフなど認めらないというのだ…国家は外部からの攻撃から武力なしでは自分を守れないが、吸える空気や飲める水のない国家は確実に生き残ることができないだろう…資源が希少な世界では、軍事安全保障の目標は常に他の目標と対立する…冷戦の終焉が軍事的安全保障をより豊富なものにしたということは、資源を安全保障から公共政策の他の目標に投入する時が来たことを示唆していそうだ…おそらく、安全保障研究という分野を廃止する時が来たのだ」(David A. Baldwin, "Security Studies and the End of the Cold War," World Politics, Vol. 48, No. 1, October 1995, pp. 117-141)。さらに、安全保障研究や戦略研究は、数理的で厳格な科学を志向する「合理的選択論者」からも非難を浴びました。こうした冷戦後の政治学の傾向にジャック・スナイダー氏(コロンビア大学)は、こう苦言を呈していました。「既にあるアイディアを拝借して、安全保障研究に大立物を(既にあることに気づかずに)再発明しているか、数理化が実際に新しい概念を加えた程度を誇張している合理的選択論者に、わたしは気づいてきた。その間ずっと、(かれらは)伝統的な安全保障研究の後進性を批判しているのだ」(『無関係性の崇拝』218ページ)。幸いなことに、安全保障研究や戦略研究は、政治学において、こうした猛攻から生き延びました。
『無関係性の崇拝』が分析するのは、アメリカの政治学の変遷や方法論上の傾向なので、これを日本の政治学界にそのまま当てはめることは出来ません。わが国では、「地域研究」は国際政治学会で確固とした地位を築いており、「理論研究」や「歴史研究」などと相まって「方法論的多様性」を保っています。ウクライナ紛争の報道では、ロシアやヨーロッパといった特定の地域を専門とする、大学に籍を置く地域研究者がメディアで引っ張りだこです。また、冷戦後、日本で安全保障研究不要論が唱えられたことは、私が知る限り、ほぼ無かったといってよいでしょう。日本の防衛政策の策定においては、懇談会などを通して学者が関与してきました。さらに、日本の政治学において、過度な数理化が推し進められることも、今のところありません。日本の政治学は、悪くいえば、まとまりがないのかもしれませんが、良くいえば、健全な「方法論的多様性」を維持してきたのです。ただし、政治学者の政策提言に関して、久米郁夫氏(早稲田大学)の次の警句は、傾聴に値すると思います。「多様な推論の意義と必要性を認めたとしても、その推論が方法論的自覚に基づいた論争に耐えるものでなければ、結局は勢いだけの提言と自己満足に堕するだろう」(『書斎の窓』第680号、2022年3月、3ページ)。方法論的多元主義とは、「何でもアリ」とは異なります。政治学者は、定性的であれ定量的であれ、社会科学の方法論に基づいて推論を行い、それを政策提言の基礎とすべきだということなのでしょう。
追記:2023年に「国際関係論と政策関与」について、新しい興味深い調査結果が、アメリカ政治学会の『パースペクティヴ・オン・ポリティクス』誌に発表されました。この論文の著者たちは、これまで言われてきた常識とは異なり「国際関係学者は政策に高いレベルで関与している」と結論づけています。その大半のやり方はブログ記事や意見広告ですが、政策レポートやコンサルティングも顕著にみられるそうです。
米国の国際関係学者にメールでアンケートを行ったところ、回答者の約7割が、キャリア形成において、政策関連の組織で働いたことがあるとのことです。約半数は学界に入る前に政策形成の世界で働いていたと回答しています。そして、回答者の約7割が、政策に関与することは教育や研究の質を向上させると考えているのです。注目すべきは、定性的方法をとる学者も定量的(数量的)方法をとる学者も同等程度、政策に関与していることです。つまり、政治学における数理化は、国際関係研究者に「政策とは無縁なものへの崇拝」を促していないということです。そしてどちらの方法論をとる研究者も、その6割前後が、大学はもっと政策への関与を終身在職権や昇進の審査で評価すべきと回答しています。
ただし、こうした政策への関与は学問的誠実さの問題も提起しています。圧倒的多数(87%)の国際関係研究者は、政策への関与が何らかの義務であると考えています。その一方で、いわゆる「御用学者」が学問をゆがめる潜在的問題も無視できないということです。この調査を実施したC. ヘンドリクス氏、J. マクドナルド氏、R. パワーズ氏、S. パターソン氏、M. ティアリー氏は、以下のように述べています。
「政策に関与する学者が、政策立案のメンバーにアピールするために、自分の本当の信念や意見を歪める心配はある」という記述に、どの程度強く同意するか、または同意しないかを国際関係学者に尋ねたところ、3分の1以上(36.4%)が同意、29.4%が同意しない、34.3%が同意でも不同意でもないと回答。興味深いことに、活動のスポンサーに反対されることを想定して、自分の本当の信念や意見を和らげたり、控えたりしたことがあると自認する国際関係研究者はごく僅か(4.7%)だった。国際関係研究者は、資金提供者や助言する組織が聞きたいことを伝えようとする誘惑に駆られたことはないと報告しているが、複数の研究者は、同僚がそうしているのでは、と心配している。このことは…学問的誠実さの問題を提起している(p. 9)。
さらに、若手研究者とベテラン研究者でも、どのように政策に関与すべきかについて、意見が割れています。
「国際関係研究者は、政策集団のメンバーとの対話において、自らの見解を優遇するのか、それとも専門家のコンセンサスを伝えようとするのか」という問いに対して…主任教授の半数近くが、学術的なコンセンサスよりも自分の研究成果を重視することに同意するのに対し、そう回答した助教は28.6%に過ぎなかった。政策決定者は、政策決定に必要な情報として学術的なコンセンサスを重視する傾向があることを考えると、この結果は厄介である。その場にいる最も年長者の声(つまり、ランクによって示される学術的な資格)は、その専門性を活かして、テーマに関するコンセンサスの立場を主張する傾向が最も低いのかもしれない (p. 10)。
政策立案過程において、声の大きな年長の国際政治学者の「個人的な」意見が、学問的コンセンサスより影響力を持ちやすいとすれば、これは必ずしも健全ではないでしょう。
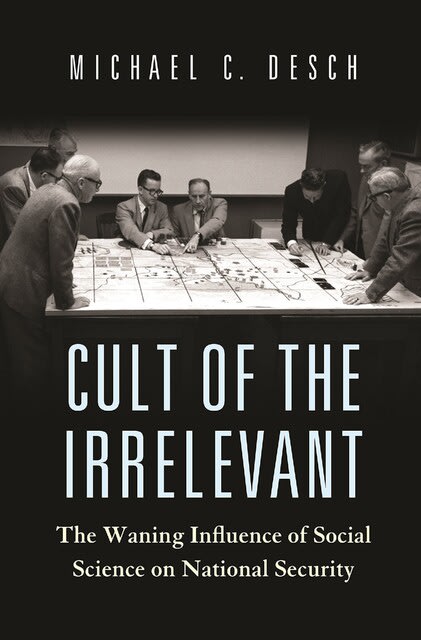
デッシュ氏は、膨大なデータから、政治学が定量的で数理化すると、政策の処方を行わなくなる傾向が認められることを実証しています。事実、この40年間で、政治学のトップジャーナルに掲載された国際関係論の論文は「科学化」する一方で、ますます政策から距離をとるようになりました。1980年時点においては、定量的・数理的アプローチをとる国際関係論の論文は全体の30%以下でした。ところが、2012年になると、その割合が倍以上に急増したのです。他方、政策的処方箋を示した論文は、1980年において約15%だったのが、2012年では10%を切ってしまいました。政治学がこうした状況になってしまったことを、かれは次のように説明しています。「現代科学の進歩は皮肉なことに、それ(政治学)がより専門的になるにしたがい、具体的な問題にますます直接適用できないものにしている…洗練された社会科学の方法(モデル、統計学、難解な専門用語)は、専門家以外の参入を阻む理想的な障壁を提供している…テクニックとして狭く定義された厳密さの追求は、政治学が実践的問題にますます関連しなくなることを意味する」(同書、3-15ページ)。
こうしたデッシュ氏の危機感は、健全な民主国家を形成する政治学の役割が失われつつあることから生じています。この点は重要なので、かれの主張を以下に引用します。
「学者は政策立案者より、他のいくつか優れた点がある。かれらは(国家が直面する)問題や地域について、大半の政策決定者に比べて、より深い知識を発展させる時間を持っている。組織での終身在職権は、少なくとも理論上は、かれらに論争となっている問題を探究する自由や不人気の立場を表明する自由も与えている…大学に籍を置く学者は政策決定者に比べれば、特定の政策や計画への既得権益がほんの少しだけである…われわれの民主的な政治システムは、アイディアという市場が上手に機能すること、さまざまな強みと弱みを持つ個人や集団における抑制と均衡、より広い政策論争に参入している偏見(バイアス)を相殺することに依存しており、したがって、それぞれの限界を補い合っているのである」(同書、242ページ)。
要するに、民主国家を市民にとってよりよいものにする政策を立案するには、政治家や官僚といった実務家だけでなく、学問の自由を享受している学者がさまざなまアイディアを出し合うことにより、より合理的で適切な選択肢は生み出されるのだから、政治学を生業とする者は、政策形成に貢献すべきだということでしょう。それでは、具体的に、政治学者は何をすればよいのでしょうか。政策立案者は忙しいので、政治学者は、かれらの立場を考慮した政策提言を行うべきだということです。新聞の論評やブログは、その媒体になります。また、それらでは、ジャーゴン(難解な専門用語)を避け、平易な英語(わが国であれば平易な日本語)で書くべきだとデッシュ氏は述べています(同書、250ページ)。
こうした主張に同意する少なからぬ政治学者は、自分の仕事はあくまでも「社会科学」なのであり、ジャーナリズムではないと悩ましく思うかもしれません。確かに、「職業としての政治学」はジャーナリズムではありません。両者の線引きは、どこにあるのでしょうか。デッシュ氏は、根本的に、多くの政治学者が政治における科学の追求を勘違いしていると、このように指摘しています。「多くの社会科学者は、自然科学の形式(数学と普遍的モデル)を科学の定義と混同している。しかしながら、これは安全保障研究にとって分類的な間違いである」(同書、252ページ)。この点は、少し分かりにくいでしょうから、別の文献に助けてもらいましょう。組織の戦略論で著名な野中郁次郎氏は、歴史研究者たちとの共同研究である『戦略の本質』(日本経済新聞社、2005年)において、次のように述べています。
「戦略論は、人間世界を研究対象とする社会科学の一分野である…われわれは戦略論の科学化を志向するけれども、自然科学と同一の厳密さでの科学化を意図していない…社会科学の面白さは自然科学ではうまく扱えない価値、コンテクスト、パワーなどの現象を事例や物語をベースに、できるだけ客観的に、禁欲的に、現実に迫っていき、最終的には『かくあるべきである』という規範的命題を提示することにある」(『戦略の本質』333-335ページ)。
上記の方法論的立場をとる研究者は、一般的に科学で推奨される演繹法ではなく、帰納法による命題の構築や限定的一般化を目指すことが少なくありません。上記の『戦略の本質』では、戦況を逆転した戦史の事例から、成功する戦略に共通するパターンを発見しようとしています。このブログでも過去に言及したアレキサンダー・ジョージ氏の抑止や強制外交の研究も、やはり帰納法をつかった事例から中範囲を理論を構築しています。独裁者の軍隊の軍事的効率性に関する研究や軍事組織のイノベーションに関する研究は、事例から理論を導出しています。これらには自然科学の研究で見られるたくさんの数式はありませんが、全て正真正銘の科学的な政治研究です。
デッシュ氏の議論に戻りましょう。かれは、政策分析やジャーナリズムと純粋な学問との間に中間地帯があると主張しています。政治学は、これらの間でバランスをとるべきだということです。そのために必要なことは、「方法論的多様性」であり、特定の方法だけを使うのではなく、目下の問題にとって最も適切なアプローチを採用するということです。ただし、これは十分条件ではありません。デッシュ氏によれば、政治学者は方法論から導出されるのではなく、取り組むべき問題から導出された研究に従事すべきだと指摘しています。これら2つの要件を満たすことにより、政治学は科学的で政策に役立つものになるのです(『無関係性の崇拝』250ページ)。
最後に、『無関係性の崇拝』を読んで、印象に残ったことを2点ほど指摘して、この記事を締めくくりたいと思います。1つは、アメリカの政治学において、「地域研究(area studies)」が、科学的ではないという理由により、「比較政治学(comparative politics)」に取って代わられたことです。第二次世界大戦時においては、アメリカで地域研究者は活躍していました。「地域研究は『戦略計画や軍事作成において最も価値』があった」ということです。日本との関連でいえば、文化人類学者のルース・ベネディクト氏による日本政治文化の研究は、応用社会科学の最も影響力のあった事例です。彼女の研究は、アメリカの戦後日本統治と再建に大きな役割を果たしたと考えられています。ところが、1960年代頃から政治学の分野でも、自然科学で用いられる数理的・数学的手法で政治現象を分析できると信じる、行動科学革命が深く入り込むようになりました。その結果、この方法に馴染まない地域研究は、政治学界では周縁化されてしまいました(「ソ連研究」は例外)。政策決定者は引き続き地域研究者を必要としていたにもかかわらず、大学は政策サークルに必要な地域の知識をますます提供できなくなってしまったのです。ベトナム戦争の悲劇は、アメリカにおける地域研究の衰退と無関係ではありません。政府の高官たちは、ベトナムに関する地域の専門知識を欲していましたが、大学から、その多くを得ることができませんでした。これは社会科学という学問が行動科学をますます志向したことにより、地域研究が衰退した結果だったのです(『無関係性の崇拝』48-49、58、199ページ)。
もう1つは、冷戦後に登場した安全保障研究「不要論」です。この主張を主導した1人が政治学者のデーヴィッド・ボールドウィン氏(コロンビア大学、プリンストン大学)でした。かれは安全保障研究者を強烈に批判して、政治学の専門分野としての安全保障研究は消滅させてもよいのではないかと、このように訴えたのです。「『政策に関連』づけたい欲求は、何人かの学者を政策立案者とのあまりにも緊密な関係に導いたために、かれらが自律した知識人とみなされなくなってしまい、政策立案の支配層の一部として考えられるようになった…安全保障研究の分野はしばしば戦略研究と同じだとされてきた…国政術の軍事的手段は…安全保障の専門家の中心的関心になった…かれらは軍事的安全保障は他の目標に優先すると主張する傾向にある…他の目標とのトレードオフなど認めらないというのだ…国家は外部からの攻撃から武力なしでは自分を守れないが、吸える空気や飲める水のない国家は確実に生き残ることができないだろう…資源が希少な世界では、軍事安全保障の目標は常に他の目標と対立する…冷戦の終焉が軍事的安全保障をより豊富なものにしたということは、資源を安全保障から公共政策の他の目標に投入する時が来たことを示唆していそうだ…おそらく、安全保障研究という分野を廃止する時が来たのだ」(David A. Baldwin, "Security Studies and the End of the Cold War," World Politics, Vol. 48, No. 1, October 1995, pp. 117-141)。さらに、安全保障研究や戦略研究は、数理的で厳格な科学を志向する「合理的選択論者」からも非難を浴びました。こうした冷戦後の政治学の傾向にジャック・スナイダー氏(コロンビア大学)は、こう苦言を呈していました。「既にあるアイディアを拝借して、安全保障研究に大立物を(既にあることに気づかずに)再発明しているか、数理化が実際に新しい概念を加えた程度を誇張している合理的選択論者に、わたしは気づいてきた。その間ずっと、(かれらは)伝統的な安全保障研究の後進性を批判しているのだ」(『無関係性の崇拝』218ページ)。幸いなことに、安全保障研究や戦略研究は、政治学において、こうした猛攻から生き延びました。
『無関係性の崇拝』が分析するのは、アメリカの政治学の変遷や方法論上の傾向なので、これを日本の政治学界にそのまま当てはめることは出来ません。わが国では、「地域研究」は国際政治学会で確固とした地位を築いており、「理論研究」や「歴史研究」などと相まって「方法論的多様性」を保っています。ウクライナ紛争の報道では、ロシアやヨーロッパといった特定の地域を専門とする、大学に籍を置く地域研究者がメディアで引っ張りだこです。また、冷戦後、日本で安全保障研究不要論が唱えられたことは、私が知る限り、ほぼ無かったといってよいでしょう。日本の防衛政策の策定においては、懇談会などを通して学者が関与してきました。さらに、日本の政治学において、過度な数理化が推し進められることも、今のところありません。日本の政治学は、悪くいえば、まとまりがないのかもしれませんが、良くいえば、健全な「方法論的多様性」を維持してきたのです。ただし、政治学者の政策提言に関して、久米郁夫氏(早稲田大学)の次の警句は、傾聴に値すると思います。「多様な推論の意義と必要性を認めたとしても、その推論が方法論的自覚に基づいた論争に耐えるものでなければ、結局は勢いだけの提言と自己満足に堕するだろう」(『書斎の窓』第680号、2022年3月、3ページ)。方法論的多元主義とは、「何でもアリ」とは異なります。政治学者は、定性的であれ定量的であれ、社会科学の方法論に基づいて推論を行い、それを政策提言の基礎とすべきだということなのでしょう。
追記:2023年に「国際関係論と政策関与」について、新しい興味深い調査結果が、アメリカ政治学会の『パースペクティヴ・オン・ポリティクス』誌に発表されました。この論文の著者たちは、これまで言われてきた常識とは異なり「国際関係学者は政策に高いレベルで関与している」と結論づけています。その大半のやり方はブログ記事や意見広告ですが、政策レポートやコンサルティングも顕著にみられるそうです。
米国の国際関係学者にメールでアンケートを行ったところ、回答者の約7割が、キャリア形成において、政策関連の組織で働いたことがあるとのことです。約半数は学界に入る前に政策形成の世界で働いていたと回答しています。そして、回答者の約7割が、政策に関与することは教育や研究の質を向上させると考えているのです。注目すべきは、定性的方法をとる学者も定量的(数量的)方法をとる学者も同等程度、政策に関与していることです。つまり、政治学における数理化は、国際関係研究者に「政策とは無縁なものへの崇拝」を促していないということです。そしてどちらの方法論をとる研究者も、その6割前後が、大学はもっと政策への関与を終身在職権や昇進の審査で評価すべきと回答しています。
ただし、こうした政策への関与は学問的誠実さの問題も提起しています。圧倒的多数(87%)の国際関係研究者は、政策への関与が何らかの義務であると考えています。その一方で、いわゆる「御用学者」が学問をゆがめる潜在的問題も無視できないということです。この調査を実施したC. ヘンドリクス氏、J. マクドナルド氏、R. パワーズ氏、S. パターソン氏、M. ティアリー氏は、以下のように述べています。
「政策に関与する学者が、政策立案のメンバーにアピールするために、自分の本当の信念や意見を歪める心配はある」という記述に、どの程度強く同意するか、または同意しないかを国際関係学者に尋ねたところ、3分の1以上(36.4%)が同意、29.4%が同意しない、34.3%が同意でも不同意でもないと回答。興味深いことに、活動のスポンサーに反対されることを想定して、自分の本当の信念や意見を和らげたり、控えたりしたことがあると自認する国際関係研究者はごく僅か(4.7%)だった。国際関係研究者は、資金提供者や助言する組織が聞きたいことを伝えようとする誘惑に駆られたことはないと報告しているが、複数の研究者は、同僚がそうしているのでは、と心配している。このことは…学問的誠実さの問題を提起している(p. 9)。
さらに、若手研究者とベテラン研究者でも、どのように政策に関与すべきかについて、意見が割れています。
「国際関係研究者は、政策集団のメンバーとの対話において、自らの見解を優遇するのか、それとも専門家のコンセンサスを伝えようとするのか」という問いに対して…主任教授の半数近くが、学術的なコンセンサスよりも自分の研究成果を重視することに同意するのに対し、そう回答した助教は28.6%に過ぎなかった。政策決定者は、政策決定に必要な情報として学術的なコンセンサスを重視する傾向があることを考えると、この結果は厄介である。その場にいる最も年長者の声(つまり、ランクによって示される学術的な資格)は、その専門性を活かして、テーマに関するコンセンサスの立場を主張する傾向が最も低いのかもしれない (p. 10)。
政策立案過程において、声の大きな年長の国際政治学者の「個人的な」意見が、学問的コンセンサスより影響力を持ちやすいとすれば、これは必ずしも健全ではないでしょう。