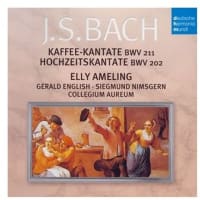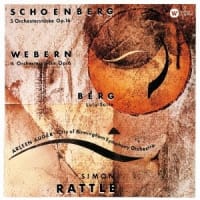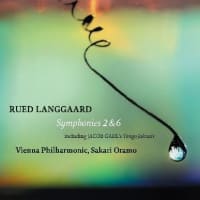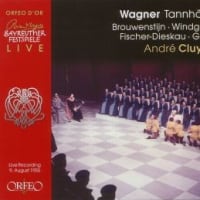JVC国際協力コンサート2008
第20回東京公演 ヘンデル『メサイア』
12月13日(土)
昭和女子大学人見記念講堂
合唱:JVC合唱団
指揮:ライダル・ハウゲ Reidar Hauge(ノルウェー)
ソプラノ:イザ・カタリナ・ゲリッケ Isa Katharina Gericke(ノルウェー・ドイツ)
アルト:マールテン・エンヘルチェス Maarten Engeltjes(オランダ)
テノール畑 儀文
バス:マグネ・フレンメリーMagne Fremmerlid(ノルウェー)
管弦楽:テレマン室内管弦楽団
重い付点のリズム(といっても最初は付点がないが)の上に歌われる"Surely Surely....(「まことに彼はわれわれの病を負い...」)"に入ると、それまで平坦だった音楽が「動き」始めた。それがオーケストラにも伝わり、ようやく全体としてまとまりが感じられるように。それまでは、音楽の密度が希薄。
NGOの日本国際ボランティアセンター(JVC)が主催するコンサート。
このコンサートのために「歌声ボランティアとして春から練習をしてきた」(プログラム)合唱団は、幅広い年齢層(遠目から見た限りではあるが)で構成され、総勢約200名がベーレンライター原典版らしき楽譜(赤)をもってステージに並ぶ様は壮観。
人数が多いこともあり、この作品において最も知られている《ハレルヤ》や《アーメンコーラス》では厚い響きを聴けた。
このブログでは、アマチュアのコンサート(主にオーケストラ)について感想を書いているのだが
その際に『アマチュアならではの熱さ、音楽への「ひたむき」な気持ちが、音楽に現れているか』と
いう点を基準としている。
今回のメサイアにおいて、どこかもの足りなさを感じた(気のせいだろうか?)。
例えば3部2曲目"Since by men came death...(「それは、死がひとりの人によってきたのだから…」 "。通奏低音によるイ短調の主和音の後、無伴奏で歌われる部分(Grave)、あるいは、同じく3部9曲(終曲)の最初、Worthyから"and hath redeemed us..."の響きの部分。聴くものをして(たとえ一瞬ではあるが)地上から引き離し天上へ誘うかのような和音進行にある本来あるべき「何か」を満たしきれないものが残る。
そのようななかで、ただ一人楽譜を持たずにこの作品を歌いきった人(ソプラノパート)が視覚的には印象に残る(楽譜を見てるからどうの、ということではないが---念のため)。その歌いぶりには音楽への献身が感じられたのだ。
指揮者、ソプラノそしてバスがノルウェーから、カウンターテナー(プログラムにはアルトと書かれている)オランダからの来日。
きびきびとした指揮ぶり、決め所において1拍目を左から真横に右への動きで示すのが特徴だ。
丁寧なサポートをするオーケストラ。特に通奏低音を担当していたチェロの柔軟なリズム。そしてトランペット。第3部4曲目"The trumpet shall sound... (「ラッパが響いて…」 )"でのさりげない装飾。
アンコール
「聖しこの夜」が最初は独唱者、ついで合唱、さらに会場へと広がり歌われた。こういった場合にありがちな月並みさがまったくない編曲で、チェロの応答のようなフレーズがとても美しかった。
(指揮者が曲が始まる前に会場に向けて促し)起立---これは一つの約束、儀式のようなもの---した"Hallelujah"では、会場でも歌う声が広がった。
高校のころ、ボールトの指揮するレコードで《メサイア》に入門、ここ数年は、聴くたびに強く親しみを感じるようになっている。実際に演奏会として取り上げられるのは、年末が多いというだけでなく、この作品がもつ祝祭的なものが聴くものをして気持ちをわくわくさせるものを持っている。
という面からすると今日の演奏では、祝祭的なものがやや少なかったようだ。