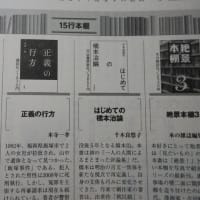太田省一『「笑っていいとも!」とその時代』
集英社新書 1034円
「森田一義アワー 笑っていいとも!」(フジテレビ系)の開始は1982年秋。2014年3月の終了まで約32年間、全8054回が放送された。
一本の番組を深掘りすることで時代と社会を読み解いていく。太田省一『「笑っていいとも!」とその時代』は、社会学者の著者による意欲的な試みだ。
この番組は戦後日本、特に「戦後民主主義が持つ可能性」を最も具現していたのではないか。本書はそんな仮説から出発している。
著者はいくつかの注目ポイントを挙げる。まず、「仕切らない司会者」という特異な存在だったタモリだ。
番組を切り回すことはせず、その場の雰囲気を自身も楽しもうとする。仕切ることを避けながら、「楽しくなければ」と連呼する80年代のテレビや時代との距離を保っていたというのだ。
次が、「テレフォンショッキング」のコーナーが象徴する「広場性」だ。ジャンルを超えたレギュラー出演者の組み合わせがテレビ的「つながり」を増幅し、様々な素人参加企画も番組の間口を広げていった。
さらに著者は、番組の拠点であるスタジオアルタがあった新宿という「場」に目を向ける。
60年代にカウンターカルチャーの聖地だった新宿。70年代半ば、歌舞伎町の飲み屋で生まれたのが「タモリ」だ。
演者と観客が渾然一体となった空間で、独自の密室芸を進化させる。そして80年代、不穏な黒メガネの男は、新宿に通勤する「仕切らない司会者」となった。
(週刊新潮 2024.05.16号)