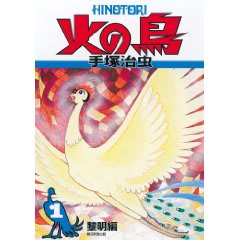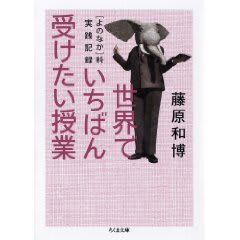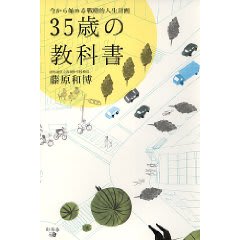 「35歳の教科書」藤原和博
「35歳の教科書」藤原和博作者の藤原和博さんは、ご存知の通り、東京都義務教育初の民間人校長として話題になった方です。
ロールプレイング(現実に似せた場面で,ある役割を模擬的に演じること)を授業に取り入れ、注目も集めました。
今回の本は
「35歳の教科書」
35はとっくに過ぎてるしなぁ(-.-)
戦略的人生計画というだけあって”35”という数字なのかもしれませんが、
40でも50でも、これから人生を作っていくうえでは年齢などあまり関係ないのかもしれません。
その気持ちさえあればね(^.^)
戦後の成長社会と今の成熟社会ではルールが違う!
正解主義ではいけないのです。
クリティカルシンキング(複眼思考)が大事だと言うのです。
わかる気がします。
藤原さんの生き方からも、多くを学べる気がします。
ただ、
やっぱり私は凡人なので、そうそう思考回路が変わるわけでもありません^^;
突然、めちゃくちゃ行動力がある人になるわけでもありません^^;
とにかく、私の人生の自由を少しでも味わいたいなぁと思います。
何歳になっても凝り固まらずに、学ぶ力を持ち続けることは大事ですね(^^)
『仕事内容のリストラ』
(1)「嫌われたくない」{好かれなければ」という気持ちを捨てる。
(2)実際に結婚式や葬式を断る。飲み会や付き合いのゴルフもやめてしまう。
(3)自分が今までやってきたことを一旦、10分の1まで減らしてみる。
・・・何かをやめることでしか、新しいことは入ってこないのですから。(本文より)
なかなか賛成です(^^)/
(結婚式や葬式…これは顔の広い方でしょうね…^^;)
なんかいいことないかなぁと思っているとき、
何かを打開したいとき、
今の状況を変えたいとき、
私は食事を抜くことがあります。または、少しにしたり…。
(アタシって変?)
だって、何もできなくて、何をしていいかわからないんだもん(^^ゞ
”やめる”ことしかできないんですー(~_~;)
”やめる”ことなら出来る!!
とりあえず、やめてみる!!