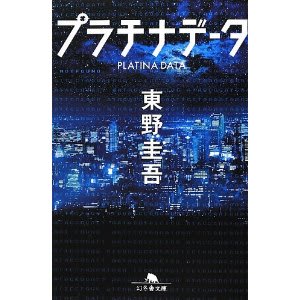世の中のニュースに限って言えば、
当事者でない自分がテレビや新聞のニュースを見て、何となく疑問を持ち(または素通りし)、そのまま自身の生活に戻ってしまう…
毎日がそういうことの繰り返しのように思います。
この本を手にした時…
ふだん、何とな~く疑問に思っていたことが、ふっと目の前の文字に現れる…
それも、何とな~くもやもやしていたことを解決してくれたりもする。
ふだん、テレビのニュースを見ていて、コメンテーターの意見もなんだか腑に落ちない…
私が、ぼや~んとある考えに至っても、言葉にまとめられないようなことを(頭わりぃー)、簡単な言葉で短く表現していたりする。
たとえば…本文90ページに、阪神大震災にふれてこう書いています。
個々の身体の経験自体、なかなか言葉にならないのだから、
自分が感じている出来事の全体と、一般に伝わる情報がつくる外観が異なっても不思議はないが、
それ以前に、個人の心身を深くゆさぶるような経験とは、そもそも言語化を逃れてゆこうとするものなのかもしれない。(2010.1.25)
人の痛みをわかろうと思っても、やっぱり同じ経験をしない限り、「胸に落ちる」ような理解はできないものですよね。
また、本文169ページには、
折りしも改正臓器移植法が七月から施行され、家族の同意があれば十五歳未満の脳死患者から臓器提供が、広く可能になった。
いよいよ家族が生死の線引きをする時代になったということだが、いったい家族はいつそんなに絶対的なものになったのだろう。(2010.8.2)
子供の脳死判定は難しいから臓器移植法は十五歳以上になったという改正前の経緯があったはずなのに、それはどうなったのでしょうか。
ふだん自分の子供が脳死状態になった時のことを考えている親が今どれだけいるでしょうか。
1日や2日で親に答えを出させる、というのも無理があるようにも感じます。
救いたい命があって猶予がないというのは、それはそうで、やりきれなさもありますが…。
そして、本文173ページには、
先日は、社民党の次期党首と目されていた名物女性代議士が、少数政党の野党でいても何もできないとして離党し、世間を驚かせた。
・・・・そもそも彼女が、自民や民主とは違うイデオロギー政党の一員であったことの意味は大きい。(2010.8.16)
そうそう。驚いた…。
残念でした。
高村さんの視点がとても好きです。
待ってました!っていう感じで、なんか心がスーッと軽くなるんですよね。
雑誌「AERA」に2009~2011年に連載された高村さんの時事評論集です。