 ファンタジーではなく、架空戦記として女性飛行士の戦いを描こうとしたとします。
ファンタジーではなく、架空戦記として女性飛行士の戦いを描こうとしたとします。現実に東部戦線ではソ連の女性飛行士たちが前線で戦っていましたし、英米共に女性飛行士が輸送任務に就いていました。ドイツでは女性テストパイロットがいました。問題は日本です。
日本人の女性飛行士が存在しないわけではありません。1913年、南部よね(1890-没年不明)はアメリカで飛行免許を取得して東洋人として初の女性パイロットとなり、国内では兵頭精(1899-1980)が1922年に三等飛行機操縦士試験に合格して国内初の女性飛行士となっています。二等飛行操縦士第一号となった木部シゲノ(1903-1980)は男装の麗人としてブロマイドまで発売される人気。西崎キク(1912-1979)は1933年8月に日本女性初の水上飛行機操縦士となっています。久岡秀子(1919-)は日本初のジェット・パイロット。及位野衣 (1916-)は日本女性として初めて米大陸横断飛行レースに参加しています(1975年になってのことだけど……)。
そういうわけで、ちゃんと名のあがる飛行士たちは存在します。しかし、彼女たちは常に先駆者でしかなく、アメリカのようにコクランの呼びかけで2万5000人の女性飛行士がWASPに応募するとか、ソ連のように各地に政府主導の飛行クラブが幾つもあってパイロットが養成されていたわけでもありません。
結局、国そのものが貧しかったのですね。飛行学校の月謝が大卒初任給の3倍、実習費は別途となれば、よほどの金銭的余裕があるか、韓国初の女性飛行士となった朴敬元(1901~1933)のようにマスコミを利用して一般からの寄付を募るしかないでしょう。そしてなんとか飛行士になれたとしても、結婚して引退とか満州で農業とか、次第に一線から外れてしまいます。戦争になってしまえば、それこそ「女が飛行機に乗って遊んでいていい時代ではない」となります。
どこまでさかのぼって改変すればいいのでしょう?『スカーレットストーム~第二海軍物語』や『大奥』のように疫病で男女比が狂ったとしなければ無理なのか、そこまでして戦争したいかってことですよね。
『スカーレットストーム~第二海軍物語』は、この手の架空戦記としてはエポックメイキング。それまで女性を主役にした戦争話というのはないでもなかったし、同人誌ネタではちょくちょくあったけれど、商業出版で真面目な話として、しかもライトノベル風のイラストをつけて出したってのは前代未聞。いわば萌え戦記の先駆け。
明治41年、シベリア奥地ツングースで謎の大爆発がおこり、それ以後、世界各国で男子の出生率が急速に低下。男子の出生率が21%にまで下がるに至り、もはや女性の社会進出は避けられることではなくなっていた。
昭和16年、凶作にあえぐアメリカは日本との開戦を決意するが、そのとき帝国海軍の一翼には女子兵による補助海軍、第二海軍があった……。
ということで、女性も前線に投入されているということ以外は、極めてまっとうな架空戦記でありました。
この本が2004年に刊行され、2003年に創刊した『ミリタリー・クラシック』の記事が偏向し始めている間に、2005年7月『萌えよ!戦車学校』が出版。ミリタリー業界に萌えの嵐が吹き荒れていくことになります。
『スカーレットストーム』は『スカーレットストーム~第二海軍物語』『新スカーレット・ストーム~南洋の大海戦』『ファイナル・スカーレット・ストーム~散る桜、咲く桜』の3冊で完結。タイトルや小だまたけしのかわいいイラストに騙されるとギョッとするくらい真っ当で面白い架空戦記でした。
【スカーレットストーム】【第二海軍物語】【南洋の大海戦】【散る桜、咲く桜】【中岡潤一郎】【小だまたけし】【男女比率】【戦争】【政治】【架空戦記】













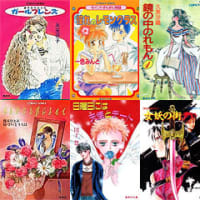

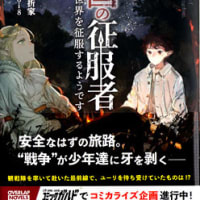

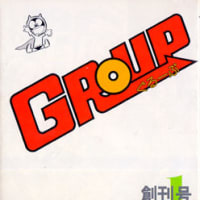
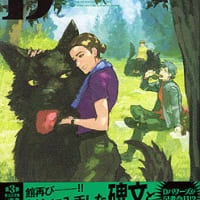
![「水路の夢[ウォーターウェイ]」 早見裕司](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/08/0c/ebdbd76e1b746940033530b209963446.jpg)





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます