1.神話時代の戦うオトメ
神代、「女が戦場に立つ」こと自体は珍しくは無かった。
・アテナからアスターテまで~戦いの女神たち
・戦う美女集団~ワルキューレとアマゾネス伝説
・巴御前~日本最強の女武将
・付喪神~擬人化されたアイテム
★レイ・カミングスの『時間を征服した男』にて科学族少女隊が実戦投入。(1929)
★アメリカンコミックに女性ヒーロー「ワンダーウーマン」登場。(1941)
2.戦後の戦う女性たち~TV時代の戦う女性集団
戦争によって不足した労働力を女性が担うようになって社会真進出が進み、1970年代初頭よりの女性解放運動「ウーマンリブ」も広まっていく。
1972年にはローラーゲームの日本人女性によるチーム「東京ボンバーズ」の試合が東京12チャンネルで毎週レギュラー放送されてブームになり、また1976年には女子プロレスラーのタッグチーム「ビューティ・ペア」が人気となり、女子プロレスがブームとなるなど「戦う女性」が広く認識され始め、少女マンガの世界でも「強い女性」が頭角を現し始める。
・戦う女性の再発見
・視聴率稼ぎのお色気アクション
・汗まみれの女たち
・女は働き、男は家を守る~キャグニー&レイシー
★山田風太郎、女性忍者集団を主役にしたの伝奇小説『くノ一忍法帖』連載開始。(1960)
★テレビドラマ『マリンコングの大逆襲』に主人公を助ける謎の仮面のヒロイン「くれない天使」登場。(1960)
★戦闘機部隊のパイロットがすべて女性という特撮人形劇『キャプテン・スカーレット』(1967)放映開始。
★国際秘密保険調査員の女性グループが暴れるお色気アクションドラマ『プレイガール』放映開始。(1969)
★襲来するUFOを迎え撃つ最前線、月面基地の作戦指揮所がすべて女性コマンダーという特撮テレビ『謎の円盤UFO』放映開始。(1970)
★『マジンガーZ』に女性型巨大ロボット・アフロダイA登場。(1972)
★『好き! すき!! 魔女先生』に「アンドロ仮面」登場。学園ものから路線変更。(1972)
★『科学忍者隊ガッチャマン』放映開始。以後、タツノコ作品には肉弾戦に参加する強いヒロインが目立つようになる。(1972)
★『キューティーハニー』放映開始。(1973)
★3人の美女探偵が活躍するテレビドラマ『チャーリーズ・エンジェル』放映開始。(1976)
★『600万ドルの男』のスピンオフ作品『バイオニック・ジェミー』放映開始。(1976)
★タツノコアニメ 『ゴワッパー5 ゴーダム』放映。リーダーが少女のロボットもの。(1976)
★女性刑事のコンビを主人公とする刑事ドラマ『女刑事キャグニー&レイシー』スタート。(1982)
3.少女マンガは戦う
『ウルトラQ』ではカメラマン、『ウルトラマン』では通信担当、『ウルトラセブン』では医療担当、『サイボーグ009』では情報収集と、少年の世界では、あいかわらず女性は戦う男たちに守られる存在であり、共に戦場に立つことがあっても治療・偵察・通信などのサポート役であり、武器を取って戦っていてもすぐに窮地に陥ってヒーローに助けられる役を割り当てられることが多かった。
1969年から連載の始まったマンガ『ワイルド7』では1年後の「コンクリート・ゲリラ篇」よりゲリラハンター・ユキが加わるがいつの間にか員数外。女ワイルドも結成されるが間もなく壊滅状態に。
一方、1975年には少女マンガ誌「別冊マーガレット」にて、和田慎二の『超少女明日香』と柴田昌弘の『狼少女ラン』が読み切り掲載。好評を博してやがて長期連載化していくことになる。
こうしたSFやファンタジーに正面から挑んだ作品が少女マンガに増え、フェミニストSFも増えていたことから男性読者の敷居も下がり、男性であってもSFファンなら少女マンガは読んでいてあたりまえという時代になっていく。

・恋する少女から戦うヒロインへ
・少女マンガにおけるSFとファンタジー
・男性作家と少女マンガ
・魔法少女から超能力少女へ
★C.L.ムーアの『処女戦士ジレル』の日本語訳刊行。(1974)
★不思議な力を使うお手伝いさんがエスパー兄妹や忍者と戦う、和田慎二の『超少女明日香』シリーズがスタート。(1975)
★古代人類の血を引く少女の孤独な闘い、柴田昌弘の『狼少女ラン』シリーズがスタート。(1975)
★大和和紀の『はいからさんが通る』連載開始。少女マンガの王道ストーリーに酒乱で暴れるパワフルなヒロインを配置。(1975)
★必殺シリーズ『必殺からくり人』に初の女性リーダー、からくり人・花乃屋仇吉登場。(1976)
★萩尾望都『スターレッド』連載開始。(1978)
★権力者の娘が管理社会に反旗を翻す、奥友志津子の『ドリーマー』連載開始。(1980)
★女の子の身体と男の子の勇気で戦う立原あゆみの『すーぱー・アスパラガス』刊行。(1982)
4.SFの浸透と拡散の時代
これまで少女マンガの世界で浸透してきていたサイエンス・フィクションという概念が、「メカと美少女」の組み合わせという枠を与えられたことで少年マンガやアニメの世界でも拡散していく。まさに「SFは絵だねえ」という言葉そのままであった。
やがて『STOL』や『アトラス』など、同人マンガ作品を中心に、戦う女性、女性型メカ、少女が操るメカなどが増えていき、そこから商業作品へと広がっていき、それにともなってマンガやアニメに登場する女性たちも通信や医療といった補助スタッフではなく戦闘要員として活躍するものが増えていった。
・戦場に立つ女たち~弓さやかからセイラ・マスまで
・生身で戦う美少女~それもダイコン3から始まった
・「メカと美少女」が「メカ美少女」になるまで~空山基と園田健一
・そして戦場は女だらけになった……
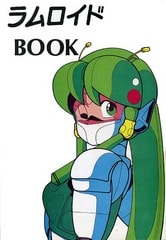 ★『グレートマジンガー』にて炎ジュンが操縦するビューナスAが戦場に登場。しかし、前作『マジンガーZ』におけるアフロダイA同様、サポート以上の活躍は無かった。(1974)
★『グレートマジンガー』にて炎ジュンが操縦するビューナスAが戦場に登場。しかし、前作『マジンガーZ』におけるアフロダイA同様、サポート以上の活躍は無かった。(1974)
★『秘密戦隊ゴレンジャー』に武器開発と爆発物処理のスペシャリストとしてモモレンジャー参加。(1975)
★同人誌「VTOL」にて園田健一が『うる星やつら』のキャラをロボット化したイラストを発表、後に『ラムロイドブック』としてまとまる。(1978)
★『機動戦士ガンダム』第16話「セイラ出撃」以後、女性が単独で兵士として戦場に立つようになる。(1979)
★怪力エスパー炎上寺由羅がテレポーター五味たむろと大暴れする、高橋留美子のコミック『ダストスパート!!』連載。(1979)
★『ダーティペア』(1979) 高千穂遙によるSFアクション。美少女エスパー2人組が災厄をまき散らす。
★人間を襲い寄生する異星生物エイリアンと女性クルーが戦う『エイリアン』公開。(1979)
★大阪で開催された日本SF大会DAICON3のオープニング映像として美少女がメカと戦うアニメが上映。後に大会の赤字対策としてビデオ販売。「戦う美少女とメカ」というビジュアルの定着。(1981)
★模型雑誌を起点に「MS(モビルスーツ)少女」に人気が出る。人型兵器の擬人化が進む。(1982)
★プラモデルのロボット「プラレスラー」を用いた競技「プラレス」を描いた『プラレス3四郎』始まる。プラレスラー桜姫が人気。(1982)
★『超時空要塞マクロス』放映開始。第12話「ビッグ・エスケープ」よりミリア・ファリーナ登場。(1982)
★コントロール中枢が美少女型アンドロイドとなった脱出用宇宙船ナダが登場する、佐々木淳子の『ブレーメン5』連載開始。(1982)
★コントロール中枢が美少女型アンドロイドとなった有機宇宙船チャイカが登場する、弓月光の『トラブル急行』連載開始。(1982)
★女性型ロボット兵器M66、M77が暴れる士郎正宗の『ブラックマジック』刊行。(1983)
★アクション映画『ストリート・オブ・ファイアー』公開。(1984)
★アニメ『重戦機エルガイム』と『魔法の天使クリィミーマミ』を足して割った設定の『ポニーメタル U-GAIM』の同人誌及びプロモーション映像ビデオ発売。(1985)
★怪力のエルフ少女が主人公の『エルフ・17』スタート。(1985)
★アニメ映画『プロジェクトA子』公開。タイトルは『プロジェクトA』のもじりだけれど、内容は女同士の三角関係に端を発した、怪力少女と強化スーツを装着した美少女による戦い。(1986)
★女性しかいない世界の未来戦記アニメ『ガルフォース ETERNAL STORY』がOVAリリース。(1986)
★必殺仕事人がモチーフの美少女SFのOVAシリーズ『バブルガムクライシス』スタート。(1987)
★新谷かおるの『エリア88』にてセイレーン・バルナックがサキ・ヴァシュタールの指揮下に入る。(1979)
5.架空戦記への女性進出
女性が単なる男のサポート役・引き立て役から対等のパートナーとなり、またメカ少女になったり現用兵器を操ることで戦場の主役へとなっていき、青少年向けのコミックや小説でも、既に主人公が女性というのは珍しいものではなくなっていた。
こうした中、閉塞感に陥っていたミリタリー・ジャンルにおいて、萌え系美少女を投入するケースが増えていき、女性ばかりの軍隊などが登場するに至る。そしてさらには兵器=女性という概念が定着していく。
・少女がすべてを蹂躙する~乙女のたしなみ
・男たちは見守る~ギャルゲーの派生から
・女たちの戦争~架空戦記の女子部隊
・メカ娘がいっぱい
・戦艦と呼ばれて~プリンセス・プラスティックから艦娘まで
★天才魔導士リナ=インバースが活躍する『スレイヤーズ』スタート。(1990)
★母親が息子を守って未来から送り込まれたアンドロイドと戦う映画『ターミネーター2』公開。(1991)
★自衛隊が世界初の女性パイロットだけのアクロバット・チームを結成するという、清水としみつの『青空少女隊』刊行。アニメ化。(1991)
★ 吉岡平のライトノベル及びOVA『アイドル防衛隊ハミングバード』スタート。自衛隊が民営化されて戦闘機を操る女性アイドルが登場する時代の物語だけれど、基本の設定は『サンダーバード』。(1993)
★コンピュータを擬人化して美少女化した、新谷かおるの『ぶっとび!!CPU』スタート。(1993)
★明貴美加によるMS少女イラストを集めた『超音速のMS少女』刊行。(1994)
★『ウルトラマンテイガ』にシリーズ初の女性隊長イルマ・メグミ登場。(1996)
★おバカな女子高生吸血鬼ハンターが主役の『バフィー~恋する十字架~』放映開始。(1997)
 ★無人機械が少女の姿をしているのがあたりまえという、米田淳一の『プリンセス・プラスティック』シリーズがスタート。おそらく個体の美少女を「戦艦」と言い切った最初の作品。(1997)
★無人機械が少女の姿をしているのがあたりまえという、米田淳一の『プリンセス・プラスティック』シリーズがスタート。おそらく個体の美少女を「戦艦」と言い切った最初の作品。(1997)
★『ウルトラマンガイア』に女性だけの戦闘機チーム「チームクロウ」登場。(1998)
★中里融司による仮想戦記『軍艦越後の生涯』では、軍艦にはそれぞれ女性の姿をした船魂が宿るとして、各戦艦に美少女が具現化。(2001)
★「Project G.A.」スタート。(2001)
★男子の出生率が下がったことで女性だけの女子補助海軍も創設された……という中岡潤一郎の『スカーレット・ストーム』刊行。(2004)
★第二次大戦中の空軍と陸軍の兵器を擬人化した、島田フミカネによるメカ少女のイラストコラム企画『ストライク・ウィッチーズ』がマンガ雑誌「月刊コンプエース」にて始まる。(2005)
★戦闘機や戦車などの兵器を擬人化した「メカ娘」が広まり、島田フミカネがデザインした「メカ娘」を、コナミがシリーズ化して発売。(2005)
★美少女たちの語りで戦車の仕組みや運用、開発史などについて教える『萌えよ!戦車学校』発売。(2005)
★ミリタリー雑誌『ミリタリー・クラシックス』から、兵器を萌え美少女化したイラストや記事の部分だけを独立させて『MC☆あくしず』創刊。(2006)
★『ストライク・ウィッチーズ』アニメ化。(2007)
★超兵器を搭載した第二次世界大戦時の軍艦群“霧の艦隊”との戦いを描いた、Ark Performanceによる海洋戦記マンガ『蒼き鋼のアルペジオ』連載開始。戦艦のコントロール中枢が美少女化。(2009)
★戦車道が乙女のたしなみとされている世界の『ガールズ&パンツァー』放送開始。(2012)
★『蒼き鋼のアルペジオ』アニメ化。(2013)
★ブラウザゲーム『艦隊これくしょん -艦これ-』始まる。(2013)
偏った読書体験から戦うヒロインの系譜についての覚え書き。
守られるべき存在、職場の華、通信・諜報・医療・事務などのサポートスタッフとして扱われることの多かった女性が戦場の主役になるまでで、全体の流れを把握するために概論のみ。レッド・ソーニャとか女ターザンは沼が深いので省きました。
原点を探していくと、「戦うヒロイン」というと日本でも源平の時代までは軽く遡れるので意味なし。創作が男性主体だと男性主役で女性が添え物になりがち、または女神として祀り上げられるということか。
「女性型ロボット」の元祖というと、映画『メトロポリス』(1927)のアンドロイド・マリアなんだろうけれど、日本人の原点としてはアフロダイAと考えるべきなのかな。それが「美少女なメカ」ということになると、年表を見ていてMS少女とラムロイドのどちらが早いかという話になるかなと思うのだけれど、そうすると当然のように手塚治虫の陰が。『鉄腕アトム』とか『疾風Z』とか『マグマ大使』とかまで行ってしまうんですよね。恐るべし。
ロボットもののヒロインは、タツノコが早期からむくつけき男をぶん殴って叩き伏せるヒロインを次々に送り出していたのに対し、全体的には紅一点で、ロボットに乗り込んでも悲鳴要員ということが多くて、忍者とか格闘技もできるとかいう設定はなかなか使われず。『超獣機神ダンクーガ』(1985)あたりまでいくとヒロインの暴れっぷりが目立ちだし、『破邪大星ダンガイオー』(1987)あたりまでいくと合体ロボットのパイロット4人中3人が女性になります。
紅一点ではなく、「女性ばかりの武装集団」でかつ「男主人公の当て馬」でない……というと『ガルフォース』『バブルガムクライシス』などのSFものから流行だし、民営化された自衛隊『ハミングバード』とかアクロバットチーム『青空少女隊』になりますが、大元祖はやはりワルキューレかアマゾネスかということになろうと思います。
とりあえず思いつくまま。(2015/02/05 改稿)
神代、「女が戦場に立つ」こと自体は珍しくは無かった。
・アテナからアスターテまで~戦いの女神たち
・戦う美女集団~ワルキューレとアマゾネス伝説
・巴御前~日本最強の女武将
・付喪神~擬人化されたアイテム
★レイ・カミングスの『時間を征服した男』にて科学族少女隊が実戦投入。(1929)
★アメリカンコミックに女性ヒーロー「ワンダーウーマン」登場。(1941)
2.戦後の戦う女性たち~TV時代の戦う女性集団
戦争によって不足した労働力を女性が担うようになって社会真進出が進み、1970年代初頭よりの女性解放運動「ウーマンリブ」も広まっていく。
1972年にはローラーゲームの日本人女性によるチーム「東京ボンバーズ」の試合が東京12チャンネルで毎週レギュラー放送されてブームになり、また1976年には女子プロレスラーのタッグチーム「ビューティ・ペア」が人気となり、女子プロレスがブームとなるなど「戦う女性」が広く認識され始め、少女マンガの世界でも「強い女性」が頭角を現し始める。
・戦う女性の再発見
・視聴率稼ぎのお色気アクション
・汗まみれの女たち
・女は働き、男は家を守る~キャグニー&レイシー
★山田風太郎、女性忍者集団を主役にしたの伝奇小説『くノ一忍法帖』連載開始。(1960)
★テレビドラマ『マリンコングの大逆襲』に主人公を助ける謎の仮面のヒロイン「くれない天使」登場。(1960)
★戦闘機部隊のパイロットがすべて女性という特撮人形劇『キャプテン・スカーレット』(1967)放映開始。
★国際秘密保険調査員の女性グループが暴れるお色気アクションドラマ『プレイガール』放映開始。(1969)
★襲来するUFOを迎え撃つ最前線、月面基地の作戦指揮所がすべて女性コマンダーという特撮テレビ『謎の円盤UFO』放映開始。(1970)
★『マジンガーZ』に女性型巨大ロボット・アフロダイA登場。(1972)
★『好き! すき!! 魔女先生』に「アンドロ仮面」登場。学園ものから路線変更。(1972)
★『科学忍者隊ガッチャマン』放映開始。以後、タツノコ作品には肉弾戦に参加する強いヒロインが目立つようになる。(1972)
★『キューティーハニー』放映開始。(1973)
★3人の美女探偵が活躍するテレビドラマ『チャーリーズ・エンジェル』放映開始。(1976)
★『600万ドルの男』のスピンオフ作品『バイオニック・ジェミー』放映開始。(1976)
★タツノコアニメ 『ゴワッパー5 ゴーダム』放映。リーダーが少女のロボットもの。(1976)
★女性刑事のコンビを主人公とする刑事ドラマ『女刑事キャグニー&レイシー』スタート。(1982)
3.少女マンガは戦う
『ウルトラQ』ではカメラマン、『ウルトラマン』では通信担当、『ウルトラセブン』では医療担当、『サイボーグ009』では情報収集と、少年の世界では、あいかわらず女性は戦う男たちに守られる存在であり、共に戦場に立つことがあっても治療・偵察・通信などのサポート役であり、武器を取って戦っていてもすぐに窮地に陥ってヒーローに助けられる役を割り当てられることが多かった。
1969年から連載の始まったマンガ『ワイルド7』では1年後の「コンクリート・ゲリラ篇」よりゲリラハンター・ユキが加わるがいつの間にか員数外。女ワイルドも結成されるが間もなく壊滅状態に。
一方、1975年には少女マンガ誌「別冊マーガレット」にて、和田慎二の『超少女明日香』と柴田昌弘の『狼少女ラン』が読み切り掲載。好評を博してやがて長期連載化していくことになる。
こうしたSFやファンタジーに正面から挑んだ作品が少女マンガに増え、フェミニストSFも増えていたことから男性読者の敷居も下がり、男性であってもSFファンなら少女マンガは読んでいてあたりまえという時代になっていく。

・恋する少女から戦うヒロインへ
・少女マンガにおけるSFとファンタジー
・男性作家と少女マンガ
・魔法少女から超能力少女へ
★C.L.ムーアの『処女戦士ジレル』の日本語訳刊行。(1974)
★不思議な力を使うお手伝いさんがエスパー兄妹や忍者と戦う、和田慎二の『超少女明日香』シリーズがスタート。(1975)
★古代人類の血を引く少女の孤独な闘い、柴田昌弘の『狼少女ラン』シリーズがスタート。(1975)
★大和和紀の『はいからさんが通る』連載開始。少女マンガの王道ストーリーに酒乱で暴れるパワフルなヒロインを配置。(1975)
★必殺シリーズ『必殺からくり人』に初の女性リーダー、からくり人・花乃屋仇吉登場。(1976)
★萩尾望都『スターレッド』連載開始。(1978)
★権力者の娘が管理社会に反旗を翻す、奥友志津子の『ドリーマー』連載開始。(1980)
★女の子の身体と男の子の勇気で戦う立原あゆみの『すーぱー・アスパラガス』刊行。(1982)
4.SFの浸透と拡散の時代
これまで少女マンガの世界で浸透してきていたサイエンス・フィクションという概念が、「メカと美少女」の組み合わせという枠を与えられたことで少年マンガやアニメの世界でも拡散していく。まさに「SFは絵だねえ」という言葉そのままであった。
やがて『STOL』や『アトラス』など、同人マンガ作品を中心に、戦う女性、女性型メカ、少女が操るメカなどが増えていき、そこから商業作品へと広がっていき、それにともなってマンガやアニメに登場する女性たちも通信や医療といった補助スタッフではなく戦闘要員として活躍するものが増えていった。
・戦場に立つ女たち~弓さやかからセイラ・マスまで
・生身で戦う美少女~それもダイコン3から始まった
・「メカと美少女」が「メカ美少女」になるまで~空山基と園田健一
・そして戦場は女だらけになった……
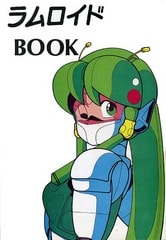 ★『グレートマジンガー』にて炎ジュンが操縦するビューナスAが戦場に登場。しかし、前作『マジンガーZ』におけるアフロダイA同様、サポート以上の活躍は無かった。(1974)
★『グレートマジンガー』にて炎ジュンが操縦するビューナスAが戦場に登場。しかし、前作『マジンガーZ』におけるアフロダイA同様、サポート以上の活躍は無かった。(1974)★『秘密戦隊ゴレンジャー』に武器開発と爆発物処理のスペシャリストとしてモモレンジャー参加。(1975)
★同人誌「VTOL」にて園田健一が『うる星やつら』のキャラをロボット化したイラストを発表、後に『ラムロイドブック』としてまとまる。(1978)
★『機動戦士ガンダム』第16話「セイラ出撃」以後、女性が単独で兵士として戦場に立つようになる。(1979)
★怪力エスパー炎上寺由羅がテレポーター五味たむろと大暴れする、高橋留美子のコミック『ダストスパート!!』連載。(1979)
★『ダーティペア』(1979) 高千穂遙によるSFアクション。美少女エスパー2人組が災厄をまき散らす。
★人間を襲い寄生する異星生物エイリアンと女性クルーが戦う『エイリアン』公開。(1979)
★大阪で開催された日本SF大会DAICON3のオープニング映像として美少女がメカと戦うアニメが上映。後に大会の赤字対策としてビデオ販売。「戦う美少女とメカ」というビジュアルの定着。(1981)
★模型雑誌を起点に「MS(モビルスーツ)少女」に人気が出る。人型兵器の擬人化が進む。(1982)
★プラモデルのロボット「プラレスラー」を用いた競技「プラレス」を描いた『プラレス3四郎』始まる。プラレスラー桜姫が人気。(1982)
★『超時空要塞マクロス』放映開始。第12話「ビッグ・エスケープ」よりミリア・ファリーナ登場。(1982)
★コントロール中枢が美少女型アンドロイドとなった脱出用宇宙船ナダが登場する、佐々木淳子の『ブレーメン5』連載開始。(1982)
★コントロール中枢が美少女型アンドロイドとなった有機宇宙船チャイカが登場する、弓月光の『トラブル急行』連載開始。(1982)
★女性型ロボット兵器M66、M77が暴れる士郎正宗の『ブラックマジック』刊行。(1983)
★アクション映画『ストリート・オブ・ファイアー』公開。(1984)
★アニメ『重戦機エルガイム』と『魔法の天使クリィミーマミ』を足して割った設定の『ポニーメタル U-GAIM』の同人誌及びプロモーション映像ビデオ発売。(1985)
★怪力のエルフ少女が主人公の『エルフ・17』スタート。(1985)
★アニメ映画『プロジェクトA子』公開。タイトルは『プロジェクトA』のもじりだけれど、内容は女同士の三角関係に端を発した、怪力少女と強化スーツを装着した美少女による戦い。(1986)
★女性しかいない世界の未来戦記アニメ『ガルフォース ETERNAL STORY』がOVAリリース。(1986)
★必殺仕事人がモチーフの美少女SFのOVAシリーズ『バブルガムクライシス』スタート。(1987)
★新谷かおるの『エリア88』にてセイレーン・バルナックがサキ・ヴァシュタールの指揮下に入る。(1979)
5.架空戦記への女性進出
女性が単なる男のサポート役・引き立て役から対等のパートナーとなり、またメカ少女になったり現用兵器を操ることで戦場の主役へとなっていき、青少年向けのコミックや小説でも、既に主人公が女性というのは珍しいものではなくなっていた。
こうした中、閉塞感に陥っていたミリタリー・ジャンルにおいて、萌え系美少女を投入するケースが増えていき、女性ばかりの軍隊などが登場するに至る。そしてさらには兵器=女性という概念が定着していく。
・少女がすべてを蹂躙する~乙女のたしなみ
・男たちは見守る~ギャルゲーの派生から
・女たちの戦争~架空戦記の女子部隊
・メカ娘がいっぱい
・戦艦と呼ばれて~プリンセス・プラスティックから艦娘まで
★天才魔導士リナ=インバースが活躍する『スレイヤーズ』スタート。(1990)
★母親が息子を守って未来から送り込まれたアンドロイドと戦う映画『ターミネーター2』公開。(1991)
★自衛隊が世界初の女性パイロットだけのアクロバット・チームを結成するという、清水としみつの『青空少女隊』刊行。アニメ化。(1991)
★ 吉岡平のライトノベル及びOVA『アイドル防衛隊ハミングバード』スタート。自衛隊が民営化されて戦闘機を操る女性アイドルが登場する時代の物語だけれど、基本の設定は『サンダーバード』。(1993)
★コンピュータを擬人化して美少女化した、新谷かおるの『ぶっとび!!CPU』スタート。(1993)
★明貴美加によるMS少女イラストを集めた『超音速のMS少女』刊行。(1994)
★『ウルトラマンテイガ』にシリーズ初の女性隊長イルマ・メグミ登場。(1996)
★おバカな女子高生吸血鬼ハンターが主役の『バフィー~恋する十字架~』放映開始。(1997)
 ★無人機械が少女の姿をしているのがあたりまえという、米田淳一の『プリンセス・プラスティック』シリーズがスタート。おそらく個体の美少女を「戦艦」と言い切った最初の作品。(1997)
★無人機械が少女の姿をしているのがあたりまえという、米田淳一の『プリンセス・プラスティック』シリーズがスタート。おそらく個体の美少女を「戦艦」と言い切った最初の作品。(1997)★『ウルトラマンガイア』に女性だけの戦闘機チーム「チームクロウ」登場。(1998)
★中里融司による仮想戦記『軍艦越後の生涯』では、軍艦にはそれぞれ女性の姿をした船魂が宿るとして、各戦艦に美少女が具現化。(2001)
★「Project G.A.」スタート。(2001)
★男子の出生率が下がったことで女性だけの女子補助海軍も創設された……という中岡潤一郎の『スカーレット・ストーム』刊行。(2004)
★第二次大戦中の空軍と陸軍の兵器を擬人化した、島田フミカネによるメカ少女のイラストコラム企画『ストライク・ウィッチーズ』がマンガ雑誌「月刊コンプエース」にて始まる。(2005)
★戦闘機や戦車などの兵器を擬人化した「メカ娘」が広まり、島田フミカネがデザインした「メカ娘」を、コナミがシリーズ化して発売。(2005)
★美少女たちの語りで戦車の仕組みや運用、開発史などについて教える『萌えよ!戦車学校』発売。(2005)
★ミリタリー雑誌『ミリタリー・クラシックス』から、兵器を萌え美少女化したイラストや記事の部分だけを独立させて『MC☆あくしず』創刊。(2006)
★『ストライク・ウィッチーズ』アニメ化。(2007)
★超兵器を搭載した第二次世界大戦時の軍艦群“霧の艦隊”との戦いを描いた、Ark Performanceによる海洋戦記マンガ『蒼き鋼のアルペジオ』連載開始。戦艦のコントロール中枢が美少女化。(2009)
★戦車道が乙女のたしなみとされている世界の『ガールズ&パンツァー』放送開始。(2012)
★『蒼き鋼のアルペジオ』アニメ化。(2013)
★ブラウザゲーム『艦隊これくしょん -艦これ-』始まる。(2013)
偏った読書体験から戦うヒロインの系譜についての覚え書き。
守られるべき存在、職場の華、通信・諜報・医療・事務などのサポートスタッフとして扱われることの多かった女性が戦場の主役になるまでで、全体の流れを把握するために概論のみ。レッド・ソーニャとか女ターザンは沼が深いので省きました。
原点を探していくと、「戦うヒロイン」というと日本でも源平の時代までは軽く遡れるので意味なし。創作が男性主体だと男性主役で女性が添え物になりがち、または女神として祀り上げられるということか。
「女性型ロボット」の元祖というと、映画『メトロポリス』(1927)のアンドロイド・マリアなんだろうけれど、日本人の原点としてはアフロダイAと考えるべきなのかな。それが「美少女なメカ」ということになると、年表を見ていてMS少女とラムロイドのどちらが早いかという話になるかなと思うのだけれど、そうすると当然のように手塚治虫の陰が。『鉄腕アトム』とか『疾風Z』とか『マグマ大使』とかまで行ってしまうんですよね。恐るべし。
ロボットもののヒロインは、タツノコが早期からむくつけき男をぶん殴って叩き伏せるヒロインを次々に送り出していたのに対し、全体的には紅一点で、ロボットに乗り込んでも悲鳴要員ということが多くて、忍者とか格闘技もできるとかいう設定はなかなか使われず。『超獣機神ダンクーガ』(1985)あたりまでいくとヒロインの暴れっぷりが目立ちだし、『破邪大星ダンガイオー』(1987)あたりまでいくと合体ロボットのパイロット4人中3人が女性になります。
紅一点ではなく、「女性ばかりの武装集団」でかつ「男主人公の当て馬」でない……というと『ガルフォース』『バブルガムクライシス』などのSFものから流行だし、民営化された自衛隊『ハミングバード』とかアクロバットチーム『青空少女隊』になりますが、大元祖はやはりワルキューレかアマゾネスかということになろうと思います。
とりあえず思いつくまま。(2015/02/05 改稿)














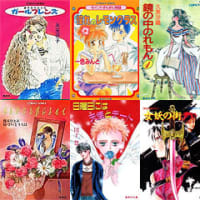

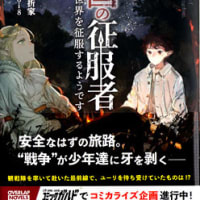

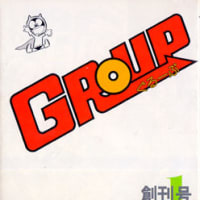
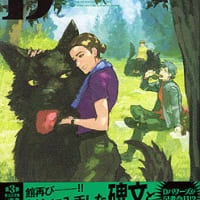
![「水路の夢[ウォーターウェイ]」 早見裕司](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/08/0c/ebdbd76e1b746940033530b209963446.jpg)






バイオニックジェミーとか好きでした。
絵画の小説では女性の探偵や軍人などなどが
多く出ており(少女探偵もいたなー)
ドキドキしながら読んだものです。
そのせいか今でも金髪美女(強い)がでるドラマが大好きですね(^_^;)