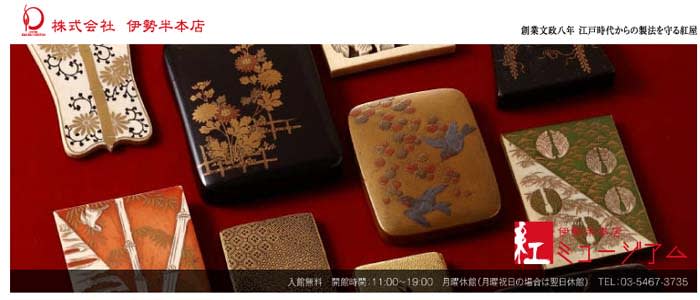***
週末コラム 16
***

美人の裏面
今週末の話題も鳥の話で・・・
カワセミという鳥を皆様ご存知ですよね
生きている宝石といわれるほど美しい小鳥
別名を「ヒスイ」といわれ、漢字では「翡翠」とかきます
「翡」 は雄のカワセミを、「翠」は雌のカワセミを指します
ともに羽が入っている文字ですから鳥類を意味します
宝石のヒスイはあとから「カワセミのようにうつくしい」ことから命名
このカワセミは美男美女の権化のような存在なので
近づいたらきっと馥郁とした香りが漂うと思いがちですが実は、猛烈な悪臭がします
英語では「Kingfisher」といい漁師の王様という意味です
東北の一部では、この鳥のことを「クサンポ鳥」といいます
臭い鳥という意味です

成鳥は水中に飛び込んで魚を捕らえるので
絶えず羽づくろいをして身綺麗にしていますが、繁殖期の巣の中は
魚の腐ったにおいに満ち溢れています
魚を消化した液状の糞を、雛が巣の出入り口に向かって射出します
巣穴の坑道は外に向かってゆるい下りになっているので
糞は、白いペイントのように坑道を流れ
雛が巣立つ頃には外に流れ出てきます
その臭いこと、百年の恋も冷めてしまうほど・・
又成鳥が魚を捕まえると岩や木の枝に叩きつけて殺します
そんな情け容赦のない殺しかたは、息のつまる残酷さです
しかし、雄は最愛の雌にとらえた魚をプレゼントします
雌が飲み込みやすいように必ず
魚の頭の方から口移しに渡します、心なごむ瞬間です
この時期は、カワセミの甲高いピッという鳴き声とともに
精力的に魚を捕まえます
ちなみの雄雌の見分け方は、嘴の下側が赤いのが雌、黒いのが雄です
お近くの川や池で見かけることが多くなりますので
ぜひ観察してみいてください

下の別ブログ名前をクリックすれば移動します
ぱふぱふの別館入口 「my Favorites photo」