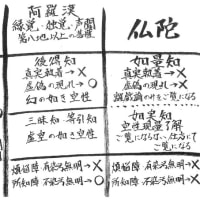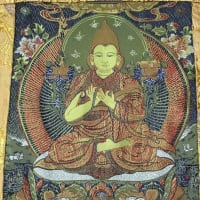初期臨済宗で楞厳呪がどのように誦されていたのかを調べてみたが、最後の偈頌、八句陀羅尼は見当たるが、全会が読誦されていたかどうかは今のところまだ分からない。
結局、修法の中心は、やはり台密法式である。
つまり、台密に禅を中心と置くか、禅に台密を補完するか、であって、栄西禅師の台密葉上流(建仁寺流)、栄朝流が、初期臨済宗では主流であったようだ。
九条道家開基、円爾禅師により臨済宗に改宗した往生院も、円爾禅師の流れとなることから、台密栄朝流による修法が中心となっていたと推測できることになる。ならば、唐招提寺に伝わった往生院にあった鎌倉期の戒体箱は、もしかしたら、この時に円爾により調えられたものであるのかもしれない。これは新しい考証となりそうである。
栄西禅師から学んだ覚心禅師が三時勤行を定めているが、仏頂尊勝陀羅尼、宝篋印陀羅尼、大悲心陀羅尼は見受けられるが、楞厳呪は、八句陀羅尼のみとなっている。台密では楞厳呪全体を読誦するものではなく、八句陀羅尼で唱えるのが主であったのかもしれない。
少しまた調べていきたい。
そうか、、栄西禅師→覚心禅師→瑩山禅師(曹洞宗)の流れがあるから、曹洞宗も早い段階から台密的な陀羅尼による修法を取り入れたものになっていったわけか、、
これは興味深い。
しかも、総持寺は、後醍醐帝、後村上帝に重用された覚明禅師による活躍から南朝勅願所となっている。
瑩山禅師、覚明禅師の法系は、南朝系と言えるわけである。これも興味深い。
ならば、総持寺と美作後南朝との関係も何か繋がる可能性があるだけに、更に深堀りしたいところである。
結局、修法の中心は、やはり台密法式である。
つまり、台密に禅を中心と置くか、禅に台密を補完するか、であって、栄西禅師の台密葉上流(建仁寺流)、栄朝流が、初期臨済宗では主流であったようだ。
九条道家開基、円爾禅師により臨済宗に改宗した往生院も、円爾禅師の流れとなることから、台密栄朝流による修法が中心となっていたと推測できることになる。ならば、唐招提寺に伝わった往生院にあった鎌倉期の戒体箱は、もしかしたら、この時に円爾により調えられたものであるのかもしれない。これは新しい考証となりそうである。
栄西禅師から学んだ覚心禅師が三時勤行を定めているが、仏頂尊勝陀羅尼、宝篋印陀羅尼、大悲心陀羅尼は見受けられるが、楞厳呪は、八句陀羅尼のみとなっている。台密では楞厳呪全体を読誦するものではなく、八句陀羅尼で唱えるのが主であったのかもしれない。
少しまた調べていきたい。
そうか、、栄西禅師→覚心禅師→瑩山禅師(曹洞宗)の流れがあるから、曹洞宗も早い段階から台密的な陀羅尼による修法を取り入れたものになっていったわけか、、
これは興味深い。
しかも、総持寺は、後醍醐帝、後村上帝に重用された覚明禅師による活躍から南朝勅願所となっている。
瑩山禅師、覚明禅師の法系は、南朝系と言えるわけである。これも興味深い。
ならば、総持寺と美作後南朝との関係も何か繋がる可能性があるだけに、更に深堀りしたいところである。