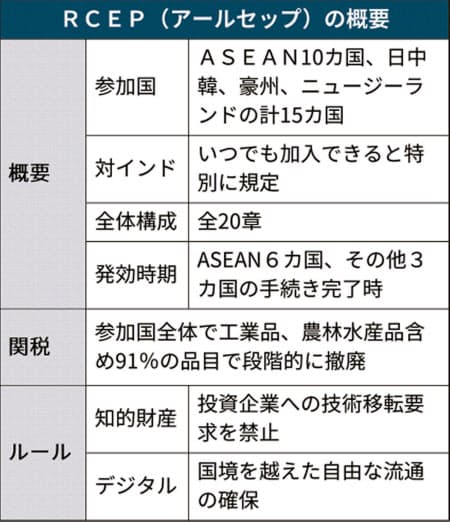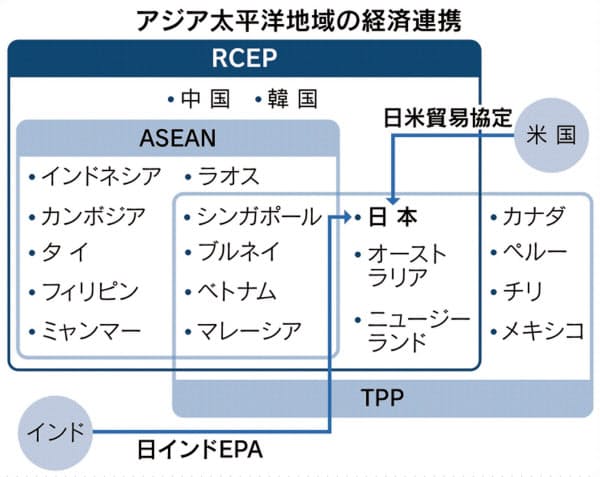批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。
通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者[1]に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により[2]、確定する[3]。
なお、アメリカ合衆国など連邦制を採用する一部の国では、国内法の制定にあたっても批准の用語が使用されることがあるが、本項では主に国家間の条約について解説する[註 1]。
目次
<label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label>概要[編集]
ひとつの国家が国・地域をまたがる条約や協定に正式に拘束されることへの同意を表明する方法(総称して「締結」と呼ばれる)は、通常、個別の条約において規定されており、多国間条約の場合には、多くは、「批准」や「受諾」(acceptance)、「承認」(approval)や「加入」(accession)による[4]。また、二国間条約の場合は、批准、受諾、承認、加入のほか、公文の交換[5]による場合もある[2]。中でも、批准は署名、議会における承認、元首等による裁可・認証、及び、批准書の寄託を経る厳格な手続きであるため、重要な多国間条約には、条約に未署名の国(条約の交渉に参加しなかった国)に対して加入による手続きを認めているほかは、批准によらなければならないとしているものも多い(例:ジェノサイド条約、欧州人権条約[7]、社会権規約、自由権規約、ウィーン条約法条約、包括的核実験禁止条約)。こうした条約は、条約に署名した国については、批准書とよばれる国家の同意や確認を示す文書を作成し、この文書を寄託または交換することによって、はじめて当該国について条約の効力が生じることとなる。
古くは外交権は君主の元に集約されており、この時代の締結は君主による条約内容の確認行為であった。大日本帝国憲法において、条約の締結が、帝国議会ではなく天皇の諮詢機関である枢密院による審議を経た背景には、条約締結権が天皇(実際には天皇が派遣した全権代表)にあると考えられていたことがある。締結が議会を経るようになったのは、アメリカ合衆国憲法において、行政府が派遣した全権代表が署名した条約内容を国民の代表である議会が国家・国民のために再検討するために議会による批准手続きを導入したことに由来している。
多国間条約の場合、締結した国の数が一定数を超えた後に発効すると定めているものが多い。発効後も、署名のみを行い未締結の国は条約に拘束されない。
上述のように、批准手続きのうちいくつかの手続を省略した受諾、承認、加入による締結を認める条約もあるが、当然ながら、締約国の国内法が簡略化された手続による条約の締結を認めない場合は、そのような条約でも締約国が国内法において定めた手続に則って処理される。また、条約に代えて、行政機関である政府間の取り決めであって、議会による承認等の煩雑な締結手続きを要さない行政協定(政府間協定)[8]を締結する場合もある。