2018年12月30日に発効された「TPP11(正式名称:CPTPP)」について解説します。
TPP11とは、日本を含めた11ヵ国が加盟する「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定」(※通称 TPP11)を指します。
わかりやすく説明すると、TPP11(CPTPP)とは、2017年にアメリカがTPPを離脱した後に再開されたFTA(自由貿易協定)であり、世界のGDPの約14%を占める巨大自由経済圏です。
TPP11では関税撤廃が定められていることから、ヒトやモノの移動がより活発化することが期待されています。
グローバル市場でビジネスをしている日本企業にとってのメリットは、海外での販路開拓・販路拡大はもちろん、特にASEAN諸国や北米、オセアニア圏といったTPP11(CPTPP)の加盟国への海外進出が容易になります。
2019年は日欧EPAの発効もあり、今後多くの日本企業にとって「海外」というワードが身近になっていきました。
さらに2020年5月、中国の国会となる全国人民代表大会(全人代)開幕後、中国の李克強(リー・クォーチャン)首相が、アメリカが離脱した後のTPP11への参加について〝前向きである〟という旨を述べたことが話題となりました。
それではさっそくTPP11(CPTPP)の概要やメリット・デメリット、そして他のメガFTA(巨大自由貿易協定)について見ていきましょう!
1. TPP11(CPTPP)とは?
日本主導の自由貿易協定
2018年12月30日に発効したTPP11(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)は、TPP11とも呼ばれているメガFTA(自由貿易協定)のひとつです。
このTPP11(CPTPP)は、世界のGDP(国内総生産)の約14%を占める巨大な自由貿易経済圏となっています。
元々は、アメリカが主導していたTPP(環太平洋経済パートナーシップ連携協定)に端を発していました。
2015年には12ヵ国で大筋合意がなされ、2016年に署名されまたのです。
しかし、2017年1月にトランプ大統領がTPPからの離脱を表明。
アメリカのTPP参加は実現に至りませんでした。
そこでアメリカに代わって指揮をとったのが日本。
アメリカを除いた11ヵ国でTPP11の実現へと交渉を再開したのです。
TPP11(CPTPP)の加盟国
TPP11は以下の国で構成されています。
■東アジア
日本
■東南アジア(ASEAN)
シンガポール
ベトナム
ブルネイ
マレーシア
■オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド
■北米
カナダ
メキシコ
■南米
ペルー
チリ
以上の11ヵ国を見てみるといずれも環太平洋(Trans-Pacific)造山帯に含まれる地域となっています。
またEU離脱を控えているイギリスは、
離脱後はEUと日本やASEAN諸国等との自由貿易協定が適用されないこともあり、TPPなどのFTA締結に意欲的であるとされています。
TPP11(TPP11)の発効基準
2018年12月に成立したTPP11(CPTPP)は、11ヵ国中6ヵ国以上が批准して60日後に発効するとなっていました。
9月末時点では、メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ(批准完了順)が批准していました。
10月31日に6ヵ国目となるオーストラリアがTPP11を批准したため、12月30日に発効しました。
残り5ヵ国(ベトナム・ブルネイ・マレーシア・チリ・ペルー)は未批准となっていますが、ベトナムは2019年1月14日に批准しました。
その一方、マレーシアでは昨年就任した老練なマハティール首相の下で、TPP11批准が検討されていますが、交渉見直しを求める意見を上がっています。
アメリカ・中国をけん制?
アメリカはトランプ政権下で保護主義政策による経済政策を進めています。
これにより、EU(欧州連合)や中国などの地域・国に影響を及ぼしています。
特に中国とは、昨年から米中貿易戦争と評される追加関税の応酬が続いています。
一方中国では、中国共産党による管理経済体制が敷かれています。
FTAであるTPP11は、このようなアメリカや中国に対してけん制の意味が込められているという見方もあります。
さらに、さらに2020年5月、中国の国会となる全国人民代表大会(全人代)開幕後、中国の李克強(リー・クォーチャン)首相が、アメリカが離脱した後のTPP11への参加について〝前向きである〟という旨を述べました。
アメリカ離脱後のTPP11に中国が参加した場合、日本よりも強い発言権を持つ可能性は充分にあるでしょう。
2. TPP11(CPTPP)のメリット・デメリット
海外進出が容易に
TPP11のメリットとして挙げられる点は、今までより加盟国への進出が容易になる点です。
加盟国には、ベトナムやマレーシアを中心に経済成長が著しい国が多くみられます。
例えばベトナムでは、政府調達の開放により、外資系企業のベトナムでの経済活動を拡大させることが見込まれています。
また現在日本とベトナムの間には、経済連携協定(EPA)が締結されており、非関税品目が定められていますが、TPP11発効により、その品目が増えます。
日越EPAでは、42%の工業製品の関税が免除されていますが、TPP11では70.2%に増加します。
また段階的な関税撤廃により、製品によっては輸出入にかかる関税のコストを削減することができます。
これにより、日本企業にとっては製品の輸出入が容易になり、海外の販路開拓・販路拡大が容易になります。
国内市場縮小の可能性
自由貿易による国際競争にさらされる国内市場では、農林水産を中心に国内市場の縮小が懸念されています。
特にニュージーランドやカナダなどの食料自給率の高い国からの安価な農作物の輸入や遺伝子組み換え農作物の輸入は問題視されており、国内の農業従事者にとって厳しい競争になると言われています。
これに対し農林水産省は、2017年に「総合的なTPP等関連政策大綱」を発表し、「2019年の農林水産物・食品の輸出額1兆円」の目標を掲げました。
目標達成のための施策として、農業機械導入への補助や農地の大区画化の支援、さらに政府による国別枠輸入量相当の備蓄米の買い入れなどを打ち出しています。
これにより、農業従事者の保護に努めながらも、国産農作物・水産物の輸出を拡大することで国内市場の拡大・海外市場への展開を目指すと考えられます。
8ヵ国とのEPAで恩恵少なく
日本は、既にTPP11加盟国の10ヵ国のうち8ヵ国と経済連携協定(EPA)を締結していることから、TPP11から受けられるメリットは少ないのではないかという指摘もあります。
EPA未締結の国は、カナダとニュージーランドとなっていますが、カナダとは交渉中断中、ニュージーランドとは、EPA交渉をしていない現状があります。
カナダとのEPAが締結されれば、日本のGDPを7,500億円まで増加すると推測されています。
一方、ニュージーランドとのEPAについては、2009年の鳩山由紀夫元総理大臣とジョン・キー・ニュージーランド首相との日ニュージーランド共同プレスステートメントでその可能性について言及されていますが、交渉段階には至りませんでした。
以上を踏まえると、カナダとのEPA締結の代替としてTPP11が機能することで上記のメリットを十分享受できると考えられます。
また、ニュージーランドとの自由貿易によるGDP推計などは不明ですが、カナダと同様数千億円のGDPを拡大するできると思われます。
しかし、日本のGDPは約500兆円となっているため、その経済効果は微々たるものであると言わざるを得ません。
3. TPP11(CPTPP)以外のメガFTA構想
日欧経済連携協定(日欧EPA)
日欧経済連携協定(日欧EPA)は、世界のGDPの約3割、貿易総額で約4割を占める巨大自由貿易圏(メガFTA)と言われています。
2009年に日欧定期首脳会談にて提案され、2017年7月に計18回の協議を経て大枠合意、同年12月に両者で交渉妥結に至りました。
2018年11月には日本が承認案を閣議決定、12月にはEU議会が承認し、2019年2月1日に発効されました。
これによってGDPで約5兆円の経済効果が見込まれています。
日欧EPA発効されたことでEU側は約99%の品目を非関税とするとともに、日本政府の調達案件への参加(入札)も可能になります。
これにより、EU産のワインやチーズなどの加工物が安く販売されます。一方日本は、約94%の品目で関税撤廃となります。
RCEP
RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership, 東アジア地域包括的経済連携)は、ASEAN10ヵ国と6ヵ国(日本・中国・韓国・オーストラリア・ニュージーランド・インド)によるメガFTA構想です。
2012年にASEAN関連首脳会議にてRCEPの交渉が開始しました。
いまだ交渉妥結には至っていませんが、2019年の妥結を目指しています。
交渉では、税関手続きや知的財産、電子商取引等の18分野が交渉対象となっており、現在までに…
・税関手続き・貿易円滑化
・衛生植物検疫措置(SPS)
・任意規格・強制規格・適合性評価手続き(STRACAP)
・中小企業
・経済技術協力
・政府調達
・制度的事項
(みずほ総合研究所「RCEP交渉年内実質妥結見送り 2019年交渉妥結を目指すも、難題は依然残る」より)
の7分野に合意がされています。
RCEPが締結されれば、世界人口の約半分、世界のGDPの約3割、世界の貿易総額の約3割を占める広域自由貿易経済圏が誕生します。
また、日本の貿易総額のうち約47%がRCEP参加国で占めていることから、日本にとって非常に重要な経済連携であると言えます。
日中韓FTA
日中韓FTAは、2012年の日中韓サミットで交渉が開始されました。2018年12月までに14回の協議が行われており、未だ締結には至っていません。
日中韓FTAは、先述のRCEPやアメリカやロシア、香港など21ヵ国・地域が参加する広範なアジア太平洋協力(FTAAP)実現のための一歩だともいわれています。
しかしながら、日中韓の関係は、政治や歴史問題などにより不安定であることから実現にはまだ時間がかかると思われます。
そのため、2019年に早期妥結を目指すRCEPが、日韓FTAより先に実現する可能性もあります。
4. TPP11(CPTPP)で海外進出がより身近に
アメリカ・中国にも注目
以上、TPP11(CPTPP)についてみてきました。TPP11により、ベトナムやシンガポールなど高成長が続く国に対して、よりアプローチがしやすくなります。また、2019年2月1日に発効された日欧EPAにより、欧州市場へとアクセスが容易になります。
その一方で、保護主義政策が続くアメリカや米中貿易摩擦であえぐ中国は、人口規模や経済規模から見て魅力的な市場にも拘らず、環太平洋地域・EUと比べて進出がしにくくなっているという印象を受けます。
しかしながら、日本企業にとっては重要な拠点であることは間違いありません。
2019年は、アメリカや中国だけでなく、TPP11加盟国やEUへの進出チャンスとなる年になるとも言えるでしょう。










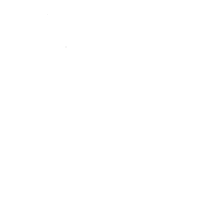

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます