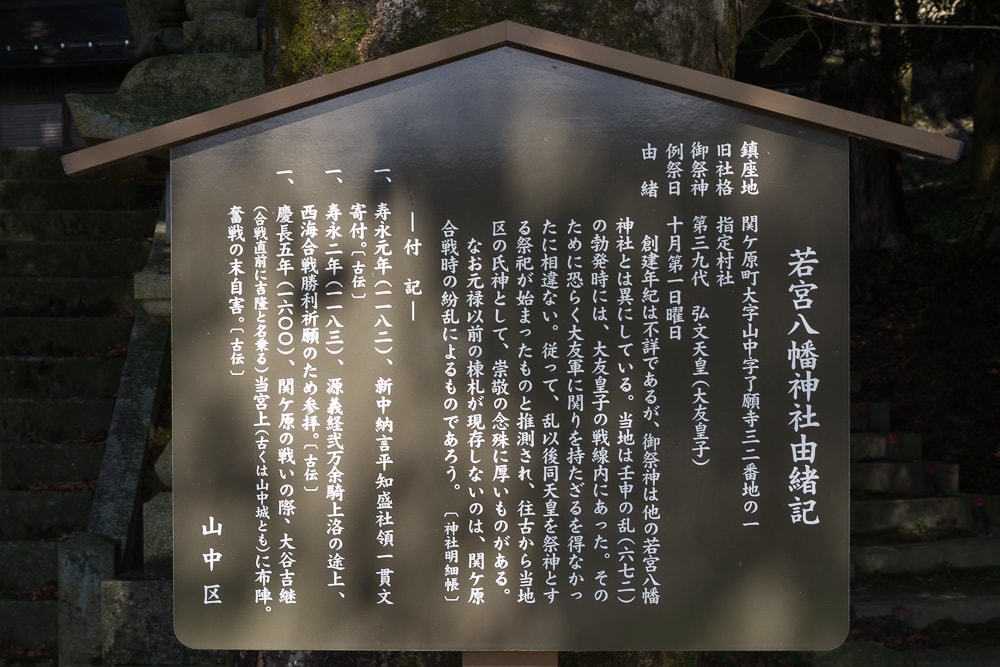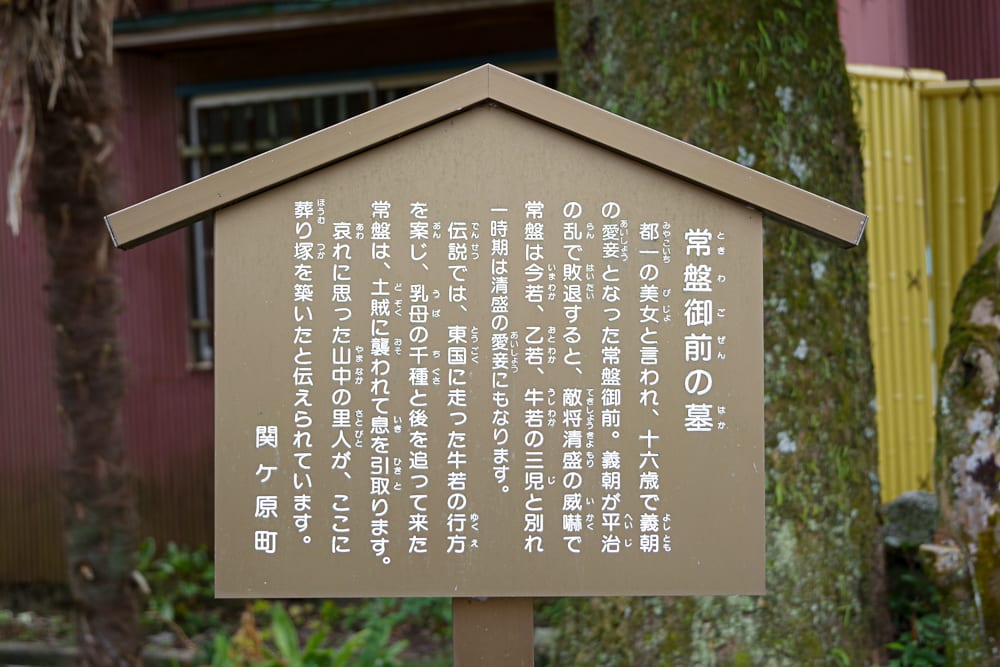GWに国宝 松本城へ出かけてきました。予想はしておりましたが予想以上に混んでいました。市営駐車場が8時からとの案内で
他で時間をつぶして8時に行ったらすでに満車で他に駐車  入城チケット購入に30分以上並んでいたら
入城チケット購入に30分以上並んでいたら
入場制限があって、今購入しても2時間後しか入れないと案内があり諦めてお城を一周してきました。

後ろの山は北アルプスです。



初めて訪れ、お堀を一周しただけですが姫路城とは違った趣き、存在感がありかっこいいです。
帰りは『寝覚の床』が良く見える木曽の信州そばを食べに立ち寄りました。ここは「絶景のそば処」で有名な蕎麦屋さんで屋外の席を頼みました。
中央本線と寝覚の床が見下ろせる場所は電車が通る時間が書いてあり写真を撮ってきました。
寝覚の床(ねざめのとこ)は日本五大名峡の一つで木曽川の水流によって花崗岩が侵食され自然にできた地形です。ここには『浦島太郎伝説』
があり、竜宮城から帰った浦島太郎がここで生業を立て暮らしているある日、玉手箱を開けて老人になったとの嘘っぽい話が実際に伝わっております。
この蕎麦屋さんはメニューが信州そばしかなく、田舎風の十割蕎麦はだし汁で頂く蕎麦湯も美味しく個人的にはお勧めです。
お店が混んでいたこともあり1時間くらい待っていたので電車の通過も気兼ねなく見ることができました。