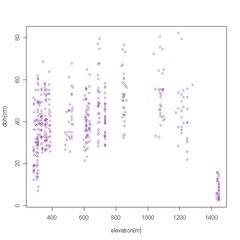・昨晩からのどが痛く、朝起きると具合がよろしくない。最近、アフター5が忙しく(といっても遊び呆けているわけではない・・・)、寒々しい体育館に通っていたので、風邪をひいたみたいだ。病院で薬をもらう。毎度受診すると、たいしたことないね、といわれるのだが、一度のどに来るとなかなか治らないんである。「あなたの風邪はどこから?」と聞かれれば、必ず「のどから」と答えるだろうな、当方の場合・・・。
・せっかくの小春日和だが、体調のせいか、どうも気分が盛り上がらない。とりあえず、LaTex化を試みようとするが、全然うまくいく気配なし・・・と。現在、当方のパソコンには飯島くんと富田くんのご尽力によりMeadowが動く環境になっているのだが、久保さんからWinShellが簡単そうだよん、というアドバイスが届く。ついふらふらと(?)、ダウンロードしてしまう。パソコンの中でけんかしなければいいのだが、ダウンロードはとりあえず簡単であった。WinShell3.0では、ヘルプの日本語訳までが作成されていて、とりあえず、ダウンロード。訳者はと見ると、”田中健太”とある。一瞬、イギリスの彼の地にいる氏かと思ったが、どうやら違うみたい。
・しばらく格闘するも、やはり一人では埒があかん・・・。ということで、いったんこの問題は放置。当方、「北海道の林木育種」という雑誌の編集委員となっているのだが、この雑誌が50周年を迎えるということで、その記念誌を作ることになっている。当然、当方にも担当(樹種)が振り当てられている。担当樹種とは、カンバ類とトネリコ類。要は、育種(造林)対象樹種について、それぞれ担当を決めて、分布、種特性などの基礎情報、遺伝情報、育種情報を整理するということになっている。が、全く進んでいないのが現状である。
・このまま放置していても駄目なので、無理やり、ウダイカンバについての文章を書いてみる。考えてみると、全国スケール、地域スケール、集団内スケールと遺伝マーカーを使った研究がそれなりに集積されていて、一つのモデルケースとなりそうな感じ。それぞれに”物語”があるわけだけど、それをいちいち書いていると他樹種とのバランスがものすごく悪くなりそう。なので、「いかに情を捨てて冷徹に書くか」、が大事になる・・・のだろうか。ううむ、相変わらず、五里霧中な感じだ。
・総会では、エゾマツの資源回復に関する話題提供をせねばならんらしい。一度、現地検討会で話したスライドに最近の話題を加えるとするか・・・。この時期、講義直前ということもあり、ばたばたしそうである。
・せっかくの小春日和だが、体調のせいか、どうも気分が盛り上がらない。とりあえず、LaTex化を試みようとするが、全然うまくいく気配なし・・・と。現在、当方のパソコンには飯島くんと富田くんのご尽力によりMeadowが動く環境になっているのだが、久保さんからWinShellが簡単そうだよん、というアドバイスが届く。ついふらふらと(?)、ダウンロードしてしまう。パソコンの中でけんかしなければいいのだが、ダウンロードはとりあえず簡単であった。WinShell3.0では、ヘルプの日本語訳までが作成されていて、とりあえず、ダウンロード。訳者はと見ると、”田中健太”とある。一瞬、イギリスの彼の地にいる氏かと思ったが、どうやら違うみたい。
・しばらく格闘するも、やはり一人では埒があかん・・・。ということで、いったんこの問題は放置。当方、「北海道の林木育種」という雑誌の編集委員となっているのだが、この雑誌が50周年を迎えるということで、その記念誌を作ることになっている。当然、当方にも担当(樹種)が振り当てられている。担当樹種とは、カンバ類とトネリコ類。要は、育種(造林)対象樹種について、それぞれ担当を決めて、分布、種特性などの基礎情報、遺伝情報、育種情報を整理するということになっている。が、全く進んでいないのが現状である。
・このまま放置していても駄目なので、無理やり、ウダイカンバについての文章を書いてみる。考えてみると、全国スケール、地域スケール、集団内スケールと遺伝マーカーを使った研究がそれなりに集積されていて、一つのモデルケースとなりそうな感じ。それぞれに”物語”があるわけだけど、それをいちいち書いていると他樹種とのバランスがものすごく悪くなりそう。なので、「いかに情を捨てて冷徹に書くか」、が大事になる・・・のだろうか。ううむ、相変わらず、五里霧中な感じだ。
・総会では、エゾマツの資源回復に関する話題提供をせねばならんらしい。一度、現地検討会で話したスライドに最近の話題を加えるとするか・・・。この時期、講義直前ということもあり、ばたばたしそうである。