今年の国立大学前期試験が終了しました。
感想は、出題範囲が狭いと難易度がかえって増す、ということです。
大学受験で、よねの時代から、二つの単元が削られています。
____________________________
一つは「空間図形」、これは「ベクトル」の上位単元です。
空間図形の花形問題は、平面を求める問題です。
・交わる2直線を含む平面
・1直線と一つの点を含む平面
・3つの点を含む平面
これらは同一の問題で、平面を定義する「垂直ベクトル」を求めれば、
解けたも同然。
ここまでが、大問の前半で、後半に球が出てきたり、別の平面が
出てきます。
大問の前半を解ければ、部分点が取れます。
大学の二次試験は、全部、解く必要がなく、完答以外の問題から
如何に部分点を取ってくるかが大事なのです。
平面を求める問題では、基本的なベクトルの計算力も
見れますから、出題者も好んで出してきます。
一方、ベクトルの単独問題でも、難易度が低くても、
差がつきます。受験生は「空間図形」をマークしていますから。
現在は「ベクトル」だけですので、当然、受験生もマークしてくる。
難易度を高くしないと、差がつかないのですね。
_____________________________
同じことが、「行列」の上位単元、「一次変換」にもいえます。
現在、一次変換は行列の単元の一部で、基本的なものしか
扱いません。
一次変換では、差をつける難問は作りづらい。
そうしますと、行列のn乗を求める問題の難易度が上がるわけです。
*実際には、東大・京大以外は、一次変換で差がつくらしい。
大阪大学で回転変換が出題されている。
何より問題なのは、行列が高3の最後の単元であるということだ。
よねの時代では高2で学習した。
浪人生に一方的に有利ではないか!!
最新の画像[もっと見る]
-
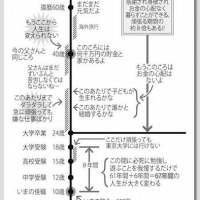 早慶高入試がブルーオーシャン 2 その1
2年前
早慶高入試がブルーオーシャン 2 その1
2年前
-
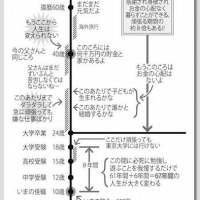 スマイルゼミを用いた 「下剋上受験」
2年前
スマイルゼミを用いた 「下剋上受験」
2年前
-
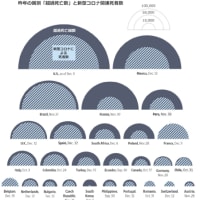 在宅死亡者の統計をとっていなかった韓国
2年前
在宅死亡者の統計をとっていなかった韓国
2年前
-
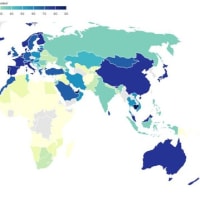 ジョンズ・ホプキンス大は「ネトウヨ」ニダ!
3年前
ジョンズ・ホプキンス大は「ネトウヨ」ニダ!
3年前
-
 パクサンヨン!?
3年前
パクサンヨン!?
3年前
-
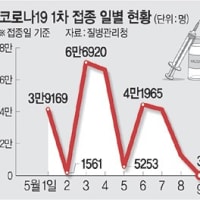 ついに、ワクチン枯渇か?
3年前
ついに、ワクチン枯渇か?
3年前
-
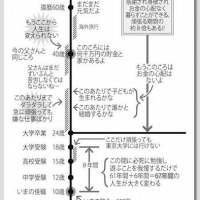 早慶付属高受験が、「ブルーオーシャン」
3年前
早慶付属高受験が、「ブルーオーシャン」
3年前
-
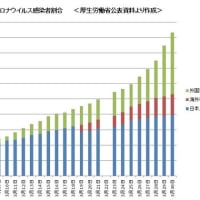 新型コロナ 外国籍が増えている??
4年前
新型コロナ 外国籍が増えている??
4年前
-
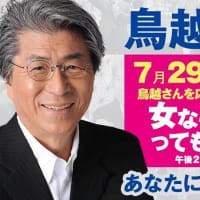 何の冗談ですか?
8年前
何の冗談ですか?
8年前
-
 オールスター出場記念
8年前
オールスター出場記念
8年前















両方ともメカ設計で必要な知識ですわ(^^;)
大学で物理の教育レベルが下がっている話が
ありまして・・・
今、大学院でやっている物理の授業は、昔、大学で
やっていたレベルだとか。
「ゆとり」教育は結局、最後にツケがまわるわけで・・
私も一次変換は高2の代数幾何の分野。高3で一年間かけてみっちり演習して「戦力」になりました。
あれが「回転」と「伸縮」だということに気がつけば、問題の見方が広がって面白いんですよね。
高校生に一次変換は無理という文部省の判断は、
あまりに愚かである、と。
>「回転」と「伸縮」だということに気がつけば、
問題の見方が広がって面白いんですよね。
おいら、気付かなかった・・・orz
必ず、大問の1つとして出題されたので、
相当に演習したのに・・・orz
おいら、数学は苦手科目だったから。