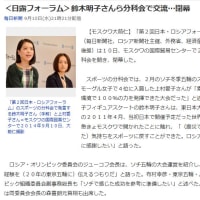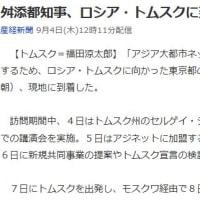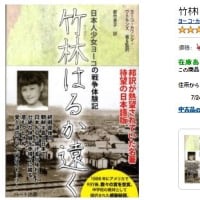「トマスの福音書」を読んでます。
何というかなかなかスーっとわかる語録集ではなく、聖書学の国際的な権威である荒井献教授のグノーシス用語の解説がなかったら、よくわからない、という感じです。
ただ一般にグノーシスっていうのは「光と闇」「天と地」「善と悪」の二元論だと言われていて、グノーシス的福音書であるこの言葉集も創造神であるデミウルゴス(旧約の神)を超越する、「至高神」が定められているのですが、「覚知(グノーシス)」することによって、至高神を知る。御国は、どこか天高くとか、海中深くではなく、偏在し、覚知者の内に実現されている。
終末の後に神の国が来るのではなく、気がつけばそこにある。(一種の「あの世」と「この世」の二元論の否定⇒御国はどこか空の上の方にあるわけでも(空間)、これから来るわけでもない(時間)。)
気づくことが、すなわち「覚知」(グノーシス)であり、生けるイエスを見ることである、ようです。
注意点は、この福音書の核にはユダヤ人キリスト教に由来するイエスの言葉伝承ではあるが、トマスがグノーシス主義的に解釈したもの、とも捉えられるようです。
ユダヤ教の神を格下げしていますので、ユダヤ人キリスト教(エルサレム教団)がこういう解釈をしていたかどうかはわからないようです。グノーシス主義者達のイエス解釈とも言えるかもしれませんが、p5「『Q資料』とトマスの福音書の語録はかなり重なっている」らしく、グノーシスフィルターはかかっていても最古層のイエスの言葉と思っても良いようです。
「異教徒は殺せ」と繰り返す、排他的で残虐な戦争神ヤハウェ以上の「何か」を想定した点は大いに頷けます。なんでも相いれぬものは「殺す」※という解決手段しか取れないのは、愚かな上に確実に悪です。
※ 「聖絶」⇒ことごとく滅ぼし尽くすこと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E7%B5%B6
「トマスの福音書」においては
「救済=覚知」
「本来の自己を取り戻す」
「アンチ選民主義」
「イエスの出現が旧約の預言の成就ではない」
ヤハウェはただの創造神
十字架⇒復活はない
旧約の預言者の否定
「単独者」として血縁から自立し、「覚知」に基づく同胞関係を勧める。
至高者は男でも女でもない(らしい。主に「父」)
敬虔さは「覚知」の条件ではない
覚知者は禁欲であれ
「隠された言葉」として、一般大衆には「隠され」ている。それはイエスによって「覚知」を得られる宗教的エリートにのみ保留されている。つまり「秘教」というわけらしいです。
でも誰しもが宗教的エリートではないので、変な例えですが僧伽(出家)主義で、小乗仏教っぽいかな、と。そういう意味では「信仰によって救済」されるパウロ主義というのが、多くの人の胸に打つものがあった、単純で、大衆受けしたかな、と思います。
(だからといってこのトマスやマリア、ピリポの教えを封殺、焚書してしまったのは大きな損失だったでしょう。「至高者」には、具体的な言葉がないので、黒人蔑視や、異教徒殺害奨励、といった旧約に神学的根拠を求めた悪しきことが回避されたかもしれません。
もともとなかった「十字架上の死による人類の救済」「肉体を持った復活」思想がどこからともなく紛れ込み、変形していった過程は不思議です。最古の福音書にも「十字架⇒贖罪」「肉体による復活」はないので。
wikiより 「マルコ福音書の変遷に関してもっとも大きな問題は、結末部分(16:9-20)の問題である。そこには復活したイエスと弟子たちが出会い、イエスが天に昇る話が描かれるが、古い写本には含まれておらず、3世紀の神学者オリゲネスが福音書の復活物語を論じたときも他の福音書からは引用しているにもかかわらず、マルコからは一切引用していない。このことは結末部分が3世紀以前には存在しなかったことを示している。」
ただ「死をもって罪を贖う」「人身御供」といった考え方はもともといろいろな地域で見られるもので、そう言ったものをユダヤ教と別れていく過程で、取り込んでいったのかも(異教であるミトラ教、ゾロアスター教、エジプトの神話などを盛り込んで教義を固めていった)、と思います。逆にインドに布教に行ったとされるトマスは、東洋思想(バラモン教、ヒンズー教、仏教)に影響をうけていったのかもしれませんし、もともとこういう教えだったのかもしれません。
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-_eLaY-fQgE
Zeitgeist ツァイトガイスト(時代の精神)
死者の復活⇒祭司階級を中心とするサドカイ派は死者の復活を信じていませんでし。それは彼らが伝統的なユダヤ教の教えを墨守していたからです。ヘレニズム的な「死者の復活」を信じていたのは、新興勢力だったパリサイ派です。
p118、「しかし正統的協会は、パウロ自身の手紙によるより、むしろパウロの名によって書かれた手紙(テモテへの手紙、テトスへの手紙)によって、「キリストの律法」に基づく教会の秩序を擁護し、救済手段としての教会制度、とりわけ聖職者位階制を原理的に否定したグノーシス主義を排斥した。
ますます排他的になり、色々な意味で「救済」を教会が独占し、罪の許しもお金で買える(免罪符など)下地が出来たようです。下の言葉も最古の「Q」にはないので(トマスにも、マルコにもない)、教団が都合により、イエスの口から言わせたと思われます。
わたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう(マタイによる福音書 16章13~20節)

それに、原人アダム(両性具有の原人)の肋骨から分離(死)することによってイブが生まれた。つまりお互い欠損部分がある。それを取り戻すのが、再結合(不死)。「結婚の場所」と呼ばれ、分離した男女が覚知(グノーシス)によって原初的統合を回復する。(聖なる結婚)という考え方もあるみたいです。全体的に小難しいですorz
「イブがアダムの中にあった時、死はなかった。彼女が彼から離れたとき、死が生じた。彼女が再び(アダムに)入り込み、彼が彼女を受け入れれば、死はないであろう」(「ピリポ福音書」71)
「聖なる結婚」で思い出したのがこれ。

ペテロ(正統派教会)が子供(覚知、真実)を殺そうとしている、の意味かと、深読みしちゃいました(^^;)ペテロの手がマグダラのマリアのお腹にナイフを突きつけてるという。(これはダ・ヴィンチ・コードの受け売りなんですが)