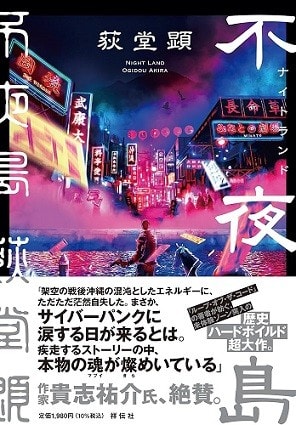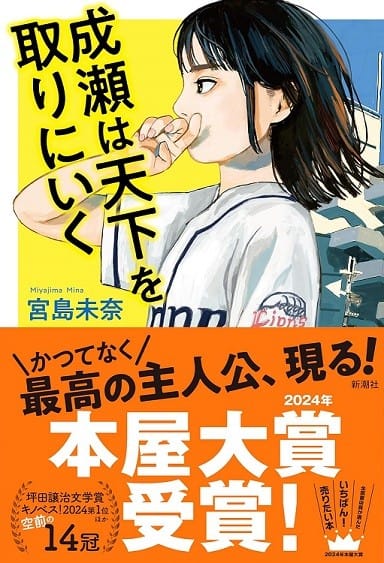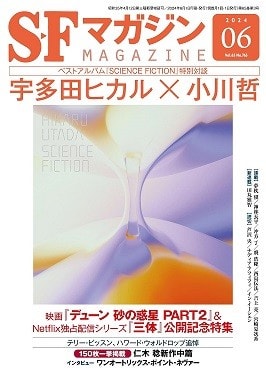村瀬秀信 集英社
昨年アレを達成した岡田監督が退任した。さて、次の阪神の監督にはだれがなるんやろ。岡田監督退任発表後のおおかたの関西人の関心事はこのことやろ。で、早急に藤川球児が次の監督になった。ま、藤川やったらええんちゃうん。やら、コーチの経験もないのに藤川でだいじょうぶやろか、かまびすしいことですじゃ。
「そら、阪神の監督なんてけったいなもんですわ」これはカバーの折り返しに記された吉田義男のことばや。阪神の監督を3回もやって日本一もどんべたも経験した吉田さんがいうことやから、説得力があるちゅうもんや。ワシら阪神ファンにとって次の首相や県知事より阪神の監督の方が重大事なんや。そんな阪神の監督にまったく無名の老人がなったことがあった。
阪神タイガース第8代監督岸一郎。第7代は松木謙治朗、第9代は藤村富美男。双方とも阪神タイガースを代表するスター選手やった。とくに藤村はミスタータイガースと呼ばれる大スターやった。
で、この二人のあいだに監督をやった岸一郎なる人物。だれやねんそれ。この本を読ませる駆動力はその1点や。
岸一郎。アマチュアで投手の経験はあるがプロの経験はない。どうしてこんなド素人が阪神タイガースの監督になったのか?ほんまのことはよう判ってへん。なんでも当時のオーナー野田誠三に「タイガース再建論」ちゅう手紙を書いて野田オーナーに気に入られて阪神監督を要請されたらしい。このへんは今も昔も阪神は変わってへん。矢野燿大が監督を辞めて、ほんまは平田勝男が監督になるはずやったらしい。でも角オーナーが早大の後輩岡田彰布を監督にしたんやて。岡田やったら経験も実績もあるからマシやけど、なんの実績もないどこの馬の骨か判らんジイさんに監督をやらせたんや。
もちろん藤村はじめ選手たちは猛反発。岸監督はたった二ヶ月わずか33試合を指揮しただけで阪神タイガースの監督を退任する。理由は持病の痔の悪化!?
で、けっきょく岸一郎とはなにもん。資料参考になるもんはほとんど残ってない。著者は吉田義男、小山正明、広岡達郎など、岸を知っている存命の人物にインタビューを重ね、岸一郎の正体を追う。そこで浮かび上がったのは「阪神タイガース」なる日本の関西の野球チームの「業」と「血」どういうことかワシは阪神ファンやから判るけど、他チームのファンは判らんやろな
この本の初版が出たのは今年の2月。巻末で甲子園歴史博物館での川藤幸三と藤川球児の対談が紹介されている。川藤がいう「ワシが藤村さんにいわれたんは阪神タイガースの歴史伝統を後輩に伝えることや」藤川が答える「カワさんのあとはぼくに任せといてください」この時藤川球児は阪神タイガースの「業」と「血」を受け継いだのだろう。「歴史と伝統」=「業と血」ちゅうこっちゃろ。そして10月藤川球児は第36代の阪神タイガース監督になった。
藤川は8代目監督岸一郎の写真に目をとめた。川藤に聞いた。
「この人はなんですか・・・?」
「ええか、球児。この人はな・・・」
昨年アレを達成した岡田監督が退任した。さて、次の阪神の監督にはだれがなるんやろ。岡田監督退任発表後のおおかたの関西人の関心事はこのことやろ。で、早急に藤川球児が次の監督になった。ま、藤川やったらええんちゃうん。やら、コーチの経験もないのに藤川でだいじょうぶやろか、かまびすしいことですじゃ。
「そら、阪神の監督なんてけったいなもんですわ」これはカバーの折り返しに記された吉田義男のことばや。阪神の監督を3回もやって日本一もどんべたも経験した吉田さんがいうことやから、説得力があるちゅうもんや。ワシら阪神ファンにとって次の首相や県知事より阪神の監督の方が重大事なんや。そんな阪神の監督にまったく無名の老人がなったことがあった。
阪神タイガース第8代監督岸一郎。第7代は松木謙治朗、第9代は藤村富美男。双方とも阪神タイガースを代表するスター選手やった。とくに藤村はミスタータイガースと呼ばれる大スターやった。
で、この二人のあいだに監督をやった岸一郎なる人物。だれやねんそれ。この本を読ませる駆動力はその1点や。
岸一郎。アマチュアで投手の経験はあるがプロの経験はない。どうしてこんなド素人が阪神タイガースの監督になったのか?ほんまのことはよう判ってへん。なんでも当時のオーナー野田誠三に「タイガース再建論」ちゅう手紙を書いて野田オーナーに気に入られて阪神監督を要請されたらしい。このへんは今も昔も阪神は変わってへん。矢野燿大が監督を辞めて、ほんまは平田勝男が監督になるはずやったらしい。でも角オーナーが早大の後輩岡田彰布を監督にしたんやて。岡田やったら経験も実績もあるからマシやけど、なんの実績もないどこの馬の骨か判らんジイさんに監督をやらせたんや。
もちろん藤村はじめ選手たちは猛反発。岸監督はたった二ヶ月わずか33試合を指揮しただけで阪神タイガースの監督を退任する。理由は持病の痔の悪化!?
で、けっきょく岸一郎とはなにもん。資料参考になるもんはほとんど残ってない。著者は吉田義男、小山正明、広岡達郎など、岸を知っている存命の人物にインタビューを重ね、岸一郎の正体を追う。そこで浮かび上がったのは「阪神タイガース」なる日本の関西の野球チームの「業」と「血」どういうことかワシは阪神ファンやから判るけど、他チームのファンは判らんやろな
この本の初版が出たのは今年の2月。巻末で甲子園歴史博物館での川藤幸三と藤川球児の対談が紹介されている。川藤がいう「ワシが藤村さんにいわれたんは阪神タイガースの歴史伝統を後輩に伝えることや」藤川が答える「カワさんのあとはぼくに任せといてください」この時藤川球児は阪神タイガースの「業」と「血」を受け継いだのだろう。「歴史と伝統」=「業と血」ちゅうこっちゃろ。そして10月藤川球児は第36代の阪神タイガース監督になった。
藤川は8代目監督岸一郎の写真に目をとめた。川藤に聞いた。
「この人はなんですか・・・?」
「ええか、球児。この人はな・・・」