第3回
日本人の没個性、中国人の自己主張
清朝を代表するような傑物を皮膚感覚で理解した浅田氏が気付いたのは、「中国の歴代の政治家は日本の歴代の政治家に比べて極めて個性的」ということだった。
日本と中国の差は、国民性の違いでしょう。日本人は狭い土地のなかに人口過密状態で暮らしているから、「突出してはならない」という道徳が身についている。みんなで同じように暮らしていかなければならないという道徳があるために、没個性にも?がるわけです。日本で派手な格好をしていたら「目立ちたがり」と戒められます。地味であるということが、過密社会のマナーだったのですね。
しかし、中国人はアメリカ人と同様に「自己表現」の世界で生きている。いかに自分をアピールするか、そればかり考えているから声も大きくなる。日本では政治家の弟子は師匠の劣化コピーみたいになりがちです。しかし、中国人政治家にはそういう「縮小再生産」は感じられません。清朝末期の軍人政治家の系譜は、曾国藩、李鴻章、袁世凱と受け継がれますが、それぞれに独特のキャラクターがあります。
そういう中国人特有の個性は、いま、中国旅行に出かけて街中で人物を観察していても伝わってきます。日本の街中で人間をしばらく見ていても、みんな似ているものだからあんまり面白味はない。でも、中国の街中で見かける人たちは、表情といい身ぶり手ぶりといい、もう誰も彼も他人のマネをするのはイヤだと言わんばかりの個性的な人たちが多い。だから、見ていて飽きないのです。日本社会は「没個性」で集団をまとめてきたから、それはそれで幸福なことだったのかもしれませんけれども。
西太后の再評価
浅田氏は『蒼穹の昴』で、それまで悪女とされてきた西太后の再評価を試みている。つまり、西太后はこれまでの一般的な評価「亡国の鬼女」ではない。本当の姿は「亡国の鬼女に見える言動をしてでも中国を救済しようとした人物である」と。『蒼穹の昴』日中合作ドラマ化にあたり、西太后再評価は中国側のスタッフにどのように受けとめられたのだろうか。
私の西太后解釈に対して、頷いてくださるスタッフが多かったですよ。私は西太后の再評価については、自分の考えに確信を持っています。なぜなら、これまで伝えられてきたような悪女であるなら、あれほどの長期政権を維持できたはずがないですから。それに西太后は老境にさしかかった頃の写真がたくさん残されています。それらの写真の数々は北京の市内で販売されていたそうです。つまり人気のあるブロマイドとして流通していたのです。これは西太后が民衆に慕われていたという証拠です。
西太后が歴史的に「悪女」になったもとを作った「戦犯」は、エドマンド・バックハウスとジョン・ブランドの共著による『西太后治下の中国』という本です。西太后は彼らの著作によって悪女というレッテルを貼られてしまったのです。
李鴻章、亡国の買弁と呼ばれて
もう一人、『蒼穹の昴』でかなり大胆に再評価をされている人物が、李鴻章だ。李鴻章の中国国内での評価は極めて低いという。
私自身は、李鴻章に関しては『蒼穹の昴』の中で高く評価をしているように、すばらしい人物だと思っています。しかし、西太后とは比較にならないくらい、まだまだ評価をされていません。『蒼穹の昴』を日中合作でドラマにするにあたって、西太后をポジティブに描くことについては中国当局の反応は「ここまではいいだろう」という雰囲気でした。しかし、李鴻章については頑なな反応でした。
李鴻章は香港を九九年も英国に貸与する条約にハンコを押した人物です。それから日清戦争の結果、台湾を割譲するハンコを押した人物でもあります。諸外国に対して「国土を貸します、あげます」という条約を結んでしまった人物です。もちろん、それが現在まで影響して中国は領土問題をひきずっているから、「李鴻章は亡国の買弁である」と批判されるのは無理もないことかもしれません。
しかし阿片戦争以降の清朝の状況を冷静に鑑みれば、李鴻章は不平等条約を結び続けながらも、中国を維持させようとした偉人なのです。李鴻章の外交があったからこそ、中国は結果的には植民地にならないで済みました。李鴻章があれほどの妥協をしていなければ、中国は諸外国に一気に攻め滅ぼされて植民地として分割されていた可能性が高い。そのような意味で、私は「強い意志を持った西太后」と「その意志を政策として実行に移した李鴻章」は黄金のタッグであったと捉えています。なにもしなければとっくに滅亡していた清王朝を五〇年間も存続させて、何とか民国政府にバトンタッチした二人の手腕は尊敬に値すると思っています。
西太后や李鴻章のなかには「植民地化を防止しよう」なんて方針はなかったかもしれません。しかし、この二人が諸外国としぶとい折衝を続けたことで、中国人が国土を支配し続けたことは紛れもない事実です。その事実は正当に評価されるべきではないでしょうか。
今回のドラマに対する中国側の反応を見ていて、浅田氏は中国の歴史観はだんだん柔軟になってきていると感じている。以前であれば、西太后さえも認められなかったであろうから、と。『蒼穹の昴』のテレビドラマにおける主役は原作と同じくのちに宦官の長官になる李春雲(春児)であるが、これは中国が製作に関わったドラマでは画期的なことだった。
中国国内でこれまで悪人としてしか描かれてこなかった宦官がテレビドラマの主人公になることは、中国の歴史解釈が柔軟になってきていることの証拠ではないでしょうか。
ところで、中国の近代史に謎が多いひとつの原因は、清朝の正史が書かれていないことです。中国には歴代王朝が交代した後、新しい王朝が前の王朝の正史を書くという伝統がありました。しかし、清朝が滅びた後は王朝がないので、清朝には国が認める「正史」がないのです。正史の代わりに『清史稿』というものが残されています。これは、元の東三省総督という、いわば一介の地方行政官であった趙爾巽という人物が中心になって書かれたものでした。「稿」という字には、「まだ認められていない草稿である」という意味があります。つまり、『清史稿』はあくまで下書きですが、私は非常に偉大な功績だと思っています。
清朝の末期というものは、明治維新のように書きやすいものではありません。日本の幕末はせいぜい一〇年や一五年というスパンにおいて語られます。しかし、清朝末期というのは、阿片戦争以降、七〇年も国が苦しみ続けるプロセスです。苦しんで苦しんで、それでもうまく歴史を転換できずにいたという、その複雑な経緯を文章にまとめることは非常に困難です。しかし、困難であるからこそ、歴史を記録に残しておく意味もあるわけで、私はそうした意味で『清史稿』をまとめた趙爾巽は尊敬するべき人物と考えているのです。










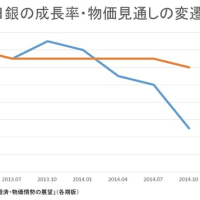
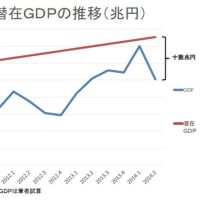


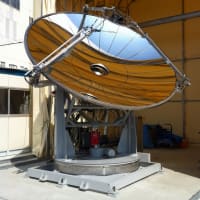
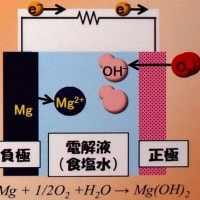

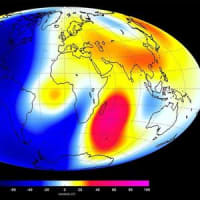


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます