今日は八尾から同じ着付師のかっさんとO先生が来られました。
結婚式の依頼が増えたので
留袖の本式着付の勉強に来られたのです。
もっと前からわかっていたのに
友人に借りっぱなしになってるm(__)m 下重ね付の留袖と
別の友人からもらった丸帯で
本式着付の練習をしました。
私は幸か不幸か…毎年、1回以上は、お着付する機会があります。
今年の方は、最初から分かっていましたが
ほとんどが、突然その日にって感じでした。
初めての時は、どうやってお着付けしたかほとんど覚えていません。
確か紅絹の留袖でした。
初めてこの留袖を持ったお二人は、あまりの重さにびっくりした様です。
そして、丸帯の重さにも…(~_~;)
本当に重たいのです。
一応、着付けていたので、最初に帯締め3種類から行いました。
着物も厚みがあるし、帯も厚みがある場合は帯締めが短くなるので
向かって左側のやり方がすっきり見えます。
左の帯締めの結び方を「しあわせむすび?」言うらしいのですが、メガネになり易いので、あまり使っていません。
帯締めは、短い時はスッキリか、通常は下の普通の結び方にしています。
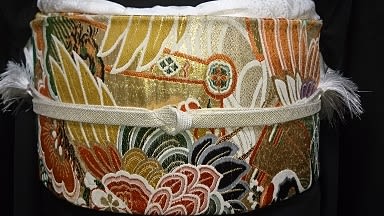


3つとも覚えると、いざという時に私の様に真っ白になってできない時があるので
幸せ結びは忘れてもらうことになりました(^_-)-☆
いつも一人着せという事なので、こういう着物の場合は
後ろは、先に裾丈を決めて衿のピンチに止める方法をお勧めしました。((助手の変わりです)
あんまり重いので、少々引いても、すそが落ちてくるので、この方法が良いですね。
普通にするのと、両方試して頂くと、全然違うって実感してもらえましたわ(*^^*)
おはしょりも地厚になるので、最初に綺麗にしておかないと難しいですわ。
帯も丸帯なので厚味があり、腰の補正はヒップパットぐらで十分です。
帯枕もタオルで作らないと、体に添いません。
私がコーヒーを入れている間に、帯が完成していました。
撮りらが結ばれた帯だったかしら?


主人が買ってきてくれたケーキでお茶をして、ひと段落

後は、振袖の帯揚げなど先日ブライダル専門美容師こだわり仕事のa先生のレベルアップレッスで教えて頂いた
帯揚げを披露しました。
最後はゴンちゃんも一緒に記念撮影です(#^.^#)
又いらして下さいね。

本日も訪問ありがとうございます。
応援クリックもよろしくお願い致します














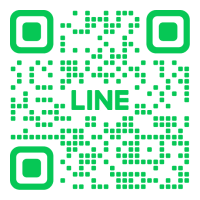
















私は本式の下重ねは喪服で一度、あります。真っ白になりました。。
帯締めのしあわせ結びは、本結びしてからくるっと回転する横着して使う事もありますよ~。
丸帯でも現在ものなら、まだ締めやすいですよね。
年代物は、本当に指が可愛そうになりますね。