この記事は、応援団には興味があまりない読者の方にも、もちろん、応援団のファンやマニアの読者の方にも、手前味噌かもしれませんが、(言葉が適当ではないかもしれませんが…)ご笑覧頂き、感想などをお聞かせ願えれば、大変幸甚に存じます。
では…始めます。
東京大学運動会応援部については、2つ程記事を書いています(こちらと、こちらです)。
どちらも、「東大、凄い…」「東大、頑張れ!」というのが結論になっていると思います。
東京大学運動会応援部の「闘志」…この凄さが一体どこにあるのか。
それを改めて感じることができたのが、KAZUさんがYouTubeにアップしていただいた、2003年にTBS系列で放送された『人間解析ドキュメント ZONE』の『我ら花の東大応援部』です。
拙ブログで以前紹介している『第53回 六旗の下に』の東京大学の幹部諸君、この当時は、なんと1年生。
幹部になって示す堂々たる「華々しさ」は、「ここ」を通過していなければ決して示すことができない…という事を改めて感じます。
まるで、「地獄」の様な合宿の厳しさを、やり通せた、乗り越えられた者だけに与えられる「勲章」である事を…。
それでは、各動画ごとに感じることを、なるべく手短に語ってみたいと思います。
ですが、この「凄さ」は、言葉で表現するには、とっても難しすぎます。
したがって、繰り返しにはなりますが、拙ブログの、応援団を応援する、応援団が大好きな読者の皆様やブロガーの皆様(例えば、くりはらさん)はもちろん、勝手に想像していますが、拙ブログに寄っていただいている、応援団とは縁が遠いssayさんや、imuimuさんをはじめとする皆様にも、動画をじっくり楽しんで頂きたいと思います。
そこで感じ取ったもの…それは、私が感じた事に相通じると、私は信じていますので。
東大応援部 涙の奮闘記 我ら花の応援団 その1,2,3連結/全8
やっぱり、応援団は、試合終盤で「敗色濃厚」であっても、下を向けない、いや、向いちゃいけない…改めてそう思います。
これは何も、試合の勝敗に限った事ではないように思います。
仕事でも何でもそう。「ここぞの粘り」が結果に結びつくこと、多いと思います。
だから、諦めちゃいけない…自戒を込めたいと思います。
ところで、私が現役当時もそうですが、胸にバッジが着いた学ランを着て通学している時…目立ちましたから、身が引き締まりました。
その点はここに登場しているリーダー長の中井君と全く同じでしたね。
私が入部した時も、「自分に自信がつく」といった説明を受けたこと、覚えています(その様子や心境は『応援団に捧げた青春』シリーズの第6話でお話しています)。
私の場合、一途に思いを寄せていた女性(TSさん)がいて、男を磨いて、今度こそ振り向いて欲しいという思いと、53番君が背中を押してくれたことが大きいですが、ここに登場する1年生の大野君の様な、「熱い」気持ちでは少なくてもなかったように思います。恐る恐るというか…少し腰が引けていたとは思います。
しかし、53番君と、「球場で会う」という約束は破れない…という「意地」みたいのものはあって、何とか3年間続いた…という思い出が蘇った事は確かです。
「出走」の練習…応援歌を歌いながらとか、拍手をしながらの「腕強化」まではいかないにしても、私の場合も、大声で声を出しながらロードワークはやりました。
途中声が小さいと、先輩から檄を飛ばされたりもしました。
ハード(体力強化)練習場所までの、最後の数百メートルのダッシュ、走ることは得意ではあったけれど、きつかったなぁ…。
東大応援部 その4/全8「地獄の夏合宿で地獄を見た」
「夏合宿」…本当に肉体的にも、精神的にも、きつかったです。
普段の練習の時間にして約3倍でしたが、3倍以上にきつかった…。
普段の練習は、「陽が傾いてから」が殆どだから、真夏の炎天下で普段の3倍の時間…考えただけで足取りは重たいし、本当にやれるんだろうか…その不安、大きかったです。
この動画で、大野君の精魂尽き果てた様子…良くわかります。本当にそうだから。
やっているときは、とにかく、「やるしかないから、やる」…もうそれだけでした。
逃げたくなるほどきつかったけれど、やり始めた以上は、やる…。
やっている途中に、「何の目的でやっているのだろうか」なんて考えている余裕は、全くないです。
そんな「暇」があるなら、目の前のことをやる…それしかなかったです。
無心でした、私の場合も。
「夏合宿」って、高校でも、本当にそんな感じでした。
当然、大学の方が、この東京大学の様に、もっときつい事は想像に難くはないのですが…。
「地獄」…適当ではないかもしれないけれど、それが一番当てはまる事は、確かです。
東大応援部 その5,6連結/全8「地獄の大出走 往路・復路編」
私達の場合、食事の支度は、1年生が担当します。
練習が終わっても、精魂尽き果てて倒れている暇は、なかった…。
でも、もっと大変なのは幹部の先輩方。
合宿にお見えになったOBの先輩方、そして引退した3年生の先輩から、「持ちテク」の指導を、1年生が食事の支度をしている間、ずっと受けています。
1年生の頃、「この次は、俺達の番か…」と思うと、気が重かったです。
大野君の様に、食事…一生懸命食べるんです。でも、体がなかなか受け付けてくれません。本当に体力的にしんどいと、食べなきゃいけなくても食べられなくなるんだ…初めて味わった感覚でした。大野君のこの時の心境…「そうそうそう!」って思いながら見ていました。
「大出走」…これは凄い。
フルマラソンよりも長い距離…大学の応援団は、こういうところに高校との決定的な違いがあります。これは経験しないと分からない…私には難しいです。
でも、時々私も口にする「応援団は、皆レギュラー」は、嘘ではないことがご理解頂けると思います。「体力がない者は、置いていく」という事がないのですから。
だからこそ、1年生の川上君の様に、ストップをかけられそうになっても「やります!」と無意識に発してしまうのだと思います。
リーダー長の中井君が、そんな川上君に対して言った…
「やるかやらねぇかどっちかだ。できるかできねぇじゃねぇ。」
この檄、重いですね。
でも、そういう事なんだろうと思います。練習でも、仕事でも、何でも。
だから、私には、その中井君の言葉の中に「優しさ」も感じることができます。
それが練習をやっている途中に、自然と身についてしまう…それが応援団の素晴らしさだと思います。
それを身につけ、やり遂げた先には、吹奏楽部やチアリーディング部全員が待っていてくれること、そして、念願の「バッジ」を手に入れること…それよりも、言葉では表せない、もっと大事な「かけがえのないもの」を得ることができます。
『応援部小唄』…胸を打ちます。素晴らしいです。泣けてきます。
合宿最後のシーン…大野君が幹部の寄せ書きと共に、「バッジ」を手にする瞬間…感動的ですね。
こうして手渡されたら、絶対に辞められないですよね。嬉しいですもの!。
「感無量」…本当にそう思います。見ている私も「感無量」でした。
東大応援部 その7,8連結/全8「2003秋季リーグ 女神は微笑むのか?」
最後まで絶対に諦めなければ、「勝利の女神」は微笑んでくれるんですね…。
この瞬間です。応援団が一番嬉しいのは。
しかも、「自己満足」ではなく、母校側のスタンドに足を運んで頂いた観客の皆様と一体になれた上で、勝った時が、本当に嬉しい。
私達は、そのことだけを考えて球場では動くのですが、本当に嬉しんです。この瞬間が。
リーダー長の中井君が、試合が終わった後、リーダー部の下級生に向けて言った…
「諦めないことの意味を知っただろう。最後のエールができるその瞬間まで、どんなに負けていようと、信じてりぁ、いつか報われんだよ。今日の喜びそれがありゃ、どんな時でも応援できるだろ、お前ら。これからも、まだまだ上を目指して…」
この言葉も、重い。深い。
「諦めない事の、本当の意味」…これを知るために、壮絶な練習を毎日の様に行い、「闘志」を燃やす…。
そこに、東京大学運動会応援部の「凄さ」や、「根底」「根っこの部分」を見た気がします。
だから、『六旗の下に』でも、素晴らしい演技ができる。
日比谷公会堂に足を運んだ観客を、「興奮の渦」に瞬く間に巻き込める。
東京大学運動会応援部の「闘志」は、どんな時であろうと消えることはないと、確信を持って断言できますね。
私自身の経験は、後々『応援団に捧げた青春』シリーズでお話することにして、読者の皆様、如何だったでしょうか。
「感動」…一言で申し上げると、それしか浮かばないです。
ありがとう、東京大学運動会応援部。
そして、東京大学運動会応援部の益々のご発展を願って止みません。
東京大学運動会応援部に、栄光あれ!。
では…始めます。
東京大学運動会応援部については、2つ程記事を書いています(こちらと、こちらです)。
どちらも、「東大、凄い…」「東大、頑張れ!」というのが結論になっていると思います。
東京大学運動会応援部の「闘志」…この凄さが一体どこにあるのか。
それを改めて感じることができたのが、KAZUさんがYouTubeにアップしていただいた、2003年にTBS系列で放送された『人間解析ドキュメント ZONE』の『我ら花の東大応援部』です。
拙ブログで以前紹介している『第53回 六旗の下に』の東京大学の幹部諸君、この当時は、なんと1年生。
幹部になって示す堂々たる「華々しさ」は、「ここ」を通過していなければ決して示すことができない…という事を改めて感じます。
まるで、「地獄」の様な合宿の厳しさを、やり通せた、乗り越えられた者だけに与えられる「勲章」である事を…。
それでは、各動画ごとに感じることを、なるべく手短に語ってみたいと思います。
ですが、この「凄さ」は、言葉で表現するには、とっても難しすぎます。
したがって、繰り返しにはなりますが、拙ブログの、応援団を応援する、応援団が大好きな読者の皆様やブロガーの皆様(例えば、くりはらさん)はもちろん、勝手に想像していますが、拙ブログに寄っていただいている、応援団とは縁が遠いssayさんや、imuimuさんをはじめとする皆様にも、動画をじっくり楽しんで頂きたいと思います。
そこで感じ取ったもの…それは、私が感じた事に相通じると、私は信じていますので。
東大応援部 涙の奮闘記 我ら花の応援団 その1,2,3連結/全8
やっぱり、応援団は、試合終盤で「敗色濃厚」であっても、下を向けない、いや、向いちゃいけない…改めてそう思います。
これは何も、試合の勝敗に限った事ではないように思います。
仕事でも何でもそう。「ここぞの粘り」が結果に結びつくこと、多いと思います。
だから、諦めちゃいけない…自戒を込めたいと思います。
ところで、私が現役当時もそうですが、胸にバッジが着いた学ランを着て通学している時…目立ちましたから、身が引き締まりました。
その点はここに登場しているリーダー長の中井君と全く同じでしたね。
私が入部した時も、「自分に自信がつく」といった説明を受けたこと、覚えています(その様子や心境は『応援団に捧げた青春』シリーズの第6話でお話しています)。
私の場合、一途に思いを寄せていた女性(TSさん)がいて、男を磨いて、今度こそ振り向いて欲しいという思いと、53番君が背中を押してくれたことが大きいですが、ここに登場する1年生の大野君の様な、「熱い」気持ちでは少なくてもなかったように思います。恐る恐るというか…少し腰が引けていたとは思います。
しかし、53番君と、「球場で会う」という約束は破れない…という「意地」みたいのものはあって、何とか3年間続いた…という思い出が蘇った事は確かです。
「出走」の練習…応援歌を歌いながらとか、拍手をしながらの「腕強化」まではいかないにしても、私の場合も、大声で声を出しながらロードワークはやりました。
途中声が小さいと、先輩から檄を飛ばされたりもしました。
ハード(体力強化)練習場所までの、最後の数百メートルのダッシュ、走ることは得意ではあったけれど、きつかったなぁ…。
東大応援部 その4/全8「地獄の夏合宿で地獄を見た」
「夏合宿」…本当に肉体的にも、精神的にも、きつかったです。
普段の練習の時間にして約3倍でしたが、3倍以上にきつかった…。
普段の練習は、「陽が傾いてから」が殆どだから、真夏の炎天下で普段の3倍の時間…考えただけで足取りは重たいし、本当にやれるんだろうか…その不安、大きかったです。
この動画で、大野君の精魂尽き果てた様子…良くわかります。本当にそうだから。
やっているときは、とにかく、「やるしかないから、やる」…もうそれだけでした。
逃げたくなるほどきつかったけれど、やり始めた以上は、やる…。
やっている途中に、「何の目的でやっているのだろうか」なんて考えている余裕は、全くないです。
そんな「暇」があるなら、目の前のことをやる…それしかなかったです。
無心でした、私の場合も。
「夏合宿」って、高校でも、本当にそんな感じでした。
当然、大学の方が、この東京大学の様に、もっときつい事は想像に難くはないのですが…。
「地獄」…適当ではないかもしれないけれど、それが一番当てはまる事は、確かです。
東大応援部 その5,6連結/全8「地獄の大出走 往路・復路編」
私達の場合、食事の支度は、1年生が担当します。
練習が終わっても、精魂尽き果てて倒れている暇は、なかった…。
でも、もっと大変なのは幹部の先輩方。
合宿にお見えになったOBの先輩方、そして引退した3年生の先輩から、「持ちテク」の指導を、1年生が食事の支度をしている間、ずっと受けています。
1年生の頃、「この次は、俺達の番か…」と思うと、気が重かったです。
大野君の様に、食事…一生懸命食べるんです。でも、体がなかなか受け付けてくれません。本当に体力的にしんどいと、食べなきゃいけなくても食べられなくなるんだ…初めて味わった感覚でした。大野君のこの時の心境…「そうそうそう!」って思いながら見ていました。
「大出走」…これは凄い。
フルマラソンよりも長い距離…大学の応援団は、こういうところに高校との決定的な違いがあります。これは経験しないと分からない…私には難しいです。
でも、時々私も口にする「応援団は、皆レギュラー」は、嘘ではないことがご理解頂けると思います。「体力がない者は、置いていく」という事がないのですから。
だからこそ、1年生の川上君の様に、ストップをかけられそうになっても「やります!」と無意識に発してしまうのだと思います。
リーダー長の中井君が、そんな川上君に対して言った…
「やるかやらねぇかどっちかだ。できるかできねぇじゃねぇ。」
この檄、重いですね。
でも、そういう事なんだろうと思います。練習でも、仕事でも、何でも。
だから、私には、その中井君の言葉の中に「優しさ」も感じることができます。
それが練習をやっている途中に、自然と身についてしまう…それが応援団の素晴らしさだと思います。
それを身につけ、やり遂げた先には、吹奏楽部やチアリーディング部全員が待っていてくれること、そして、念願の「バッジ」を手に入れること…それよりも、言葉では表せない、もっと大事な「かけがえのないもの」を得ることができます。
『応援部小唄』…胸を打ちます。素晴らしいです。泣けてきます。
合宿最後のシーン…大野君が幹部の寄せ書きと共に、「バッジ」を手にする瞬間…感動的ですね。
こうして手渡されたら、絶対に辞められないですよね。嬉しいですもの!。
「感無量」…本当にそう思います。見ている私も「感無量」でした。
東大応援部 その7,8連結/全8「2003秋季リーグ 女神は微笑むのか?」
最後まで絶対に諦めなければ、「勝利の女神」は微笑んでくれるんですね…。
この瞬間です。応援団が一番嬉しいのは。
しかも、「自己満足」ではなく、母校側のスタンドに足を運んで頂いた観客の皆様と一体になれた上で、勝った時が、本当に嬉しい。
私達は、そのことだけを考えて球場では動くのですが、本当に嬉しんです。この瞬間が。
リーダー長の中井君が、試合が終わった後、リーダー部の下級生に向けて言った…
「諦めないことの意味を知っただろう。最後のエールができるその瞬間まで、どんなに負けていようと、信じてりぁ、いつか報われんだよ。今日の喜びそれがありゃ、どんな時でも応援できるだろ、お前ら。これからも、まだまだ上を目指して…」
この言葉も、重い。深い。
「諦めない事の、本当の意味」…これを知るために、壮絶な練習を毎日の様に行い、「闘志」を燃やす…。
そこに、東京大学運動会応援部の「凄さ」や、「根底」「根っこの部分」を見た気がします。
だから、『六旗の下に』でも、素晴らしい演技ができる。
日比谷公会堂に足を運んだ観客を、「興奮の渦」に瞬く間に巻き込める。
東京大学運動会応援部の「闘志」は、どんな時であろうと消えることはないと、確信を持って断言できますね。
私自身の経験は、後々『応援団に捧げた青春』シリーズでお話することにして、読者の皆様、如何だったでしょうか。
「感動」…一言で申し上げると、それしか浮かばないです。
ありがとう、東京大学運動会応援部。
そして、東京大学運動会応援部の益々のご発展を願って止みません。
東京大学運動会応援部に、栄光あれ!。











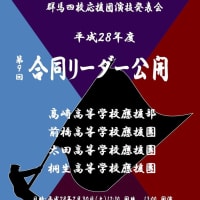





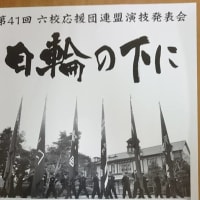
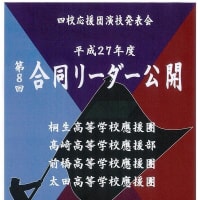






一年生の当時は何から何まで辛い練習だったけれど、走るのが苦手だった私にとってランニングはついて行くのがやっとで、車道に飛び出して車に轢かれて死にたいくらいの辛さでした。
東大の「大出走」を見ているとあの時の辛さを思い出します。
やはり中高にくらべても、大学の(特に東大は?)応援団の練習は凄いですし、
先の双子の父さんのコメントにも唸っていしまいました。
ただ、これが優勝のためとか、あのライバルに勝つためとかいうものがないので、
ほんと、観念的ですし、抽象的なんですよね。
もちろん、応援する母校が試合に勝ってほしいという思いはありますが、
実際に競技をするのは選手達ですので。
ダイレクトに分かりにくい、伝わりにくいのが応援団の魅力なのでしょう。
だからこそ、多角的に、ゆるゆると攻めてみてください。
ぼくも、ゆるゆるとお付き合いします。
かなり衝撃的だったのがきっかけでした。
自分たちが競技をしているわけでもないのに
どうしてこんなに一生懸命なんだろう…と。
私自身、学生時代に体育会で競技をする方の立場だったので
よけいにそう感じたのかもしれません。
そして、春のリーグ戦で新幹部の顔つきが
下級生の頃と全く違っているのを見た時も驚きました。
髪型が変わった、服装が変わったなどという次元ではなく
(うまく表現できなくてもどかしいのですが…)
何て言うか…持っている空気が違うんですよね。
この不思議な魅力を言葉で伝えるのは本当に難しいと思います。
Danchoさんの多角的攻撃、また楽しみが一つ増えました。
コメント、ありがとうございます。
★双子の父さん
少々レスが遅くなりました、申し訳ありません。
言い訳を一つだけさせていただくなら、この記事は、私達の様に、応援団に関わった方だけでなく、全く応援団とは無縁の読者の方にも動画をご笑覧頂いて、多くの感想をお聞きしたく、暫く待っていたので…というのが理由です。しかし、なかなか喰いつかないですね。難しいです。
仰るように、辛かったですよね。経験すると、あの辛さ…良く耐えたなぁって、思います。
同じ夏の練習でも、合宿の前と後では、「きつさ」が少し違う様な気がしました。応援団にとって「夏合宿」がやはり一つの節目の様な気がします。「あれ」を乗り切るかそうでないか…1年生の時は、そこが大きな分岐点ですよね。
冷静に考えれば、あの時の辛さから比べたら、仕事で多少きつくても、乗り切らなきゃ…って思うようにもなりました。本当に、その当時は、言葉にもならないほど辛かったですからね。
私達応援団経験者にとって、夏は、良い意味で「自己を省みる」季節なのかもしれませんね。
類まれではあるけれど、お互い、貴重な経験をさせていただきましたよね。
今後の人生にも、お互い培ったものを役立てて、頑張っていきましょう。
★ssayさん
以前は、やはり明治が凄かったと思います。私達の世代は、「応援団は、明治が日本一」と思って、そこを目指していましたから。
(ここでは敢えて取り上げませんが、私が応援団に興味を持った動画、YouTube上にあります。『明治 ある青春』で検索をかけると、出てきます。ちょっと「刺激」が強すぎますが。)
東大の場合、東京六大学野球が良い例ですが、「勝つ」事が「当たり前」ではないことを良く知っているから、あそこまで鍛えようとするし、「限界」とか、「壁」みたいなものがないのだと思います。そこに見てる側は、胸を打たれるわけです。自分達がいるのに、何故味方は負けるのか…そこをいつも考えているのだと思います。
仰る通り、「観念的」だし、「抽象的」で、言葉巧みで、それを仕事にしている方なら上手に表現できるのかもしれませんが、私には文才がないので、「挑戦」し続けるしかないかなぁ…と。
とにかく、ssayさんには励まして頂きました。それは本当に、今後ブログを続けていく上でも元気を頂いた気がします。
私なりに、頑張ってみます。
「ゆるゆる」お付き合い下されば、幸甚に存じます。
★烈さん
仰るように、「野球部を無心に応援する」という非常に単純明快で純粋なところが、共感を呼ぶところはあるのかもしれません。
実際に応援活動をしている現役諸君は、スタンドに陣取る学生や観客をどうやって乗せて「一体感」を生むことができるのか…しか考えていませんので(私の経験上は、そうでした)。
実は、私は運動音痴ですが、スポーツはその当時から見るのは好きでしたので、「全員レギュラー」な応援団は、運動部では私には合っていたのかもしれないとも感じます。
結果的に、「無心」…もっと良い表現を使えば「夢中」になれたという、凄く貴重な経験をさせていただき、改めて良かったと思っています。
双子の父さんもコメントなさっていますが、「夏合宿」は、やはり岐路の様で、そこを乗り切るかどうか、そして、下級生時代を何とか乗り切ったという「自信」が、幹部になって風格が伴うのだろうと思います(法政の鶴田君を見ていると、それが凄く伝わります)。
「幹部の格好良さ」は、実は「下級生時代の格好悪さ」がベースになっています。
上手に言えなくて申し訳ないのですが、これは烈さんが仰る「多角的攻撃」で、ssayさんが仰って下さったように、訴え続けていくしかないのかもしれません。
どこまでその魅力をブログという「ネット上の我が家」で語ることができるか…自信はありませんが、頑張ってみるつもりです。
今後とも、ご支援・ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
先ずは、「激励」と受け止めて良いと思うのですが、そんなとっても有難く、貴重なコメントを頂戴した御三方に対し、心より御礼まで。
誠に、ありがとうございました。