「なぜ来た!」先生から発せられた言葉に息をのんだ。
「霊なんて言うから・・・」先生の困惑した顔から、予想外のことが起きていると直感した。小さい声で「馬鹿!」と言ってから暫く黙っていた頭をもたげ、「もう帰りなさい」と私を突き放した。(やはり晴明は道を踏み外したのか?)
先生がこのような態度を見せるのは初めてであった。親近の情を抱いて指導を仰ぐ気持ちで来たが、先生のもとを退出して屋外の高台から海を見つめる眼も、茫洋と定まらなかった。胸の動悸は高鳴ったまま、おぼろに水平線を見つめていたが、暫くして眼前の島影に眼を移すと胸の鼓動もようやく収まって来た。眼前の島が露わになるにつれて、島を覆う全体の気迫が自分と一つになり、太平洋の大海原とこの高台の大地から立ち上る大気の抱擁を一生忘れまいと心に誓った。清二の胸の中に熱いものが流れた。
こうなる前に清明が自嘲気味に話したことがある。
既に二人の間には輝かしい気脈は脱薄して、清明の方が一歩引いていたのであるが、「俺がどのように変わるか君は分かっていない」と、ぽつりと言った。悲痛さはなかったが将来に幻滅した様子が窺われた。清二は返す言葉が無かったが、その意味を理解していた。運命の対極に存在する私を通して、彼は自らの運命を予見したのである。
もっと以前にもこんなことがあった。
彼の家には彼の他に誰もいなかったが、居間にあった蓄音機で一枚のレコードをかけてくれた。題名は覚えていないが彼の説明によると、絶望した少年が沖合の海に向かって何処までも泳いでいくという悲歌だった。この時に不思議な予感が頭をよぎったのを思い出すのである。彼も泳ぎが得意だった。海の家でアルバイトをしていたのも、彼には相応しい姿だった。海に育ち海の申し子のようにV形の胸元が眩しかった。
いつの間にか清明少年のことは表面的には意識から遠のいていった。職場にすっかり馴染んできて、美術工芸品の製造ラインに組み込まれながらも、自分の将来に希望が持てるようになっていた。バラ色の夢といかないまでも、少なくとも今よりは豊かな生活ができることを信じて、仕事に精を出していた。夢を追うような淡い希望の灯が、微かに燈ったのである。
そのような情況が続いていたなかにも、清明への再起を願う気持ちが心の隅にあった。彼の将来に軌道を外す事など無いように、心密かに祈ることで私の心も救われていた。
仕事が一通りできるようになり、生活にも潤いが出て来たところで、女が近づいてきた。女は積極的に私の前に現れたが、或る使命感があったのと、女の方に邪淫な感性を観たので深く付き合うことはなかった。女は淡い輪郭を描いたまま別の男へ飛んでいった。
清明に限らず眼に見えない対立が何処に起こっていても不思議はなかった。不運にも会社の経営者が清明と同じ壇ノ浦系だったので、職場の中にも渦潮が逆巻いていたのだった。私欲の強い経営者ではあったけれど、社員の福利厚生では毎年一度の一泊バス旅行を企画して、関東信越の温泉地を巡って来たのが思い出になっている。企画は当番制で社員が当たっていた。
問題も起こしていた。社員宛の郵便小包を勝手に開封して私物化したことや、技術的な特許申請で他社と揉めたことがあった。もっとも小包を開封した件は、ずっと後になって判明したことであり、在社中はあり得ないことと思っていた。10年後のふとした切っ掛けが元で、社長の義理の妹が口にした言葉、『返すように言ったのだけれど・・・』この言葉が清二の脳の中枢を刺激した。(・・・自分が知らないところで事実あったのだ!)何かとごたごたが起きやすい会社ではあったが、規制の緩い社風が若者を惹きつけた面もある。
絶えず新人の入れ替わりがあった流動性の強い職場には、若者の熱気と退廃が同時進行しているところがあって、良く言えばほどほどの自由な空気の中で仕事をしていたことになる。清二も当初はなかなか社風に馴染めなかったので、直ぐに消えていく流動社員の一人と見られていたようである。当の本人は10年間も会社に居続けて、すっかり板についた社員になっていた。
入社してから10年目を迎えたある日、社長室に呼ばれた。「君も10年勤続だな。社の方針として、長年勤続の優秀な社員の中から、独立させる考えがあるんだがどうかな」少し間をおいて「君より先輩もいるが、君が一番適当と思うのだがどうだろうか、君の気持を聞きたい」
社長の言葉が本心から『優秀だ』と思っているか如何かは疑問だが、「これも潮時かな」と思って応諾した。社長の声掛かりで工場を三鷹市に開設し、結婚したばかりの妻と夜遅くまで就業した。働けば働くほど自分たちの収入も増えると思っていた。確かに借金を返すほどに始めは良かったけれど、その内に社内幹部から特別扱いだと言う苦情が出て、あっという間に釉薬の単価が二倍に跳ね上がり、いくら生産してもぎりぎりの生活費を稼ぐだけとなるのであった。そうこうして30年も下請工場を続けることになったのである。美術工芸品の焼き物を製造する工場は、出来高に対する工賃制であるから、安い工賃で会社に上手く取り込まれることであった。製品を加工して納めるだけの自転車操業で30年が過ぎた。










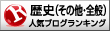






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます