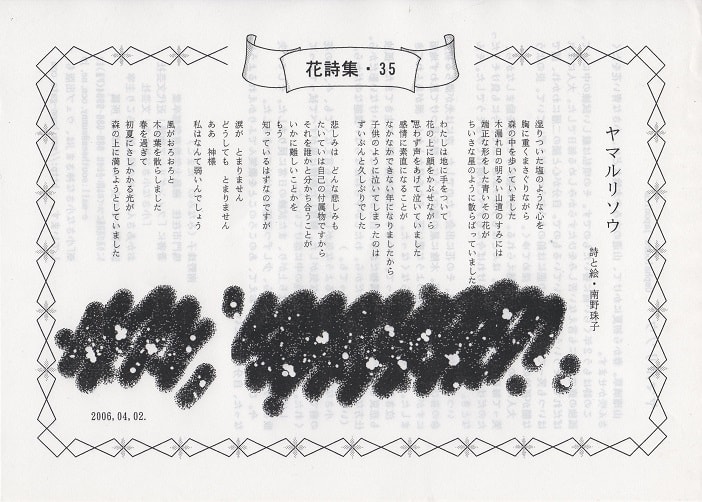ヤマルリソウ Omphalodes japonica
山瑠璃草。春から初夏にかけて、山道のすみや木陰などに、小さな青い花をたくさん咲かせます。
この詩はもう2年くらい前に書いたものです。その頃私は厳しい試練の中にいて、孤独の底でだれにも言えない苦しみをひたすらかみしめる毎日でした。大人になれば、だれでもそういう悲哀は抱いているもので。自分が心と顔の二層に分かれ、顔はいつも笑っていながら、胸の底には鉛のようなうつろがうずいていて、墨のような闇が孤独の輪郭ばかりを濃く深めてゆく。
大人だもの。大丈夫さ。乗り越えられる。半分は強がりで自分を励ましながら、笑って毎日を過ごしていました。ほんとうはもうあっぷあっぷで、今にも負けそうだったのだけど。虚勢をはっていなければ今にもすべてが崩れていきそうでした。そんなとき。
いつもゆく山の道のすみで、その花に出会ったのでした。空には光が満ちる初夏。命の喜びが風に満ちている季節。木陰に星の塊のような一群を見つけて思わず地面にすがりついた。まるで涙粒のような青い花。それを見たとたん、涙があふれてきました。次から次へと、とまらなくなった。
泣きたいことなら山ほどあって。いつもそれを瞳の奥に隠して生きてきた。孤独も悲哀も、すべては自己の付属物だから。自分が背負わなくてはいけない影だから。仕方ない。これは私の荷なのだから。わたしがやらねばならない課題なのだから。
(いいよ、今くらい。弱くなっても)
小さな花がささやいてくれるような気がした。誰にも言えなくても今、この花の前でなら言ってもいいような気がした。解放した感情は風がすべて拭っていってくれた。何もかもは初夏の光の中に溶けていった。
しばらく泣いた後、私は立ち上がり、また試練の日常に戻りました。そして、失敗とやり直しを繰り返しながら、少しずつ課題を片付けていきました。
今。ひとつのことをやりおえて、あのころのことをほほ笑んでふりかえれるようになった、自分がここにいます。
(2006年4月、花詩集35号)
山瑠璃草。春から初夏にかけて、山道のすみや木陰などに、小さな青い花をたくさん咲かせます。
この詩はもう2年くらい前に書いたものです。その頃私は厳しい試練の中にいて、孤独の底でだれにも言えない苦しみをひたすらかみしめる毎日でした。大人になれば、だれでもそういう悲哀は抱いているもので。自分が心と顔の二層に分かれ、顔はいつも笑っていながら、胸の底には鉛のようなうつろがうずいていて、墨のような闇が孤独の輪郭ばかりを濃く深めてゆく。
大人だもの。大丈夫さ。乗り越えられる。半分は強がりで自分を励ましながら、笑って毎日を過ごしていました。ほんとうはもうあっぷあっぷで、今にも負けそうだったのだけど。虚勢をはっていなければ今にもすべてが崩れていきそうでした。そんなとき。
いつもゆく山の道のすみで、その花に出会ったのでした。空には光が満ちる初夏。命の喜びが風に満ちている季節。木陰に星の塊のような一群を見つけて思わず地面にすがりついた。まるで涙粒のような青い花。それを見たとたん、涙があふれてきました。次から次へと、とまらなくなった。
泣きたいことなら山ほどあって。いつもそれを瞳の奥に隠して生きてきた。孤独も悲哀も、すべては自己の付属物だから。自分が背負わなくてはいけない影だから。仕方ない。これは私の荷なのだから。わたしがやらねばならない課題なのだから。
(いいよ、今くらい。弱くなっても)
小さな花がささやいてくれるような気がした。誰にも言えなくても今、この花の前でなら言ってもいいような気がした。解放した感情は風がすべて拭っていってくれた。何もかもは初夏の光の中に溶けていった。
しばらく泣いた後、私は立ち上がり、また試練の日常に戻りました。そして、失敗とやり直しを繰り返しながら、少しずつ課題を片付けていきました。
今。ひとつのことをやりおえて、あのころのことをほほ笑んでふりかえれるようになった、自分がここにいます。
(2006年4月、花詩集35号)