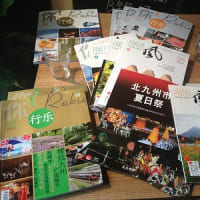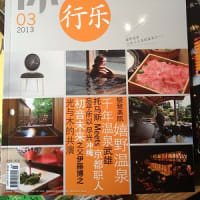今回、久しぶりに不動産ネタ。
日本でも「中国の不動産バブル」が話題となっていましたが、最近はあまり見受けないように思う。筆者だけかな・・・?
まあ、ちょっと聞き飽きた感もあるし、最近はかなり強い抑制策を打ち出していますからね。
で、実際のところはどうか・・・と言うと、
2012年後半からジワリジワリと回復傾向を示しているらしい。
中国指数研究院が発表したデータによると、全国100都市の住宅平均価格が1平方mあたり9,715元となり、前月比としては7ヶ月連続の上昇、前年同月比でも9ヶ月ぶりに小幅上昇を記録した。
昨年10月の国慶節に不動産フェアを偵察に行ったときも、結構な賑わいでしたからね。でも、その当時はまだ回復を鮮明に印象付けるほどではなかったんですが・・・、中国はホントに変化が早いです@@@
実際、上海では賃貸物件の値上がりも続いている。
筆者が住んでいるマンションは、地元民ばかりで日本人があまり住んでいないので結構安い物件だが、地下鉄の駅から近いという利点と第二期のマンション郡が発売開始になったこともあって、賃料もドンドン騰がっているとのこと。
だいたい昨年比で10パーセントぐらいアップしているようです。
物件は古くなる一方なのに、賃料は騰がっていくばかりっていうのは、日本では考えられないですよねぇ。。。
日本もこうした市況になれば、不動産を購入しようとする若い世代が増えて、経済が活性化するんでしょうが、将来不安のほうが強すぎて、不動産を購入しようとする若年層は減る一方ですもんね。
住宅って、設備の塊みたいなモンだから、経済波及効果大きいんですよねぇ。
いやはや、何とかしたいもんです。
【上海関連の情報が満載の「にほんブログ村 上海情報」はコチラ】
こうした社会背景もあって、一時は下火になっていたものの、都市部を中心に住宅の購入を急ごうとする若年層が増えているようだ。
これは、将来の値上がりを期待するという向きもあるが、若年層にとってはもっと切実な問題で、これ以上高騰すると将来住宅購入が不可能になるという想いが強いのだ。
しかし、実態経済に目を向けると、こうした不動産価格の上昇、高止まりとは裏腹に、若年層の所得は同じペースでは上昇していない。
中国全体としては高成長を維持しているように見えるが、生活者の感覚からすると、いまは1、2年前と比較すると明らかに「景気が悪い」という状況のように思える。
先日、旅行業界の方と話をする機会を得たが、春節の旅行商品の販売状況も芳しくなく、前年であればほぼ全ての旅行商品が完売状態だったのに、今年は70パーセントほどの成約率に止まっているという。
勿論、訪日観光で中国の富裕層がブランド品をドカ買いしていた当時が異常だったという見方もできるが、そればかりでもなさそうだ。
話を不動産に戻すと、中国政府は不動産市場に対して断固たる抑制姿勢を示し、過去最大級と言っていいほどの不動産購入抑制策を展開したにもかかわらず、現在ではその効果も消えつつあると言っていい。
中国でよく言われる「上に政策あれば、下に対策あり」というヤツで、中国人民は時の経過とともに政策への免疫力を強めていったのである。
こうした傾向は土地取引の現場で顕著となっており、上海をはじめとする10以上の都市で次々に土地取引額の最高額が更新されるという現象が起きている。
不動産開発、土地がないと何も始まりませんし、よい土地ほど価値が失われる可能性が少ないですからね。コレ、全世界共通の常識かと。。。
もっとも、中国における都市開発には政府、金融機関が強く関与しており、都市化を積極的に推進しようとする主体が地方政府であることを考えると、この傾向は当分収まりそうもない。
地方政府にとって、財政面から言うと地価の高騰は歓迎すべきものなのだから。
【中国関連の話題が満載の「にほんブログ村 中国情報(チャイナ)」はコチラ】
このような状況に対して、中央政府が神経を尖らせているのは言うまでもない。
政府はコトあるごとに「不動産抑制策の堅持」の意思を表明しているし、必要があれば新たな抑制策も検討する可能性があるとも言及している。
しかし、実体経済からみると、こうした姿勢をどこまで貫くことができるのか、甚だ怪しいと言わざるを得ない。
中国最大の貿易相手国である欧州の経済は、相変わらず経済危機に直面したままで、輸出は減少傾向が続いている。
尖閣諸島問題で日中関係も冷え込んだままで、実質的に最大の対中投資国だった日本からの投資は期待できないまま。開発区の担当者たちは「土地の売り先が見つからなくてヒマな状態」が続いている。
その意味では、同問題の影響を受けているのは日本だけではないのだ。
日本も安倍政権に代わり、金融緩和姿勢が鮮明になった。
欧州も現在の金融危機を乗り切るには金融緩和を継続するしかなく、米国も同じような状況が続く。
そうなると、投資先を渇望する大量の資金が市場に出回ることになり、こうした資金の矛先は「値上がりの確率が高い物件」へと向かうことになる。
つまり、日本の不動産ではなく、中国をはじめとするアジア諸国の不動産へと向かうワケです。ミャンマーが投資ブームに沸いているのが良い例ですね。
中国はリーマンショック後、巨額の公共投資で経済を立て直し、その後は金融引き締め策を強力に推進することで、経済のバランスを維持してきた(見かけ上は)。
ただ、少し無理をし過ぎたこともあって、実態との乖離が進み、今までのような政策実行は困難になってきたと言わざるを得ない。
経済成長とともに確実に進むインフレ。
このインフレに強いのは、結局のところ不動産と株式をはじめとする金融商品。
株は水物だけに、不動産の人気が衰えることはなさそうで、中国政府による舵取りは日を追うごとに難しさを増している。
世界経済の行方とあわせ、中国政府の政策動向にこれからも注意が必要だ。
↓ご愛読ありがとうございます。よければ応援クリックをポチっとお願いします。(ブログランキングに参戦中)
にほんブログ村