社会の先生の授業の役割ついて自分なりに考えたことを書きたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<社会の先生の授業での役割とは・・>
「教科書はあくまで事実の羅列」です。
教科書は,
「○○年にB国で××運動がおこり,A国はその運動を弾圧した。その結果,B国はA国の保護下におかれた。」
とか,
「○○戦争に参加した知識人にCとDがいる。」
などと,事実だけを書いてありますよね。(後の研究でその事実が覆ることもありますが,それはおいておいて)
こう言うと「だから教科書はダメなんだ!」という人がいますが,そうではありません。
むしろ,「事実の羅列」を教科書はしてくれればいいです。
ただし,ただ単に羅列だけをする教科書は,私には使いづらいですが・・。
私には前後の流れの記述や理解できるような文章構成は教科書でも必要なので・・。
教科書で事実の羅列をしてくれると,
「ここに書いてあるのが,真実。(現在で)」ということで,
数ある説などに惑わされずに済むので。なにごとも教科書が基本ということです。
でも,教科書にかかれている事実と事実の間を埋める情報があると,
さらに分かりやすいんですよね。
また,各人物がどういう人物であるかも知っているとさらに。
たとえば,
「○○年にB国で××運動がおこり,A国はその運動を弾圧した。その結果,B国はA国の保護下におかれた。」
という教科書の記述に,
B国はA国の人間を人間と思わない行為,たとえば死んでしまうほどの強制労働に我慢の限界を感じ,
××運動というA国への反対運動をおこした。しかし,A国の方が軍事力が強かったため,B国の××運動は
沈められた。もともとA国はB国の地下資源(天然ガスなど)を自分の手に入れたいと思っていたので,
××運動の鎮圧を機に,B国の保護国化した(自分の支配下おいた)。」
など,事実と事実の隙間と隙間を埋めるような内容があるとわかりやすいんですよね。
そのような事実と事実の隙間を埋める役割をするのが,
社会の先生の授業だと思うんです。
社会の先生で,
教科書にのってないことを説明する,ということに関して
「入試とは全然関係ないマメ知識を話す(たとえば,登場人物の恋愛事情など)」と思いがちの人がいます。
別にマメ知識を話すこと自体はわるいことではないのですが,そればかりに特化して話すのはどうか,と。
しかし,そういう人の多くは「だって,教科書に書いてあることを話しても・・。」と言います。
そりゃ,教科書の言葉をそのまま羅列して話しては,先生がいなくても良いでしょう。
(でも,教科書読んどけ!と言って,自主的に読む生徒はおそらく1割にみたいないでしょうが・・)
でも,入試で出るのは教科書の内容だし,
入試うんぬん以前に,一般教養として知っておかなければならない内容です。
だから,授業で何度も説明することで子供たちは頭に入っていくのです。
その際に,先ほど言ったように,
教科書に書いてある言葉を理解しやすいよう,
事実と事実の隙間を埋めてやるのが先生としての役割だと。
また,教科書の言葉は,植民地化や憲法制定など難しい言葉・具体的に
どういうことか想像できない言葉も
多いので,それをもう少しかみくだいて説明する必要もあります。
それには先生が心の底から用語を理解していなければならないので,先生たちも日々研究が必要だと。



ーーーー
ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けると嬉しいです。










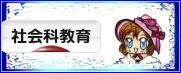










 そのあとで答え合わせをさせ、どれぐらいで覚えられたかを確認します。
そのあとで答え合わせをさせ、どれぐらいで覚えられたかを確認します。


 また、もう1つ印象に残っていることがあります。
また、もう1つ印象に残っていることがあります。 )
)
 私も一度、試験のすりなおしをしたことが・・。
私も一度、試験のすりなおしをしたことが・・。 ちなみに、現在の首相を聞く場合は、
ちなみに、現在の首相を聞く場合は、