
モーリス・ヴァンデールと聞いてすぐに反応できる人はかなりの通だ。
彼はフランスの渋いピアニストである。ジャケットでいえば真ん中にいる人が彼だ。
このアルバムは1961年にパリのブルーノートでのライヴを記録した隠れ名盤といえる。
なぜこのアルバムが一部のマニアの中で珍重されているかというと、その録音のすごさからなのだ。特に大ベテランのケニー・クラークが叩くドラムスの迫力が圧倒的なのである。
ライヴ録音は非常にむずかしい(のだと思う)。遠くから録ろうとすると一様にメリハリのない音になってしまう。だからといって近づけると音の大きな楽器の音のみがクローズアップされてしまい、バランスが著しく損なわれてしまう。だからその場でどのマイクの音を絞ったり拡げたりするかは、担当するミキサーの技量がものをいうわけだ。
しかし時は1961年だ。しかも街のライヴハウスでの録音だから設備の整ったホールではない。当然、今のような優秀なミキシング・コンソールがそこにあるとは思えない。
ここがポイントだ。この場を担当したミキサーは、当たるも八卦当たらぬも八卦、ここは一発勝負とばかり、思いっきりドラムスに焦点を当てた録り方をしたのだ。これが大正解。明らかに他のアルバムとは違う迫力が生まれた。
正直いってこんなリアルなスネアの音はあまり聞いたことがない。手を伸ばせばそこに届くような感じさえする。
これがうるさいと感じる人もおられるだろう。でも録音技術が進んだ現在では聴けない音であることも確かなのだ。
全体のバランスのいいことが必ずしもいい録音かどうか、もう一度考え直してみたいものだ。


















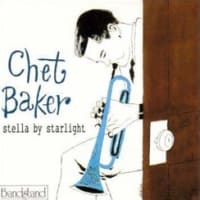

最近古い録音を聞くことが多く、ステレオ録音初期の、妙に生々しい音に「リアリティー」と「愛着」を感じています。