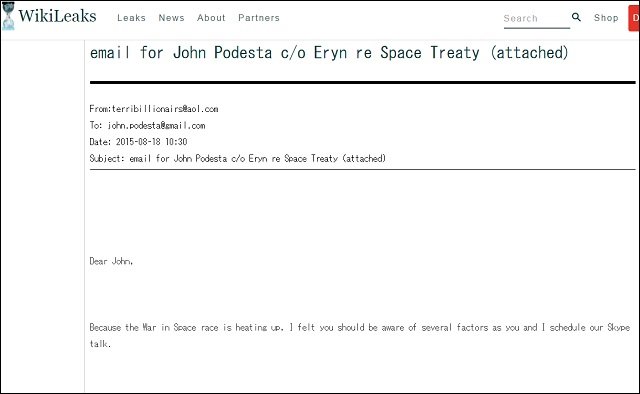理想国家日本の条件 さんより転載です。
http://www.mag2.com/p/money/24246 より
 2016年10月11日
2016年10月11日
第三次大戦が迫っている――ロシアのメディアは去年早くから、こうしたことを自国民に向けアピールしてきましたが、西側が真剣に報じるようになったのはつい最近のことです。(『カレイドスコープのメルマガ』)
※本記事は、『カレイドスコープのメルマガ』 2016年10月6日第176号パート1、10月11日第176号パート2の一部抜粋です。。
「もう私は何も言わない、何も期待しない」プーチン怒りの理由とは
開戦前夜
「今は第三次世界大戦前夜である」
数年前から、米国の数多くのオールターナティブ・メディア(企業にスポンサードされていない中立メディア)が、その可能性について指摘してきたことですが、ほんの数ヵ月前からは、いわゆる西側の企業メディアと言われている主流メディアでさえ、それを隠さなくなっています。英BBCが、独紙フランクフルター・アルゲマイネによって公表されたドイツ内務省の「民間防衛計画書」を取り上げて、ドイツ政府が国民に国家的緊急事態に備えるよう勧告していることを報じたのが今年8月。
それに先駆けて、オバマが5月31日のホワイトハウスの公式ページで「緊急事態に備えて、携帯電話にFEMAアプリをインストールすることを推奨」するだけでなく、同じく、ホワイトハウスの8月31日の公式ページでは、国家の非常事態に対処するため、国民一人一人に備えをしておくよう「国家準備月間 2016」を宣言しました。さらに、その前の8月2日のホワイトハウスの公式ページでは、「米国で緊急事態が起こったとき、トランプではそれに対処する能力が十分ではない」と、来月に迫った大統領選でトランプを潰すための方便に利用することも忘れていません。
(※第160号「経済崩壊と世界規模の気候大変動と日本版FEMAの創設」、あるいは、第174号パート1「国民に計画的『大艱難』への準備を奨励するホワイトハウス(その1)」にて詳述)
大方は、もはや不可避となっているドイツ銀行の破綻が、リーマンショックを一ケタも上回る経済災害を引き起こすためであって、米欧の経済大国が注意喚起のために、こうした警告を出すに至ったのである、と見ています。
ロシア緊急事態省が核戦争の危機を警告
しかし、その憶測は、9月29日のロシア・トゥディが、ロシア緊急事態省(EMERCOM)の「モスクワの全市民を地下シェルターに避難させる準備がととのった」との声明を報じたことによって、すぐに吹き飛んでしまいました。そして、翌日の9月30日、今度は英語圏向けに「モスクワは、米国が核兵器使用の準備が済んでいることに留意し、その対応に備えている」と、明確に核戦争の危機が迫っていることを警告したのです。
これは、ロシア・トゥディだけでなく、同日のプラウダでも報じられました。ロシア・トゥディもプラウダも、ロシア政府にコントロールされたメディアである以上、それらの英語圏向けの記事は、自国民向けの警告とともに、米国民に向けて核戦争の脅威を喧伝する目的も、その一方にあることは言うまでもないことです。ロシア国民に向けて、(英語のように)バイアスのかかっていないロシア語で正確に伝えているロシアのメディアによれば、その内容は次のとおりです。
ロシア緊急事態省(EMERCOM)のNo.2であるアンドレイ・ミスチェンコ(Andrei Mishchenko)は、「民間防衛体制の新しいアプローチとして、核攻撃その他の非常事態が生じた場合に備えて、モスクワの都市人口の100%を保護することができる地下避難施設の準備を完了した」と述べた。
ロシア政府は、民間防衛体制を強化するために、制御および緊急警報システムを近代化するための法的枠組みを更新した。さらに、ミスチェンコは、「われわれロシア緊急事態省は、民間防衛体制の分野において、市民の訓練システムの改善に取り組んでいる」と付け加えている。ロシア情報技術・通信省、ロシア財務省、ロシア産業貿易省、ロシア連邦準備制度理事会、そしてロシア銀行は、ロシア軍の突然の立ち入り検査にも応じている。これらの政府関連部門は、戦争の可能性に備えながら、戦時モードで各々のシステムの試験に取り組んでいる。
(ワシントンの権力者たちにとって都合の悪いニュースの暴露に専念している)ワシントン・フリー・ビーコン(Washington Free Beacon)は、ロシアが、突然、巨大燃料庫の建設を始めた、という米情報筋のソースを引用して記事にしている。
公表された情報によれば、このような掩蔽壕(えんたいごう)はロシアの国中に多数建設されているということである。専門家は、これらの建造物は、予期される事態に対応するための統合化自動コマンドとロシアのミサイル戦力の第五世代コントロール・システムに関係していると指摘している。それだけでなく、ロシアの民間防衛体制と緊急事態対応の組織に強い権限と責任を持っている部門によれば、この特別プログラムは2015年にモスクワでスタートしたということである。
その特別プログラムの範囲内で、空爆避難所と放射性降下物退避所がロシアの首都のあらゆる地区で建造され、あるいは再開されている。2年前、ロシアは、モスクワへの核攻撃を阻止して、徹底的な報復攻撃を加えるために実戦的な演習を行った。伝えられることろによれば、その実戦演習では、プーチン大統領は「核のスーツケース」を使用したということである。
2015年に、ロシアとアメリカ双方の将軍は、米国とロシアの間の核戦争は一触即発の危機にあると初めて述べた。「モスクワ市民を含む大多数のロシア国民は、彼ら住人にもっとも近い空爆避難所の場所を知っているわけではないが、それにもかかわらず、避難所のリストは存在している。避難所は、現在、人災によって引き起こされる非常事態、あるいは核攻撃に晒される数日間をやり過ごすことができるように維持されている」とロシア緊急事態省は述べている。
ロシアのメディアは、去年早くから、こうしたことを自国民に向けてアピールしてきましたが、西側の企業メディアが真剣に報じるようになったのは、つい最近のことです。
去年の暮、秘密結社のローマ法王フランシスコの言ったことを思い出してください。
「今年は、人類にとって最後のクリスマスになりそうだ」。クリスチャンは、こんなことを言う聖職者が悪魔憑きであることが、どうして分からないのでしょう。
プーチン「怒りのスピーチ」
米ロの核戦争が現実味を帯びてきたのは、ロシア第二の都市、サンクトペテルブルクで6月16~17日の2日間にわたって開かれた国際経済フォーラムからです。プーチンが数ヵ国の報道機関の代表を招いて行ったスピーチで話したことが衝撃となっています。その模様は、クレムリンの公式ホームページにアップロードされている動画によって確認することができます。幸運にも、ここには、そのフル・スピーチが翻訳字幕付きでアップされています。元の動画はコチラ。全世界で実に274万6千回も視聴されています。
プーチンは、集まった報道機関の代表者たちに、「私がこれから言うことを、あなた方が正確に報道するなどと期待してなどいない。しかし、私たちは大人である。大人としての対応を各人がすればいいことである」と、毎度、事実をゆがめて報道する西側メディアを牽制しながらも、率直に迫りつつある世界的危機について語りました。おそらく、この10分間のプーチンのスピーチも、いつものように、西側メディアの多くは封印しようとするでしょう。
国境なきハザール・マフィアの国際金融資本と、彼らの世界支配のツールであるCIAにコントロールされた西側メディアによって洗脳されている西側世界のすべての人々が、このスピーチの中味を理解できるかどうかに、地球の運命がかかっています。しかし、この動画の翻訳がところどころ間違っているため、予備知識や免疫のない人々には誤解を与えかねません。以下は、スピーチの重要ポイントを抜き出して補足を加えながらも簡潔に要約した正確な内容となります。
この70年は、東西(米ソ)の核戦力が微妙なバランスを保つことによって第三次世界大戦は回避されてきました。この二つの超核大国は、攻撃目的の戦略的核弾頭ミサイルの製造を停止しました。理由は単純で、どちらか一方の軍事力が潜在的に支配的になったとき、核弾頭ミサイルの発射スイッチを押したくなるものだからです。米ソ両国は、1972年5月に「戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイル・システムの開発、配備を厳しく制限するABC条約」を締結しました。
本土から、あるいは、核弾頭ミサイルの搭載が可能な原子力潜水艦などから発射された核弾頭を搭載してミサイルを、迎撃ミサイルによって撃ち落とせば、両陣営の核抑止力が機能しなくなってしまうからです。たとえると、同じ剣を持った同じ能力の戦士のどちらか一方が、決して突き破られない強固な盾を持って戦った場合、常識的には、その盾を持った戦士が戦いに勝利することになります。
その盾を制限することによって、互いに核による先制攻撃を思いとどまらせることこそが核抑止力になる、という考え方からABC条約が生まれたのです。しかし、大陸間弾道ミサイルの製造停止は、世界的世論によって受け入れられたものの、戦争で利益を上げたいと画策している米・軍産複合体にとっては致命的なダメージとなったのです。
そこで、ブッシュ米大統領は、ABM条約から脱退する旨を露骨に表明して2002年6月13日に同条約から正式脱退したのです。これによって、両核大国の軍事バランスは不透明になって、強い盾を持った一方が戦いに勝つことになってしまうのです。そのため、ABM条約の正式脱退によって足枷を解かれた米・軍産複合体は、企業メディアを使いながら一方で(北朝鮮などを使いながら)核の脅威を実態以上に煽って弾道ミサイルの迎撃システムの市場を開拓していったのです。
私は(プーチンは)、ブッシュら、ネオコンの策動に気が付いていたので、ロシアは、核戦力を増大させることによって東西の核抑止力を取り戻そうとしたのです。それは、事前に私(プーチン)から米側の支配者に通達されており、米支配者側も私(プーチン)の考えを受け入れたのです。なぜなら、その当時、ロシアは経済的に疲弊しており、米支配者側も、ロシアが旧ソ連時代以上の核戦力を取り戻すことなど想像だにしなかったからです。しかし、それは達成されたのです。
今では、ロシアの軍事力は、米国のそれ以上にハイテク化され、米国の戦力を凌駕するまでに巨大かつ強力になりました。しかし、それは、今まで、約束を守らず世界に嘘ばかりついてきた米国の軍産複合体とネオコンに対する警戒心から、そうせざるを得なかったことであって、ロシアが米国に対して先制的に戦争を挑むつもりなど毛頭ない、ということだけは言明しておきたいと思います。しかし、問題は、米国と米国の同盟国が配備しているミサイル迎撃システムの対ミサイルの種類です。
外形的にはトマホークなどの小型攻撃用ミサイルの形をしていても、小型の高性能核弾頭を搭載しているかどうかを知ることはできないからです。それは、たった数時間で取り付け可能です。艦船の上での作業によって、急きょ、核弾頭ミサイルに造り替えることができるのです。ワシントンのホワイトハウスにいる総司令官は、「非核から核へ」のたった一言で、すべてのことを済ませることができます。また、私(プーチン)が米国側のパートナーと話をしたとき、米国は核弾頭抜きの弾道ミサイルを開発したいという意向を持っていることを知りました。
米国本土から、あるいは、原子力潜水艦が深く静かに潜航してロシアの領土に近づき、そこから弾道ミサイルを発射した場合、ロシアは、その瞬間、それが核弾頭を搭載した弾道ミサイルであると断定してしまうでしょう。そのことによって、ロシアは自国防衛と、地球を核汚染でダメにしてしまう前に、それを止めるために大陸間弾道ミサイルを米国本土に向けて応酬するでしょう。これは、ネオコンによる罠であって、運よく人類が生き残った場合、ロシアを核の狂人であると責め立てるためのプロパガンダに使うでしょう。
このプーチンのスピーチのテーブルについている西側メディアの報道機関の代表と言われている人々の表情を見てください。彼らのうち、一人二人は気が付いたような表情をしていますが、大半の代表は、理解できないようです。私たちは、こうした人々が毎日、送り出している捏造情報を鵜呑みにしながら、一歩一歩、第三次世界大戦に向かっているのです。
「それが何をたらすのか分かっているのか!」プーチンの真意とは
さて、ここで重要なことを思い出してください。ロシア首脳陣による半ば非公式の公開討論会で、プーチンが、ISISが米国と、その同盟国によってつくられたことを正式に暴露した直後に、ロシアの戦闘爆撃機がシリアのISISをターゲットとして、果敢な空爆を行ったことを。それまで、ロシアはシリアに対して援軍を送りませんでした。しかし、主権国家であるシリアのアサド大統領からの正式な要請を受けて、プーチンのロシア軍は、ISISの掃討と同時に、米国とNATOが資金援助と武器を提供しているシリア反政府軍をターゲットとして本格的な反転功勢に出たのです。
結果、オバマの米軍が、それまで数万回もの空爆を繰り返しても、大した打撃を与えることができなかったISISを、たった2週間で、ほぼ殲滅させることに成功したのです。その後、ISISの残党は、姿を変えて東に分散・移動し、東南アジアでテロを引き起こしたり、アメリカのワシントンの手引きによって米国本土に潜入していることは既報のとおりです。
プーチンは、今度のメディアに対するスピーチで、このように言いました。「私たちは、全員、大人です。もう、私はあなた方には何も言わないし、何も期待しない」恐らく彼は、最後に、こう言いたかったはずです。「それが何をたらすのか、分かっているのか」と。前回同様、プーチンのロシアは、100%勝てることを確信した上で、こうした発言をするのです。これから何が起こるのか、それは自明です。プーチンが西側メディアを集めて、彼らに説教するときは、常に戦闘体制に入った後のことであることを忘れてはならないのです。
一方のホワイトハウスも、間違いなく、第三次世界大戦の準備をととのえ終わったようです。企業メディアでさえ、オバマ政権と彼の背後にいるグローバリストの戦争アジェンダを隠そうとしなくなりました。200年以上も国際金融資本の寡頭勢力による新世界秩序と闘ってきたプーチンのロシアは、ロシアが米国によって攻撃されようとしていることを確信をもっても感じ取ったからこそ、ロシアが防御モードに入ることを「国家主権に基づく措置である」と 国際社会に訴えるようになったのです。
西側のメディアによって、その声がかき消されてしまうことを知りながら。米ロの直接対決は、米国の敗北を意味します。そして、グローバリストによる米国の破壊計画は、何十年も前から用意周到に練られてきたのです。
ロシアは、核弾頭17,000発分のプルトニウムを備蓄している
核弾頭17,000発分のプルトニウムを備蓄
定評のあるサバイバル・サイト「デイジー・ルーサー(Daisy Luther)」は、最近、ソースを明記した上で「ロシアとの戦いが切迫している8つの警告に値する兆候」という見出しの「まとめ記事」をアップしました。それによると、「ロシアは、プルトニウムを備蓄している」ということです。米・国務省は、ロシアが備蓄しているプルトニウムの総トン数は、17,000発の核弾頭を製造するのに十分な量となっていることを点に注目しているとのこと。
同時に、ロシアは、シリアへの米国の侵略を想定したミサイル防衛システムを展開していることを正式に発表しました。これは、ロシアがヒラリーの勝利を前提として、彼女がシリアでの飛行禁止空域の設定を強行に進めようとすることを想定してのことであると思われます。世界の人々は、米国の同盟国であるアラブ連合が、カダフィーを打倒するために国連に働きかけてリビアに飛行禁止空域を設定したことを忘れてはいないでしょう。グローバリストの一民間組織に過ぎない国連のこの横暴な措置によって、NATOによるリビア侵略は国際世論の承認を得たことにされてしまったのです。飛行禁止空域が解かれたのは、カダフィーが殺害された後のことでした。リビアのカダフィーというアフリカの盟主を失った北アフリカは、その後、アルカイダとISISの餌食になったことは周知されていることです。
プーチンのロシアは、シリアで再び、それが繰り返されることに危機感を募らせているのです。ワシントンのプロパガンダ・メディアとして有名なFOXニュースは、ロシア外務省が、最近以下のような大変気がかりな声明を出したことを報じています。
「われわれは、ワシントンがシリアの首都、ダマスカスの政権をなんとしてでも交代させようと、悪魔と取引する準備ができていることを確信をもって言うことができる」と、ロシア外務相は述べました。「シリアのアサド大統領を追い出す目的のために、米国は、歴史の道筋を引き戻そうとするかのように、非情なテロリストと同盟を組み、テロリストたちを再び放とうとしている」とつけ加えて…
FOXニュース自体が、米国のワシントンが、アルカイダ、そして、ISISと連携してロシアの同盟国を倒そうとしていることを報じているのです。FOXニュースは、ロシア外相の声明を借りて、いったい何を言っているのでしょう。少なくとも、アルカイダはワシントンが創り出した、と言っているのです。
さすがのFOXニュースでさえ、第三次世界大戦が濃厚になって来たので、これを阻止しようとワシントンの暴露に動き始めた?違います。事態は、もっと深刻です。グローバル・リサーチに多数の記事を寄稿していることで知られているカート・ニモー(Kurt Nimmo)は、先週、そのグローバル・リサーチに、「米国は、まもなくテロリストがロシアの都市を攻撃するであろうとロシアに通達した。なんと、そのテロリストは米国と同盟関係を結んでいる」という記事を書き上げました。
国務省のスポークスマン、ジョン・カービーは、「シリアの急進的なサラフィスト(Salafist)のテロリストがロシアの都市を明日にでも攻撃するかもしれない」と、先週の水曜日にロシアに警告しました。「過激派グループは、彼らの活動を拡大するためにシリアにある空白地帯を食いつくし続けている。それは、ロシアの利害に対する攻撃をも含んでいる。おそらく、ロシアの都市でさえも。結果、ロシアは、ロシア兵を遺体袋に入れてシリアから帰還させることになるだろう。そして、ロシアは、重要な戦力、そう航空爆撃機さえ失い続けるだろう」とジョン・カービーは言います。シリアの領土に入り込んでいる「過激派グループ」は、米国とその同盟国である湾岸の首長国のパートナーよって支援されているので、カービーのこのコメントは、米・国務省がロシアを恫喝していると解釈する以外にないのです。
ワシントンとオバマの背後にいるグローバリストは、今まで彼らのアジェンダを必死に隠してきましたが、主権国家であるシリアにまったく事実に反する難癖をつけ、その同盟国のロシアまでテロによって脅迫するようになったことは、事実上、米国のグローバリストは、シリアとロシアに対して宣戦布告したことになるのです。ワシントンと、グローバリストの操り人形であるオバマ、そして、すでに死んでいようが、影武者であろうが、その後釜に据えられようとしているヒラリー・クリントンが、明確にロシアのプーチン打倒を言い出したということなのです。戦いの準備はできています――
※本記事は、『カレイドスコープのメルマガ』 2016年10月6日第176号パート1、10月11日第176号パート2の一部抜粋です。