
普通、テンカラではウイングの付いた毛鉤は使いません。それは伝承毛鉤のほとんどにウイングは付いていないからだと思います。
以前、沢山の伝承毛鉤を見た事は前スレで書きましたが、その時の一つに大きなカケスの羽根で作られたウイングが付けられた毛鉤を見ました。
伝承毛鉤はその使い手の工夫が凝縮され、加えて無駄は一切削除されています。その中にウイングがあるのには驚きました。
で、画像の毛鉤は『釣鈎図譜』という本からの抜粋です。先にも書きましたが、この本はいつ誰が何の目的で書いたのか?まったく判っていない書物です。ただ単に全国の色々な釣り針を絵で図鑑のように羅列されているだけの本です。別冊に明治22年頃に中村利吉という人が著したらしいと推定されているだけです。
そこに毛鉤も掲載されているのですが、ほとんどが普通の蓑毛と胴なのに対し、これだけはウィングが付けられています。ウィングの中央にストークが確認出来ることから、普通のフライのウイングとはちょっと違う感じです。
いずれにしてもこうした絵が残っている以上、少しでも多くの魚を釣るために、先達たちは様々な紆余曲折を繰り返しながら自分の毛鉤を完成に近づける努力をしていた事だけは伺えますね。
最近、突拍子もない良い案が浮かんで来なくなってしまったのは悲しい現実です。
以前、沢山の伝承毛鉤を見た事は前スレで書きましたが、その時の一つに大きなカケスの羽根で作られたウイングが付けられた毛鉤を見ました。
伝承毛鉤はその使い手の工夫が凝縮され、加えて無駄は一切削除されています。その中にウイングがあるのには驚きました。
で、画像の毛鉤は『釣鈎図譜』という本からの抜粋です。先にも書きましたが、この本はいつ誰が何の目的で書いたのか?まったく判っていない書物です。ただ単に全国の色々な釣り針を絵で図鑑のように羅列されているだけの本です。別冊に明治22年頃に中村利吉という人が著したらしいと推定されているだけです。
そこに毛鉤も掲載されているのですが、ほとんどが普通の蓑毛と胴なのに対し、これだけはウィングが付けられています。ウィングの中央にストークが確認出来ることから、普通のフライのウイングとはちょっと違う感じです。
いずれにしてもこうした絵が残っている以上、少しでも多くの魚を釣るために、先達たちは様々な紆余曲折を繰り返しながら自分の毛鉤を完成に近づける努力をしていた事だけは伺えますね。
最近、突拍子もない良い案が浮かんで来なくなってしまったのは悲しい現実です。















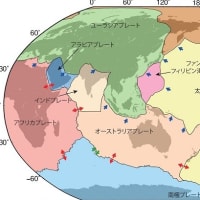




そしてこの毛鉤を使っている方にお会いしたいです
どんな使い方をするのかとても興味があります
それにしてもテンカラ毛鉤というのは本当に同じ物がありませんね みなさんそれぞれの思いのこもった最高の毛鉤ですね!
僕もこの毛鉤を巻いた人がどんな人だったのか?とても興味があります。
毛鉤はとても小さくて、普通に見ただけではせいぜい『虫っぽい』と思える程度です。場合によっては虫にさえ見えない場合もあります(笑。それどころか、ただのゴミか綿埃にしか見えないものさえあります(自爆。
それでも、使い手は一本の竿と糸を通して熱き思いをその毛鉤に送り込み、魚にとって美味しそうな虫に見えるように操作して魚を手中にするわけです。
これで感動がないはずはあり得ませんね!
やはりテンカラは高貴な釣りです。