「ハノン39番」を始めたのはこの4月ですが、実は「ハノン」購入したのはすごく前なんですよね…
 ←いつまでやる? それは目的次第で…
←いつまでやる? それは目的次第で…
と思って、自分のブログを検索してたらみつけた:
「蔵出し: ハノンを買ったときの話(2006)」
またろうの中学合唱コンに行ったら、クラスごとに伴奏者がいる中で、ほかの子たちと次元の違う、同じピアノとは思えないほど美しい音色で弾いている子がいて、その話をピアノのレッスンのときしてみたら、なんと同じ先生に習ってた、という話。
この先生というのはおゆき先生ではなくて、ヤマハのときの先生。ハノンをやれとはまったく言っていなかったけれど、私のほうから「合唱コンで聞いた子がすごかった」という話をしたら「彼は一時間レッスンのうち最初の15分、音階を弾いている」と教えてくれたんですよね。
「アンダンテさんはやりたくないだろうけど」(←笑)音階弾いていくと音は変わると思う、と。
おゆき先生が「ハノン39番」を奨めてくれた理由は、音階を滑らかに美しく弾く訓練をするということよりは、調性感覚、和声感覚をつけるというか、「基本の和音をさっと押さえられる」というほうに力点があるようなのですが
さて、購入から二十年近く経ってようやく活用を始めたわけですが…その感想として、おゆき先生が言っているような効果はあると思う…「思う」というのはまだハッキリその域に達していないからだけど、まぁもうしばらく続けていればそうなっていくという感触はある。
しかし「音がキレイに」のほうは、ちょっと話が遠いというか、まったくナシではないんだけれど、現状私がやっていることは別にそっち方面につながっていない気がする。
つまり、昨日書いた話「無駄な力を抜く」とも関連するのですが、ピアノでいっても音色の向上というのはやはり「無駄な力を抜く」が必要だと思うんですね。
私が現状、音階を弾いてるときって、かなり考え考えやっているというか、別に身についてスーッと行けてるわけじゃないので、「ようやく弾いている状態」。全体に準備が遅いのですね。あーなんとか間に合った、という打鍵。
そうではなくて、もう考える必要もないくらい、音や指使い、黒鍵と白鍵の形を考慮した最適な指運びというものが体の中に入っていて、速い音階を弾く場合であっても細かく見れば十分に間に合って鍵盤直上にスタンバイして最小の動きで打鍵しているのであれば、それはキレイな音の打鍵を日々経験として塗り重ねていくことになるだろうし、それが「音階+カデンツ」というたいへん応用の効くパターンであれば曲の中でも自然と生きてくるであろう、というような。
そこまでやるのはかなり長い道のりだなぁ、と思う。
「音色」ということであれば、難しくない曲できちんと仕上げるまで弾くのであれば似た効果があるんじゃないか? とも思うし…たぶんそりゃ音階であることの良さ(シンプル)はあるんだろうけども。

というか結局20年塩漬けしてたのと違う楽譜を見ているのだが(↑ハノンより薄くて良い)
----- 今日の録音:
バッハ/ガボット(新しいバイオリン教本2)
「余分な力を抜く」を考えてちょっと音よくなったと思う
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
と思って、自分のブログを検索してたらみつけた:
「蔵出し: ハノンを買ったときの話(2006)」
またろうの中学合唱コンに行ったら、クラスごとに伴奏者がいる中で、ほかの子たちと次元の違う、同じピアノとは思えないほど美しい音色で弾いている子がいて、その話をピアノのレッスンのときしてみたら、なんと同じ先生に習ってた、という話。
この先生というのはおゆき先生ではなくて、ヤマハのときの先生。ハノンをやれとはまったく言っていなかったけれど、私のほうから「合唱コンで聞いた子がすごかった」という話をしたら「彼は一時間レッスンのうち最初の15分、音階を弾いている」と教えてくれたんですよね。
「アンダンテさんはやりたくないだろうけど」(←笑)音階弾いていくと音は変わると思う、と。
おゆき先生が「ハノン39番」を奨めてくれた理由は、音階を滑らかに美しく弾く訓練をするということよりは、調性感覚、和声感覚をつけるというか、「基本の和音をさっと押さえられる」というほうに力点があるようなのですが
さて、購入から二十年近く経ってようやく活用を始めたわけですが…その感想として、おゆき先生が言っているような効果はあると思う…「思う」というのはまだハッキリその域に達していないからだけど、まぁもうしばらく続けていればそうなっていくという感触はある。
しかし「音がキレイに」のほうは、ちょっと話が遠いというか、まったくナシではないんだけれど、現状私がやっていることは別にそっち方面につながっていない気がする。
つまり、昨日書いた話「無駄な力を抜く」とも関連するのですが、ピアノでいっても音色の向上というのはやはり「無駄な力を抜く」が必要だと思うんですね。
私が現状、音階を弾いてるときって、かなり考え考えやっているというか、別に身についてスーッと行けてるわけじゃないので、「ようやく弾いている状態」。全体に準備が遅いのですね。あーなんとか間に合った、という打鍵。
そうではなくて、もう考える必要もないくらい、音や指使い、黒鍵と白鍵の形を考慮した最適な指運びというものが体の中に入っていて、速い音階を弾く場合であっても細かく見れば十分に間に合って鍵盤直上にスタンバイして最小の動きで打鍵しているのであれば、それはキレイな音の打鍵を日々経験として塗り重ねていくことになるだろうし、それが「音階+カデンツ」というたいへん応用の効くパターンであれば曲の中でも自然と生きてくるであろう、というような。
そこまでやるのはかなり長い道のりだなぁ、と思う。
「音色」ということであれば、難しくない曲できちんと仕上げるまで弾くのであれば似た効果があるんじゃないか? とも思うし…たぶんそりゃ音階であることの良さ(シンプル)はあるんだろうけども。

というか結局20年塩漬けしてたのと違う楽譜を見ているのだが(↑ハノンより薄くて良い)
----- 今日の録音:
バッハ/ガボット(新しいバイオリン教本2)
「余分な力を抜く」を考えてちょっと音よくなったと思う
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社










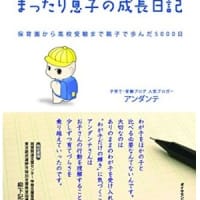



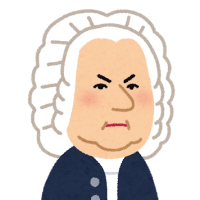

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます