「蜜蜂と遠雷」にサン=サーンスのアフリカ幻想曲というのが出てきましたが、ナニソレ聞いたことない…
 ←そういえばヨーロッパとアフリカってわりと近いんですね
←そういえばヨーロッパとアフリカってわりと近いんですね
そもそもピアノ独奏曲じゃなくてピアノ+オーケストラ曲なんだけど、それを風間塵がセルフ編曲して弾いているという設定。「蜜蜂と遠雷」の8枚組CDを買ったけれどもこの曲は元のままオケありバージョンのが入っていて、映画ではどうするつもりなんでしょう。まさかほんとに藤田真央くんが自分で編曲して熱演してたりしたら胸アツですねぇ。
YouTube検索したらソロ版弾いてる人はいた→サン=サーンス: アフリカ幻想曲,Op.89(ピアノ独奏版)
でもあんまりイイ感じに聞こえない。これ、(ソロ版にしてコンクールで聞かせるって)難しいんじゃないかなぁ。
CDに入ってたピアノ+オーケストラの演奏で聞くとなかなかいい曲でした。
これアフリカなのかなぁ…とは思ったんだけど。いや、じゃ、アフリカって何なのさって言われたら知らないから困るんだけど(^^;; ほら、バルトークがあちらこちらの民謡を採取して作曲したのとか、明らかに民族調というか、それまでの西洋音楽の本流とは全然違うものに聞こえるでしょう。それに比べると、なんかふつうっぽい、西洋音楽の本流から外れない感じがします。
というかそもそも、サン=サーンスがフランスの人のはずだけど曲はあんまりフランスっぽいイメージ(ドビュッシー、ラヴェル、フォーレ、サティみたいな?)じゃないよね。
いったいサン=サーンスにとってアフリカってどんなポジションなんだろうと思いました。
「クラシックでわかる世界史」で見ますと、サン=サーンスはベト様推しで「フランス人による古典的な交響曲の創作がほとんどおこなわれない自国の現状を深く憂慮していた」とかで、作曲のコンクールに「無名のドイツ人作曲家」であると偽って交響曲を出して受賞したんだって。
ソコなんで偽る、って感じなんですが、当時のフランスの人たちは演奏会場でドイツ音楽を聴くことは好むものの、フランス人がドイツっぽい曲を作ることはよしとしなかったそうで、なんか複雑なんですね。なのでサン=サーンスについては「ドイツ贔屓」といわれ批判が多かったそうです。
フランスとドイツなんて、近いけど(近いから)ずーっと仲悪いものね。アルザス・ロレーヌ地方をあっちやったりこっちやったり(「最後の授業」(*))。
ところで普仏戦争の直前、スエズ運河が開通していて、ヨーロッパからアジアへのルートが劇的ショートカットされた。そんなことがあってアフリカ(というか特にエジプト)への関心は高まっていたので、たとえばヨハン・シュトラウス二世が「エジプト行進曲」というのを書いてたりする。
「アフリカ幻想曲」は1891年作曲だけど、そのちょっと前の1889年にはパリ万博があって、植民地(アジアやアフリカの)の人々の生活を展示したりしてたから、ドビュッシーもここでガムランを聞いて作曲に取り入れたりしている。
サン=サーンスは、万博でちょっと見た聞いたというのでなしに、頻繁にアフリカに行っていて、ただ、アフリカといっても広いんだけど、サン=サーンスにとってのアフリカとは、北アフリカ…チュニジアらへんだそうです…ということを、ピティナピアノ曲事典で読んだんだけど、したら
「確かに、サン=サーンスのオリエンタリスムは表層的だとの批判は多いけれども、東洋に行ったこともないのに想像だけで描くのと、実際行ったことはあるけれども、自分の表現手段として取捨選択の上あえて露骨に東洋の素材を用いない、というのは遠目には仕上がりは似ていても、本質は全く異なるということを理解して頂きたい。」
と書いてあった。私が上に書いた「なんかふつうっぽい、西洋音楽の本流から外れない感じがします。」が聞こえてたような…いえ悪口ではないんですよ別に…
(*)…あれが、母語を取り上げられる話じゃないって知ったときはすごく裏切られた気分になりました
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
そもそもピアノ独奏曲じゃなくてピアノ+オーケストラ曲なんだけど、それを風間塵がセルフ編曲して弾いているという設定。「蜜蜂と遠雷」の8枚組CDを買ったけれどもこの曲は元のままオケありバージョンのが入っていて、映画ではどうするつもりなんでしょう。まさかほんとに藤田真央くんが自分で編曲して熱演してたりしたら胸アツですねぇ。
YouTube検索したらソロ版弾いてる人はいた→サン=サーンス: アフリカ幻想曲,Op.89(ピアノ独奏版)
でもあんまりイイ感じに聞こえない。これ、(ソロ版にしてコンクールで聞かせるって)難しいんじゃないかなぁ。
CDに入ってたピアノ+オーケストラの演奏で聞くとなかなかいい曲でした。
これアフリカなのかなぁ…とは思ったんだけど。いや、じゃ、アフリカって何なのさって言われたら知らないから困るんだけど(^^;; ほら、バルトークがあちらこちらの民謡を採取して作曲したのとか、明らかに民族調というか、それまでの西洋音楽の本流とは全然違うものに聞こえるでしょう。それに比べると、なんかふつうっぽい、西洋音楽の本流から外れない感じがします。
というかそもそも、サン=サーンスがフランスの人のはずだけど曲はあんまりフランスっぽいイメージ(ドビュッシー、ラヴェル、フォーレ、サティみたいな?)じゃないよね。
いったいサン=サーンスにとってアフリカってどんなポジションなんだろうと思いました。
「クラシックでわかる世界史」で見ますと、サン=サーンスはベト様推しで「フランス人による古典的な交響曲の創作がほとんどおこなわれない自国の現状を深く憂慮していた」とかで、作曲のコンクールに「無名のドイツ人作曲家」であると偽って交響曲を出して受賞したんだって。
ソコなんで偽る、って感じなんですが、当時のフランスの人たちは演奏会場でドイツ音楽を聴くことは好むものの、フランス人がドイツっぽい曲を作ることはよしとしなかったそうで、なんか複雑なんですね。なのでサン=サーンスについては「ドイツ贔屓」といわれ批判が多かったそうです。
フランスとドイツなんて、近いけど(近いから)ずーっと仲悪いものね。アルザス・ロレーヌ地方をあっちやったりこっちやったり(「最後の授業」(*))。
ところで普仏戦争の直前、スエズ運河が開通していて、ヨーロッパからアジアへのルートが劇的ショートカットされた。そんなことがあってアフリカ(というか特にエジプト)への関心は高まっていたので、たとえばヨハン・シュトラウス二世が「エジプト行進曲」というのを書いてたりする。
「アフリカ幻想曲」は1891年作曲だけど、そのちょっと前の1889年にはパリ万博があって、植民地(アジアやアフリカの)の人々の生活を展示したりしてたから、ドビュッシーもここでガムランを聞いて作曲に取り入れたりしている。
サン=サーンスは、万博でちょっと見た聞いたというのでなしに、頻繁にアフリカに行っていて、ただ、アフリカといっても広いんだけど、サン=サーンスにとってのアフリカとは、北アフリカ…チュニジアらへんだそうです…ということを、ピティナピアノ曲事典で読んだんだけど、したら
「確かに、サン=サーンスのオリエンタリスムは表層的だとの批判は多いけれども、東洋に行ったこともないのに想像だけで描くのと、実際行ったことはあるけれども、自分の表現手段として取捨選択の上あえて露骨に東洋の素材を用いない、というのは遠目には仕上がりは似ていても、本質は全く異なるということを理解して頂きたい。」
と書いてあった。私が上に書いた「なんかふつうっぽい、西洋音楽の本流から外れない感じがします。」が聞こえてたような…いえ悪口ではないんですよ別に…
(*)…あれが、母語を取り上げられる話じゃないって知ったときはすごく裏切られた気分になりました
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社










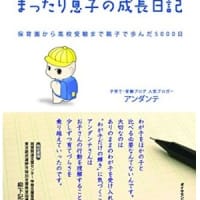










リストがヴェルディのオペラを元に書いたパラフレーズのどれかにこんな感じのがあったという気がします。気のせいかもしれません。
「最後の授業」のウィキとアンサイクロペディアを読みました。ショック…。アルザス人は物語の時代にはフランス語が話せなかったんですね…。今まで騙されてました…。
アラ(^^;;
国語の教科書に載っていましたか? でも小学校の先生は背景とか教えてくれなかったですよね~