昨日の鍵ハモは、どの曲もたいへん気分よく吹いていて絶好調だったのですが、
 ←言語化、意識化が安定のためには大事
←言語化、意識化が安定のためには大事
どうもうまくいかないな?? という日もあったんですよ。なんか、息が続かない…吹きにくい…
何が違うんだろうか、と不思議に思っていたのですが…
ようやく、違いに気づきました。以下、うまく説明できるか心もとないんですが書いてみます。
長いフレーズを、息継ぎなしで吹きたいと思ったらどうしますか?
吹き始める前に、めいっぱい息を吸う??
息は節約ぎみに使っていく??
はい、これが落とし穴だったんです、たぶん。
こうやってると、あれ~?? なんか続かないなー?? って焦って、もっとめいっぱい吸って、息節約しようとして、そしてドツボにハマります。
逆なんです。
水泳とかやる人は知っていると思うのですが、息いっぱい吸ってー、そのまま止めて!! ってしているより、息をちゃんと吐いたほうが苦しくならないんですよね。あれってどういうふうに説明されてるのかな。と思って検索してみましたがまぁこんな感じです:
息継ぎ入門: 効率のよい空気の入れ替え
殆どの人にとって呼吸は、「息を吸うこと」であり、「息を吐くこと」は二の次です。しかし水泳に限らず息切れを伴う運動に関して言えば、吐くことにもっと重点を置くべきなのです。息を吐き出すことに集中し、息を吸うのは自然に任せます。
その理由は次の通りです。一回の呼吸で肺に取り込まれる空気中、21パーセントが酸素、そして二酸化炭素はほぼ皆無です。息を吐き出す際は、14パーセントの酸素と6パーセント近くの二酸化炭素が排出されます。これが何を意味するかというと、吸って取り込んだ分のほんの3分の1の酸素しか消費しないことから、酸素不足が原因なのではなく血中の二酸化炭素量の上昇によって息切れ感が引き起こされるのです。
-------------------------
息を吸うことは自然に任せて、適宜「余った息をパイプの外に捨てる」感じで吹いていくのが吉です。
フルート吹いてたときはどうしてたんだい、って話ですが、フルートは息ガバガバ使うんですよね、鍵ハモに比べると…
いくら、ピアニッシモで吹いてたとしても、息の吐き方が不足して云々ということはありませんでした。
私の「好不調」は、無意識でうまい息の使い方をしていた日が好調、
「あれ?? うまくいかないな」でドツボにハマった日が不調、
ということだったように思います。
つまり、好調の日がありつつ、何をどうやって吹いてるのかは無意識だったってことです。どういうわけだか。
気が付いてよかったです(^^;;
(実際のところ、息のうまい使い方についてはもうちょっと細かい体感があって、でも言語化できない。。)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
どうもうまくいかないな?? という日もあったんですよ。なんか、息が続かない…吹きにくい…
何が違うんだろうか、と不思議に思っていたのですが…
ようやく、違いに気づきました。以下、うまく説明できるか心もとないんですが書いてみます。
長いフレーズを、息継ぎなしで吹きたいと思ったらどうしますか?
吹き始める前に、めいっぱい息を吸う??
息は節約ぎみに使っていく??
はい、これが落とし穴だったんです、たぶん。
こうやってると、あれ~?? なんか続かないなー?? って焦って、もっとめいっぱい吸って、息節約しようとして、そしてドツボにハマります。
逆なんです。
水泳とかやる人は知っていると思うのですが、息いっぱい吸ってー、そのまま止めて!! ってしているより、息をちゃんと吐いたほうが苦しくならないんですよね。あれってどういうふうに説明されてるのかな。と思って検索してみましたがまぁこんな感じです:
息継ぎ入門: 効率のよい空気の入れ替え
殆どの人にとって呼吸は、「息を吸うこと」であり、「息を吐くこと」は二の次です。しかし水泳に限らず息切れを伴う運動に関して言えば、吐くことにもっと重点を置くべきなのです。息を吐き出すことに集中し、息を吸うのは自然に任せます。
その理由は次の通りです。一回の呼吸で肺に取り込まれる空気中、21パーセントが酸素、そして二酸化炭素はほぼ皆無です。息を吐き出す際は、14パーセントの酸素と6パーセント近くの二酸化炭素が排出されます。これが何を意味するかというと、吸って取り込んだ分のほんの3分の1の酸素しか消費しないことから、酸素不足が原因なのではなく血中の二酸化炭素量の上昇によって息切れ感が引き起こされるのです。
-------------------------
息を吸うことは自然に任せて、適宜「余った息をパイプの外に捨てる」感じで吹いていくのが吉です。
フルート吹いてたときはどうしてたんだい、って話ですが、フルートは息ガバガバ使うんですよね、鍵ハモに比べると…
いくら、ピアニッシモで吹いてたとしても、息の吐き方が不足して云々ということはありませんでした。
私の「好不調」は、無意識でうまい息の使い方をしていた日が好調、
「あれ?? うまくいかないな」でドツボにハマった日が不調、
ということだったように思います。
つまり、好調の日がありつつ、何をどうやって吹いてるのかは無意識だったってことです。どういうわけだか。
気が付いてよかったです(^^;;
(実際のところ、息のうまい使い方についてはもうちょっと細かい体感があって、でも言語化できない。。)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社










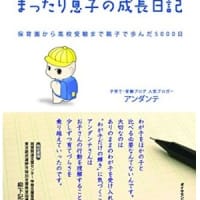



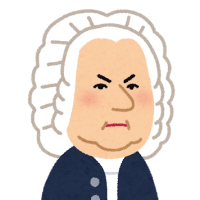

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます