子どものころ、ピアノ習ってた人、スラーはどう習った? 「音をつなげて(滑らかに)弾きましょう」…それだけだったな、私は。
 ←五線譜システム、よくできてるようなそうでないような
←五線譜システム、よくできてるようなそうでないような
ところが、「ベートーヴェンを"読む" 32のピアノソナタ」にはこうある:
「18世紀から19世紀初頭にかけてのスラーの基本原則は、とても単純なものだった。
1) スラーがかかっている最初の音は、わずかに強調される(ごく軽いアクセントを示すと考えてもよい)
2) スラーがかかっている最後の音は、強調されたり、アクセントが付けられたりせず、軽く演奏される。なお、最後の音は、常にではないものの、一般に記譜よりも若干短く演奏される。
このことを最初に言葉でしっかり見た(聞いた)のは「shig式譜読みメソッドテキスト(草稿)」の中だったのだが、ハッキリ言って「聞いてねっし!!」驚愕であった。
考えてみれば、子どものころから、まともな演奏を耳にする機会も多々あったわけで、そう弾かれていることがあると知らないわけではなかったけれど、それはみんな「なんとなく」「勝手に」(^^;; やってるもんだと思っていた。元々楽譜がそのように意図して書かれているなんて思ってもみなかった。
音符の長さにしても同じく、算数でいうように解釈していて、八分音符なら四分音符の半分、三連符なら三分の一であって、「三拍子系の中に付点パターンが出てきたら、作曲者の意図はもしかしたら2:1分割パターンなのかもしれない」(「shig式譜読みメソッドテキスト(草稿)」より)なんて言われたら、
うっそーん(o_o)
って感じ。
私は、ピアノも音楽も得意じゃないけど「譜読みは得意」と思っていたけどその譜読みは…!? 実は譜読みでないなにか
(ドはドでレはレで、1と2と3と4と…みたいな範囲で即物的に読むだけ)
だったんだなとか。
まぁ私はそんな感じだけど、音楽専門の人ならまるっと明確にわかってるかといえばそれはそう簡単に割り切れるものでもないらしく、
「小澤征爾さんと、音楽について話をする」にあった、音楽キャンプで子どもたちの弦楽四重奏の指導をしていたときの話。
ラヴェルのカルテットに長いスラーがあって、まぁ弦楽器やる人にとってはスラーって「ひと弓で弾け」って指示にとるけど、ひと弓で弾くには長くてたいへん。
そこで、ひとりの先生は
「スラーはフレーズのまとまりを示すものであって弓の運びの指示ではない。弓は返してもかまわない。弓の長さは決まっているんだから、無理したって意味ない」と指導し、
また別の先生は
「せっかく作曲家がそう書いているんだから、いちおうそういう弓の運びをしてごらんよ」と指導した。
この件について小澤さんは、
「両方正しいんです。それはね、学生が両方を試してみて、自分が正しいと思う方を選べばいいんです」
といっている。
この話を思い出したのは、シフさんのベトソナレクチャーでこんなくだりがあったから。
「(ベトソナにある非常に長いスラーに触れてから)モーツァルトやハイドンの音楽のスタイルはもっと・・・実用主義的で、とても短いスラーがついています。長くても1小節くらいで、それよりも短いものもあります。こういったことから、アーティキュレーションも知ることができますね。それと彼らは(どちらかというと)弦楽器音楽寄りの作曲家です。そして、ハイドンやモーツァルトを解釈する際、これらのスラーを理解することはとても重要です。例えばモーツァルトのスラーは常に一弓で弾くことが出来ますので、細かく変える必要はありません。昨今のバイオリニストは、大きくはっきりした音を求めて不必要なところで弾き直しているのをみかけますが・・・そういうことが作曲者の目的ではないのです。ですから個人的には、モーツァルトのスラーを勝手に切ってしまうのは犯罪だなと思っています。」
つまりシフさんによれば、少なくともモーツァルトさんの曲の中では、スラーを弓運びの指示でもあると解釈すべきで、より大きな音を求めて返してしまうのは間違い。ラヴェルさんの曲の中ではそこまではっきりしていなくて、フレーズをそのスラーに沿って作ればよく、弓の返しは自分で考える(と思う人もいるしそうでない人もいる?)
「正しい」「正しくない」というくくりをあえてするなら、作曲者の頭にあった意図というのがまずは正しいんだろうけど、それが時代背景などの手がかりによって明らかなのであればそれに従うとして(その裏付けがわかるというのが知識の力)、
それが明白でなければ、可能な中から何を選ぶかは自分のセンス??
さらに問題を複雑にしていることに、版の違いがある。スラーをガン見して一生懸命「譜読み」して弾いたつもりでいたらば、それが自筆譜とは違う、とかよくあることで、たとえば私が持ってる古い全音版のショパンノクターンのスラーなんてかなりテキトーなのだが、エキエル版ですら自筆譜(およびショパンの意図していたところ)とは異なるという主張もあったり…
(「クラシックの真実は大作曲家の「自筆譜」にあり!」)
いやいやいやいや、スラーひとつだってこりゃ一生私なんぞにはわからないね。
たかが譜読みされど譜読み、一生できるようにはならないような気がする。
だからといってピアノ弾かないというわけにもいかんので(←そりゃつまらない)、
近似的な理解に基づいて、ずびずばと思ったように進んでいくしかないよ。
近似的な理解というのは…
スラーがかかっていたら、それはアーティキュレーションまたはフレーズを示していて、
最初の音は強め、最後の音は軽く弾く。とりあえずそれだけ。
(タイは同じ記号に相乗りしてるけど意味は違う。誰だ、いっしょの記号にしちゃったやつ。責任者でてこい)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
ところが、「ベートーヴェンを"読む" 32のピアノソナタ」にはこうある:
「18世紀から19世紀初頭にかけてのスラーの基本原則は、とても単純なものだった。
1) スラーがかかっている最初の音は、わずかに強調される(ごく軽いアクセントを示すと考えてもよい)
2) スラーがかかっている最後の音は、強調されたり、アクセントが付けられたりせず、軽く演奏される。なお、最後の音は、常にではないものの、一般に記譜よりも若干短く演奏される。
このことを最初に言葉でしっかり見た(聞いた)のは「shig式譜読みメソッドテキスト(草稿)」の中だったのだが、ハッキリ言って「聞いてねっし!!」驚愕であった。
考えてみれば、子どものころから、まともな演奏を耳にする機会も多々あったわけで、そう弾かれていることがあると知らないわけではなかったけれど、それはみんな「なんとなく」「勝手に」(^^;; やってるもんだと思っていた。元々楽譜がそのように意図して書かれているなんて思ってもみなかった。
音符の長さにしても同じく、算数でいうように解釈していて、八分音符なら四分音符の半分、三連符なら三分の一であって、「三拍子系の中に付点パターンが出てきたら、作曲者の意図はもしかしたら2:1分割パターンなのかもしれない」(「shig式譜読みメソッドテキスト(草稿)」より)なんて言われたら、
うっそーん(o_o)
って感じ。
私は、ピアノも音楽も得意じゃないけど「譜読みは得意」と思っていたけどその譜読みは…!? 実は譜読みでないなにか
(ドはドでレはレで、1と2と3と4と…みたいな範囲で即物的に読むだけ)
だったんだなとか。
まぁ私はそんな感じだけど、音楽専門の人ならまるっと明確にわかってるかといえばそれはそう簡単に割り切れるものでもないらしく、
「小澤征爾さんと、音楽について話をする」にあった、音楽キャンプで子どもたちの弦楽四重奏の指導をしていたときの話。
ラヴェルのカルテットに長いスラーがあって、まぁ弦楽器やる人にとってはスラーって「ひと弓で弾け」って指示にとるけど、ひと弓で弾くには長くてたいへん。
そこで、ひとりの先生は
「スラーはフレーズのまとまりを示すものであって弓の運びの指示ではない。弓は返してもかまわない。弓の長さは決まっているんだから、無理したって意味ない」と指導し、
また別の先生は
「せっかく作曲家がそう書いているんだから、いちおうそういう弓の運びをしてごらんよ」と指導した。
この件について小澤さんは、
「両方正しいんです。それはね、学生が両方を試してみて、自分が正しいと思う方を選べばいいんです」
といっている。
この話を思い出したのは、シフさんのベトソナレクチャーでこんなくだりがあったから。
「(ベトソナにある非常に長いスラーに触れてから)モーツァルトやハイドンの音楽のスタイルはもっと・・・実用主義的で、とても短いスラーがついています。長くても1小節くらいで、それよりも短いものもあります。こういったことから、アーティキュレーションも知ることができますね。それと彼らは(どちらかというと)弦楽器音楽寄りの作曲家です。そして、ハイドンやモーツァルトを解釈する際、これらのスラーを理解することはとても重要です。例えばモーツァルトのスラーは常に一弓で弾くことが出来ますので、細かく変える必要はありません。昨今のバイオリニストは、大きくはっきりした音を求めて不必要なところで弾き直しているのをみかけますが・・・そういうことが作曲者の目的ではないのです。ですから個人的には、モーツァルトのスラーを勝手に切ってしまうのは犯罪だなと思っています。」
つまりシフさんによれば、少なくともモーツァルトさんの曲の中では、スラーを弓運びの指示でもあると解釈すべきで、より大きな音を求めて返してしまうのは間違い。ラヴェルさんの曲の中ではそこまではっきりしていなくて、フレーズをそのスラーに沿って作ればよく、弓の返しは自分で考える(と思う人もいるしそうでない人もいる?)
「正しい」「正しくない」というくくりをあえてするなら、作曲者の頭にあった意図というのがまずは正しいんだろうけど、それが時代背景などの手がかりによって明らかなのであればそれに従うとして(その裏付けがわかるというのが知識の力)、
それが明白でなければ、可能な中から何を選ぶかは自分のセンス??
さらに問題を複雑にしていることに、版の違いがある。スラーをガン見して一生懸命「譜読み」して弾いたつもりでいたらば、それが自筆譜とは違う、とかよくあることで、たとえば私が持ってる古い全音版のショパンノクターンのスラーなんてかなりテキトーなのだが、エキエル版ですら自筆譜(およびショパンの意図していたところ)とは異なるという主張もあったり…
(「クラシックの真実は大作曲家の「自筆譜」にあり!」)
いやいやいやいや、スラーひとつだってこりゃ一生私なんぞにはわからないね。
たかが譜読みされど譜読み、一生できるようにはならないような気がする。
だからといってピアノ弾かないというわけにもいかんので(←そりゃつまらない)、
近似的な理解に基づいて、ずびずばと思ったように進んでいくしかないよ。
近似的な理解というのは…
スラーがかかっていたら、それはアーティキュレーションまたはフレーズを示していて、
最初の音は強め、最後の音は軽く弾く。とりあえずそれだけ。
(タイは同じ記号に相乗りしてるけど意味は違う。誰だ、いっしょの記号にしちゃったやつ。責任者でてこい)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










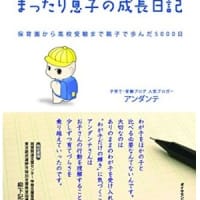










敢えて言おう。バッハだ(笑)
ところで弧線の役割についてつい先日私信の中で書いたものがあります。
埋もれさせとくのももったいないなと思ってたのでここに貼っつけときます。
--
いくつかの楽譜を観察して抽出されるのは、弧線にはいくつかの意味があるということです。すなわち、
1.弦楽器で演奏するときひと弓で弾くことを表すもの
2.フレーズを表すもの
3.意味上のまとまりを表すもの
おそらく1.の弧線が最初に現れたのでしょう。すなわち、アーティキュレーションを示す弧線です。
18世紀音楽に出てくる弧線はだいたいこのグループと見てよいです。
2.と3.の区別はやや曖昧ですが、ショパンに見られる長い弧線はひと息というよりなんらかの意味のまとまりと考えたほうが自然です。
で話が終わればよいのですが、ヴェルサイユ楽派の弧線にはイネガル奏法に対する特別な意味があります。
短い音にかかる弧線が対象なのですが、その「短い」の定義は拍子と関連しておりこれまたややこしい話になります。
4.2音にかかる弧線は、前の音を短く、後ろの音を長く弾くべきであることを表す場合がある
5.3音を超える弧線は、その中にある音符を均等に弾かなければならないことを表す場合がある
なんのこっちゃ?と思われるかもしれませんが、大切なことは「作曲者が弧線を書いたとき、それの意味するところには様々な可能性がある」ということです。
積極的に書かれた弧線は確実に何かを意味しているわけですが、4.とか5.とかの可能性も合わせるとその意味を読み解くのはそんなに易しいことではありません。
弧線解説貼っていただきありがとうございます。
ますますわからなくなったような気もするが…
クープランがせっかく書き分けてくれてたのに…(笑)
今から復活させるわけにもいかないので注釈でいいからタイって書いといてくれると助かるのにといつも思います。
そうね今から記号かえられないよね。紛らわしいときに注釈するだけでもないよりまし。