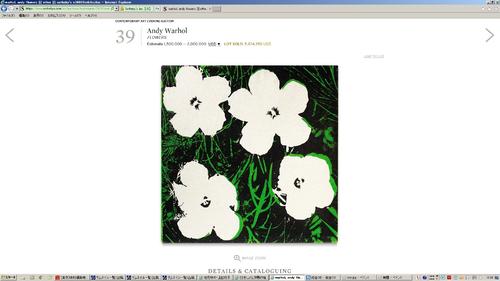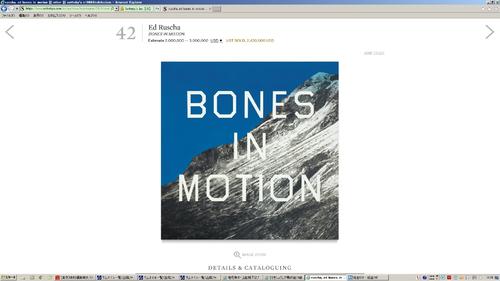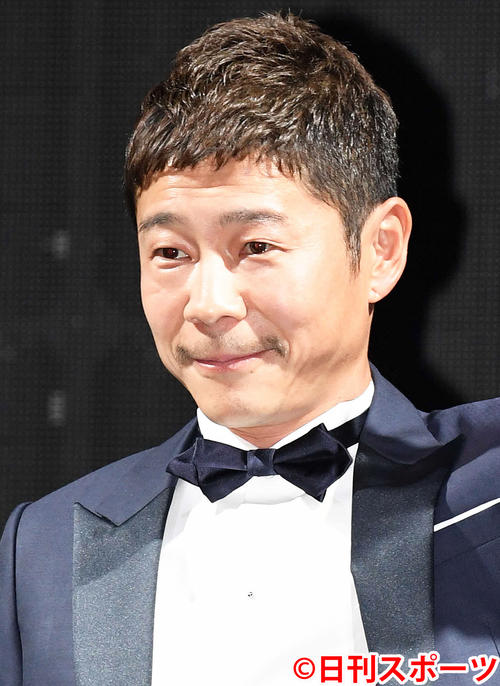【社説①】:シニアの雇用 活躍の場広げる知恵を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:シニアの雇用 活躍の場広げる知恵を
政府が、希望する高齢者の雇用を七十歳まで延ばす法改正の考え方を示した。多様な働き方を支えていく方向だが、実現には乗り越えるべき課題もある。活力あるシニアを増やす知恵を絞りたい。
最初に指摘しておきたい。
政府は、働くシニアを増やすことで、少子高齢化で伸び続ける社会保障費の抑制を狙う。だが、給付を充実させるための年金制度改革や、高齢化に対応した医療、介護の体制整備など政府がやるべき仕事はなくなるわけではない。手を抜かず取り組むべきだ。
ファストフード店やスーパーなどで働くシニアが増えた。人生経験を積んだ落ち着いた接客が利用者にも好評で、生き生きと働くシニアの姿は珍しくなくなった。
寿命は延びている。二〇一五年に六十五歳の男性の三人に一人、女性の五人に三人が九十歳まで生きるとの試算もある。働く意欲のある人も多い。働く環境の整備は進めねばならない。
現行法では、定年廃止や六十五歳までの定年延長や継続雇用制度のいずれかの導入を企業に義務付けている。今回の政府案は、さらに七十歳までの定年延長に加え他企業への再就職、起業やNPOなど社会貢献活動への資金提供を企業に求めるものだ。
現行でも企業は六十五歳までの雇用確保に苦労している。増やした選択肢はそれへの配慮だろう。
多様な選択肢は歓迎するが、実現へハードルがある。
働く側は定年後にスムーズに転職や起業ができるわけではない。それまでに専門性を身に付けたり、他業種を経験したり地域活動に取り組んだりと定年後へ、準備が要るだろう。
企業は社員を支援するため、働き方の選択肢を増やしたり、他の業種・職場を経験する兼業・副業の拡大、ボランティア休暇制度の充実など人材育成や人事制度にも発想の転換が求められる。
同時に、どの世代も待遇と意欲を下げないよう生産性の向上も迫られる。こうした努力は企業にも利益になるはずだ。
いずれ終身雇用や年功賃金などの雇用慣行のあり方まで及ぶ大きな課題にもなるのではないか。
もちろん働かない自由もある。政府は公的年金は希望すれば七十歳超の受給開始を選べる案を示したが、支給開始を原則六十五歳に据え置いたことは理解できる。
シニアは健康状態やライフスタイルが個々で違う。多様な生き方を支える社会にしたい。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2019年05月18日 06:10:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。