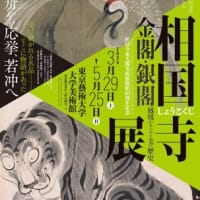なんやかんやで、平日休みの11/15金曜日。
上野の国立西洋美術館で、先月10/19より開催中の
『ハプスブルク展』に行って見ました。
平日なので、空いているかなぁと思ったのですが、
思ったよりは、空いていませんでした。
平日だと、おばちゃんとかが多いんですね。
展示されているのは、絵画だけじゃなくて、
ハプスブルク家にまつわる、様々な財宝、至宝。
鼈甲と銀で作られた《ハート形の容器》とかは、
興味深いですねぇ。
16世紀のものだそうなのですが、この時代から、
ハートの形って、何かの象徴なんですね?
絵画では、ポスターになっていたのは、
ディエゴ・ベラスケスの
《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》
なんですけど、これよりも興味を引いたのが、
マルティン・ファン・メイテンス(子)の
《皇妃マリア・テレジアの肖像》。
描かれているマリア・テレジアは、30歳ごろらしいのですが、
いま世の中に居る30歳の女性とは全く異なる
貫禄のある女性像が描かれています。
“貫禄がある”と言っても、太っているという意味ではなくて、
権力者の余裕と言うか、貫禄と言うか・・・。
この頃のハプスブルク家は、凄い権勢を誇っていましたからねぇ。
それを窺わせる作品でした。
ハプスブルク家の“クンストカンマー”の展示でした。
特別展のチケットで、常設展も見られるので、そちらも見てきました。
これは、忘れ去られていた、モネの《睡蓮、柳の反映》

1921年に、松方がモネから購入し、第二次世界大戦中に、
フランス北部の寒村に疎開したそうなのですが、
痛みも激しかったことから、忘れられていたそうなのですが、
2016年に、ルーヴル美術館で発券され、2017年に、松方家より、
国立西洋美術館に寄贈されたものだそうです。
その補修や、在りし日の姿の復元は、この展覧会の前に
開催されていた『松方コレクション展』で展示されていましたが、
こちらが、その実物。
いやぁ、在りし日の、実物を見たかったですねぇ。
版画素描展示室では、
『内藤コレクション展「ゴシック写本の小宇宙――文字に棲まう絵、言葉を超えてゆく絵」』

をやっていたので見てきました。
これを、つい最近まで、個人が集めていたんですね。
“好きこそものの上手なれ”と言う言葉がありますが、
正に、それを地で行っている感じです。
コレクションの多くは、13世紀ごろのものだったのですが、
800年くらい経過しているのに、印刷はくっきりとしていますし、
獣皮紙も、まだまだ白くて、しっかりしている感じでした。
国立西洋美術館は、国立の美術館なので、保存技術なども
しっかりしていると思いますが、個人で、こんなにちゃんと
保存できているって、なんかすごいですね。
常設展示室に戻って、
フランク・ブラングィンの《松方幸次郎の肖像》

この国立西洋美術館の大元となる
コレクションを築いた松方幸次郎を描いたものです。
松方さん、ありがとうございました。
上野の国立西洋美術館で、先月10/19より開催中の
『ハプスブルク展』に行って見ました。
平日なので、空いているかなぁと思ったのですが、
思ったよりは、空いていませんでした。
平日だと、おばちゃんとかが多いんですね。
展示されているのは、絵画だけじゃなくて、
ハプスブルク家にまつわる、様々な財宝、至宝。
鼈甲と銀で作られた《ハート形の容器》とかは、
興味深いですねぇ。
16世紀のものだそうなのですが、この時代から、
ハートの形って、何かの象徴なんですね?
絵画では、ポスターになっていたのは、
ディエゴ・ベラスケスの
《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》
なんですけど、これよりも興味を引いたのが、
マルティン・ファン・メイテンス(子)の
《皇妃マリア・テレジアの肖像》。
描かれているマリア・テレジアは、30歳ごろらしいのですが、
いま世の中に居る30歳の女性とは全く異なる
貫禄のある女性像が描かれています。
“貫禄がある”と言っても、太っているという意味ではなくて、
権力者の余裕と言うか、貫禄と言うか・・・。
この頃のハプスブルク家は、凄い権勢を誇っていましたからねぇ。
それを窺わせる作品でした。
ハプスブルク家の“クンストカンマー”の展示でした。
| 名称 | 日本・オーストリア友好150周年記念 ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史 https://habsburg2019.jp/ |
|---|---|
| 会期 | 2019年10月19日(土)~2020年1月26日(日) |
| 会場 | 国立西洋美術館 |
| 当日観覧料 | 一般1700円、大学生1100円、高校生600円、中学生以下無料 |
| 開館時間 | 09:30~17:30 ※毎週金・土曜日は21:00まで開館(ただし11月30日(土)は17:30まで) ※入館は、閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜日(ただし、11月4日(月・休)、1月13日(月・祝)は開館)、11月5日(火)、12月28日(土)~1月1日(水・祝)、1月14日(火) |
特別展のチケットで、常設展も見られるので、そちらも見てきました。
これは、忘れ去られていた、モネの《睡蓮、柳の反映》

1921年に、松方がモネから購入し、第二次世界大戦中に、
フランス北部の寒村に疎開したそうなのですが、
痛みも激しかったことから、忘れられていたそうなのですが、
2016年に、ルーヴル美術館で発券され、2017年に、松方家より、
国立西洋美術館に寄贈されたものだそうです。
その補修や、在りし日の姿の復元は、この展覧会の前に
開催されていた『松方コレクション展』で展示されていましたが、
こちらが、その実物。
いやぁ、在りし日の、実物を見たかったですねぇ。
版画素描展示室では、
『内藤コレクション展「ゴシック写本の小宇宙――文字に棲まう絵、言葉を超えてゆく絵」』

をやっていたので見てきました。
これを、つい最近まで、個人が集めていたんですね。
“好きこそものの上手なれ”と言う言葉がありますが、
正に、それを地で行っている感じです。
コレクションの多くは、13世紀ごろのものだったのですが、
800年くらい経過しているのに、印刷はくっきりとしていますし、
獣皮紙も、まだまだ白くて、しっかりしている感じでした。
国立西洋美術館は、国立の美術館なので、保存技術なども
しっかりしていると思いますが、個人で、こんなにちゃんと
保存できているって、なんかすごいですね。
常設展示室に戻って、
フランク・ブラングィンの《松方幸次郎の肖像》

この国立西洋美術館の大元となる
コレクションを築いた松方幸次郎を描いたものです。
松方さん、ありがとうございました。