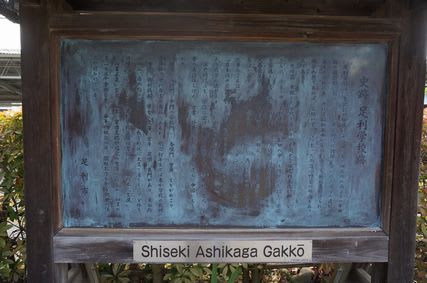先週金曜日の2016/05/13(13日の金曜日!!!)、
旧古河庭園で開催されている春のバラフェスティバルの
夜間ライトアップに行ってきました。
先週はね、色々と忙しかったので今週になって、
やっとUPです。
旧古河庭園に到着したのは、やっと暮れかかった頃。
当然、会社が終わってから行ったんですが、
ライトアップには調度良いくらいの時間でした。
それと、今回のライトアップは、バラの見頃の時期にピッタリ。
そう言う意味でも、調度良かったですね。
沢山写真を撮ったんですが、流石に全部UP出来ないので
(ならば、何故そんなに沢山写真を撮ったとも言いますが(笑))、
ごく一部、私の印象に残ったものを示します。
(UPの順序は、順不同です。)
まずは“バラといえば・・・”と言う事で、
世のプリンセスたちの名前がついた品種から。
バラと言えば、イギリス。
と言う事で、《ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ》

言わずと知れた、故ダイアナ妃に捧げられた品種です。
故ダイアナ妃に捧げられた品種は、他にもあって
《プリンセス・オブ・ウェールズ》

《ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ》は、
ピンク系ですが、こちらは可憐な白ですね。
説明プレートには「白に淡いピンクのグラデーション」と
ありますが・・・。
イギリス王室にちなんだ品種の次は、日本の皇室から。
まずは、美智子皇后に因んだ《プリンセス・ミチコ》

故ダイアナ妃に因んだ品種とは異なり、
こちらは、見事な朱色ですね。
(説明プレートには“蛍光色の様な濃いオレンジ”とありますが)
美智子皇后が来たならば、雅子妃。
《エグランタイン(マサコ)》

基本的には“エグランタイン”と呼ばれるようですが、
別名として、雅子妃の名前がついています。
そしてこちらは、《ロイヤル・プリンセス》

愛子さまに因んだ品種です。
人の名前が来たので、次は有名人。
《ローラ》

《ローラ》とは言っても、“あの”ローラじゃ無いんですけどね(苦笑)
在仏コロンビア大使夫人の名前に因んでいます。
《カトリーヌ・ドヌーヴ》

言わずと知れた、あの“カトリーヌ・ドヌーヴ”
そしてこちらは、《マリア・カラス》

《イングリット・バーグマン》

この中で、女優として好きなのはイングリット・バーグマンですね。
女性の最後としては、《クレオパトラ》

確かにクレオパトラっぽいかも??
女性がいれば、男性も居て《ヨハネ・パウロ2世》

イキナリの超大物です。
女性が《クレオパトラ》で終わったんで、
男性の最初は、超大物からです。
超大物の次は、歴史上の偉人しか無いかな。
《ミスターリンカーン》

そして、男性部門の最後は《クリスチアン・ディオール》

男性の俳優の名前の付いた品種って無いんですかね?
クラーク・ゲーブルとか、ジョン・ウェインとか。
まぁ、イメージもあるんで、男性の俳優の名前はつけにくいのかな。
ここからは、色で分類。
青いバラと言えば、サントリーの《アプローズ》が、
世界初の青いバラとして有名ですが、他にも有るんですね。
《わたらせ》

《青の軌跡》

“奇跡”じゃなくて、“軌跡”です。
《ブルー・ライト》

これらを作った方は、個人のバラ園芸家で、
特に《わたらせ》と《青の軌跡》は、同じ方が作られています。
サントリーと違って、遺伝子操作ではなくて、交配で作っている所が凄いですね。
青が来たので、赤いバラ。
《朱王》

もう、バラといえば、真っ赤なバラの一言(笑)。
《丹頂》

こちらも赤いです。
青、赤・・・、じゃあ、黄色?
と言う事で、《ローズ・ヨコハマ》

横浜のシンボルローズだそうです。
名前が付いているんじゃぁ、そりゃそうだよね
《インカ》

黄色が鮮やかですね。
この色合、結構好きです。
今度は、今年に因んだ?ものを。
《リオ・サンバ》です。

今年は、オリンピックイヤーですからね。
そして、オリンピックと言えば《ゴールデン・メダイヨン》

日本は、いつく金メダルを取れるのか?
バラでイメージするのは“恋”?
と言う事なので、《初恋》

初恋って、白なんでしょうかね(笑)?
そして《恋心》

“恋”は、ピンクかな(笑)
あとは、順不同で。
まずは、《デザートピース》

最近、世界中が危険ですから、リアルに平和を望みます。
《ニュー・アベマリア》

まぁ、祈りたくもなりますよねぇ(笑)
《ホワイト・クリスマス》

冬にバラは咲かないと思いますが、
これが冬のクリスマスの頃にあったら、
それはそれで、かなり良いかも。
《ライラック・ビューティー》

ライラックはライラックで、きちんと花が有るんですがね?
色のイメージが、ライラックに似ているという事でしょうか。
《サハラ》

一つ一つ独立しているバラも良いですが、
こう言う、密集した品種もなかなか良いですね。
色もグラデーションがかかっていて、キレイです。
《アンジェラ》

“アンジェラアキ”じゃ無いですよ(苦笑)
《アロマテラピー》

あぁ、いまの私に必要な物かも。
まぁそれはともかく(笑)、園内全般的に、
意外にバラの香りがしませんでしたね。
何でだろ?
「バラの香りを嗅ぎたい!」とか言っている人もいました。
少しだけ気持ちがわかります。
日本庭園の方も行ってみると、こんな感じ。

既に日が完全に落ちていて、暗かったので、
足元には厳重注意です。
滝の感じはこうです。

あとは、洋館とバラのコンビネーション



最後に、バラ園全景。

満開のバラ、良かったですよ!
おまけ
《ジャーマンアイリス》

バラじゃないんで、ライトアップされていませんでしたが、
こちらも見事に満開でした。
旧古河庭園で開催されている春のバラフェスティバルの
夜間ライトアップに行ってきました。
先週はね、色々と忙しかったので今週になって、
やっとUPです。
旧古河庭園に到着したのは、やっと暮れかかった頃。
当然、会社が終わってから行ったんですが、
ライトアップには調度良いくらいの時間でした。
それと、今回のライトアップは、バラの見頃の時期にピッタリ。
そう言う意味でも、調度良かったですね。
沢山写真を撮ったんですが、流石に全部UP出来ないので
(ならば、何故そんなに沢山写真を撮ったとも言いますが(笑))、
ごく一部、私の印象に残ったものを示します。
(UPの順序は、順不同です。)
まずは“バラといえば・・・”と言う事で、
世のプリンセスたちの名前がついた品種から。
バラと言えば、イギリス。
と言う事で、《ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ》

言わずと知れた、故ダイアナ妃に捧げられた品種です。
故ダイアナ妃に捧げられた品種は、他にもあって
《プリンセス・オブ・ウェールズ》

《ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ》は、
ピンク系ですが、こちらは可憐な白ですね。
説明プレートには「白に淡いピンクのグラデーション」と
ありますが・・・。
イギリス王室にちなんだ品種の次は、日本の皇室から。
まずは、美智子皇后に因んだ《プリンセス・ミチコ》

故ダイアナ妃に因んだ品種とは異なり、
こちらは、見事な朱色ですね。
(説明プレートには“蛍光色の様な濃いオレンジ”とありますが)
美智子皇后が来たならば、雅子妃。
《エグランタイン(マサコ)》

基本的には“エグランタイン”と呼ばれるようですが、
別名として、雅子妃の名前がついています。
そしてこちらは、《ロイヤル・プリンセス》

愛子さまに因んだ品種です。
人の名前が来たので、次は有名人。
《ローラ》

《ローラ》とは言っても、“あの”ローラじゃ無いんですけどね(苦笑)
在仏コロンビア大使夫人の名前に因んでいます。
《カトリーヌ・ドヌーヴ》

言わずと知れた、あの“カトリーヌ・ドヌーヴ”
そしてこちらは、《マリア・カラス》

《イングリット・バーグマン》

この中で、女優として好きなのはイングリット・バーグマンですね。
女性の最後としては、《クレオパトラ》

確かにクレオパトラっぽいかも??
女性がいれば、男性も居て《ヨハネ・パウロ2世》

イキナリの超大物です。
女性が《クレオパトラ》で終わったんで、
男性の最初は、超大物からです。
超大物の次は、歴史上の偉人しか無いかな。
《ミスターリンカーン》

そして、男性部門の最後は《クリスチアン・ディオール》

男性の俳優の名前の付いた品種って無いんですかね?
クラーク・ゲーブルとか、ジョン・ウェインとか。
まぁ、イメージもあるんで、男性の俳優の名前はつけにくいのかな。
ここからは、色で分類。
青いバラと言えば、サントリーの《アプローズ》が、
世界初の青いバラとして有名ですが、他にも有るんですね。
《わたらせ》

《青の軌跡》

“奇跡”じゃなくて、“軌跡”です。
《ブルー・ライト》

これらを作った方は、個人のバラ園芸家で、
特に《わたらせ》と《青の軌跡》は、同じ方が作られています。
サントリーと違って、遺伝子操作ではなくて、交配で作っている所が凄いですね。
青が来たので、赤いバラ。
《朱王》

もう、バラといえば、真っ赤なバラの一言(笑)。
《丹頂》

こちらも赤いです。
青、赤・・・、じゃあ、黄色?
と言う事で、《ローズ・ヨコハマ》

横浜のシンボルローズだそうです。
名前が付いているんじゃぁ、そりゃそうだよね
《インカ》

黄色が鮮やかですね。
この色合、結構好きです。
今度は、今年に因んだ?ものを。
《リオ・サンバ》です。

今年は、オリンピックイヤーですからね。
そして、オリンピックと言えば《ゴールデン・メダイヨン》

日本は、いつく金メダルを取れるのか?
バラでイメージするのは“恋”?
と言う事なので、《初恋》

初恋って、白なんでしょうかね(笑)?
そして《恋心》

“恋”は、ピンクかな(笑)
あとは、順不同で。
まずは、《デザートピース》

最近、世界中が危険ですから、リアルに平和を望みます。
《ニュー・アベマリア》

まぁ、祈りたくもなりますよねぇ(笑)
《ホワイト・クリスマス》

冬にバラは咲かないと思いますが、
これが冬のクリスマスの頃にあったら、
それはそれで、かなり良いかも。
《ライラック・ビューティー》

ライラックはライラックで、きちんと花が有るんですがね?
色のイメージが、ライラックに似ているという事でしょうか。
《サハラ》

一つ一つ独立しているバラも良いですが、
こう言う、密集した品種もなかなか良いですね。
色もグラデーションがかかっていて、キレイです。
《アンジェラ》

“アンジェラアキ”じゃ無いですよ(苦笑)
《アロマテラピー》

あぁ、いまの私に必要な物かも。
まぁそれはともかく(笑)、園内全般的に、
意外にバラの香りがしませんでしたね。
何でだろ?
「バラの香りを嗅ぎたい!」とか言っている人もいました。
少しだけ気持ちがわかります。
日本庭園の方も行ってみると、こんな感じ。

既に日が完全に落ちていて、暗かったので、
足元には厳重注意です。
滝の感じはこうです。

あとは、洋館とバラのコンビネーション



最後に、バラ園全景。

満開のバラ、良かったですよ!
おまけ
《ジャーマンアイリス》

バラじゃないんで、ライトアップされていませんでしたが、
こちらも見事に満開でした。