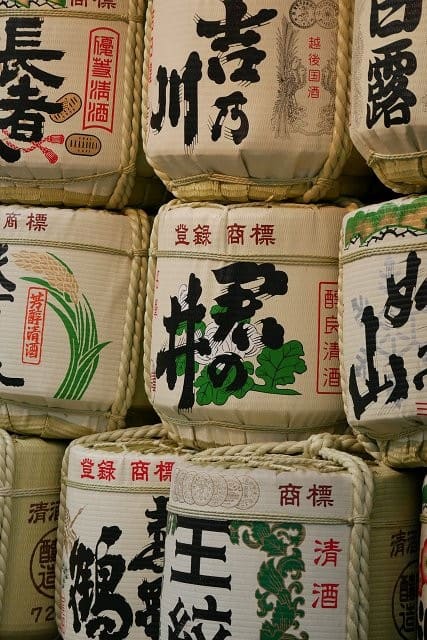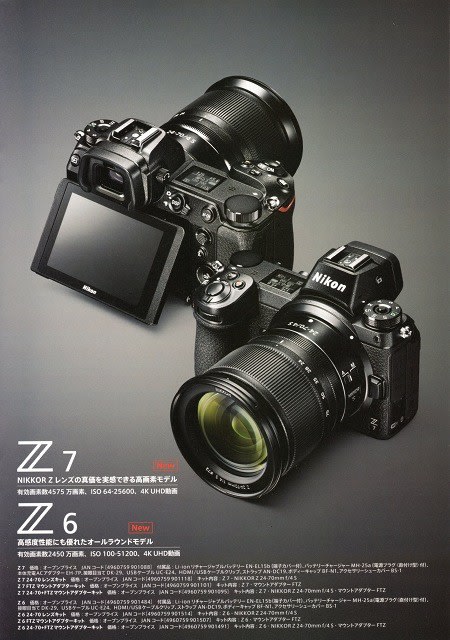衝動買いをしちゃいました。
買ったものは写っているレンズ(LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S.)です。
このレンズはマイクロフォーサーズ用のレンズで、35mm換算で200mm-800mmという超望遠レンズです。
フルサイズカメラで800mmレンズというとバズーカ砲ですが、マイクロフォーサーズだと本当にコンパクトです。
フルサイズカメラの70-300mmレンズと遜色ない大きさに感じました。
重さは1Kgを僅かに切ります、この手の超望遠レンズとしたら本当に軽量です。
愛機のLUMIX G7に装着した写真が下の2枚です。
上が100mm、下が400mmです、望遠側はビヨーンと伸びます。
見た目G7に装着した姿はバランスは悪く感じません、でもG7は筐体がプラスチック製で、レンズは筐体が金属なので、重量面はいささかアンバランスです。
G8とかG9に装着すれば、重量的なバランスは良いのかなと想像します。
このレンズ、フードがチンケです。
フードは内蔵タイプで、引き出して使用するのですが、レンズ面から5cmくらいしか引き出せないので、フードとしての機能は殆どないのではと感じました。
昔、ニコンの200mmF4というマニュアルフォーカスレンズを持っていましたが、それと全く同じ構造です。
一応、引き出したフードに被せるように装着するオプションフードが用意されています。オプションフードですが、単品で6-7千円もします、結構なお値段です。
私が買った中古は、オプションフードが付属していました、それも衝動買いの理由の一つです。
ただし、そのオプションフードも、作りはとても6-7千円の品物ではありません。
LEICA認定レンズですから、フードくらいはしっかりしたものをつけて欲しかったなと思います。
このレンズ、メーカー希望小売価格は230,000円(税抜)もします。
もちろん私のレンズは新品ではありません、キタムラのウェブで見つけて中古で購入したものです。
中古とはいえ、新品の半値よりは少し高めですから、私には高価なレンズです。
まあ、フルサイズカメラ用の800mmレンズと比較したら、桁が一つは違うのですが。