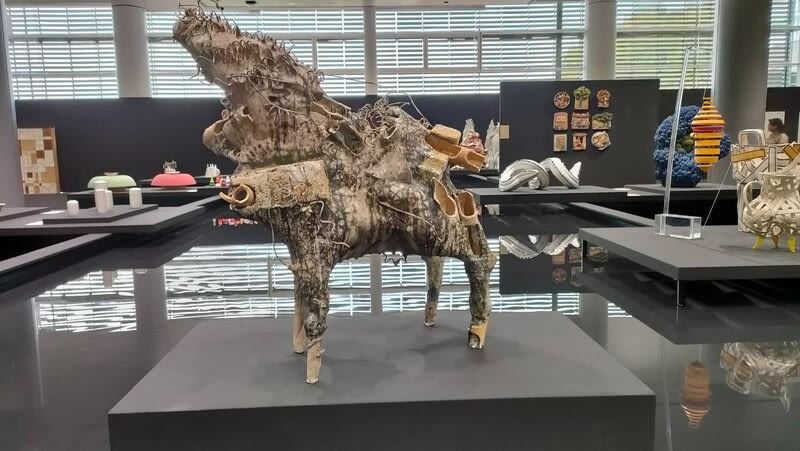工房には、便利な電気のスカット窯(アメリカ製)がある。
マイコン制御なので、スイッチ一つで酸化焼成なら焼き上がりまで何もしなくてよい(笑)。
しかし経年による傷みが激しくなり今回、大掛かりな修理となった。
写真は2021年暮れのころ。蓋の錆が少し気になる。

事の初めは、自分が工房不在の時に、仕事場と窯を友人に貸している。彼が焼成したときに温度が上がっていないようだと報告を受けたのが始まりである。
この窯の熱電対(温度を測る金属の棒)は、消耗品と以前代理店のヒューステンから聞いていたのでそろそろ寿命かと思い、取り寄せ交換した。
次に焼成したとき、エラーが出たので、『???』となり、ヒューステンに尋ねる。
担当者曰く、エレメント(電熱線)かリレー(温度調節をする部品)かもしれないと言うことで確認するとどうもリレーが調子悪くこれも交換。
図の下方にある四角い絵。通電したり切ったりを繰り返しながら徐々に温度を上げる働きをする。

3度目の正直で、素焼きは無事完了した。
素焼きの温度は、およそ800℃。粘土が植木鉢程度の硬さになる。余談だが、火葬場の温度もそれぐらい。😁
ところが、窯本体を覆っているステンレスのバンド(帯)が長年の焼成により錆びてボロボロである。
⁉ピンとが合っていない(笑)。

蓋のバンドは、2021年以降に交換したので比較的キレイ。
窯の下には、錆が粉になって落ちている。

本焼き焼成は1230℃にもなるので、窯内部が膨張する。それを抑えているバンドが外れると窯が崩壊して大火事になる。
現在、自分が陶芸活動を積極的にできない状況にある中で、どこまで費用をかけるか『う~ん』と悩む。
ここまでの部品交換で、すでに数万円掛かっている。

しかしこれからのことを考えると直さずには済まないだろう。
ちなみに新品を買うと60万円近くする。😅
仕方ない、今回のアルプス遠征にかける費用をすべてつぎ込む!
それで足りるかもビミョ~💦
取り寄せてみると、一部(2か所)がひしゃげた感じにめくれているではないか。
こう言うのってアメリカだなぁと思うところ。
交換してくれと言うのも時間かかるし面倒なのでハンマーで叩いて使えるようにする。これもピントが・・・

さて、まずはバンドをはず前にそこに付いているものを取り外さなければならない。
コントロールボックスをはずす。と言うか留め金具が壊れて取れてしまった。😓

エレメントとコントロールボックスに繋がる端子ケーブルほか。
音楽は音量大で仕事に励む(笑)。

記録用にと適当に撮ったので写真ブレたり、ピンと甘かったりで・・・😓
バンドをはずしたところ。

自分も初めて見るスカット窯バンドの内側。こんな感じか。🤔
錆がレンガについいている。

手前に飛び出ている電熱線が分かるだろうか、これがエレメントと呼ばれる電熱線である。
このエレメントの先端が、端子を外しているとき折れてしまったのである。
窯は高温になるので、癒着してしまっていたのだ。
折れた部分だけのエレメント交換しても焼成全体のバランスが悪い。
こうなったら、エレメント一式交換だ。諭吉さんが飛んでいく~😭😭😭
腹が決まったら行動は早い!
ここ数か月、連続してヒューステンから購入しているので少し割り引いてくれた。感謝。
それでも高額だけど・・・。
丁寧に古いエレメントを窯から抜き出す。レンガも脆くなっているので慎重に。
その後、レンガの粉塵や、ゴミを捕るために掃除機をかける。
そこまで作業が進んでから、ステンレスバンドを取り付ける。
途中の写真を撮り忘れたので、出来上がったもので。
苦労したのは、バンドが緩いと意味をなさないのできつく締めるとこ。
いったん締めた後、ガスバーナーでバンド全体をあぶって温めてさらにきつく締める。
バンドが付いたら、蓋止め金具や窯の上下をつなぐ金具を取り付けるためにステンレスバンドに穴を開ける。
ステンレスに穴を開けるビットは、力を入れすぎるともろいレンガまで行ってしまう。
その力加減が難しい。

ステンレスバンドと付属品を取り付けたら次はエレメントの取り付けである。
新品のエレメントの封を開ける。『ん?、何か変?』
一つだけ、使えない部品が入っている。やっぱりアメリカだ~。
さすがにこれは、連絡をして使えるモノを送ってもらう。

上から1段目に挿入。蟻の巣みたいでしょ(笑)。

レンガは耐火レンガ。このレンガは空気を多く含み熱効率を上げる。軽くていいのだが、その分もろい。
棚板など当てると欠けてしまう。経年劣化もありあちこちボロボロ。
順調に作業が進む。穴の置いているところは、熱電対の穴。付着しているカーボンをサンドペーパーで取る。
エレメントは焼成すると固くなり動かせない。また膨張するので窯内部に飛び出さないようにピンで要所々々を留める。

全てのエレメントを入れ終えたら、端子ケーブルをつないで元に戻していく。
コントロールボックスを留める金具もバンドに穴をあける。

蓋のバンドも少し傷んできたけど、まだ大丈夫。ただ、蓋を留める横の金具はそのうち交換だな。
多少のミスはあったが、一番のミスは、上から3つ目の色見穴にステンレスバンドが少し被ってしまったことだ。
穴をふさぐ白いプラグが入らない。仕方ないので少しずつステンレスを削って何とか収まるようにした。

全てが完了したら、空焚きである。エレメントに被膜を作るのである。
重要な工程だ。本来はそのまま空焚きなのだが、棚板を数枚補修したのでそれを入れて焼成した。
これですべて完了だ!
その後、友人が本焼きを試みた。
3つ目のプラグがまだ少し浮いているな。あと気になるのが蓋の隙間。こんなにも膨張したっけ⁉
ちょっと気になるので、対策を考えよう。これが蓋のバンドが痛む大きな要因である。

焼成はしっかり温度が上がったようだ。
エレメントが新品になったので今までより釉薬がやや溶け過ぎになったほど。
ここまでにかかった費用はおよそ17万円!!
アルプス山行どころではなく、削りに削ってかき集めた。
窯にかかった費用は、窯で稼ごう。
やる気が出てきた。山に行きたいけど、その費用も稼ぐぞ!😆
作品を紹介できるようにしたい。
まずは固まった粘土の土練りからだな。先は遠いけど一歩ずつ一歩ずつ。
がんば!自分。
追記
だいぶ以前、マイコンの基盤がダメになったことがある。基盤は高値である。😭
この窯にいくら掛かってんだか・・・💦
💖