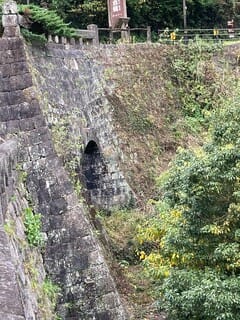通潤橋の放水(この写真も以前に撮影したもの)

通潤橋を下から見上げると↑です。
五老ヶ滝川の水面から橋の上までの高さは約20.2m
上の方(吹上口の方)から橋を見おろすと↓

3本の通水管があります。

このような通水管を漆喰で繋いで
水路としています。
1本が何らかの不都合で使用できなくなった時のために
3本(写真で分かりますね)になっているそうです。
写真奥が取入口の方で
手前が吹上口。
水路の長さ約123.9m
橋の長さ約76.0m
取入口と吹上口の高低差約1.1m
石造アーチ架橋サイフォン式という
サイフォンの原理を利用して、高いほうへ水が吹上げられます。

こちら(吹上口)側に白糸台地があり、給水されます。

通水管をつなぐ漆喰を作っていた小屋(写真左上)があり
当時の道具が雑然と保管されていました。
取入口にいたるまでの水の取水は笹原川上流。


このような水路が円形分水盤まで続きます。
(↓は、笹原川の堰)

水路を通って来た水はここで葉っぱなど除外されて
分水盤へ

分水盤と銀杏落葉

ここで、2か所に分けられる。

通潤橋から約6キロの地点にあります。
水路の総延長は、約30Km
(このブログで用いた数字は全て、
頂いた資料に拠ります)
その1で書きましたが、
こういうインフラは
手永会所(今の市役所や役場のようなもの)に
蓄えられた会所銭で賄われたということでした。
この会所の統括は惣庄屋で、
藩からの命令で赴任、転勤もあり、
地方公務員みたいなものでしたが
半官半民だったということです。
さらに、
この会所は警察の役目も果たし、
留置所に相当する施設もあったそうです。
白糸台地に水を送るために尽力した
惣庄屋・布田保之助が祀られていました。
布田神社↓

今回は、
通潤橋の水路の仕組みや手永制度について
学びが沢山あり、
今までの謎が解けた感じで、スッキリ~