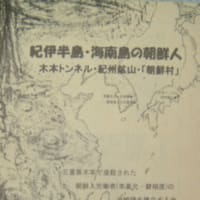三、日本の高校日本史教科書における朝鮮古代史叙述
現在、日本の高等学校日本史教科書は、AとBの2種あり、
Aの記述はほとんど近現代史に限られている。したがって、
ここでは2007年3月22日に日本文部科学省が検定を通過さ
せた日本の高等学校日本史教科書のうちBについてのみ論
じる。Bにおいても三国時代以前の朝鮮(扶余、東扶余な
ど)にかんする記述はまったくない。
■『新日本史』B改定版(著者、久留島典子ほか3人)、山川出版社。
本書の年表には、「391年 倭軍、百済・新羅を破る」と書かれているが(397頁)、本文にはこのことに関する記述はない。
同書には、古朝鮮にかんする記述はまったくなく、4世紀以後の朝鮮史にかんしては、つぎのように書かれている。
「朝鮮半島の3国のうち、北にあった強国の高句麗は、313
年に晋の朝鮮半島支配の拠点である楽浪郡と帯方郡を滅ぼ
し、さらに旧楽浪郡の平壌を拠点として南下策をとり始めた。
一方、朝鮮半島南部では、4世紀前半に馬韓から百済が、辰韓
から新羅が建国し、百済は高句麗の南下を受けて、倭に近づい
て同盟を結んだ」(29~30頁)、
「倭は、4世紀には朝鮮半島南部の弁韓地域にあった伽耶諸
国(加羅)と密接な関係を持ち、鉄資源を確保した。そこは生
産技術を輸入する半島の拠点であり、倭人も集団的に移住し
ていたらしい」(30頁)、
「高句麗は、4世紀後半に南下を続け、広開土王の一代の功
業を記した広開土王碑(広太王碑、中国吉林省集安市)には、
高句麗が倭に通じた百済を討ち、倭に侵入を受けた新羅を救
い、400年、404年に倭軍と交戦して勝利を得たことが記され
ている。鉄や文物の供与を受けていた倭は、伽耶や百済の要
請で派兵し、軍事援助をしたらしい」(30頁)、
「朝鮮半島では、6世紀に入ると、百済・新羅とも勢力を強め
たが、百済は強国高句麗の南下を受けて南遷し、512年、ヤマ
ト政権は朝鮮半島南部の伽耶諸国のうち、西部の4つの国
(「任那四県」と称した)を百済が支配することを承認した。さ
らに新羅も強大化し、562年までに伽耶諸国は百済と新羅の
支配下にはいって滅亡し、ヤマト政権も半島における拠点を
失った。
伽耶西部に対する支配の承認と引きかえに、百済から513年
に五経博士が渡来し、さらに易博士・歴博士・医博士も渡来
し、儒教やその他の学術が伝えられた。また、538年(一説に
552年)に、百済聖明王から仏教も伝えられた」(33頁)。
この教科書の筆者は、「らしい」というあいまいな表現をくりかえして、いいかげんな史実記述をしているだけでなく、民衆が歴史を動かすという歴史観と対立する歴史観によって書かれている。この教科書に従って授業がなされるならば、生徒は、いつわりの歴史を宣伝されるだけでなく、権力者が歴史を動かすというあやまった歴史観をおしつけられてしまう。
■『高校日本史』B改定版(著者、石井進ほか12人)、山川出版社。
本書は、『新日本史』Bと同じ出版社からだされている教科書だが、『新日本史』Bの記述のように悪質ではない。
『高校日本史』Bの年表には、『新日本史』Bにあるような「391年 倭軍、百済・新羅を破る」という史実と異なる記述はなく、4世紀の部分には、「このころヤマト政権、統一進む」と書かれている。
朝鮮古代史にかんして、同書には、つぎのように書かれている。
「中国東北地方から朝鮮半島北部に国家をつくった高句麗
の王、広開土王の碑には、倭の兵が辛卯の年(391年)以降、
朝鮮半島にわたり、高句麗軍とたたかったことが刻まれてい
る」(20頁)。
「4世紀の朝鮮半島 半島南部の加耶は加羅とも表記され、
それ以前に弁韓よばれていた国ぐにを総称したものである。
一方馬韓の国ぐにから百済が建国されたが、半島南西部は
百済に属するの加耶に属するのかまだよくわかっていない」
(21頁)。
「ヤマト政権はあたらしい文化や鉄資源を求めてはやくから
朝鮮半島南部と深いつながりを持っていたが、4世紀後半に北
方の高句麗が南へ進出してきたため、百済などとともに高句麗
とたたかうことになったのである」(20頁)。
「6世紀をむかえると、朝鮮半島では高句麗がいちだんと
勢力を強めて南下した。これにおされた百済・新羅は、国
内の支配体制をかためるとともに、ヤマト政権とも結びつ
きの強い加耶諸国へ進出するようになった」(26頁)。
「6世紀前半の朝鮮半島 高句麗の南下と新羅の西進を受
けて、百済は南に勢力を広げ、加耶西部を支配におさめた」
(26頁)。
「562年、新羅はついに加耶諸国を支配下におさめ、ヤマト
政権は朝鮮半島への足がかりを失ったのである」(27頁)。
「〔倭(日本)は〕国内では豪族の力がまだ強かった。国外
では唐と結んだ新羅にほろぼされた百済をたすけるために軍を
おくったが、663年の白村江の戦いで唐・新羅軍に大敗し、半
島からしりぞくことになった」(31頁)。
「907年、唐がほろぶと東アジアは大変動期に入り、渤海も
ほろび、朝鮮半島では高麗がおこり新羅がほろんだ」(54頁)。
■『日本史』B改定版(著者、脇田修ほか14人)、実教出版社。
本書では、年表の4世紀の部分に、「このころ大和政権の形成すすむ 4世紀末ごろ、倭軍朝鮮半島に侵出。百済とむすび、新羅・高句麗とたたかう」と書かれており、6世紀の部分に「562 新羅、加羅を滅ぼす」と書かれている。
本文には、
「6世紀には朝鮮との交流がいっそう密接になり、中国の
宗教や学問も流入・受容された。百済から五経博士や易・
歴・医の諸博士が渡来して、儒教その他の知識を伝えた」
(52~53頁)
と書かれている。
■『高校日本史』B新訂版(著者、宮原武夫ほか15人)、実教出版。
本書の年表には、「4世紀末ごろ、倭軍朝鮮半島に侵出。百済とむすび、新羅・高句麗とたたかう」と書かれている。
本文には、つぎのように書かれている。
「奴国王・邪馬台国王・倭の五王、高句麗・百済・新羅の
国王は、いずれも冊封体制のなかで、その地位を中国皇帝か
ら公認されていた」(22頁)、
「中国の朝鮮半島に対する支配力が衰えると、中国東北部
に本拠地をもつ高句麗が、中国が設置した楽浪郡、帯方郡を
滅ぼして朝鮮半島北部に勢力をのばし、南下政策をすすめ
た。南部には馬韓・辰韓・弁韓の3つの小国による連合が
形成っされていたが、4世紀には馬韓から百済が、辰韓から
は新羅がうまれた。朝鮮のすぐれた生産技術や鉄資源を求め
た大和政権は、弁韓の地域に成立した加羅諸国(伽耶、任那)
に4世紀後半、百済とむすんで出兵した。さあらに新羅を圧
迫し、北方の高句麗とたたかった。これに対して高句麗は、
新羅を救援し、百済を攻めて、倭の軍隊とたたかった。この
間の事情は高句麗の好太王の碑文に記されている。
5世紀にはいり、百済・新羅の国力が充実してくると、朝
鮮半島における大和政権の勢力はしだいに弱まった」(23頁)。
本書には、「歴史のまど 三韓の調」と題して、つぎのような根拠の不確かな、わけのわからないことが書かれている。
「645年(大化元)年6月12日、中大兄皇子と中臣鎌足
(のちの藤原鎌足)らは、飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿を殺し、
大化の改新がはじまった。なぜこの日が暗殺に選ばれたの
だろうか。それは、この日に三韓の使者が調を献上するこ
とになっていたからであった。三韓とは高句麗・百済・新
羅の3国のことで、調とは服属を表す献上品を意味する。
つまり、朝鮮3国が大和政権に服属していることを確認する
重要な儀式の日にあたったため、天皇(大王)をはじめ群
臣は必ず出席しなければならなかったのである。
しかし、実際には、3国とも倭国に統合されておらず、
使者を送る義務はなかった」(30頁)。
ここで、筆者は、「服属」と「統合」を同義語として使い、「朝鮮3国が大和政権に服属していることを確認する重要な儀式の日にあたったため」などという虚偽を書いている。このような記述は、ほかの教科書にはない。
■『日本史』B改定版(著者、青木美智男ほか12人)、三省堂。
本書には、つぎのように書かれている。
「313年、中国東北地方から朝鮮半島北部へ勢力を広
げていた高句麗が中国の直轄地である楽浪郡を滅ぼした。
馬韓・辰韓・弁韓という三つの小国連合体が分立してい
た半島南部では、4世紀なかごろ、馬韓と辰韓はそれぞれ
百済・新羅に統一され、南端の弁韓はいぜん伽耶(加羅)
とよばれる小国家連合体がつづいていた。4世紀後半には
高句麗が南下して百済や伽耶との間で対立を深めた。中
国の直接支配からはなれて戦乱をくりかえす朝鮮半島の
動きは、伽耶や百済を足がかりにして、鉄などの資源や
農業・土木・建築、各手工業の技術を手に入れようとす
るヤマト王権(倭)にとって大きなできごとであった」
(19頁)。
「朝鮮半島では、5世紀後半から6世紀にかけて、新羅
や高句麗が領土拡大につとめ、百済や伽耶に侵入しはじ
めた。
527年、ヤマト王権はつながりの深かった伽耶へ援軍
を派遣しようとしたが、新羅とむすんだとされる筑紫の
国造磐井によってこれをはばまれた(磐井の乱)。さら
に、外交を担当していた大連の大伴金村が百済に伽耶の
領土への拡大をみとめたこともあって、新羅と百済の伽
耶への侵入は強まり、562年、伽耶は新羅に滅ぼされた」
(24頁)。
「朝鮮半島では、高句麗や新羅が唐の律令を摂取して、
国力の充実につとめたが。唐が高句麗に遠征すると、新
羅は唐に急接近し、百済は倭とのつながりを深めようと
した」(28頁)。
「7世紀前半、朝鮮半島では新羅が勢力を増し、660
年、百済を滅亡させた。孝徳天皇にかわった斉明天皇
のころ、朝廷は復興をはかる百済の遺臣の要請にこた
えて大軍を派遣したが、663年、朝鮮半島南部の白村江
で新羅・唐の連合軍に大敗した(白村江の戦い)。さ
らに新羅は高句麗も滅ぼし、676年に朝鮮半島を統一し
た」(29頁~30頁)。
■『日本史』B改定版(著者、加藤友康ほか10人)、清水書院。
本書には、つぎのように書かれている。
「朝鮮半島北部には、中国東北部からおこった高句麗が
侵入し、313年、楽浪郡を滅ぼし、強力な統治機構を形成
した。南部においてもそれまで韓族が馬韓・辰韓・弁韓
(弁辰)などの部族的小国を形成していたが、馬韓地方
では百済、辰韓地方では新羅が国家形成へと向かいはじ
めた」(26頁)。
「4世紀後半から5世紀にかけて、朝鮮半島では、高句
麗・百済・新羅の3国が対立抗争をくり返した。とくに
高句麗の勢力は強大でたびたび南下し、百済と新羅は滅
亡の危機を迎えている。そこで新羅は高句麗の支配下に
はいり、百済は倭国と同盟関係を結んで、これに対抗し
た。……4世紀末に倭国は百済の求めに応じて、海を渡
って高句麗と戦っている。倭国と百済の交流は、ヤマト
政権に先進的な文化や知識をもたらした。これによりヤ
マト政権は外交権や先進技術を独占することになり、倭
国内におけるより優位な立場を得ることになった」(27
頁)。
「朝鮮半島では、中国王朝の影響力の低下もあって、
高句麗・百済・新羅の抗争がいっそうはげしくなった。
高句麗の軍事的圧迫に苦しむ百済と新羅は、倭国と友好
関係にあった伽耶諸国に進出し、560年代にこれら諸国
を併合した」(31頁)。
現在、日本の高等学校日本史教科書は、AとBの2種あり、
Aの記述はほとんど近現代史に限られている。したがって、
ここでは2007年3月22日に日本文部科学省が検定を通過さ
せた日本の高等学校日本史教科書のうちBについてのみ論
じる。Bにおいても三国時代以前の朝鮮(扶余、東扶余な
ど)にかんする記述はまったくない。
■『新日本史』B改定版(著者、久留島典子ほか3人)、山川出版社。
本書の年表には、「391年 倭軍、百済・新羅を破る」と書かれているが(397頁)、本文にはこのことに関する記述はない。
同書には、古朝鮮にかんする記述はまったくなく、4世紀以後の朝鮮史にかんしては、つぎのように書かれている。
「朝鮮半島の3国のうち、北にあった強国の高句麗は、313
年に晋の朝鮮半島支配の拠点である楽浪郡と帯方郡を滅ぼ
し、さらに旧楽浪郡の平壌を拠点として南下策をとり始めた。
一方、朝鮮半島南部では、4世紀前半に馬韓から百済が、辰韓
から新羅が建国し、百済は高句麗の南下を受けて、倭に近づい
て同盟を結んだ」(29~30頁)、
「倭は、4世紀には朝鮮半島南部の弁韓地域にあった伽耶諸
国(加羅)と密接な関係を持ち、鉄資源を確保した。そこは生
産技術を輸入する半島の拠点であり、倭人も集団的に移住し
ていたらしい」(30頁)、
「高句麗は、4世紀後半に南下を続け、広開土王の一代の功
業を記した広開土王碑(広太王碑、中国吉林省集安市)には、
高句麗が倭に通じた百済を討ち、倭に侵入を受けた新羅を救
い、400年、404年に倭軍と交戦して勝利を得たことが記され
ている。鉄や文物の供与を受けていた倭は、伽耶や百済の要
請で派兵し、軍事援助をしたらしい」(30頁)、
「朝鮮半島では、6世紀に入ると、百済・新羅とも勢力を強め
たが、百済は強国高句麗の南下を受けて南遷し、512年、ヤマ
ト政権は朝鮮半島南部の伽耶諸国のうち、西部の4つの国
(「任那四県」と称した)を百済が支配することを承認した。さ
らに新羅も強大化し、562年までに伽耶諸国は百済と新羅の
支配下にはいって滅亡し、ヤマト政権も半島における拠点を
失った。
伽耶西部に対する支配の承認と引きかえに、百済から513年
に五経博士が渡来し、さらに易博士・歴博士・医博士も渡来
し、儒教やその他の学術が伝えられた。また、538年(一説に
552年)に、百済聖明王から仏教も伝えられた」(33頁)。
この教科書の筆者は、「らしい」というあいまいな表現をくりかえして、いいかげんな史実記述をしているだけでなく、民衆が歴史を動かすという歴史観と対立する歴史観によって書かれている。この教科書に従って授業がなされるならば、生徒は、いつわりの歴史を宣伝されるだけでなく、権力者が歴史を動かすというあやまった歴史観をおしつけられてしまう。
■『高校日本史』B改定版(著者、石井進ほか12人)、山川出版社。
本書は、『新日本史』Bと同じ出版社からだされている教科書だが、『新日本史』Bの記述のように悪質ではない。
『高校日本史』Bの年表には、『新日本史』Bにあるような「391年 倭軍、百済・新羅を破る」という史実と異なる記述はなく、4世紀の部分には、「このころヤマト政権、統一進む」と書かれている。
朝鮮古代史にかんして、同書には、つぎのように書かれている。
「中国東北地方から朝鮮半島北部に国家をつくった高句麗
の王、広開土王の碑には、倭の兵が辛卯の年(391年)以降、
朝鮮半島にわたり、高句麗軍とたたかったことが刻まれてい
る」(20頁)。
「4世紀の朝鮮半島 半島南部の加耶は加羅とも表記され、
それ以前に弁韓よばれていた国ぐにを総称したものである。
一方馬韓の国ぐにから百済が建国されたが、半島南西部は
百済に属するの加耶に属するのかまだよくわかっていない」
(21頁)。
「ヤマト政権はあたらしい文化や鉄資源を求めてはやくから
朝鮮半島南部と深いつながりを持っていたが、4世紀後半に北
方の高句麗が南へ進出してきたため、百済などとともに高句麗
とたたかうことになったのである」(20頁)。
「6世紀をむかえると、朝鮮半島では高句麗がいちだんと
勢力を強めて南下した。これにおされた百済・新羅は、国
内の支配体制をかためるとともに、ヤマト政権とも結びつ
きの強い加耶諸国へ進出するようになった」(26頁)。
「6世紀前半の朝鮮半島 高句麗の南下と新羅の西進を受
けて、百済は南に勢力を広げ、加耶西部を支配におさめた」
(26頁)。
「562年、新羅はついに加耶諸国を支配下におさめ、ヤマト
政権は朝鮮半島への足がかりを失ったのである」(27頁)。
「〔倭(日本)は〕国内では豪族の力がまだ強かった。国外
では唐と結んだ新羅にほろぼされた百済をたすけるために軍を
おくったが、663年の白村江の戦いで唐・新羅軍に大敗し、半
島からしりぞくことになった」(31頁)。
「907年、唐がほろぶと東アジアは大変動期に入り、渤海も
ほろび、朝鮮半島では高麗がおこり新羅がほろんだ」(54頁)。
■『日本史』B改定版(著者、脇田修ほか14人)、実教出版社。
本書では、年表の4世紀の部分に、「このころ大和政権の形成すすむ 4世紀末ごろ、倭軍朝鮮半島に侵出。百済とむすび、新羅・高句麗とたたかう」と書かれており、6世紀の部分に「562 新羅、加羅を滅ぼす」と書かれている。
本文には、
「6世紀には朝鮮との交流がいっそう密接になり、中国の
宗教や学問も流入・受容された。百済から五経博士や易・
歴・医の諸博士が渡来して、儒教その他の知識を伝えた」
(52~53頁)
と書かれている。
■『高校日本史』B新訂版(著者、宮原武夫ほか15人)、実教出版。
本書の年表には、「4世紀末ごろ、倭軍朝鮮半島に侵出。百済とむすび、新羅・高句麗とたたかう」と書かれている。
本文には、つぎのように書かれている。
「奴国王・邪馬台国王・倭の五王、高句麗・百済・新羅の
国王は、いずれも冊封体制のなかで、その地位を中国皇帝か
ら公認されていた」(22頁)、
「中国の朝鮮半島に対する支配力が衰えると、中国東北部
に本拠地をもつ高句麗が、中国が設置した楽浪郡、帯方郡を
滅ぼして朝鮮半島北部に勢力をのばし、南下政策をすすめ
た。南部には馬韓・辰韓・弁韓の3つの小国による連合が
形成っされていたが、4世紀には馬韓から百済が、辰韓から
は新羅がうまれた。朝鮮のすぐれた生産技術や鉄資源を求め
た大和政権は、弁韓の地域に成立した加羅諸国(伽耶、任那)
に4世紀後半、百済とむすんで出兵した。さあらに新羅を圧
迫し、北方の高句麗とたたかった。これに対して高句麗は、
新羅を救援し、百済を攻めて、倭の軍隊とたたかった。この
間の事情は高句麗の好太王の碑文に記されている。
5世紀にはいり、百済・新羅の国力が充実してくると、朝
鮮半島における大和政権の勢力はしだいに弱まった」(23頁)。
本書には、「歴史のまど 三韓の調」と題して、つぎのような根拠の不確かな、わけのわからないことが書かれている。
「645年(大化元)年6月12日、中大兄皇子と中臣鎌足
(のちの藤原鎌足)らは、飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿を殺し、
大化の改新がはじまった。なぜこの日が暗殺に選ばれたの
だろうか。それは、この日に三韓の使者が調を献上するこ
とになっていたからであった。三韓とは高句麗・百済・新
羅の3国のことで、調とは服属を表す献上品を意味する。
つまり、朝鮮3国が大和政権に服属していることを確認する
重要な儀式の日にあたったため、天皇(大王)をはじめ群
臣は必ず出席しなければならなかったのである。
しかし、実際には、3国とも倭国に統合されておらず、
使者を送る義務はなかった」(30頁)。
ここで、筆者は、「服属」と「統合」を同義語として使い、「朝鮮3国が大和政権に服属していることを確認する重要な儀式の日にあたったため」などという虚偽を書いている。このような記述は、ほかの教科書にはない。
■『日本史』B改定版(著者、青木美智男ほか12人)、三省堂。
本書には、つぎのように書かれている。
「313年、中国東北地方から朝鮮半島北部へ勢力を広
げていた高句麗が中国の直轄地である楽浪郡を滅ぼした。
馬韓・辰韓・弁韓という三つの小国連合体が分立してい
た半島南部では、4世紀なかごろ、馬韓と辰韓はそれぞれ
百済・新羅に統一され、南端の弁韓はいぜん伽耶(加羅)
とよばれる小国家連合体がつづいていた。4世紀後半には
高句麗が南下して百済や伽耶との間で対立を深めた。中
国の直接支配からはなれて戦乱をくりかえす朝鮮半島の
動きは、伽耶や百済を足がかりにして、鉄などの資源や
農業・土木・建築、各手工業の技術を手に入れようとす
るヤマト王権(倭)にとって大きなできごとであった」
(19頁)。
「朝鮮半島では、5世紀後半から6世紀にかけて、新羅
や高句麗が領土拡大につとめ、百済や伽耶に侵入しはじ
めた。
527年、ヤマト王権はつながりの深かった伽耶へ援軍
を派遣しようとしたが、新羅とむすんだとされる筑紫の
国造磐井によってこれをはばまれた(磐井の乱)。さら
に、外交を担当していた大連の大伴金村が百済に伽耶の
領土への拡大をみとめたこともあって、新羅と百済の伽
耶への侵入は強まり、562年、伽耶は新羅に滅ぼされた」
(24頁)。
「朝鮮半島では、高句麗や新羅が唐の律令を摂取して、
国力の充実につとめたが。唐が高句麗に遠征すると、新
羅は唐に急接近し、百済は倭とのつながりを深めようと
した」(28頁)。
「7世紀前半、朝鮮半島では新羅が勢力を増し、660
年、百済を滅亡させた。孝徳天皇にかわった斉明天皇
のころ、朝廷は復興をはかる百済の遺臣の要請にこた
えて大軍を派遣したが、663年、朝鮮半島南部の白村江
で新羅・唐の連合軍に大敗した(白村江の戦い)。さ
らに新羅は高句麗も滅ぼし、676年に朝鮮半島を統一し
た」(29頁~30頁)。
■『日本史』B改定版(著者、加藤友康ほか10人)、清水書院。
本書には、つぎのように書かれている。
「朝鮮半島北部には、中国東北部からおこった高句麗が
侵入し、313年、楽浪郡を滅ぼし、強力な統治機構を形成
した。南部においてもそれまで韓族が馬韓・辰韓・弁韓
(弁辰)などの部族的小国を形成していたが、馬韓地方
では百済、辰韓地方では新羅が国家形成へと向かいはじ
めた」(26頁)。
「4世紀後半から5世紀にかけて、朝鮮半島では、高句
麗・百済・新羅の3国が対立抗争をくり返した。とくに
高句麗の勢力は強大でたびたび南下し、百済と新羅は滅
亡の危機を迎えている。そこで新羅は高句麗の支配下に
はいり、百済は倭国と同盟関係を結んで、これに対抗し
た。……4世紀末に倭国は百済の求めに応じて、海を渡
って高句麗と戦っている。倭国と百済の交流は、ヤマト
政権に先進的な文化や知識をもたらした。これによりヤ
マト政権は外交権や先進技術を独占することになり、倭
国内におけるより優位な立場を得ることになった」(27
頁)。
「朝鮮半島では、中国王朝の影響力の低下もあって、
高句麗・百済・新羅の抗争がいっそうはげしくなった。
高句麗の軍事的圧迫に苦しむ百済と新羅は、倭国と友好
関係にあった伽耶諸国に進出し、560年代にこれら諸国
を併合した」(31頁)。