 |
冗談 (Lettres) |
| ミラン クンデラ | |
| みすず書房 |
作者の写真、ものすごい気難しそうで、小難しい小説なのかとちょっと怯みましたが、バックカバーの、”20世紀小説の傑作”という言葉と、物語の前に挿入されている、まえがきで、本書はラブストーリーなんだという著者自身の言葉に魅かれて、とりあえず図書館なので、読めなくてもいいかと借りてみました。
結果、ほんと読んでよかった。
実は私、全くミランクンデラのことを知らなかったのです。読み終わって、ネットで検索してはじめて、『存在の耐えられない軽さも』の作者だということを知ったくらい。(といって、『存在の耐えられない軽さも』読んでないんですけどね)
主人公のルドヴィークは、大学時代に、ガールフレンドに宛てた手紙に書いた軽はずみな言葉により、党から追放され、この国での出世の道はとざされるが、軍隊生活などを経て、とりあえずしがない科学者として生活していた。そんな彼のところにヘレナという放送局の女性レポータが取材にくる。既婚者の彼女と故郷のモラヴィアで密会の約束をした。実は、彼女の夫が、彼を党から追放した張本人で、彼への復讐として、妻のヘレナを誘惑したのだ。
と書いてしまうと、なんかエキサイティングなストーリー展開になると思われるかもしれませんが、物語は淡々と進んでいきます。
ルドヴィークは、なんとなく体制からはみ出してしまった人間。
ヘレナは、”党の犬”とか”ドグマティスト”などと同僚から陰口をたたかれているほど、体制に疑問をもたずに生きてきた”女”。
ルドヴィークの幼馴染のヤロスラフは、首都から離れたモラヴィアで、伝統音楽の演奏家として細々と生きている。
敬虔なクリスチャンであり、その信仰をすてなかったために、やはり体制からはみ出してしまったコストカ。
これらの人たちが、党や時代の流れに面と向かって逆らうことはないのだけれど、どこか心にひっかかるものを抱えながら生きているのです。
そして、ルドヴィークの軍隊時代の恋人ルツィエとの偶然の再会から、蘇る記憶。
当時のチェコ社会をこの物語がよく反映しているのだとしたら、西側に比べれば、自由の制限された社会ではあるものの、スターリン時代のソ連とのイメージとは随分違っていました。
確かに著者が言うように、社会主義は、とても特徴的で、存在感のある大道具ではあるけれど、それは、この物語の普遍性を損なうものではなく、たとえば、日本に置き換えても、それが祖母の時代でも、両親の時代でも、共感できるものがあるのではないかと思います。
ヘレナのことを騙して、一夜を過ごしたあと、勝利を手にしたのは、ルドヴィークではなく、時代に応じて自分の主張を変えながら生きてきた、ヘレナの夫でした。
この成り行きには、途中、著者は女性を蔑視しているのではと、ちょっと疑った自分を恥じました。そんなレベルではなかったのです。
ゼマネーク(彼の友情、弁舌、思い出や彼の良心)が私に関して無関心であったと同じように、私の過去のすべてが私に対して無関心であったように。その過去をひっさげて私は、それに復讐するためにここ故郷の町で逢引きをしたのだが、私など知らぬかのように過去は一瞥も与えず、私のそばを通り過ぎてしまった。
ルドヴィーク、ヘレナ、ヤロスラフ、コストカは、その時代時代に流されながらも、ひた向きに生きてきた、愚かなる、愛すべき人たちでした。
そう、人は、一生懸命生きれば生きるほど、文化、伝統などのある価値観にこだわればこだわるほど、客観的に見てしまうと喜劇を演じてしまうものなのかもしれないですね。
ヤロスラフは、ヴァイオリンを顎につけたまま歌い、私はこの歌の中で、心あたたまる思いがした。その歌の中では、悲しみは上っつらのものではなく、笑いに偽りがなく、愛はたわむれでなく、憎しみにおずおずしたところがなく、人々は身と心で愛している。
まえがきの冒頭に、
私はたずねられたことがある。「あなたの小説を理解するのに、チェコスロヴァキアの歴史を知っておく必要がありますか?」と。私は答えた。「いいえ、それについて知らねばならないすべてを、小説自らが語っています。」
と著者のお墨付きもあり、確かに本書を読むのに、チェコのことを知っておくことが、必須ではありません。私も、殆ど何も知らない、よくいえば先入観のない状態で読み、心から楽しめましたから。
とはいえ、やはり知っていればもっと楽しめるであろうことは間違いないと思います。
とにかく、これは今年読んだ本のなかのベスト3に入るものでした。















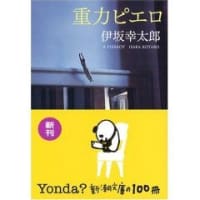



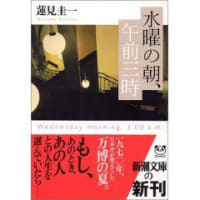

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます